
毎年この時期は創作期間なので時間もたっぷりあることもあって、なるべく色々なものを観たり聞いたりしてます。まあ半分楽しんでいるのですが・・・。先日のロイヤルバレエも素晴らしかったし、モネ展も良かった。もう30年ほど前にモネ展を観に行ったことがあるのですが、こうして年齢を重ねてから観ると、また以前とは違うものを感じることが出来ますね。
先週は雑賀バレエのスタジオパーフォーマンスにも行って楽しい時間を過ごしましたが、今週はコンサートを2本(クラシック・邦楽)聴きに行って、美術系の催しなどにも伺って…毎日どこかを彷徨い歩いています。
 若き日の村上龍
若き日の村上龍
毎日読書は欠かさないのですが、この所読む量がぐんと増えました。先日は友人に勧められて村上龍の「心はあなたのもとに」を読んでみました。村上龍はデビュー作の「限りなく透明に近いブルー」が出た時リアルタイムで読んでいて、近作では「55歳からのハローライフ」など、色々と作品は読んでます。村上は社会と人間との関わりという事が一貫したテーマのようで、己の世界に入って超然と道を極めて行くような芸術家タイプではないですね。
この作品もそうした社会の中に生きる人間像が描かれているのですが、特殊な病気が一つのテーマになっている作品だけに、医療の専門家などからは意見も多いものだと思います。また主人公が投資などの経済分野のエリートという設定なので、経済の事もかなりの分量が書かれていて、私にはよく判らない話も多く、ちょっと読みにくいところもあったのですが、読み終わって涙が止まらなかった。
まあ恋愛小説の部類に入るものだとは思いますが、文章を読んで涙が出るというのは、田端明さんの講演の内容を読んだとき以来でした。
https://biwa-shiotaka.com/blog/51185086-2
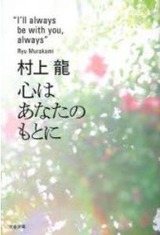
「小説というのは、読み手の人生のどこかにリンクする部分を必ず持っているもの」とはある先輩の言葉ですが、この小説の主人公は私と同世代ではあるものの、私とは真逆の人物。ちょっと鼻持ちならないような俗物でもあり、あまり好きにはなれないような人物です。しかしそんな全く縁のなさそうな主人公が語る物語のどこかにリンクする部分を感じてしまうと、不覚にも引き込まれてしまいます。小説というものの罠なんでしょうね。
私はこの小説が優れているかどうかという事はあまり関心が無いのです。なので書評は書けません。それよりもこの小説を読んで、自分の心が動いたという事の方が大きな事実として、今私の中に残っています。
ラストシーンで主人公が「I’ll always be with you, always」という言葉を解説しています。人は現実にはいつも一緒に居る事は出来ない。だからこの意味は「心はあなたのもとに」ということになる、と。この「心はあなたのもとに」という言葉は、彼の恋人がいつもメールの最後に付けていた言葉であり、彼女からすれば、あなたと一緒にいることが出来ない、という一種のせつない訴えでもあります。物語上での色々な意味合いもあるのですが、それ以上にこの言葉は独り歩きをして、私に色々な事を想起させます。

何時も思う事でもありますが、やっぱり言葉は諸刃の剣であり、時に言葉はまったく意味を伝えないのではないか?。そういう私の中に燻っている想いが読後に蘇り、それが強烈に迫ってきました。誤解の無いように書いておきますが、村上龍の文章が下手だとか、小説の内容が悪いとかいう事ではありません。彼の書いたストーリーが、私に言葉というものの本質を感じさせたのです。
例えば、おはようと言ってもその裏側に、他人には判らない悲しみがあるかもしれないし、また憎しみがあるかもしれない。想いと言葉は別で、もう言葉に意味など無いのではないか、とさえ思えてきます。人間は言葉を介し、解り合えているようなつもりになっているだけで、結局は自分の想いは伝わらず、相手の想いも解らないのかもしれません。解ったようなつもりになることで、日常というものが滞りなく過ぎて行く。社会とはそんなものなのだと思えてくるのです。だから音楽に於いても、言葉を伴う歌には敏感になってしまいます。
本の最後に作家の小池真理子氏が、「恋の相手とは、常に不在なのではないだろうか ロラン・バルト」 この言葉を載せていました。書評としての内容は別として、この言葉からも思う事が色々あります。
相手が居ないからこそ心が掻き立てられる、想いが湧く。それは根本的にコミュニケーションではなく、自分の中でのいわば妄想。その妄想が大きくなればなるほど、相手を求めたくなる。求め合う二人の間に本当の意味の意思疎通があるのだろうか。言葉は無理でも、言葉を超えて肉体が感じ合えているのだろうか。もしかしたら解り合えないという「あきらめ」の上に、人と人との「関係」は成り立っているのかもしれない。
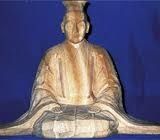 世阿弥
世阿弥想いを言葉で具体的に表すことは、本質的に不可能なのではないか。具体的な言葉を使って表現をすればするほど本質からの距離が大きくなるのではないか、と思えてしょうがないのです。伝えるのなら抽象的表現が一番その距離を縮められる。それは受け手の想像力に訴えるから。つまり理解ではなく、受け手が感じる事によって喜怒哀楽などの想いを身の内に湧き上がらせることが出来るからです。受け手に押し付けるのではなく、受け手が自分で感じて、受け手の心が自由に動くことが理解や感動に繋がるのではないでしょうか。
こんなことをつらつら考えていると、ここぞという所で抽象表現を持ち込んだ世阿弥は、やはり天才以外の何物でもないですね。改めてそう感じます。
とりとめも無く書きました。
「心はあなたのもとに」・・・。私の心はあなたのもと
に届いているでしょうか??



