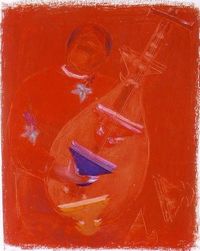来週の琵琶樂人倶楽部は毎年恒例になっている、琵琶製作者の石田克佳さんを迎えての琵琶トークをやります。石田さんはもう実質上お父様と共に国内唯一の琵琶の制作を担う方です。また正派薩摩琵琶の演奏もしますので、先ずは「小敦盛 二段」を演奏して頂き、私が「壇ノ浦」を演奏。二つの琵琶の聴き比べをします。その後二人で色々琵琶についてのトークを繰り広げるという毎度恒例の構成です。今回は琵琶に使われる材料についてお話を聞かせて頂こうと思います。
私の中型琵琶の裏側に使っている花梨の木ももう入って来ないようですし、桑の木や撥に使う柘植の材等、これまで通りという訳には行かなくなっているようですので、その辺りの事をお聴きしたいと思っています。小さな会ですので、お席も25人程でマックスです。ご興味のある方は是非ご連絡くださいませ。
私は最初から自由に琵琶の活動をしていますので、いわゆる流派の方とはほとんど交流がありません。意識的に避けてきた部分もありますが、作曲と演奏を不可分やっている私にとって、流派の形をそのままやろうとするスタイルと私とでは、あまりにも見ている所が違い過ぎて、同じ琵琶と言えども、話が出来る所があまりなかったというのが実情です。その分、私は能や長唄・日舞等の邦楽の他のジャンルの方々や洋楽の演奏家・作曲家、他ダンサーや詩人等様々なアーティスト達と幅広くお付き合いさせてもらっています。
石田さんはそんな私のやり方にも理解を持ってくれて、私がどんな音楽をやりたいいのか、どんな音を欲しているのか、その辺りをよく理解して「塩高モデル」を創り上げてくれました。流派でやって行く人から私のようなオリジナルスタイル迄、自然に対応してくれるのが嬉しいですね。今回もなかなか普段は聴けない話を聴く良い機会となると思います。是非お越しください。
琵琶はどこへ行っても大体耳なし芳一や琵琶法師というイメージで捕らえられてしまいます。また演者も珍しいとか唯一などという特別感を売るようになってしまうものです。確かにその場ではお客さんもそんな雰囲気に浸り見ることが出来満足してくれると思いますが、その繰り返しをした結果が今のこの衰退の現状ではないでしょうか。タレントとして売れたいのか、それとも音楽家・芸術家として評価をされたいのか、あいまいな姿勢でいると何も成就しません。永田錦心や水藤錦穰、鶴田錦史等本気で琵琶樂を創り上げて行った、そんな志を持った人がもっと出てきて欲しいですね
世界の音楽の流れを見ると、今受け継がれている音楽を作った人は皆、新たなものを創った人達です。パガニーニ、バルトーク、シェーンベルク、ドビュッシー、ラベル、ジョンゲージ、武満、黛、パーカー、マイルス、コルトレーン、オーネット、ジミヘン、パコデルシア、ピアソラ、ボブマーレイetc.
皆時代の音楽を創り上げたのです。時代と共に社会が変わるように形を変えながらも、先人達の感性や精神を受け継いでいったからこそ音楽が出来上がり、今に残っているのです。日本には世阿弥、利休、芭蕉をはじめ宮城道雄、海神道祖といった人達がずっと日本の音楽・文化を創り続けて来ましたが、今は創るという事を本当にしなくなってしまった。特に琵琶樂に於いてはそれが顕著です。よく平成は失われた30年と言われていますが、それは邦楽に於いても全く同じだと私は思っています。
 19年前 第一回高野山常喜院演奏会にて 笛の阿部慶子さんと
19年前 第一回高野山常喜院演奏会にて 笛の阿部慶子さんと
何度も書いていますが、私は30代で活動を始めた時、某雑誌の編集長から「琵琶で呼ばれている内はまだまだだ。塩高で呼ばれるようになれ」とアドバイスを受けました。琵琶の珍しさに寄りかかり、その珍しさを売りにしても、ネットで少しばかりアピールしても、そんなものはすぐに同じような賑やかしの輩に取って代わられる。
私は琵琶の音色に強烈に惹かれ琵琶を手にしました。弾き語りに惹かれたわけではありません。この音色にこそ惹かれたので、声はかえって無い方が純粋に琵琶のあの妙なる音色を聴かせることが出来ると琵琶を手にした最初から感じていました。笛や尺八筝曲三味線は皆独奏曲があり、その音色を存分に聴かせているのに、琵琶はいつまで経っても歌の伴奏しか弾こうとせず、弾き語りという形を演者が変えようとしなかった。変わって行く事こそ継承であり、伝統を創って行く事ではないでしょうか。私はジャズをやっていた頃からずっとそう思って音楽に接しています。雅楽ですら平安時代にも明治時代にも大きな改革をして、変わって来ているからこそ現代に伝えられているのです。
私は子供の頃から古典文学や歴史に接していたので、ジャズをやっていたにも拘らず、すんなりと邦楽の世界に入って行けました。また大人になってから琵琶に出逢った事も良かったですね。子供の頃からやっていたら今のようにはならなかったでしょう。ジャズを通り越したのは実に良い事だったと思っていますが、そのせいか自分が創り出すものの土台が何であるのか、その土台から何を表現したいのかという哲学的な部分では琵琶を手にした最初から一定の想いを持っていました。だからジャズをやる事よりも自由に創作が出来たのです。
そして石田さんが最初から近くに居た事は私にとって大きな大きな運命だったと思っています。塩高モデル無くして私の音楽はありえません。
私は現代の琵琶樂を創りたい。私にしか出来ないものを創り上げたい。能や雅楽、長唄などと違い、まだ歴史の浅い薩摩琵琶の世界では、創作は自由自在にやれますし、樂琵琶も雅楽の外側に居たからこそ自由にやって来れました。色んな事が実にタイミングよく自分の身の周りにあったし、今になって思うと導かれたんだなと感じています。これからも自分の想う所を進んでいきたいですね。
琵琶トーク是非お楽しみに。