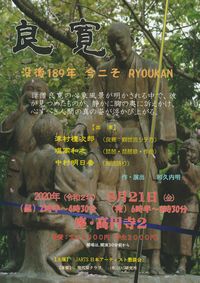エドワード・ヴァン・ヘイレンが亡くなりました。
琵琶人にとっては、どうでも良い話かもしれません。しかし私にとっては大きな大きな時代の節目なのです。このブログでもヴァンヘイレンについては色々と書いてきましたが、やはりジミヘン以降、その爆発的なテクニックとスタイルで、時代を一気に次の段階へと推し進めた、その事実はこれからも語り継がれてゆくでしょう。
私の琵琶は、ヴァンヘイレンの1stアルバムの中に収録されている「Eruption」の音を基に設計されました。あの唸る低音と、他の追随を許さない圧倒的な音の煌めきと存在感。新たな時代を告げる最先端のセンスは、正に私が琵琶に求めたものと一致したのです。ライトハンド奏法や斬新なアーミングという新しいテクニックは、驚く以外に何があるだろう、という位凄いの衝撃で、彼の登場以前と以降では、歴史区分が変わるほどの大きなターニングポイントとなったのです。ギター本体にも大きな変化あり、今では当たり前になっているパーツもヴァンヘイレンから一般的になりました。その変化は、平安から鎌倉に移るくらいのインパクトがありましたね。
 ウズベキスタンのイルホム劇場にて、アルチョム・キム率いるオムニバスアンサンブルと、拙作「まろばし」演奏中
ウズベキスタンのイルホム劇場にて、アルチョム・キム率いるオムニバスアンサンブルと、拙作「まろばし」演奏中
もう30年近く前、私は琵琶の音に惹かれて琵琶を始めたのですが、いざ演奏会に行っても、とにかく皆さん琵琶を弾かずに、顔を真っ赤にして歌っているばかり。そしてその音程はかなり調子っぱずれで、歌詞は戦争や人が死んでゆく話ばかり。正直本当にがっかりしました。ギターだろうがピアノだろうが、音楽が良くなければ、誰でも聴きたくはないですよね。ジャズをやっていた人間からすると、これだけ魅力的な音色を持っている楽器を手にしているのに、自分の音楽を創ろうとせず、歌に意識が行ってしまって楽器を弾こうとしない事に、全く持って理解不能でした。更に付け加えるとやたらと〇〇流だの、何とか先生だのという会話もうんざりでしたね。そんな状況を、琵琶を手にした最初に目の当たりにしたので、私は早い段階から流派を離れて活動しているのです。20年以上プロとして活動をしてきて、全ての仕事で自分の作曲した曲を演奏して活動していますが、我が道を貫いて来て、本当に良かったと思っています。
とにかく声と切り離して、琵琶の音を聴かせたかった。これだけ魅力的な音色を持っているのに、何故それを響かせようとしないのか、未だに不思議です。弾き語りというのは、語るべき強い想いのある人には有効なスタイルだと思いますが、歌手や語り手としてみたら半人前以上にしかならないし、楽器の演奏者として見ても、到底高いレベルには至らない。やる側に、ボブディランやジョンレノンの様に語るべき大きな世界があってこそ成り立つスタイルです。お稽古で習った曲を得意になってやっても、誰も聞いてはくれません。私は琵琶の、あの妙なる音を、とにかく大いに響かせたかったのです。
左:キッドアイラックアートホールにて灰野敬二、田中黎山各氏と。中:季楽堂にて吉岡龍見さんと。
右:みずとひにて安田登先生と
器楽としての琵琶樂を最初から標榜している私としては、先ず器楽演奏に耐えられる楽器を作る所から始めました。ヴァンヘイレンがフロイトローズのアームユニットを取り付けたようなものです。先ず自分で大体の設計をして、琵琶製作者の石田克佳さんに依頼しました。石田さんに細かい所を見直してもらって、色々なやり取りの末、製作してもらったのですが、その時頭に描いていたのが、ヴァンヘイレンの「Eruption」です。多分石田さんにも聴かせたと思います。能管や尺八と一緒にやっても対等に渡り合える音量・音圧、そして一音の存在感。これがどうしても必要でした。従来の薩摩琵琶は弾き語りの伴奏という発想しかなかったので、ここがとにかく音が弱々しかったのです。私は、薩摩琵琶のポテンシャルの高さを感じていたし、この魅惑的な音色を何とか、全面トップに持って行き、これから始まる琵琶の新時代にふさわしい機能と質を持った楽器として薩摩琵琶を再生したかったのです。
 この塩高モデルのお陰で私は1stアルバム「Orientaleyes」を作り、第一曲目に今でも私の代表曲である「まろばし」を冠し、世に打って出たのです。かなり遅いデビューではありますが、やっと私の考える音楽が具現化して、それをCDで出す事が出来るという事が本当に嬉しかったですね。
この塩高モデルのお陰で私は1stアルバム「Orientaleyes」を作り、第一曲目に今でも私の代表曲である「まろばし」を冠し、世に打って出たのです。かなり遅いデビューではありますが、やっと私の考える音楽が具現化して、それをCDで出す事が出来るという事が本当に嬉しかったですね。国内では今でも毎月の様に、また海外でも行く度に「まろばし」を演奏してきました。薩摩琵琶の演奏会で「まろばし」を演奏しないという事はまずありえません。残念ながらヴァンヘイレンの様に世界中に広まることは無かったですが、この塩高モデルのお陰で「まろばし」が出来上がり、私は器楽としての琵琶樂をやって行く決心がつき、これまでずっとやって来れました。
これを作った時は私も石田さんもまだ30代。お互い若かったですが、あの頃の勢いがあったからこその今だと思っています。
これまで多くの天才たちが、新たな時代を創り上げ、時代を創って行きました。日本では世阿弥や利休、芭蕉。琵琶でしたら永田錦心。ジャズならマイルスやオーネット・コールマン。タンゴならピアソラ。クラシックならバルトークやドビュッシー・・・・。キリがないですが、エドワード・ヴァン・ヘイレンもその一人。ブリティッシュの色が強く、重く暗かった当時のロックを一気に明るく、リズミックにアメリカンなセンスに塗り替え、アドリブに使うスケールもブルーノート一辺倒から、ダイアトニックなどを意識したメロディーラインに変えていったのがヴァンヘイレンです。今では当たり前のテクニックも楽器のハードな面も皆、彼から始まったのです。私の琵琶人生もエドワード・ヴァン・ヘイレンなくしてあり得ません。彼のあのギターの音があったからこそ、器楽としての琵琶の音楽を創り、これまでやって来れたと思っています。
左:大型琵琶が出来上がった頃、かつて日暮里にあった邦楽ジャーナル倶楽部 和音にて、
左:現在の私 日本橋富沢町楽琵会にて、能楽師 津村禮次郎先生と(photo新藤義久)
今夜はCDを聴きながら、ゆっくりと振り返っています。やすらかに。
 この塩高モデルのお陰で私は1stアルバム「Orientaleyes」を作り、第一曲目に今でも私の代表曲である「まろばし」を冠し、世に打って出たのです。かなり遅いデビューではありますが、やっと私の考える音楽が具現化して、それをCDで出す事が出来るという事が本当に嬉しかったですね。
この塩高モデルのお陰で私は1stアルバム「Orientaleyes」を作り、第一曲目に今でも私の代表曲である「まろばし」を冠し、世に打って出たのです。かなり遅いデビューではありますが、やっと私の考える音楽が具現化して、それをCDで出す事が出来るという事が本当に嬉しかったですね。 この塩高モデルのお陰で私は1stアルバム「Orientaleyes」を作り、第一曲目に今でも私の代表曲である「まろばし」を冠し、世に打って出たのです。かなり遅いデビューではありますが、やっと私の考える音楽が具現化して、それをCDで出す事が出来るという事が本当に嬉しかったですね。
この塩高モデルのお陰で私は1stアルバム「Orientaleyes」を作り、第一曲目に今でも私の代表曲である「まろばし」を冠し、世に打って出たのです。かなり遅いデビューではありますが、やっと私の考える音楽が具現化して、それをCDで出す事が出来るという事が本当に嬉しかったですね。