先日、医療関係の友人と話していて、興味深い話を聞いて来ました。
現代は性差医療というものが進んできているようなのですが、我々人間の性別に関しても、今までは男・女という二つの性でくくっていたものが、現代では染色体などの関係から、5つに分ける考え方が出てきたとのことです。勿論私は全くの門外漢なので、詳しいことは判らないのですが、その友人の言によれば、こういう考え方が世間に浸透する時代もいつか来るだろうと言っていました。私は話を聞いていて、この概念や考え方が、今後の世の中を大きく変えてゆくような気がしました。
そして、今月初めには早稲田にあるドラードギャラリーで「空想病院展」という企画展示を観てきました。テーマとして「性」が強く出ている展示でしたが、作品がまだ男・女という区別の中から抜け出せない感じがしました。作品はそれぞれ力作だったのですが、それぞれ「性」を独自に捉えている作家さんの意識が、まだ旧来の概念の枠の中から抜け出していないようで、澁澤龍彦(写真)あたりが描いていた世界の焼き直しのように思えました。肉体的な性別が二つでなくなって、GID(性同一性障害)などに対する認識も広まり、精神面でも複雑な在り方が確認され、其々が共生している現代社会に、作家の概念や視点の方が現実に追いついていないという感じでしょうか。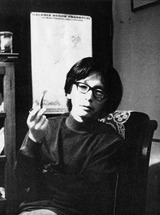
芸術は元来、因習や権威、宗教をも乗り越えて、人間存在の根本を描き、暴き、人間本来の姿を取り戻そうとする行為でもあると思います。それゆえ芸術家は「性」に対して独自のアプローチを持ち、こういう変化にかなり敏感な方が多いのです。今回は「性」が一つのテーマとなる展示で、作家さん自体もテーマとしている風に見える方々でしたので、ちょっと意外な感じがしました。
ダダやシュールなどは勿論、印象派でもキュビズムでも、芸術家は常に時代を先取りし、人々を社会や常識の呪縛から解放し、次世代の感性を示し、育ててくれるものでした。しかし現代では、どんな状況なのでしょうか??。全体的にあまり社会とコミットせず、作家の個人的な領域に内向しているのでしょうか?色々と思う所がある展示でした。
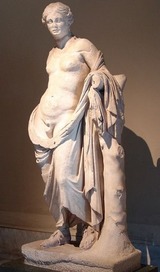 男・女の役割は勿論、性に対する概念や哲学すら変わって行く時代に、人間本来の姿を描こうとする芸術家が性の問題を取り上げ、新しい視点で創作活動してゆくのは、当然だと思います。性別が二つに限定される旧概念の枠内で個人的な幻想世界を描いても、それはもはや懐メロの域を出ない。
男・女の役割は勿論、性に対する概念や哲学すら変わって行く時代に、人間本来の姿を描こうとする芸術家が性の問題を取り上げ、新しい視点で創作活動してゆくのは、当然だと思います。性別が二つに限定される旧概念の枠内で個人的な幻想世界を描いても、それはもはや懐メロの域を出ない。
常識や習慣に囚われて生きている我々にとって、男女の他に性別があるという事は、なかなかすぐには受け入れがたいと思います。しかしもう現実は受け入れざるを得ない所まで来ています。そんな時代には新たな概念や感性が出て来るのは当たり前であり、どんな軋轢があろうとも、時代は受け入れる方向にどんどんと向いて行きます。何故ならば、多様な性があるという事は古より歴然とした事実であり、今まではそれを「男女という二つのものにすべて区分し、男はこうであるべき、女はこうであるべき」という因習の中に押し込め、封印して、知らされなかっただけなのですから・・・。決して新しく作り出したものではないのです。むしろ本来の姿がやっと表に出てきたというべきでしょう。
政治の分野では世田谷区議の上川あやさんのように、ジェンダー問題に積極的に取り組んでいる方も出てきましたが、今、セクシャルマイノリティーと言われている人々が、特別な存在として認知されるのではなく、肌の色が白でも黒でも黄色でも、普通に平等に暮らし生きているように、マイノリティーが違和感なく認知されてゆく時代がもうすぐそこに来ているような気がします。

さて、こんな時代に琵琶楽はどこを向いているのでしょうか。残念ながら琵琶楽はそんな芸術とは無縁の所にあります。お稽古事の世界に留まるのならば、今までと同じでも別に問題は無いでしょう。しかし音楽として世の中に発信してゆくのであれば、世の中と共に変わって行かないと後がありません。自分の姿が自分で見えないというのであればもう終わりが見えたともいえるかもしれません・・・。新時代の音楽、新時代の感性・・永田錦心の志は誰が継いでゆくのでしょうか?
古典でも、そこに今までとは違う、時代に即した感性・視点を当てて最構成し、 次世代に向けて発信してゆく、そんな創造性を琵琶は獲得できるだろうか。バッハでも、時代によって色々な解釈がなされ、楽器も進化し現代のピアノで演奏され、それでまた新たな魅力を見いだされ、時代時代で人々を魅了してゆくのです。そうして時代の感性に晒され、汲めども尽きぬ魅力を放つものが「古典」となって行き、その新しい感性と創造性がバッハを次の時代へと繋げてゆくのです。狭い小さなヒエラルキーの中で、ありがたがって保存し崇めているだけでは、ただ朽ちてゆくだけなのです。
次世代に向けて発信してゆく、そんな創造性を琵琶は獲得できるだろうか。バッハでも、時代によって色々な解釈がなされ、楽器も進化し現代のピアノで演奏され、それでまた新たな魅力を見いだされ、時代時代で人々を魅了してゆくのです。そうして時代の感性に晒され、汲めども尽きぬ魅力を放つものが「古典」となって行き、その新しい感性と創造性がバッハを次の時代へと繋げてゆくのです。狭い小さなヒエラルキーの中で、ありがたがって保存し崇めているだけでは、ただ朽ちてゆくだけなのです。
美術とはまた違う側面があるので、同じ土俵で語る訳にはいきませんが、何も新しいものをやらなくても、時代も性別も何も超えて響く、人間の通奏低音のようなものがあるはず。せめてそういう精神で接して欲しい、と私は思います。そして新しい時代の感性による新作も、永田錦心がやったように、今後も積極的に作られるべきだと思います。

時代は刻々と変化してゆきます。今まで常識だと思っていたことが、ただ目隠しをされていた、という事実もどんどん暴かれてゆくでしょう。これからどんな哲学と感性が生まれてゆくのだろう。どんな社会になって行くのだろう。私のような凡夫には、想像も及びませんが、芸術家はこの現実と共に歩み、次の時代の感性を育て創ってゆく役割があると私は思います。次世代に向かって、今何を表現すべきなのでしょうか。大きな問いかけが、目の前に横たわっているのだと思います。
歩まざる芸術家は、どこに向かっているのだろう?




