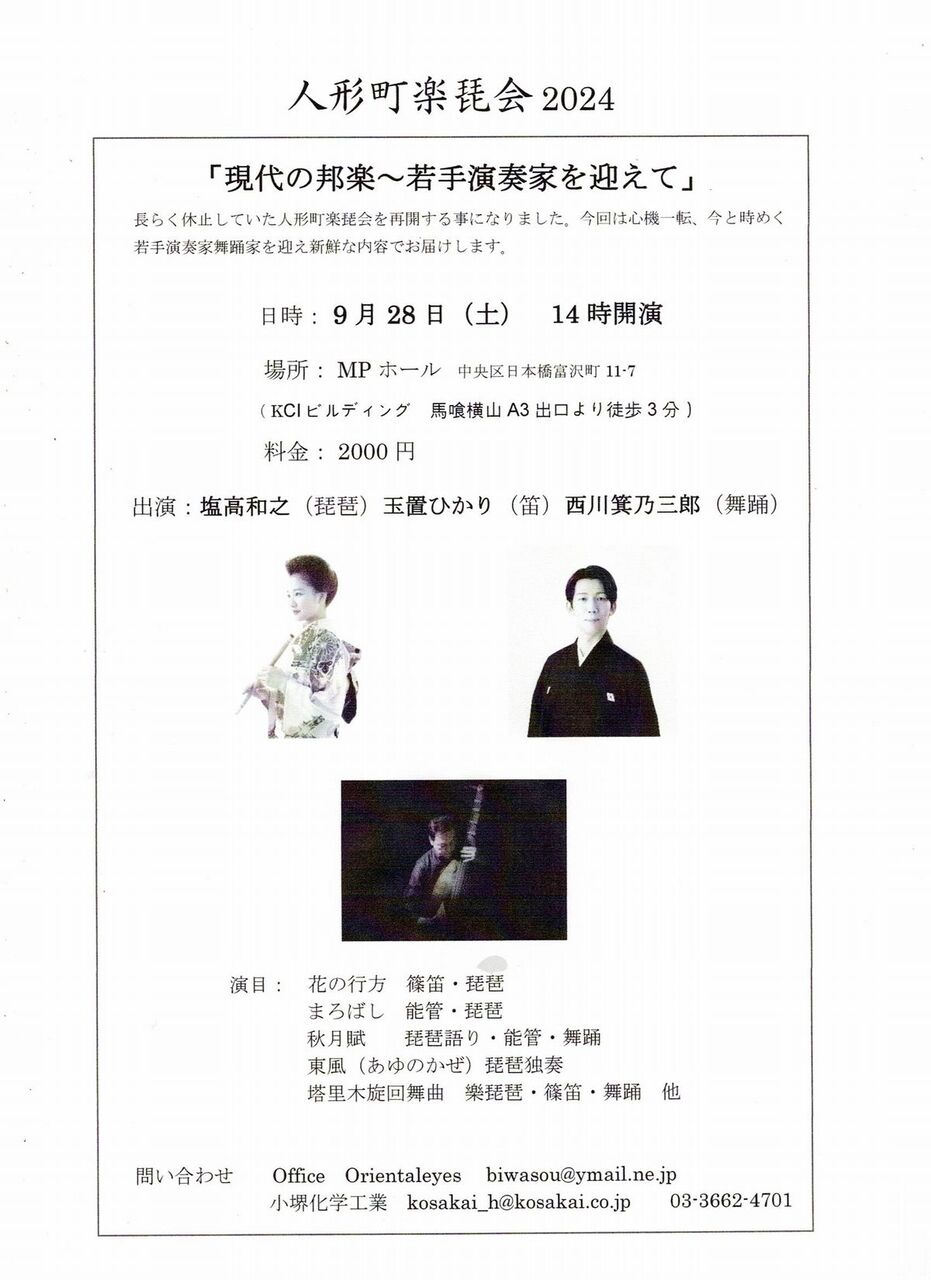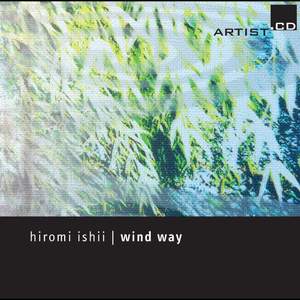普段ぶらぶらしている私も、秋はさすがに何かと飛び回っています。前回お知らせしたように人形町楽琵会も久しぶりに再開するし、次のアルバムのレコーディングもあるし、大学の講義もあるし、何だか久しぶりに追われている感じです。
私はいつも普段から時空を飛び越えるような荒唐無稽な夢ばかり見ているのですが、こういう追われている時期には更に変な夢をよく見ます。怖い夢ではないのですが、ちょっと自分の心の闇が暴かれるような、何とも言えない変な夢が出て来ます。ちょっと頭の回路が変わっているんでしょうね。私は演奏だけでもソロ、デュオから舞踊や語り等、かなりのヴァリエーションでやってますし、その上レクチャ―等も入れると結構な数になります。且つ演奏曲は全部自分で作曲しますので、やっつけ仕事は出来ないのです。総ての仕事が塩高の作品という気持ちでやらせてもらってます。
人間は、知識、情報、技術に本当に弱いんだなと年を経るごとに感じます。そういうものを身につけていると必ずそれを使いたがり、使って見せている事で満足し、本来やりたい事を忘れてしまう。上手な人ほど、それらを使い飛び回っている事で満足してしまう。だから技術や知識を勉強すると共に、精神の成長もして行かないと、かえって視野を狭め、得た知識や技術が妨げになってしまいます。音楽家も上手くなればなる程問われるのは技術ではなくて音楽です。歴史を振り返ればヴィジョン無き技術は原爆を生み、現代では太陽光発電等、後先考えないものが悲劇を生んで絶え間なく溢れています。
習った曲が上手に弾けるとそれを披露したくなるのはお稽古事としての楽しみでしょう。しかし自分のやりたい事よりも上手に出来る事を見せようとする心ではその先の世界へは行けません。上手を見せるのが自分の音楽だと勘違いして、果てにはおだてられてお墨付きをもらって、自分はそれなりだと思い込み、そこで思考を止めてしまう。本来見えるはずの世界を見ようとせずに自分で閉ざしている。そんな人を見ていると残念ですね。そこにその人の音楽が在るでしょうか。
私がいつも取り上げている永田錦心や宮城道雄は、邦楽の世界で自分のやりたい事を貫いて、その当時の最先端の日本音楽の姿を現しました。確かに演奏する全てが完全なオリジナルではなかっただろうし、二人とも若くして亡くなり志半ばであったと思いますが、あの明治という新時代に自分の考える独自のセンスと形を世に示したことは、日本の音楽や芸術にとって称賛すべき事だと私は思っています。お稽古事をやっている人と音楽家の違いはこういう所ではないでしょうか。
練習も勿論ですが、それと同じ位考える事も大事だと私は思います。初歩の段階で、感じる事、考える事を習慣づけてあげるのは先生の役目だと思っています。私も少しばかり生徒に教ていますが、常にどうやりたいかを問います。その根拠も問うし、自分の責任で演奏する事も合わせて言います。初心だろうがベテランだろうが、自らが考えて音を出す事、出す音に責任を持つ事が先ずは一番だと思って生徒に接しています。曲にも先生にも寄りかかっている状態ではは舞台に立って生きて行く事は出来ません。
私がするのは、生徒がやりたい事に対し、少しの技やアイデアを教え後押しする事。そして常に考える事を勧めているだけです。生徒が迷いの中に居る時に手取り足取り教えてしまうと、考える事を止めてしまう。大いに迷い、悩めばよいのです。その時の生徒にとって必要だと思えるアドバイスを少ししてあげる程度にしてあげるのが一番良いと、自分の経験上思いますね。とにかく好きなようにやらせますが、その「好き」というのを自分で探って、何故好きなのか、何故その音なのか、その「好き」が発生する根拠はどこにあるのか、そんな事を掘り起こす作業が重要だと考えています。その為に自国の文化を勉強し、歴史を紐解き、自分の感性の土台が何処にあるのかを自分で見つけて行かなければ、いつまで経っても表層意識の領域でうろうろしているだけです。共演者にも、自分で考え演奏して欲しいので、譜面もあえて細かく書き込まないようにしています。演奏家は出だしの音から、どうやれば一番ふさわしいかじっくり考えて頂き、その音に責任を持たなければ音が出せないように書いています。そうやってお互いで創り上げて行く作業が創造だと私は考えています。
これらの思考は作曲の石井紘美先生の影響です。石井先生ははっきり言って作曲のお勉強的な事は教えてくれませんでした。私は10代からジャズをやっていたので、一通りの音楽理論は解っていましたが、一応やって来ました感を出そうと思ってバス課題やソプラノ課題などやって譜面を書いて持って行っても「そんなものはあなたには本を読めばすぐ判るでしょ」なんて具合で、ろくに見てもくれませんでした。いつもアートとは何か、曲の背景には何があるのか等々ずっと話を聴くのがレッスンでした。シェーンベルクの「浄められた夜」なんかをかけて、その感想や分析を話してくれたり、時にはバルトークの「弦チェレ」という曲の音価やリズムを先生がグラフに表した図形楽譜のようなものを見せてくれて(ちんぷんかんぷんでしたが)、もうほとんど哲学の講義を何時間もお茶を飲みながら聴くというのが常でした。私が「格好良いですね」なんて適当な事を言おうもんなら、「そういう表面しか感じようとしない感性ではだめ。あなたはアートとエンタテイメントの違いが判ってないわね」等と冷~たく言い放たれる。今でもよく想い出しますね。とにかく深く考える、感じるという事を教えてもらった素晴らしいレッスンでした。あの20代の頃の体験が私の原点です。
振り返ってみると私が先生と呼ぶ人は皆そういうタイプの人でしたね。小学生の時に習ったクラシックギターの竹内京子先生も「好きなように弾きなさい」という人でしたし、ジャズギターの潮先郁男先生も、沢山の技術や知識を教えてくれた後に「自分のスタイルで弾きなさい」と言ってくれました。最初に琵琶を習った高田栄水先生も「芸術音楽として琵琶を弾くんだ」とよく言っていました。誰一人として上手に弾きなさいという方はいませんでしたね。本当に良い師匠達に巡り合ってきました。
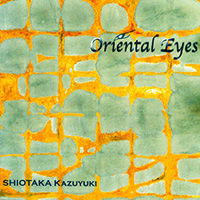 1stアルバム「Orientaleyes」
1stアルバム「Orientaleyes」
私はギターで仕事をしていた20歳の頃、色んな仕事をやって、結局駒のように使われている自分に納得がいきませんでした。つまり技術の切り売りをしているだけで、上手な人がやれば私でなくともよいという事です。
それで20代の中頃になって、多分にラルフ・タウナーの影響もあり、アコースティックギターの独奏曲を創って、オリジナル性を打ち出し、小さなライブを細々やっていました。その後琵琶に転向してからは最初から一貫して、私でなければ成り立たない100%完全オリジナルな曲を創って演奏する事を第一の指針としてやって来ました。それで1stアルバムから今回リリース予定の10枚目のアルバム迄全て自分で作曲して演奏して来たのです。石井先生の作品が唯一例外ですが、その「HIMOROGI Ⅰ」も石井先生と何度も打ち合わせを重ね創り上げたので、私でなければ弾けないという自負を持っています。
音楽はその人がどんな思考をしているかで、奏でる音楽は随分と変わります。同じ曲でも全く違う曲のようになります。何故その曲を演奏するのか、どのように演奏したいのか、その発想の源はどこにあるのか、そういうものが自分の中に確固としておらず、視野もこり固まって様々なアプローチを想像する事が出来ないようでは、そこに自分の想いを載せる事は出来ません。
音楽をやるには歴史や宗教、文化・芸術・社会等々、音楽以外の様々な事にアンテナを張って、目を向けていないと、個人の小さな器の中でただ「格好いい」「いい感じ」みたいな浅い所でしか音楽を捉えることが出来ず、お上手以上のものは出て来ません。修行と称して自分を閉ざしていては音楽は響かないのです。世の流れはとてつもなく早いもので、有能は若手もどんどんと出てくるものです。すぐに追い抜かれてしまいます。小さく狭い意識では活動は続けて行けないのです。
日本人は「いいものはいいんだ」とすぐに論理的思考をやめて、自分の殻に閉じこもってしまいますが、それはこだわりでも何でもないですね。この世界がつながっている時代に小さな思考に囚われて、目の前に溢れる流行や自分を取り巻く小さな世界としか調和出来ないようでは、今どういうものが世界に流れていて、何が起きているのかが見えていないという事です。結局世のプロパガンダに流され最期には駆逐されてしまいます。コロナの数年間でそれは如実に可視化されました。「世界の中の私」という感覚はもう各自が持っていないと、生きて行け無い時代に入っていると私は思います。
グローバル意識は欧米標準という事ではないのです。むしろもう欧米の時代が終わったことを認識する事がグローバルでしょう。アメリカやヨーロッパに憧れ、アメカジやヨーロッパブランドの服を着て英語交じりでしゃべって喜んでいるような人がまだ沢山うようよいるのが現代日本です。これだけ文化の豊かな国に生まれ育ちながら、ろくに自国の歴史も知らず、日々垂れ流されるエンタメを見て喜んでいるばかり。それこそ世界標準の目でみたら、自分の生まれた国に誇りを持てない人間など、どの国に行っても最低レベルの人間と思われても仕方ありません。自国の文化も解らない人間が、どうして相手の国の事を理解できる??。そんなそんなことも解らないようになっているのが日本の衰退の一番の原因だと私は思います。
以前とある大学で講義をした時に英文科の講師だか先生が同時通訳で海外の学生向けにやりたいというので、お任せしたんですが、始めてすぐに「室町時代と鎌倉時代はどっちが先でしたっけ」なんて言って質問してきたことがあります。結局通訳は出来ず、その先生は早々に撤退して行きましたが、私はその時、もうこの国は終わるかもしれないと思いましたね。大学の英語の先生がまるで自国の事も知らずに英語を教えている現実。失われた30年なんて言葉がありますが、そうなるのは当たり前ですね。
現代人は精神よりも肉体に興味があって、精神の方が貧弱な人が多いように感じます。人間は肉体的な存在でしょうか。私は精神的な存在だと思います。いくら着飾ったところで、その人の中身は目つき、手つき、姿勢、動き、言葉に全部出てしまうので、中身が伴っていないとかえって表面を繕っているのが見すかされてしまいます。精神があって、そこに肉体が伴ってはじめて文化が生まれ、音楽が鳴り響くのではないでしょうか。
楽しく音楽をやるのは素晴らしい事です。しかし音楽を通して色んな事を考え、時代の中で生きて、深い想いを持って音を紡ぎ出す人も是非いて欲しい。特に琵琶のような旧く長い歴史を持ち、日本だけに留まらずオリエント全体に渡る深い歴史を持つ楽器なのですから、是非そんな方が居て欲しい。何を考え、どこを見て、どうやって生きて次の世代に渡したいのか。それがそのまま音楽になると私は思っています。この日本の風土や歴史に根差して音楽を創っている人と、一緒に音楽をやりたいですね。