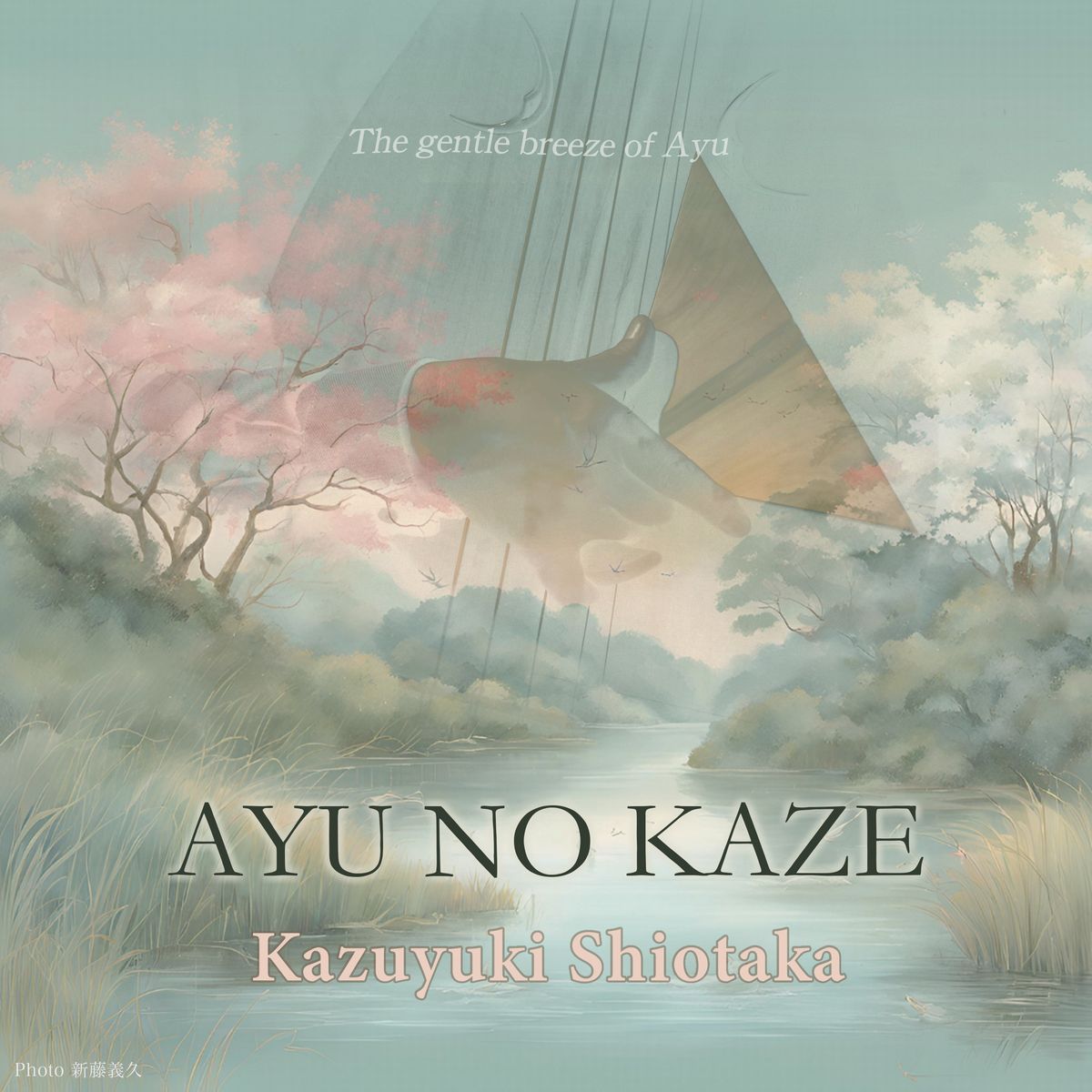私は有り難い事に良い仲間に恵まれていて、いつも書いているお茶の会(時々酒の会)なんかも時々やって仲間と顔を突き合わせて話し込みます。皆さん本当に話題が豊富で楽しい方ばかりで、ついつい長引いてしまいますね。先日もASax奏者のSoon・Kimさんと「自分の原点は何だろう」なんて話で盛り上がりました。
キムさんは20代の頃からNYに渡り、あのOrnette Colmanに内弟子のような形でついて研鑽を積み、その後は主にヨーロッパで活躍していた方なので、私には無い経験が豊富で、とにかく話をしているだけでも面白いんです。キムさんと私の共通項はジャズ。今回もジャズ話で楽しい時間でした。
私が今やっている音楽の土台は父からの影響です。シルクロードも古典文学も父の影響で、琵琶に転向してから何の違和感もなくすんなりと入って行けたのは父親譲りだと思っています。また父がギターを弾く人だったので、私も小学生の時からずっと弾いてます。父が最初にギターを買ってきてくれた日の事は今でも覚えていますね。その後、中学でブラスバンド部に入り、コルネットを吹いたことでジャズ界隈に沼って行きました。
シルクロード・古典文学・ギター・ジャズこれらは琵琶を手にすることによって、私の音楽として新たな形となって表れて来たのです。特に年明けにリリースした10thアルバム「AYU NO KAZE」はそんな私の音楽を充分に表現出来たと自画自賛しています。
キムさんと会った日は、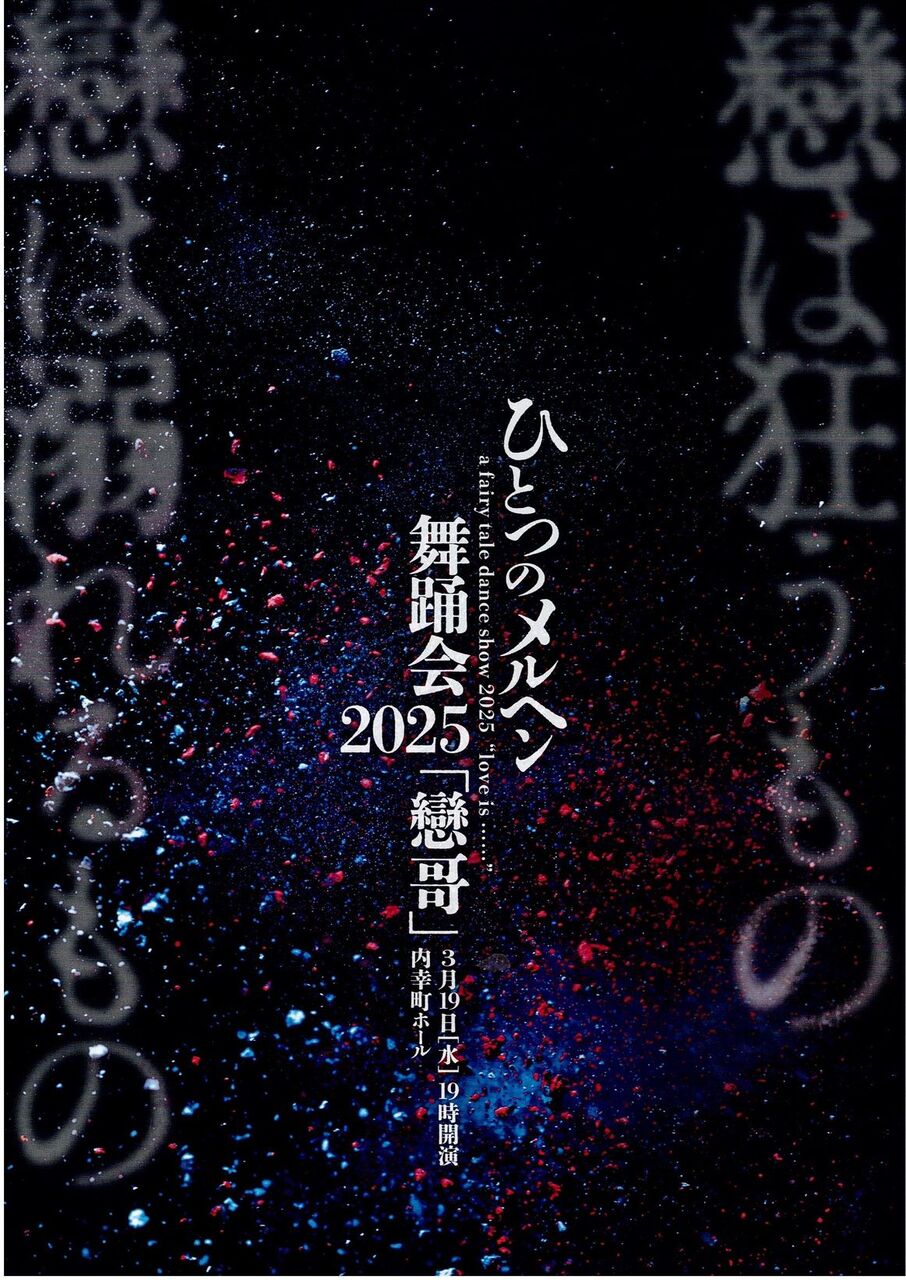 六本木のストライプハウスでTpの金子雄生さん、ナオミミリアンさんらのパフォーマンスがあり、それををキムさんと観に行ったのですが、彼らも原点にジャズがあるので、何とも繋がりを感じる事が出来て面白かったです。金子さん、ナオミさんとは、今年の3月、内幸町ホールで行われた舞踊公演で御一緒させてもらって以来のお付き合いで、特にダンサーのナオミさんは、今大変に活躍している若手なので、是非一緒にライブをやってみたいと話をしているところです。来年は是非琵琶樂人倶楽部でも、ダンスを入れてやろうかと思っているのですが、あの狭さで何がやれるか、ちょっと思案中です。
六本木のストライプハウスでTpの金子雄生さん、ナオミミリアンさんらのパフォーマンスがあり、それををキムさんと観に行ったのですが、彼らも原点にジャズがあるので、何とも繋がりを感じる事が出来て面白かったです。金子さん、ナオミさんとは、今年の3月、内幸町ホールで行われた舞踊公演で御一緒させてもらって以来のお付き合いで、特にダンサーのナオミさんは、今大変に活躍している若手なので、是非一緒にライブをやってみたいと話をしているところです。来年は是非琵琶樂人倶楽部でも、ダンスを入れてやろうかと思っているのですが、あの狭さで何がやれるか、ちょっと思案中です。
私は、自分の育った風土大地とは違う音楽の視点を一時期持った事で、より自分が生まれ育った風土を認識させる貴重な体験をしたと感じています。かのゲーテも「ひとつの外国語を知らざる者は、母国語を知らず」と言っていますが、私は深く共感納得出来ますね。今邦楽・琵琶樂全体が衰退に向かっていますが、それは正に別の視点や経験からの眼差しがほとんど無い所がその要因ではないでしょか。これは日本全体にも言えるかもしれないですね。
ただ海外のものを勉強するのは良い事ですが、憧れるばかりで、欧米文化の一員になる事で満足していて、ジャズやクラシックかぶれになり自分の足元を見失っていては何も創り出せません。まだまだ日本には欧米文化が世界だと思い込んでいる人が多いですが、残念でなりませんね。また伝統邦楽の中にも欧米コンプレックスがまだまだ強く残っています。情けないですね。
世の中にはセミナーや動画で良い話をしてくれる先生方も多いのですが、聴いている方が良く解らないカタカナ語満載で得意になって知識を羅列するばかりな方も多いですね。まともに美しい母国語をしゃべることが出来ないのによく自分から発信出来るなといつも感じます。それは単にコンプレックスなのか、誇りの欠如なのか、はたまた知性の低さなのか・・。音楽だろうが何だろうが、母国語で次世代へのヴィジョンを語れないようでは、その知識が邪魔をして自分が立っているこの大地が見えないのと同じではないでしょうか。
何処まで行っても母国語は大地であり、誰にとっても原点です。是非美しい母国語を話して欲しいものです。音楽も同じで、洋楽が溢れているこの現代社会の中で、様々な知識や技術を使いながらも、創る音楽は次世代の日本音楽でありたいのです。私の創る音楽は、ジャズでもクラシックでも何でもなく、次の琵琶樂でありたいのです。
琵琶樂人倶楽部にて photo 新藤義久
キムさんとの話では、もう一つ関連する話題として「最近音色が無くなった」という話が印象に残りました。60年代位迄のジャズマンは皆その人の音色を持っていました。それぞれの声のように音色が皆違っていました。現代は技術も理論も進み、どんどん上手になっているのに、そこに個人の音色が感じられません。コルトレーンにはコルトレーンの音色がありましたし、マイルスも、オーネットも皆独自の音色がありました。鶴田錦史もそうでしたね。でも今、上手で器用な人は増えたのに、そういう個性あふれる音色を感じる演奏家は本当に見当たりません。誰が弾いているのか区別がつかないのです。これも時代のセンスだと言ってしまう事は簡単ですが、何か音楽の根本とする部分がズレてしまっているように思えてならないのです。これはつまり大地を忘れているという事ではないでしょうか。上述のカタカナ知識を羅列している先生方と同じ状態だと思います。
今、現代人は大地を忘れてしまったかのような暮らしをしています。これが文明だとすると、この生活は果たして本当に進化なのか。疑問ですね。人間は大地・風土と深く交わる事で「交差の構造」を築いて生きて来たのに、今は物が人間と大地の関りという関係を飛び越えて勝手に流通し、故郷の大地でさえ観光資源になってしまい、資本主義や貨幣経済が発達するにしたがって、その「交差の構造」が消えしまいました。本来土地との一番強いつながりを持っていた食料さえも、貨幣を対価としてやり取りをする商品になり、社会の急激な変化が人間同士の在り方そのものを、大きく変化させてしまいました。
2010年大分能楽堂 寶山左衛門追悼演奏会にて 福原道子氏、福原百桂氏と
音楽も作曲演奏する人間自体が大地との「交差の構造」を失い、生活は文明という名の虚実の中に取り込まれ、そのまま音色を失ってきたのでしょう。大地と縁を結ばないこの文明に踊らされていたら、自ら時代に餌になるようなものです。こんな時代にもう一度、大地の音色を感じさせるのが音楽の役割なのかなと私は思っています。現代は世界中の情報が行き交い、人間もどこへでも行ける時代ですから、音色も様々なものが溢れて重なって来るでしょう。しかし自分の立っている大地の音色を忘れ、文明の名の元、ビックデータの一部情報に成り下がってしまったら、そこに自分の音色は出てくるでしょうか。自分はただ一人しかいないのです。今こそ人間が生まれ育つ大地が、人間にとって一番大事なものとして見直される時代になって来たのではないかと思います。
自分の大地を今一度見直して、取り戻し、自分の音色を奏でたいですね。