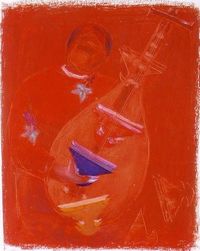今月10日(水)の琵琶樂人倶楽部は、発足当時の初心に戻って、薩摩琵琶の発祥から現在までを辿るレクチャーをやります。琵琶樂人倶楽部を始めたきっかけが正に、薩摩琵琶の歴史をしっかりと伝えようという想いで始めたので、200回目を目前にもう一度初心に立ち返ろうという訳です。
こちらは17年前琵琶樂人倶楽部が発足した時に邦楽ジャーナルに載った記事です。私が琵琶で活動を始めた25年程前は、琵琶史観が全くめちゃくちゃで、琵琶樂の研究者もまだろくに居ませんでした。一番新しく80年代辺りに流派として認知された所が「古典です」なんて言ってはばからないような状態で、私自身も最初は薩摩琵琶の歴史をろくに知らず、そんなもんかなと思っていました。
若手が格好つけたくて大げさに言うのは可愛いものですが、「琵琶は千年以上の歴史」があるなんてキャッチコピーで、先生方までもが宣伝しているようでは、さすがによろしくない。そういうものに対して誰もがだんまり状態というのは情けないと思うと同時に、琵琶樂衰退の原因はここだなとも感じていました。ようは琵琶に対する意識レベルの低下という事です。何故胸を張って「最先端の琵琶樂です」と言えないのでしょうか。古典というと何だか権威がありそうで立派に見えるとでも思っている人が多いかと思いますが、そんな所に寄りかかっていること自体が既に音楽家でも芸術家でもないですね。大概新しい流派程「古典」と言いたがるのは何の分野でもそうなのですが、これは田中裕子先生が言っている「伝統ビジネス」と同じセンスだと思っていました。
 若き日
若き日
また私は活動の最初から何故か大学や市民講座等でレクチャーの仕事もしていました。私にはキャリアもアカデミズムも何も無いのですが、どういう訳か、そういう所に呼ばれて喋るという運命が、琵琶を手にした頃から与えられたのです。これも勉強だと思って毎年やれるところはやっていますが、そんなアカデミックな専門研究の場で、まだ何十年しか経っていないものを古典とはとても言えないし、相手にもされません。2003年にヨーロッパツアーに行った際にロンドンシティー大学で世界の作曲家に向けてレクチャーをやりましたが、その時にも「薩摩琵琶は日本音楽の中でも、近代に新しく成立したジャンルであり、特に私が持っている5絃タイプのものは昭和時代に開発されたモダンスタイルな楽器です」と言ってレクチャーと演奏をやりました。
私は最初から日本音楽の最先端をやってやるという想いで琵琶を弾いているので、捏造のような歴史観には違和感以外のものを感じませんでした。薩摩琵琶を古典と言っている人は未だに居ますね。何か寄りかかるものが無いと自分を保てないのでしょう。私には自己顕示欲とコンプレックスに囚われているとしか思えないですね。
私は随分と気合の入り過ぎた硬い顔してますね。まあ無理もないですが
右:演奏会終了後の打ち上げにて大役を務めた後、一気に気が抜けて吞んでしまって、寶先生、百華さんの横で腑抜けてます
まだ私が30代の頃、長唄の寶山左衛門先生の舞台などに出させてもらいましたが、長唄という数百年の歴史のあるジャンルの中で、数十年の歴史しかないものを古典だとはとても言えませんし、40代からは能の津村禮次郎先生や日舞の花柳面先生とも何度も共演させてもらって、こちらがしっかりと正しい日本文化の歴史観を持たないと、とてもじゃないけど一流の芸能者とは一緒にはやって行けないという事も学びました。日本の音楽をやっているのなら、歴史も古典も一通り精通していて当たり前。習った事しか知らないなどと言うオタクレベルでは全く通用しないのです。
今はネット配信で即刻リリースしたものが世界に流れる時代。日私の曲も聴いて買ってくれる外国の方にアピールするのなら世界の歴史の流れや文化もある程度視野に入れておくのが常識な時代です。仲間内の小さな琵琶村感覚をいい加減脱しないと、誰も相手にしてくれません。既に永田錦心が生前同じ事を熱く語っています。琵琶樂人倶楽部発足当時は、同じ思いを持っている人が誰一人居ませんでした。そこがとても悔しかったですね。
 鈴木晨平 photo 新藤義久
鈴木晨平 photo 新藤義久
だから琵琶樂人倶楽部を立ち上げ、まともな琵琶樂の歴史について知ってもらおうと思ったのです。今回はそんな発足当時に立ち返り、薩摩琵琶の発生から現在までの変遷をお話させてもらおうと思っています。また現在の姿という事で、今ライブ活動を頑張っている鈴木晨平君に、現在進行形の薩摩琵琶の姿も披露してもらいます。お稽古事ではなく、一から薩摩琵琶という新しいジャンルを創り上げ盛り上げて行った永田錦心、水藤錦穰、鶴田錦史の各先人のように、彼も現在進行形で自ら創って行こうと頑張っています。そんな彼の今を聴いて頂きたいと思います。
何とか流という名前があると、何だか凄いもの、偉いものに思えてしまうものですが、そんな名前やありもしない権威に寄りかからないで、どこまでも自分の軸で、先人の志をこそ受け継ぎ、微力ながらも次世代へと繋げたいですね。「媚びない、群れない、寄りかからない」は何ごとにも必須の精神だと思っています。
薩摩琵琶樂は魅力ある現在進行形の音楽です。現代、そして次世代の人にアピールできる薩摩琵琶の音楽をどんどん創りたいのです。それはそのまま永田錦心や水藤錦穰、鶴田錦史たち先人がやってきたことに他ならないのです。微力ではありますが、先輩たちの志を次世代の琵琶人に伝えていきたいですね。そして次世代の琵琶樂を創り出す人材を応援したいですのです。