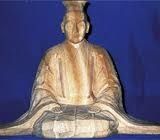ちょっとこのところ更新が間延びしていてすいません。この秋もお蔭様で、色んな仕事を頂いて忙しくさせてもらってます。毎年順調に(奇跡的に?)お仕事の量も質も上がり有り難い限りです。とにかく常に心して音楽に立ち向かうのみですね。
先週は定例の日本橋富沢町樂琵会、そしてこれも毎年恒例の阿佐ヶ谷ジャズストリートで演奏してきました。
日本橋富沢町樂琵会にて、笛の大浦典子さんと
私が活動をしてゆく上でいつも心がけている事は、囚われないという事です。同時に、あらゆるものに関心を持つという事です。人間がんばっていると、得てして頑張りが拘りになり、頑なになって、自分の価値観以外のものを受け入れようとしなくなるものです。世の中にはあらゆる考え方があり、それぞれに価値があります。自分の考え方が絶対という人は、次第に自分に頷いてくれる人としか交流しなってしまいます。まあ他のものが入ってきて自分のこだわりが崩壊してしまうのだとしたら、元々その程度のものでしかないということですね。
世界情勢や自然環境を見ても同じですが、様々なものを受け入れてこそ、個というものの存在が成り立っていることを思えば、日々の生活も音楽も世の摂理も同じですね。
 小劇場プロットにて
小劇場プロットにて
私はともすると小さなもに囚われてしまうので、常に我が身を振り返るようにしています。幸いよきアドバイスをくれる友人知人先輩も周りに沢山いて、日頃からよく話をするので、自分で見えないところも多々気づかせてもらってます。
のんびりと日々お散歩していても、自然の移り変わりを見て下手な短歌を作ってみたり、美術音楽文学問わずいろんな芸術家や作品に接して、その魅力をどんどんとこの身の上で体験して、感じるよう心がけています。
日々は常に驚きと刺激の連続。色んな人に知り合うことも多いし、美味しいものにも多々出会う。いろんな場所に行って、いつもと違う風景に接していると、自分を取り巻く世界が小さくならずに、どんどん豊かに広がって行くのを感じます。
こうして何とか活動をしていているのですが、やればやるほど学ぶ、創る、表現する、といったことが一つに繋がって行きます。形を限定するのが好きな日本人は、「~~でなければだめだ」と声高に言いますが、時代は刻一刻と変化し続けているのです。それに伴い表現の仕方は勿論の事、学び方も色々変わって良いのではないでしょうか。
現代人は和服を既に来ていませんが、日本人としての意識はちゃんと皆持っている。けっして形の問題ではないですね。形に拘るとかえって現代の社会とのギャップが生まれてしまいます。学び方も教え方もどんどんと変化すべきと私は思います。
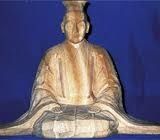 世阿弥
世阿弥
邦楽では「守・破・離」ということとがよく言われます。学び方の基本としては素晴らしいものだと思っていますが、それに囚われてもいけないと思っています。薩摩琵琶では、未だに生徒を自分の色に染めようとする先生もけっこう居ますが、私はそういう教え方には大反対です。プロとして生業にしている能や歌舞伎などの伝統芸能の先生ならまだしも、薩摩琵琶にはプロとして生業にしている人はほとんど居ません。正直なところ、「プロでもない人がいったい何を教えているのだろう??」と思います。私だったら、その道で食べてもいけないような状態では、とても人には教えられませんし、習うのならその道のプロに習いたい。
歌舞伎や能などの伝統芸のは文化そのものを教え、更に技も知識も教えるからこそ機能しているのです。だから所作一つにしてもちゃんと意味が判るようになるし、古典の知識も歴史も自然と身につく。決して技だけを教えている訳ではないのです。
残念な事ですが、薩摩琵琶では所作が出来ているなと思える人がほとんど居ません。「所作など大したことではない」と言い張る先生もいます。とんでもないことです。結局日本文化を何も判っていないとしか思えません。琵琶を弾く前にこういうところが出来て居なかったら、日本の音楽にはならない。歌舞伎は何が凄いかといえば、舞台に関わる全員が江戸の風情を身に付けているということですよ。文化そのものを教育しない限り、小手先の業だけを教えても何も伝承されないことは明らかでしょう。
能などの古典として洗練を経て成立し残っているようなものは、一度現代という視点をはずして、先ずは真似るというところから入るのは大事なことでしょう。しかし薩摩琵琶のように、流派というものが出来てまだ100年程で、現行の曲が大正や昭和に出来た曲という新しい芸能でしたら、今はどんどんと時代とともに変化していかなくてはいけない時期です。創っては壊すということを繰り返して、更に100年200年とやり尽くしてから初めて洗練が始まるのです。そこからは古典音楽としての深みと魅力が出てくるでしょうから、また学び方も変わる事でしょう。今はあらゆる曲が次々に作られ、色んな演奏家が出てきて、色んな学び方が乱立する百花繚乱状態であるくらいが好ましい。
伝統ものを学ぶ人には、何でもきちんと言われたようにやるのが良いと、優等生的に固くなる人がやたら多いですが、ロックもジャズも皆そんな風にお勉強していたら生まれ出て来なかったでしょう。ティーチャーズペットほど見苦しいものはないです。
一人づつ顔も姿も違うように、学び方も創り方も自分なりで何でも良いのです。60代70代の先生と20代の若者では良いと思うものや音色が違うのは当たり前なのです。
今、新ためて学ぶ、創る、演奏するということが私の中で展開し始めました。まあ年を重ねれば重ねるほどに、囚われからも離れ、自分らしくなってゆくのは良いことですが、私がこれまで何か引っかかっていた事がすんなりとほぐれてきたという気がしているのです。
このところ取り組んでいる琵琶唄の問題も一皮向けてきました。琵琶では「語り」と言い張る人が多いですが、往年の琵琶名人の演奏を聴くと、私には皆「うた」に聞こえます。唯一例外的に鶴田錦史の声は「語り」に聞こえますが、永田錦心や水藤錦嬢は「うた」だと感じます。今も琵琶で「語り」系の人は聴いた事がないですね。鶴田錦史が薩摩琵琶100年の歴史の中では異質なのかもしれません。音楽が良ければどんな形でも結構だと思いますが、私は「うた」を歌う人ではないし、さりとて「語る」人でもないので、やはり声を使うのなら、今までとは違う自分独自の声の使い方を創って行くしかないだろうと思ってます。
琵琶樂人倶楽部100回記念演奏会 尺八の田中黎山君と
そして「琵琶の音が聞きたい」という声を今年も沢山聞きました。私はこれが現代日本人の素直な意見ではないかと感じています。琵琶の演奏会に来たのだから琵琶の音色を聞きたいというのは当たり前。ろくに琵琶を弾かずに調子っぱずれのうなり声ばかり聞かされては、琵琶ファンが増えようがありません。また「琵琶って弾き語りでやるの?」という意見もしょっちゅう言われます。それだけ弾き語りでやるものという認識すらも現代日本人にはないのです。私自身もそうでした。単に琵琶という楽器を弾きたかったのです。
琵琶のお稽古をしている人だけが「薩摩琵琶はかくあるべき」と思っているのかもしれません。
ショウビジネス云々ということではなく、聞く人あっての音楽という部分は忘れてはいけませんね。神様でも人でも聴いてくれる人、聴かせる対象が居なくなったら、もう演奏する意味はなくなります。
若者には自由に学んで、新たな琵琶楽を創って行ってもらいたいものですね。

 こちらは先日のレコーディング風景。芝公園のサウンドシティ別館のスタジオでの録音でした。即興演奏ですので、15分のものを2本取りましたが、結局一本目が良いという事で、スリリングな演奏の方が採用となりました。
こちらは先日のレコーディング風景。芝公園のサウンドシティ別館のスタジオでの録音でした。即興演奏ですので、15分のものを2本取りましたが、結局一本目が良いという事で、スリリングな演奏の方が採用となりました。







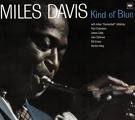




 次は劇団アドックの「月さびよ」。私は今回役者としても少し出演し、細川幽斎(藤考)というガラシャの義父の役をやらせていただきました。まあ二言三言なのですが、それでも慣れないことをやるのは緊張します。加えて二日目の公演には細川護煕さんがお見えになっていて、開演前に楽屋で色々とお話もしてくれたので、ご先祖様としてはとちる訳にもいかず、久々に良い汗をかきました。
次は劇団アドックの「月さびよ」。私は今回役者としても少し出演し、細川幽斎(藤考)というガラシャの義父の役をやらせていただきました。まあ二言三言なのですが、それでも慣れないことをやるのは緊張します。加えて二日目の公演には細川護煕さんがお見えになっていて、開演前に楽屋で色々とお話もしてくれたので、ご先祖様としてはとちる訳にもいかず、久々に良い汗をかきました。