森田童子さんが亡くなりましたね。私は熱狂的なファンというわけでもなかったのですが、あの歌声と独自の世界はしっかりと耳に焼き付いています。久しぶりに聴いてみたら、直球で若き日のあの頃に飛んでしまいました。
琵琶をやっている人にとっては、何だこれはと思うでしょう。普段から声を張り上げ、名文句でコブシを回しにまわして、お見事!なんて声がかかるような琵琶唄とは真逆な「うた」です。まだ尾崎豊のほうが歌手としては随分上手いので判ってくれるかもしれませんが、森田童子の「うた」は、琵琶人には耐え難いようなものかもしれません。
しかし私にはこの歌声が、そのまま響いてくるのです。歌詞もしっかり入ってきて、その世界がそのまま感じ取れる。もっと言えば言葉が聞き取れなくても、もうその世界に連れ去られるように自分の心が持っていかれるので、言葉を超えた世界が、そのまま聴いている自分の心の中に満ちてくるのです。

琵琶唄と比べること自体がナンセンスという方も多いでしょう。でも私は森田童子も尾崎豊も、BB・キングもロバート・プラントもジョン・レノンもボブ・ディランも、多感な少年時代から今迄ずっと聴いて生きてきたのです。30歳の頃には波多野睦美さんの声に触れて声楽が好きになり、今はオペラのLive veiwingもよく観に行って、つたない観劇記も書いています。それぞれ違うジャンルというのは簡単ですが、声を使ってうたっている以上、自分の中で琵琶唄とこれらを区別するわけにはいかないのです。
何時もこうした「うた」に触れると凄い勢いで心が震えてきます。そして同時に「琵琶唄は何も伝わらない、伝えられない」という想いも溢れ出てきます。現在の琵琶唄の内容はあまりに男尊女卑的だったり軍国主義的だったりして、今を生きる自分の感性がその内容を拒否してしまうのです。今時、忠義の心といわれてもね・・・。。
大体恋の歌が無いジャンルは、世界中探してもありえないと思えませんか?。それだけ明治から大正~昭和初期に成立した琵琶唄は軍国のイデオロギーに歪められ、日本人の心から生まれた「うた」になっていないのだと、私は思っています。
このブログではオペラの事をよく書きますが、オペラは観ていてとても楽しい。ただ森田童子の「うた」と違って、声という楽器の器楽演奏を聴いているといった方が近いですね。あの声に感激しているのであって、チェロやヴァイオリンの演奏を聴いているように聴いています。だから歌詞の内容にいちいち共感するというよりも、ざっくりと「うた」に描かれる人生の悲しみや喜びという普遍的な感性を、素晴らしい魅力的な声で身に迫ってうたってくれる、そんなところに感激するのです。
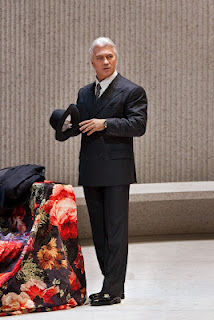
もうオペラを引退したナタリー・デセイと、私が大好きだった故ディミトリー・ホロフトフスキー
この二人の舞台は本当にわくわくして観たものです
その点、森田童子や尾崎豊は、声もさることながら歌詞がそのまま自分の体験とリンクして来ます。二人共に魅力のある声をしているのですが、いつしか声すらも忘れてその世界に浸ってしまう。オペラもこちらも魅力的なのですが、この違いはとても大きいですね。尾崎などたまに聞くと、そのまま自分の中学高校時代の景色や空気まで思い出します。自分があの頃抱えていた想いを、この人はそのまま歌ってくれていると感じるのです。
これは一つの、時代の共同幻想とも言えるかもしれませんが、ただそこに留まっていたら何てことない懐メロです。後の時代の人には全然伝わらない。軍国の琵琶唄と同じです。しかし語り継がれて行く「うた」は時代が変わっても共感を持って受け入れられるのです。
尾崎の「卒業」に歌われているように、未だに学校を卒業する時、窓ガラスを割って行くやつがいるというのですから、現代でも共感を持って聴かれているといううことでしょう。そこが時代の流行歌とは明らかに違うところ。森田童子も尾崎もジョンレノンもボブディランも皆、詩人であり、時代を超えて現代の人に明確な世界を今でも届けている。ジョンレノンの「Love&Peace」は世界の人が共感し語り継がれているのは皆様ご存知の通り。
これこそがジャンル関係なく「うた」というものの大きなポイントだと思っています。結局「うた」というものは、自分にとって共感できる内容のものかどうかということがとても重要な要素なのだと思います。その声質も大きいですし、うたわれる中身に対する共感があってこそ、時代も国も越えてゆくのです。共感があれば、歌の技術などあまり関係ないと思うのは私だけではないでしょう。
上手くても眼差しの先が「お上手」にある人と、自分が「うたうべき世界」に向いている人では天と地の差が出てしまう。音楽全般そうですが、特に「うた」は人の内面を隠せない。心の中がしっかりと出てきてしまう。肩書きを基準に物事を判断している人はそういう「うた」になる。お上手な歌手が得意になって歌い上げる「イマジン」や「ヘイジュード」など、もうどうあっても聴いていられないと思いませんか?。私には耐え難いものがあります。つまり見ている世界が違い過ぎるという事です。

ウズベキスタンのイルホム劇場にて、「まろばし」演奏中。指揮アルチョム・キム
私はあくまで琵琶のあの音色に感激して演奏家になったので、はじめから琵琶楽に於いて唄にはほとんど興味がありませんでした。残念ながら琵琶唄にはその張り上げてコブシを回すうたい方も歌詞の内容も、どこにも共感が感じられなかったのです。今でも永田錦心や鶴田錦史の「うた」や演奏を聴いても、私は別に感激はしません。ただ二人の活動からは「新らしい時代へ向かって走れ」という力強いメッセージだけが私に響いてきます。もし私が二人の「うた」に共感したのなら、私はうたっていたでしょう。
私はもう随分前から切った張ったの曲はやらないようにしています。そんなものを自分がやりたくないのです。一応琵琶樂のスタンダードとしてCDでは「壇ノ浦」等や「敦盛」等収録していますが、歌詞は随分と変えて、従来の琵琶歌とは違う形に曲自体を創り直しています。それにそれらの曲ももう、ほとんど演奏会でやらなくなっています。長い弾き語り自体、人前でやるのは年に数回あれば良い方です。歌詞の内容に大いに共感が出来、普遍の哲学を感じられる曲ならうたえますが、「鉢の木」や「乃木将軍」などは、たとえお仕事であっても、とてもうたえないですね。心が拒否してしまいます。何故ああいうものを舞台で出来るのか、私には音楽家として理解が及びません。
この動画の「僕たちの失敗」をきいて、私はつくづくうたう人ではないなと思いました。人それぞれ役割があるのです。やはり私は琵琶の音色の魅力をもっともっと聴いてもらいたいので、琵琶の音色が一番生きるような曲を、これからもどんどん創ってゆきます。ジェフ・ベックが「Blow by Blow」や「Wired」でうたを入れずギターの音色だけで音楽を確立し、それがのちのギターミュージックのスタンダードになったように、また武満さんの「エクリプス」や「ノヴェンバー・ステップス」が琵琶の器楽曲としてスタンダードになって行ったように、私もこの深い魅力に溢れた琵琶の音色で音楽を創りたい。声やうたを拒否している訳ではないですが、限られた人生「うた」にまで時間を使えるかどうか・・?。私の奏でる琵琶曲や琵琶の音色が「うた」のように次世代に語り継がれていったら嬉しいですね。でもきっとこれからは心の中から湧きあがる「うた」を創る琵琶人が出てくることでしょう。期待していますよ!!。

むしろこれから薩摩筑前の琵琶唄は出来上がって行くのではないでしょうか。逆に今を生きる日本人、そして次世代の人々に共感される「うた」を琵琶楽が創って行くことが出来なければ、琵琶楽は「うた」のジャンルとしては滅ぶしかないだろうとも思っています。
新たに出来上がった琵琶唄が何十年も経って、今私が森田童子や尾崎豊に涙するように、後の時代の人がそのうたわれている世界の事を、熱く語って共感してくれたら素敵ですね。今を生きる人の心の中から出てきた歌詞を、世界を、琵琶を弾きながらうたう人が出てきて欲しいです。
くしくも尾崎豊が4月25日、森田童子が4月24日に旅立っていきました。
語りつがれる「うた」は素晴らしい。





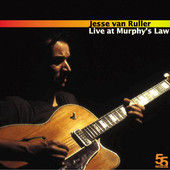



 今月は13日の水曜日の開催です。右の絵は琵琶樂人倶楽部の看板絵。鈴田郷さんというおばあちゃまが、大阪での公演の時に聴きに来てくれて、その時の私の姿を書いてくれた作品です。
今月は13日の水曜日の開催です。右の絵は琵琶樂人倶楽部の看板絵。鈴田郷さんというおばあちゃまが、大阪での公演の時に聴きに来てくれて、その時の私の姿を書いてくれた作品です。

 演奏会の後でいただいた絵
演奏会の後でいただいた絵








 今回の国立劇場で演奏した曲「胡絃乱聲」は、作曲家の平野一郎さんによるものでしたが、彼と色々話をしていて「これからようやく西洋音楽第一の偏狭な感性から脱し、日本人による日本独自の新しい音楽が生まれて来るんだ」ということを改めて確認しました。彼は洋楽のほうから、私は邦楽のほうから、このアプローチをやってきているという訳です。同じ視線を日本音楽の中に投げかける仲間が居るということは嬉しいですね。彼のこれからに期待したいです。
今回の国立劇場で演奏した曲「胡絃乱聲」は、作曲家の平野一郎さんによるものでしたが、彼と色々話をしていて「これからようやく西洋音楽第一の偏狭な感性から脱し、日本人による日本独自の新しい音楽が生まれて来るんだ」ということを改めて確認しました。彼は洋楽のほうから、私は邦楽のほうから、このアプローチをやってきているという訳です。同じ視線を日本音楽の中に投げかける仲間が居るということは嬉しいですね。彼のこれからに期待したいです。

 青梅宋建寺での演奏会「琵琶の調べ~紡ぐ響き」は無事終わりました。今回はまとめ役の笛奏者 長谷川美鈴さん以外は、パーカッション、ピアノ、ベースという洋楽器の方々と一緒だったのですが、メンバー皆さんフランクでとても楽しい演奏となりました。またスタッフの皆さんも地元愛に溢れた方々が実に素晴らしいサポートをしてくれて、お客様も本当に沢山いらしてくれて、手作り感のある素敵な演奏会となりました。是非また青梅で演奏会をやりたいですね。
青梅宋建寺での演奏会「琵琶の調べ~紡ぐ響き」は無事終わりました。今回はまとめ役の笛奏者 長谷川美鈴さん以外は、パーカッション、ピアノ、ベースという洋楽器の方々と一緒だったのですが、メンバー皆さんフランクでとても楽しい演奏となりました。またスタッフの皆さんも地元愛に溢れた方々が実に素晴らしいサポートをしてくれて、お客様も本当に沢山いらしてくれて、手作り感のある素敵な演奏会となりました。是非また青梅で演奏会をやりたいですね。

