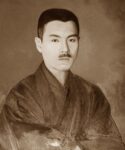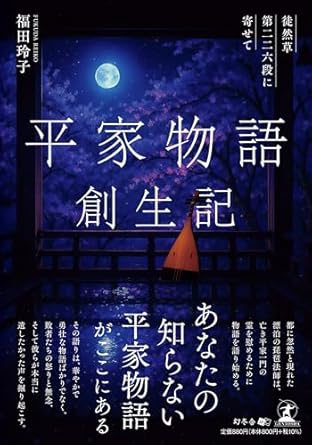ちょっとご無沙汰している間にすっかり秋の風情になってきましたね。嬉しい限りです。早く革ジャンを着れる季節になって欲しいものです。
私は、元々何か一筋、何とかバカみたいな人が好きではありません。確かに芸術家や一部の学者は常識を超えてしまっている所があって、一般の方から見ると○○バカみたいに見えるかと思いますが、芸術家達とゆっくり話してみると色んな分野に話が及び、一晩かけても話が尽きない程に面白い。私には一般の方々のほうが視野が狭く、常識に囚われていると感じます。
芸術系には、「是一筋」みたいな事を自ら売りにしているような人も良く見かけますが、格好からして何か特別感を誇示ような恰好をしている人も多く、私はあまり馴染めません。一人称で自分の世界のみで生きていて、自分に寄って来てなびいてくれる人だけを相手にしているような人とは全く話が出来ないです。言い方を変えると、そういう人は相手の話を聞く余裕がないのではないかと思います。自分と違う視点ややり方を持った人と意見を交わす事の出来ない人が本当に多過ぎる。他のものを受け入れ、他に視線を向けるキャパが無いのは、そのままその人の器を示しています。だからやっている事もその器のものしか出て来ない。筝は成りたくないですね。

私は元々あらゆる分野に視野が行き渡る人が好きなんですが、武道の達人も意外な事に精通している人が多いですね。まあ周りの事に視線を向けないようではすぐにやられてしまいますし、当たり前ではあるのですが、結局器の大きさがそのままその人の実力であり魅力だと思えて仕方ありません。 いつも書いているように宮本武蔵はその代表です。武蔵は実にあらゆるのはこのブログでも都度都度書いていますが、絵を描かせれば「枯木鳴鵙図」なんていう名作も遺していますし、仏像も彫れば五輪書のような深く鋭い文章も書く。剣以外の事でも色々と勉強していたんじゃないでしょうか。多分武蔵は世に言われているような天才タイプとはまた違うタイプだったのではないでしょうか。故に、色々と考え、実践してきた末にあの境地に至ったと私は思っています。佐々木小次郎は逆に当時考えられている剣の上手であったが故、それ迄の常識の上から抜け出せない人だったように思うのですが如何でしょう。

武蔵は遅刻して来たり、小舟の櫂を削りその太く長い木刀で戦ったり、その当時としては考えられないやり方を選択して勝利を得ています。心が常識の中にあると、立派でなくてはいけない、その時思える正統でなくてはいけないというバイアスが支配して、その他の世界が見えないものです。 現世に於いて天才と言われている人は、その時点に於いて天才なのであって、言い方を変えれば、既に引かれているレールの上に居るという事で、そこが弱点のように思います。素早く剣が振れる、素早く音が弾ける等というなものは、確かにずば抜けた上手であるかもしれませんが、そこがあるが為にその先の世界が見えない、考えつかないのではないでしょうか。現世では人より多少色んなものが解って、一般の人からすると優れているように思えるかもしれませんが、その先が見えて、現世の常識やルールとは全く違う発想をしているような本物の天才は、そう沢山は居るものではないと思っています。どんなものでも別の視点からすれば正義は悪になり、格好良いものが陳腐に映ったりするのは世の常です。だから広い視野と周りのものを把握する深い知性がある人が次世代スタンダードを創って行くのです。
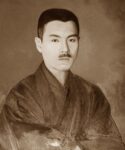
これは音楽家もそうで、なかなか常識やルールから離れられる人は居ません。永田錦心や宮城道雄が凄いのは、そういう当時の常識やルールの遥か上を行く次世代の発想をし、それを実現化・具現化した事です。皆ある程度上手になって名も知れるようになってくると、現世の中で立派な自分でありたいと思うのが通常ですが、そんな所に囚われている時点ですでに天才には程遠い。そんな想いに支配されていると、音楽家としての自分は居なくなって肩書やら評価が気になり、そちらに意識が行ってしまう。本来芸術はそういう俗な心を飛び越えてもっと人間の本質に迫るものであると、私は思うのですが、皆様はどうお考えでしょうか。
photo 新藤義久
私のような凡人は、とにかく小さなことに常に囚われます。実に弱い。だから私はなるべく自分を取り巻く環境に、囚われの原因になるようなものを置かないようにしています。流派や団体などの組織は勿論、小さなグループであっても常に自分のスタンスを感じながら付き合っています。
流派のような小さな枠に入って、そこに我が身をゆだねてしまうと、そのコミュニティーが全てになってしまい、そこに漂う価値観に支配され、そこを離れると何も出来なくなると想い込みがちです。自由にやりたいと思いながら、そんな心にがんじがらめになって留まっている人を何人も見ました。一旦固まった心はなかなか崩れません。流派も会社も正解ではないのです。ルールでもないのです。小さな村の優等生になっても、大きな都会に行けば誰も気にもかけてくれませんし見向きもされません。ちょっとばかり上手なものがあったとしても、大きな世界に行けばもっと凄い奴がわんさか居ます。大きな視野を持って、世の中と繋がる感性こそが音楽本来の魅力だと私は思います。

私は作曲の師である石井紘美先生から「実現可能な曲を書きなさい」と言われ、それ以来自分で作曲したものを弾くというスタイルでやって来ました。それを実現するためには自分の世界をしっかりと保ちながらも、自分を取り巻く社会や時代を感じる感性が無いと、作曲した所で、ただの独りよがりのオタク音楽になってしまいます。自分は世の中は全て繋がりの中で成り立っているという事を解ろうとしないで、がなり立てて主張していても、それはただの一人称の叫びでしかありません。一緒に創り上げるというアンサンブルという概念がない。
例えば好きな人にいくら「愛してる」と言っても二人の関係を築いて行こうという気持ちが無かったら、関係は成り立ちません。ただのストーカーです。音楽でも、メンバーに俺の思うようにやってくれという意識しか持てないような人は音楽を創れません。それが解らないままに一人称の世界に閉じこもって満足しているのはオタク以外の何物でもないのです。
琵琶や尺八などは独奏でやることが多いので、周りとのアンサンブルが出来ない人、やろうとしない人をよく見かけますが、今後日本の伝統芸能に試されているのは最後にはどれだけの器があるかという事だと思えてなりません。
やっと秋の風情になりましたね。
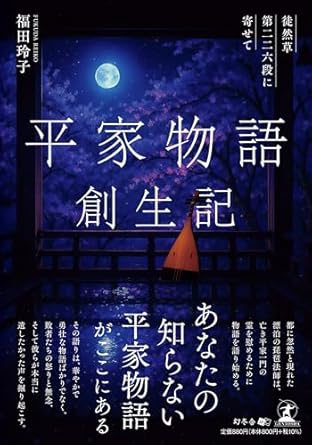
この秋は嬉しい動きがいくつかあります。先ずはここ何年かお付き合いのある作家の福田玲子さんが「平家物語創生記」という小説を幻冬舎から出しました。福田さんは若い頃、太宰治賞の次点に入るほどの実力で注目されていたのですが、その後事情で筆を置いていて、またここ5,6年前から作品を発表しはじめました。私は、福田さんが前作「新西行物語」を上梓した頃からのお付き合いなのですが、ここ数年は平家物語誕生の頃の事を生仏(平曲を最初に弾き語った人物)を主人公に描いてみたいという話をされていて、少しばかり私の知識等も交え、やり取りをさせてもらって来ました。生き生きとした生仏の姿を通して大きな時代の流れを感じる事が出来ます。是非お読みください。
エスター・ラムネックHP
他に、このところ海外の作曲家の方からいくつか連絡を頂いています。現在NY大学のエルター・ラムネックさん、メキシコシティー在住のアレハンドロ・コラビータさんとのトリオで音源を送りあって、即興的なサウンドコラージュのような作品を創っているのですが、いよいよ佳境に入ってきました。年明けには作品集として世に出すことが出来ると思います。乞うご期待!。 また先日はハンガリーのナジ・アコーシュさん、アメリカのマイク・ベルナスキーさんからも連絡があり、一緒に作品作りをしたいとの申し出を頂きました。皆さん電子音楽~現代音楽の専門なのですが、私が2002年にリリースした「MAROBASHI」に収録した石井紘美先生作曲の「HIMOROGI 1 」を聴いてくれているようです。この演奏はドイツのWergoレーベルとロンドンのNaxosレーベルから石井紘美作品集「Wind way」としてリリースされているアルバムに収録されていて、そちらで聴いてくれているようです。リリースが2005年位だったと思いますが、当時はネット配信も無かった時代ですので、電子音楽と琵琶という組み合わせは興味を引いた事と思います。
石井紘美「wind way」より 「HOMOROGI 1」
この「HIMOROGI 1」は私にとっては初めての海外公演の時(2003年)に演奏した曲で、ロンドンシティー大学での演奏会のライブ録音をそのまま収録したものです。石井先生は作曲の師であり、音楽や芸術に対する考え方や音楽家としての姿勢を教えてくれた方で、私の音楽家としての基礎は石井先生の教えで出来上がりました。だから先生の作品をロンドンで初演した時は、結構気合を入れてやりましたね。英語もしゃべれない私が、琵琶を担いでよくぞまあロンドンまで行って演奏して来たと褒めてやりたい位です。もう20年以上前の事ですが、あの体験が私をここまで導いてくれたように思っています。
他にも以前の仲間と、最近また活発にやり取りをはじめ、これから色々始まりそうで面白くなってきました。 先日の台湾文化センターでの講演・演奏もそうでしたが、色んな事が有機的に繋がり広がって、様々に展開して行くのはワクワクしますね。縁は単純な因果の繋がりではなく、輪のように網状になっていて、直接の因果とは思えないような所からも縁が繋がって行きますもう何かに「導かれている」としか思えません。この想いは年々強くなって行きます。
人間は社会の中で生きて行く以上、人と人とのつながりの中で営みをするしかないので、縁に導かれるのは当たり前ではあるのですが、それは自分でコントロールしているというよりも何かの「はからい」に導かれていると言えるのではないでしょうか。思えば琵琶奏者として活動をしてこれまでやって来たのは奇跡みたいなものです。自分で生きてきたつもりではありますが、今振り返ってみると、確かにここ迄導かれたと実感します。まあそれだけ私も年を取ったからこそ、そんな事を思うのだと思いますが、自分という小さな器の中で動いているより、自分の器の外のものがどんどん自分に関わって来て、自分では考えもつかないような展開になって行く。こんなワクワクして面白い事は無いのです。
先月の佐渡相川春日神社能舞台での創作能「良寛」公演 津村禮次郎先生と

頂いたご縁はじっくりと温めて、丁寧に繋げて来ました。長い時間で考えて行かないと何も始まりません。ゆっくりと良い形でお付き合いが出来て行くと、必ずと言って良い程、次なる展開が待っていますね。そんな様々な縁によって今ここに導かれてきたのです。だからこれからが楽しみなのです。
こうした縁や出逢いは運命という事なのでしょうね。哲学者のセネカは「運命は志ある者を導き、志の無き者を引きずって行く」と言っていますが、是非導かれる人生でありたいものです。
やっと朝晩少し涼しくなって体が楽になりました。私は本当に夏に弱いので、今年は難儀でしたね。

今年も良い仕事をさせてもらっていますが、小さなレクチャーやライブなどは少な目なので、その分作曲と、これ迄の作品の見直しをしています。独奏曲は良い感じのものが出来舞ましたが、デュオの作品はまだこれからという感じです。またいつもより時間があるのでレッスンも良くやるようになりました。ただ私は教室の看板を挙げている訳でもなく流派も名乗っていませんので、私の演奏が気に入ってどうしても教えて欲しいという人だけが集まって来ます。中にはもう舞台で活躍している人も何人か居て、レッスンも楽しくなってきました。
近江楽堂にて 笛の大浦典子さんと
私が教室の看板を上げないのは、自分があくまで舞台人として生きていたいので、稽古代の収入をあてにしているような形にしたくないからですね。門下生を集めて立派な風を気取っているお教室の先生には成りたくないのです。門下や配下を集め、○○流○○会等と体裁繕っていると、自分の音楽を自由にやって行くのが難しいという事を経験的に感じてもいましたので、私は常に一音楽家として生きて、習ってみたい人には私の出来る事を少し教えるというスタンスがちょうど良いように思います。会の名前があった方がいいという意見もありますので、年に一度だけ琵琶樂人倶楽部で、今勉強している方々に演奏してもらう時に「創心会」という名前でやっていますが、そんな程度で充分ではないかと思っています。
私にとって音楽活動するという事は、創造するという事です。自分で音楽を創り舞台で聴かせるのはロックやジャズでは当たり前ですし、琵琶だったら永田錦心も水藤錦穰も鶴田錦史も皆同じように自分のオリジナル作品を創り、それを舞台をやっていました。画家や文筆家が自分の創作したものを発表するのと同じです。あくまで作品を創り発表する事です。それ以外にはありません。したがって表面の上手さを売ろう聞かせようとして執心している人の気が私には判りません。お教室で習った「敦盛」を舞台でそのままやるなんて事は私には全く持って考えられませんね。
photo 新藤義久
 という具合なので、私の周りには、自然と何時ものスローガン「媚びない・群れない・寄りかからない」の精神を是とする人だけが集まって来てます。流派や組織、系統だの肩書をが気になるような人は、最初から私の所には来ないでしょう。私も手取り足取り教える事はしませんので、私の所に来ている人は皆、自分で課題を見つけてやってきますね。
という具合なので、私の周りには、自然と何時ものスローガン「媚びない・群れない・寄りかからない」の精神を是とする人だけが集まって来てます。流派や組織、系統だの肩書をが気になるような人は、最初から私の所には来ないでしょう。私も手取り足取り教える事はしませんので、私の所に来ている人は皆、自分で課題を見つけてやってきますね。
今の時代、先ずYoutubeを観てリサーチするでしょうし、私の作品を聴けば、私がどういうスタイルで演奏し、何を考え志向しているのか、そういう所も解るでしょう。私は来る人に、自分がこの30年程で経験したことを基に、音楽的な事の他、サワリの調整の仕方や、色んな場面での舞台の務め方、繊細な絹絃の扱い等、動画では見えない事を教えます。大体皆さん、曲の表面的な部分等は、教えなくとも動画を観て自分でコピーして来ますので、私はその先を教えているという訳です。
私は薩摩琵琶を古典音楽とは捉えていないので、薩摩琵琶の曲の形式等は教えません。私自身は錦心流で稽古を始めましたので、多少の形式やフレージングなどは習いましたが、それらは次に創るものの参考(踏み台)になった程度です。勿論教えて欲しいという事であれば、私の知る限りに於いて、少しレクチャーしていますが、流派のものを知りたい人は流派に行けばよいだけの事。琵琶を弾くのであったら、先ず何よりも日本の文化への理解考察が第一です。私は新たな人が来ると、最初に古今和歌集とその解説書(鈴木宏子先生のものが解り易く且つ中古でも安いので勧めています)を買うように言います。日本の文化を育んできた歴史や文化の変遷等、そういうものに興味の無い人はどうにも稽古は始められません。私が琵琶を始めた頃、琵琶の会などに行って先輩方々と話をしてみて、歴史や文学に詳しい人があまり居ないのにびっくりしました。私は琵琶の会なら、そこに集う琵琶人達は和歌の一つや二つさらさらと出てくるものだろうと思っていましたので、以外に思いましたが、今思えば、それがそのま琵琶樂の衰退を表していたという事ですね。
ゲンロンカフェに手能楽師の安田登先生と
とはいえ、いつも私のレッスンでは、お茶飲みながら2時間も3時間もかけてのんびりしゃべりながらやっているので、全く厳しくやる事は無いですが、撥弦楽器は基本的な技術は同じなので、撥のタッチ等の基本技術はしっかりと教えます。琵琶ではタッチ以上に左指の運指もとても大事で、様々な方法を経験して動かせるようにならないと予定調和の稽古した事しか弾けません。定番のものに安住し、旦那芸に陥って、音楽を創造することが出来なくなったら音楽家としては終わりです。
琵琶を学ぶことで自由に自分の世界を羽ばたかせるようになって欲しいものです。
今年の残暑はいつになく厳しいですね。毎年夏になるとクーラーの効いた部屋で「文明は素晴らしい」などと口にするのですが、そんな文明のなかでぬくぬくとしていると、更なる快適をもっと欲しがり、いつしかその「文明」に振り回され、野生などすっかり忘れ去って骨抜きになって行く自分の姿が見えて来るようです。何だか麻薬みたいなですね。
先日の台北フィル、イーストアジアミュージックサークルシンポジウムにて 於:台湾文化センター
以前の私は最先端でありたいという想いばかりが強く、30代の頃は琵琶樂をぶっ壊す(以前どこかの政治家が言っていたような)位の感じで、「絶対に俺にしか弾けないものを創るぞ」なんていうつっぱり具合でしたね。
しかし長いこと舞台を飛び回って、アルバムもそれなりにリリースしてくると、だんだん見えて来るものもあるものです。2015年辺りから、やっと自分の思い描く琵琶樂の形が具体的に作品となって来た事で、その頃から琵琶の音色のもっと奥の世界へと視点が向いて行きました。私は若い頃から(今でも)自給自足の暮らしに憧れるような部分が多分にあって、出来ればアーミッシュの村みたいな場所で暮らしたい位なのですが、それがここ10年位で音楽に於いても、原点への思考が加速してきたようです。少しづつ心に余裕が出て、本来の想いが表に出て来たのでしょうね。
鎌倉其中窯にて Photo 川瀬美香
ご存じのように薩摩琵琶は、まだ成立してから100年ちょっとの歴史しかありません。平安時代に確立していた樂琵琶に比べれば出来立てほやほやの新ジャンルです。だから古典でも何でもない大正昭和の軍国時代に作られた曲や形式に固執するなんて事は私にはナンセンス以外の何物でもありません。むしろこれから、そんな軍国時代の遺物を乗り越えて、薩摩琵琶本来の魅力を開拓する時代だと思っています。だからこそ新世代の薩摩琵琶を創り上げる為にも、その原点となる根源的な琵琶の音色や琵琶樂の根理というものを求めたいのです。この根理根源を忘れ、目の前のエンタテイメントに走ってしまったからこそ、琵琶楽や邦楽は衰退してしまったのかもしれません。
表面の形を追いかけていたのでは流行に流されるだけで、一事の賑やかし以上にはなりません。表面的な憧れで琵琶法師だの放浪芸だのという形を真似して喜んでいるようなものはただの物真似パフォーマンスだと思っています。過去の形に寄りかかるその精神が情けない。 常に移りゆく時代の中で変わる事無く続いている感性。その感性が「いいな」と思う日本の音色こそ求めたいのです。ステーキやワインも美味しいですが、風土がこの身体にもたらし、育ててくれた味覚や感性は、どんなに時代が変遷してもずっと同じく受け継がれて来ているのです。
Viの田澤明子先生と 琵琶樂人倶楽部にて
かつて日本は大陸の仏教や儒教そして雅楽等の文化を受け入れて、そこから日本独自の文化を形創って、独自の文化を打ち立てました。その日本文化発祥の経緯を見れば、現代、様々な問題は在れど、現状の日本に拘るあまり異文化を拒否するのは不自然です。現実の暮らしは洋服を着て珈琲を飲み、ベッドで寝ているのです。受け入れるものは受け入れ、そこからどうやって日本独自のスタイルを形創り、独自の文化を生み出して行くのかが問われていると私は思えてなりません。
アメカジを着て英語をしゃべって喜んでいるようなただの「かぶれ」親父状態で、異文化に飲み込まれるだけなのか、それとも色んなものを取り入れながら独自のものを創り上げて次世代へ新たな日本文化を創造し渡して行くのか。日本はずっと奈良平安の昔から後者をやって来たではないでしょうか。社会や生活の暮らしと共に、形は変化して当然なのです。でもその根源にある音色に対する感性は、味覚や感性と同様、この大地から沸き上がるり、受け継がれて来たものでありたいのです。過去の模倣に終始し、過去に寄りかかっている近視眼的な心では、次世代にこの音色は届けられないと思うのですが、如何でしょうか。
先週、佐渡にて公演してきました。今回は創作舞「良寛」、創作能「トキ」のプログラムで、私はもう10年近くやっている「良寛」の方で演奏して来ました。佐渡の公演では地謡も加わりかなり能仕立てになっていて、場所も能楽堂でしたので、いつもと違った感じで良い刺激を頂きました。
新潟日報記事 https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/676066
津村禮次郎先生、中村明日香さん、一噌幸弘さんらと
当日は薪能のスタイルでしたので、いわゆる野外公演状態。また絃が湿気を吸って、恐ろしい程にチューニングが落ちるのが本当に困りましたが、これも良い経験ですね。そして今回はメイン楽器として分解型薩摩琵琶を使いました。分解型もやっとこの所使えるようになってきて、これからどんどんと活躍してくれそうです。
佐渡は世阿弥が流された事によって能が根付いて行ったのですが、今回の舞台、相川地区の春日神社能舞台は佐渡の能楽発祥の地であり、一番最初に作られた能楽堂だそうです。こういう所で演奏出来るというのは本当に有難いですね。この御縁を大切にして行きたいと思います。
海がすぐそこという事もあって、前日には夕日の沈む頃に海辺に行って沈みゆく夕陽を眺めていました。1時間もしない内に夕陽が真っ赤になって沈んで行く様は本当に圧巻で、私のような者でも、何か大いなるものを感じずにはいられませんでしたね。
佐渡の夕陽
この地球の生命活動に抱かれている自分を感じられると、小さな日々の出来事などはあまり気にならなくなります。都会に生きていると大地や地球という生命の土台を考える事も無く、その中で命を与えられているという当たり前の事も感じることなく日々が過ぎて行きます。現代社会の一番の問題は、実はこの人間の生に対する感性の衰えではないでしょうか。もしかすると音楽や芸術というものは人間の根本や土台を改めて呼び覚ます生命装置なのかもしれません。世界中に歌や踊りの無い民族は居ないし、神話を持たない民族も存在しない事を思うと、音楽や芸術は人間と大地を結ぶ行為として、必然的に人間が生み出していったのかもしれないですね。神話などを読んでいると、そんな風に思えて仕方がありません。
太陽の動きには躍動的なエネルギーに満ち、日々が止まる事無く移り変わるという不変の法則があり、男性的な象徴ともいえる存在。一方月の満ち欠けは女性の身体活動そのもので、満月から新月迄の循環に生死の法則があると言われていますが、そういう自然の動きと我々は同期して、我々自身が自然の一部として生きているという事を現代人は忘れてしまいます。生と死を切り離し、生のみに執着している現代人は、結果的に生を自分という小さな器に閉じ込めて、死に向かう事だけを見ている。死があるからこそ生があり、その循環運動こそが自然の営みであるという自然法則を見失っているような気がします。また生死だけでなく正邪も善悪も、総てが内包されているこの地球の法則と姿を我々は今一度思い出す時なのかもしれません。佐渡の夕陽を見つめながら、そんな事を思いました。自分の存在の根本を見失しなえば、その意識は「生」や「個」という小さな牢獄の中に留まり、結果として小さな牢獄の中に発生する俗欲にかられ果てしなく争いを続けるループの中でうごめいてしまう。今大地を感じ、この地球と共に生きる方向に舵を切れるか。それとも個の欲を滾らせ、目の前の満足を突き進むか。その分岐点に来ているのかもしれません。コロナの数年間を経て人間にその選択を迫られているのだと私は感じています。
出雲崎から佐渡を見つめる場所にある良寛堂
来年再来年とこの美しい夕陽を私たちは観る事が出来るでしょうか。是非またこの風景に出逢いたいものです。
お知らせ
2019年にほ放送されたNHKeテレ「100分de名著 平家物語」の再放送があります。9月5日(金) 前1:00~2:40(=9/4(木)25:00~26:40)是非ご覧になってみてください