ちょっと御無沙汰していました。
ブログネタは沢山あったのですが、何しろ時間が無く振り回されていました。
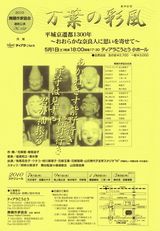
そんな中、5月1日にティアラこうとうでやった「万葉の彩風」は日舞・クラシックバレエ・モダンダンスの方々が一緒になって、万葉集をテーマに私の楽琵琶で踊るという、なかなか面白い会でした。残念ながら写真を撮る暇も無く紹介できませんでしたが、幻想的な感じの舞台で、まか不思議な空間が出現しました。
何時もお世話になっている雑賀淑子先生と日舞の花柳面先生の監修・演出で、共演もお馴じみの、かじかわまりこさんはじめ、ウタコさん、花柳面萌さんなど総勢10名の踊り手が舞台に舞いました。
出演者が集まって作り上げてゆく舞台というのは楽しいですね。是非是非またやってみたいです。
 photo MORI osamu
photo MORI osamu
私は大体週に1回程度演奏をしています。琵琶奏者としては多い方かもしれませんが、もっともっと舞台に立って演奏して行きたいです。
毎回演奏会は私にとって最大楽しみで、且つ最高に厳しい現場であるのですが、どの演奏会もあっという間に終わり、演奏の2時間ほどは瞬く間に過ぎ去っていきます。大舞台だろうが小さなサロンコンサートだろうが、終わったとたんに現実に戻り、あの舞台にそよぐ風はもう身には感じません。
それだけ舞台というのはどんな場所でも異次元空間なのだと思いますが、以前のように舞台の余韻に浸って酒を飲むというようなことはなくなりました。瞬時に時空を行き来するのが上手くなったのでしょうか。ちょっと寂しい気もします。

これは何時も写真を送ってくれる京都の森修さんの作品ですが、森さんの写真の中には永遠にゆったりと流れる風が常にそよいでいるかのようです。

私の音楽は聞く人の心の中にずっとそよいでいるのだろうか。あっという間に吹き渡り、過ぎ去っていってしまうのだろうか???
まあそれもまた良いのかもしれません。何時かまた風のように甦り聞いてくれた人の心にそよいでくれたら嬉しいです。
今日もまた風を求めて・・・・。
演奏会のお知らせ
15日に練馬高野台のグリーンテイルさんで小さなサロンコンサートをやります。もう足掛け5年ほど、年に2回づつ続けているもので、毎回違うゲストを迎えてやっています。
今回は若手尺八の俊英 田中黎山君。前回も尺八の中村仁樹君でしたので、前回お越しになった方もぜひ二人の個性の違いを楽しんで下さい。
若き才能は素晴らしいです!!
詳しくはHPのスケジュール欄をご覧下さい。
HP 現代邦楽の未来へ http://biwa-shiotaka.com/
先週、アンネゾフィームターのコンサートに行ってきました。30年に渡りヴァイオリン奏者として世界のトップを走り続け、今円熟の極みとも言われるムターに、行く前から期待が膨らむばかりでしたが、その期待を大きく上回るコンサートでした。演奏を聴きながら色々なことを思いました。
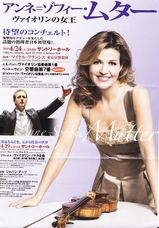
私と同じくらいの年だと思うのですが、相変わらず美しいですね。
プログラムのスタートはムターの弾き振りによるバッハのヴァイオリン協奏曲第1番。共演の東京交響楽団の弦パートがチューニングし終わり会場の照明が落ち、待ちに待ったムター女史が登場しました。
後光が差しているという表現がありますが、正にその姿は光り輝いて、目が釘づけになってしまいました。演奏はもちろんですが、音楽を聴きながらその姿を見続けていたら、これこそ、この姿こそ西洋クラシックなんだな、と思えてきました。
何世代にも渡って、ヨーロッパの地に生まれ育ち、その土地、社会に育まれた感性を身に付け、その文化の中で伝統を背負い生きている、そんな紛れも無い西洋人のヴァイオリニストという姿をしていました。我々とは全く違うのです。
日本でも江戸っ子といわれるには3世代以上江戸に住んでいる人、といわれますが、この日本の土壌、気候、社会やそこにある感性、生活、習慣からクラシック音楽は到底生まれない。
建築でも宗教でも哲学でも論理的で構築的に成り立っている西洋文化と、「南無阿弥陀仏と唱えていれば成仏する」というような、論理ではなく直感でものを計る日本の文化とでは大きく違うし、気候が違えば楽器も違うものが発達するのは当たり前です。
いくらちょっとばかりの技や知識を得たとしても、何百年という歴史を経て受け継がれ、育まれて来たものを、たかだか100年足らずの教育、それも本格的に教育されたのは50年にも満たない日本人がやろうとしても、物まねにしかならないのは当然なのです。日本の社会の中で生きていながら異文化をなぞっていてはいたしかたない。
しかし希望は満ちています。それは歴史が証明している。平安時代に輸入した大陸文化は、次の中世には日本の感性を土台にして、そこに輸入した技や理論・哲学を活用して、日本独自の文化・宗教を創り出した。クラシックでもジャズでももう異国の文化をなぞるような時代はもう終わり、創造の時代に入っている。そういう活動をしている人はいっぱいいるはずです。武満さんもその一人だったと思います。
この日最後に演奏したソフィア=グヴァイドゥリーナのヴァイオリン協奏曲はいわゆる現代音楽でしたが、こういうものは西洋の歴史の延長上としても解釈できるし、新しい視点で見ることもできる。こういう現代音楽といわれている分野には、大いに活路があるのではないでしょうか。
どこの国でもそうですが、日本人特有の感性は本当に素晴らしい。他には類を見ないものです。だったらその感性を土台に西洋音楽の技と理論を活用してゆく事は大いに可能性があると思います。
クラシック、ジャズの次のジャンルは日本から世界に発信して行きたい。亜流ではない新しいジャンル。日本にはそれを創り出す原動力=西洋には無い感性と技がある。そのジャンルが世界標準になるようなそんな音楽を創ってゆきたい、やりたいと思いました。
以前、日記で紹介した、私のジャズギターの師匠 潮先郁男先生の芸暦60周年記念ライブが、新宿ピットインでありました。
私は一緒に通っていた30年来の盟友A氏と共に、最前列で堪能してきました。

これは来場者に配られたお土産。Thank youと書かれたカードに先生の名前が入ったピックが添えられてました。
憎いね~~。
この日の編成はヴォーカルと先生のギター、それにサイドギターという本当にシンプルなもの。それというのも潮先先生の真骨頂は伴奏にこそあるのです。
以前にも書きましたが、先生は本当に梅花のような人。結してフロントに立って華やかに弾きまくる事はありませんが、その存在は周りから熱く信頼されています。どの世界でも派手にデビューしてあっという間に消えてなくなる人が多い中、ずっとジャズ界の一線で脇にいながらも静かに、確実に演奏し続けてきたのです。
流れるようなラインで実に気の効いたコードワーク。常に相手を乗せてスウィングするリズム。これが先生のスタイルなのです。だからヴォーカルとギターというこの上ないシンプルな編成は一番先生の魅力が出る絶好のお膳立てという訳です。
曲も通好みのスタンダードばかり。A氏と共に聞いていてなんとも幸せな気分になりました。そしてプロのギタリストを目指して仲間達と切磋琢磨していた10代のあの頃の空気が甦ってきて、懐かしいやら嬉しいやら・・・・、お互いの顔があの頃に戻っていました。
あの頃はお金はもちろんのこと、服も物も何にも持っていませんでしたが、先生の演奏を聴いていて、先生の所に通いながら自分は何と素敵な時間を過ごすことが出来たんだろう、とあらためて思い、ちょっと目頭が熱くなってしまいました。

この日は三味線の和完さんも駆けつけてくれたんですが、彼もまた潮先先生の所でギターを習っていたんです。
写真はちょっとボケ気味ですが、左から私、ヴォーカルのさがゆきさん、先生、卒業生のギタリスト竹中さん、和完さん。
先生の生徒さんはのべ600人ほどいるそうで、プロのギタリストとして活躍している人も沢山います。私も一応、潮先スクール卒業生の端くれなのですが、ギタリストにならなかった私にも先生は何時も声をかけてくれて、CDを出すたびにお祝いの電話をくれて激励を頂いてます。
師匠というのは本当にありがたいですね。結して優等生でもなく、こんな不義理の徒にも、遠くから暖かい眼差しを注いでくれます。
私にも2,3人の生徒がいますが、私は果たして自分の師匠達のように、弟子をずっと見守ってあげるほどの器に成れるだろうか・・・・。
帰りにA氏と話しながら「素晴らしい先生に就いて習うことが出来、幸せだったね」とお互いうなづきあって、我々の中で潮先先生という存在がいかに大きかったか、思い知りました。
先生、是非芸暦70周年もやって下さいよ。今度は琵琶を持って駆けつけます。
京都の仕事が二週に渡っていて、途中三日程空いていたので、大阪に行って楽しんできました。
 こちらは寝屋川沿いの桜、昨日から公開された造幣局の桜通り抜けもこの辺りですが、桜の宮から天満橋までこれでもか、というくらい延々と桜が咲いていて春を満喫してきました。観光客もほとんどいなくて、ゆっくりと見ることが出来、かなりリフレッシュできました。
こちらは寝屋川沿いの桜、昨日から公開された造幣局の桜通り抜けもこの辺りですが、桜の宮から天満橋までこれでもか、というくらい延々と桜が咲いていて春を満喫してきました。観光客もほとんどいなくて、ゆっくりと見ることが出来、かなりリフレッシュできました。
川沿いは両側に桜が咲いていて、正に桜のトンネルのよう。
大阪では中崎町のコモンカフェという所で、ダンスのヤンジャさんとライブをやったのですが、今までお世話になったギャラリーなどをゆったりと巡って楽しんできました。
さて、コモンカフェではPlaypotという古楽器のグループとのジョイントでした。

■playpot
西村喜子 viola da gamba
城坂さおり viola da gamba
倉本高弘 viola da gamba
若尾久美 violin
佐々木真知子 cello
もともと古楽は好きで、波多野睦美さんの歌やつのだたかしさんのリュートなど追っかけのように聞きに行っていた時期があったのですが、この所ごぶさたしていました。
この日はPlaypotの方々と一緒に演奏する事は無かったですが、久しぶりに西洋古楽器の音をゆっくりと聞くことが出来うれしかったです。

チェロの佐々木さんが琵琶を弾くの図
ダンスのヤンジャさんとはもう結構長い付き合いです。大阪や横浜で一緒にやってきましたが、何にも打ち合わせしなくても不思議とぴったり来るんです。


ヤンジャさんのスタイルは舞踏ともちょっと違うし、コンテンポラリーダンスでもない。彼女独自のものです。体も感性もしなやかで柔らかい、常に自由な風に包まれているような感じ、それがヤンジャさんのダンスです。
そのヤンジャさんと私が組むきっかけを作ってくれたのが、このゴマメことまっちゃんです。(with パートナーのふうちゃん)
 今回久しぶりにゆっくり飲めて嬉しかったです。
今回久しぶりにゆっくり飲めて嬉しかったです。
大阪には写真家の赤阪友昭さんや、海月文庫、芦屋画廊、自然館のたかりんさん、語りの竹崎さんなどなど友人がいっぱいいて、何時行っても楽しい街。今回も毎日楽しい日々を過ごしました。
この後また京都に行ったのですが、京都は京都でまた素敵な所。祇園の街も良い感じでした。
ぜひまた関西を満喫したいです。
皆様御無沙汰してます。暫く京都・大阪に行っていました。
京都南禅寺界隈の清流亭というところで、演奏してきたのですが、見事なまでの桜・桜・桜の10日間でした。清流亭はまもなく重要文化財に指定されるそうで、それはそれは素敵な場所でした。

この桜の下が演奏会場

そしてこんな感じで夜桜ライトアップの元で演奏会をしてきました。
今回は本当に桜の満開に合わせての演奏会だったのですが、前半の第一週目はソメイヨシノが満開、第二週目は枝垂桜が満開という具合で、京都中に人が溢れ、凄い賑わいでした。
初日はかなり寒く、手も声もこごえてしまいましたが、後は大分あたたかくなりました。ただ中継が入り、その寒い時に撮られてしまったので、ちょっと残念。
 良い感じでしょ?photo 森修
良い感じでしょ?photo 森修
今回は第一週目が横笛の阿部慶子さんと、第二週目が筝の小笠原沙慧さんと夫々組んで、計6日間に渡る演奏でした。最終日は雨だったので室内での演奏で、部屋から庭を眺めて頂く感じで演奏してきました。雨に濡れる庭の感じも美しかったです。
ちょっと写真が小さいですが、こちらが小笠原沙慧さん。お疲れ様でした。 
清流亭はちょうど野村別邸の前なので、とても静かで落ち着いた雰囲気でした。この会は呉服問屋さん主催の会だったので、ご招待の人しか入れなかったのですが、道行く人が結構覗いていてバチバチ写真を撮られてしまいました。
笛の阿部慶子さんとコンビを組んで、もう10年ほど経ちますが、一緒にやり始めた頃、「桜満開の所で演奏会をやりたいね」と言っていたのがそのまま実現しました。この時期の京都は街中が桜だらけで、高瀬川沿いの木屋町通りや白川通りなどは見事な咲きっぷりでした。夜11時近くなっても人通りが絶えず、まさに宴も盛りといった感じでした。
今回は桜の時期の演奏会としてはこれ以上のシチュエーションはちょっと考えられないほどに素敵な演奏会でした。精鋭的な芸術の場ももちろん素敵ですが、こうしたしゃれた演奏会もたまには良いものです。たん熊のお料理も美味しかったです。
今回のおまけ。お世話になっている呉服屋さんが贔屓にしている真筝姉さん。祇園でばったり会いました。ちょっと大人可愛い美人の芸妓さんです。

さて第一週目が終わり、大阪に移り、これまた面白いライブをやってきました。こちらは次にまた書きます。
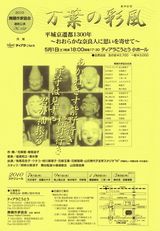
 photo MORI osamu
photo MORI osamu





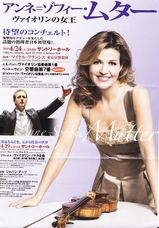


 こちらは寝屋川沿いの桜、昨日から公開された造幣局の桜通り抜けもこの辺りですが、桜の宮から天満橋までこれでもか、というくらい延々と桜が咲いていて春を満喫してきました。観光客もほとんどいなくて、ゆっくりと見ることが出来、かなりリフレッシュできました。
こちらは寝屋川沿いの桜、昨日から公開された造幣局の桜通り抜けもこの辺りですが、桜の宮から天満橋までこれでもか、というくらい延々と桜が咲いていて春を満喫してきました。観光客もほとんどいなくて、ゆっくりと見ることが出来、かなりリフレッシュできました。




 今回久しぶりにゆっくり飲めて嬉しかったです。
今回久しぶりにゆっくり飲めて嬉しかったです。





