私は多感な高校生の時にJazzにどっぷりと浸かっていたので、どうしてもJazzの匂いがする所に惹かれてしまいます。もうこれは拭いきれないですね。

琵琶なぞをやっていると珍しいのか、色々な人に声をかけられ、多くの人に出会うのですが、その人がJazzを通り越して来た人なのか、そうでないのかは直ぐに判ってしまいます。別にどちらが良いという訳では無いのですが、同じ匂いのようなものには何かしらのシンパシーを感じてしまうのです。
Jazzが身に染み付いている人もいれば、Jazzを纏っているだけの人もいます。音楽家でもアドリブを聞いていてJazzを感じない人もいます。あの時代特有の匂いなのかもしれませんが、若い人にはJazzの匂いのする人は少ないですね。
今夜はフラメンコピアニストの安藤紀子さんのソロライブに行ってきたのですが、彼女の演奏にもJazzを感じてしまいました。彼女は元々Jazzから入ったそうで、フラメンコを演奏してもその奥底にJazzがあるんでしょうね。

こちらが安藤さん。今日はちょっとおすまし気味ですね。
安藤さんの演奏は「情」という言葉が似合います。フラメンコはよく情熱という言葉で表現されますが、彼女の演奏には情熱だけでなく、叙情、詩情という言葉もまた似合います。もちろんフラメンコの人ですので、喜怒哀楽がはっきりしていて、さっぱりさわやかなお人柄なんですが、その演奏からはJazzを基本とした叙情・詩情性がいつでも聞こえてくるのです。
今夜はオープニングの「こきりこ節」から彼女の「情」が溢れていました。まるでリッチーバイラークが弾いているかのような詩情溢れる繊細で抜群のアレンジメント。安藤さんにはぴったりの選曲と演奏でした。
二部に弾いた「Turn out the star」 とハンコックの曲(曲名失念)、それからオリジナルの「再生」「さくら」はどれも詩情・叙情に溢れ、音楽に身を預けることが出来ました。
今でも感じるのですが、やはりJazzは私の原点だと思います。作曲に関してもクラシックではなくJazzの手法が根底にあるし、演奏に関しても感性は伝統邦楽のそれですが、演奏方法はJazzが基本になっています。実際の演奏はロックテイストに溢れているようですが、これはまあ性格ですね。やはり自分が浸っていられるのはJazzなのです。まあそこが私の帰る港ですね。
安藤さんの演奏を聴いていたら、リッチーバイラークの「Sunday song」に全身を震わせ、エバンスの「People」で癒され、コルトレーンの「Impressions」に熱狂し、ドルフィーの「Last date」にとち狂い、マイルスの「Kind of Blue」に洗脳されていた「あの頃」が甦ってきました。嬉しいでも悲しいでもないのですが、眼がウルウルとするこの感じは久しぶりに味わいました。
そんな安藤さんと10月、11月に共演することとなりました。楽しみです。
いよいよ今年も秋の演奏会シーズンが始まった。このタイトルで書くお知らせも2005年から続いてきて、毎年年を追うごとにどんどん忙しくなってきている上に、シーズンの始まりが早くなってきているというのが嬉しい。という訳で、ざっとご紹介。
9月
4日 21世紀トリオライブ at ヴェルカント(昼の部と夕方の部の2回)
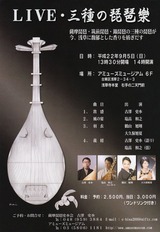
5日 三種の琵琶楽~二天門ライブ
薩摩四弦・五弦・筑前の三流派による演奏
15日 琵琶樂人倶楽部
「平家琵琶と楽琵琶~妙なる平安・
鎌倉の調べ―その秘曲と秘伝について」
24日 京都御苑内 白雲神社
「日露音楽交流協会主催演奏会」ロシアの音楽家との演奏
26日 阿佐ヶ谷地域区民センター 邦楽演奏会「古典が今、語りだす」」
筝と笛とのトリオによる演奏

10月
1日 お江戸日本橋亭「ええ語ろう会」
3日 北鎌倉古陶美術館 Reflections Live
龍笛と楽琵琶のデュオ 久々です
11日 岡山倉敷 慈眼院 元高野山大学密教学
教授 越智淳仁先生の晋山式で記念演奏
13日 琵琶樂人倶楽部「現代の合奏曲」
15日 音楽堂anoano 「遭遇前夜 フラメンコピアノ y 琵琶」
フラメンコピアノの安藤紀子さんとのデュオ
17日 東京 座高円寺2 Casablanca Night
ダラブッカ奏者 Domnatiさんが主催するオムニバス企画
20日 埼玉熊谷 常光院 十三夜法要琵琶演奏会
23日 和歌山 子供の寺 童楽寺
「琵琶を楽しもう-尺八と共に at 童楽寺」
24日 和歌山 第五回塩高和之琵琶演奏会於高野山」
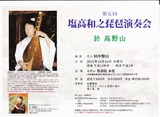
高野山公演も今年で5回目となりました。
今年は尺八の田中黎山君をゲストに、しっとりと語ってきます。
25日 和歌山 高野山大学琵琶演奏会(学生向け)
27日 兵庫 西宮高校音楽科特別授業(学生向け)
シタールの田中峰彦さんと音楽科の生徒達とセッション
11月からは
・津田ホール 21世紀トリオ大演奏会
・大分能楽堂 福原百桂さん、福原みち子さんと共演
・京都清流亭 楽琵琶と龍笛の大浦典子さんとのデュオでよる三日間
・新宿ウルガ フリージャズのドラマー大沼兄貴と
ロックギターはりやさんとのトリオ
・ギャラリー蒼での2デイズライブ ゲスト尺八田中黎山君
・AVANCE 芸大作曲科 福士則夫門下の作品発表会
郡司敦作新初演
・近江楽堂「創心会」
・フラメンコピアノの安藤紀子さん、ダンスの渡邊倫子さんと
公園通りクラシックスでのライブ
・ハクジュホール
・渋谷伝承館 21世紀トリオ
という具合にまだまだ延々と続いてゆきます。こちらはまたあらためてUPします。
昨年はシルクロードツアーでてんぱってましたが、この秋もかなり気合の秋となりそうです。乞うご期待!!ぜひぜひお越しくださいませ。
先日陶芸家 佐藤三津江さんの「江の京窯」が主催する Bon appe 亭がそば処 道心で開催されました。

この方が佐藤三津江さん。私が勝手にファンだと公言しているのですが、江の京の窯開きの時も私が演奏させていただきました。お孫さんもいるとは思えないこの笑顔!!
江の京HP http://www.adachi.ne.jp/users/k-miyako/
佐藤さんの主催するこのBon Appe亭は、食と器を楽しんでもらうコラボレーションの会なのですが、これまでにも色々な料理と共演してきたようです。今回は蕎麦とのタッグですので色々と工夫を凝らした作品が並びました。今回の器の写真が無いのが残念です。ぜひ上記の江の京HPをご覧になって下さい。

こちらは佐藤さんの作品。佐藤さんはオブジェ作品がメインなのですが、生活雑貨の中にもアートを取り入れることをテーマにしているので、お皿でも器でも彼女らしいセンスが光っています。この土瓶型のランプも良い感じだし、左の三つ足の作品は、オブジェにも雑器にも色々なシリーズに出てくる彼女独自のスタイルです。
今回私はお囃子隊。最初の景気付けに「壇ノ浦」をやりました。景気付けに壇ノ浦は無いだろう?とも思いましたが、琵琶といえばやっぱり・・・というわけでやらせて頂きました。盛り上がったかな???

会場となった道心では、これまでにも琵琶のライブなど何度もやってブログでも紹介してきましたが、何しろ蕎麦が旨いです。こだわってやっているあんちゃんが一人でがんばっています。


ちょっとピンボケですが、「楽」と書かれた箸置きを頂きました。
音楽でも美術でも「それだけ」というのではなく、色々なものと関わり、色んな視点で鑑賞し、楽しむ事は世界を豊かにします。最近は古典邦楽の世界も表面的な技ばかりに目が行って、上手に壇ノ浦は弾けるけど、平家物語の事は良く知らない、なんて輩も増えてきました。個人の自由とはいえ、もっと豊かな感性と視点が欲しいですね。
佐藤さんとはこれからも色々な形でコラボして行きたいです。
そしてこの日は私の仲間で、フラメンコピアニストの安藤紀子さんも駆けつけてくれて、お手伝いしてくれました。

佐藤さんといい、安藤さんといい、皆さん自分の道を進んでいる方は格好良いですね。
負けられません!!
さて、9月からはまた秋の演奏会シーズンです。今年も目いっぱい演奏して回りますので、ご期待下さい。
ちょっと御無沙汰していました。
毎年夏のこの時期は、高野山公演の御挨拶の為、関西方面をうろうろとしているのですが、今年は尼崎で語りの竹崎利信さんと「二人界」というコンビで小さな公演をしましたので、その公演をはさんでうろついてきました。

この方が竹崎さん。まんま坊さんですが、もう直ぐ本当のお坊さんになる為に修行に入るとのことです。
今回は宮沢賢治の「二十六夜」を二人でやりました。色々と至らぬ点もあり反省しきりですが、何かを作ってゆくというのは楽しいものです。以前関わった劇団アドックでも劇団員皆で芝居を作り上げてゆく様が本当に素敵でした。これからもゆっくりとしたペースで充実した良い作品を作ってゆきたいです。
今回の旅は先ず大阪を経由して和歌山から入りました。
大阪では何時もお世話になっている、老舗の喫茶店 心斎橋麓鳴館に寄って名物のカレーを食べて、ママとゆっくりおしゃべりして高野山公演のチラシを置いてゆくのが毎年の恒例。
その後は和歌山へ。和歌山ではマネージャーのO氏と共に、今回高野山で共演する尺八の田中君の家まで行き、田中君と和歌山ラーメンの老舗で腹を満たし、鉄分たっぷりの花山温泉に浸かって来ました。それから尼崎に移り、上記の「二人界」をやって、その後は京都奈良をぶらぶらと・・・。
実は来月、京都御所の直ぐ横、つまり御苑内の白雲神社で日露音楽交流協会主催の演奏会があり、私が日本代表??で演奏しますので、その打ち合わせを宮司さんとしてきました。

ここは琵琶の名手 藤原師長を祭ってあるところで、もちろん弁天様がいます。師長は妙音天といわれ、芸能者がさかんに奉納している所なんです。
その後は御苑内をぶらぶらと


左は二月堂から見た奈良の町、右は春日大社のはずれ「ささやきの小道」
こんな感じで丸々一週間気分の赴くままに関西をうろついて参りました。
何をして過ごそうと時はただ淡々と過ぎて行くというものです。充実感は必要ですが、仕事をして成果を挙げて・・・・という充実感だけでは疲れてしまいますね。
何ら仕事も成果も挙げていないかもしれないけれど、ゆったりとした落ち着いた気分は、体に栄養が満ちてゆくように心にも満ちて行きます。
PS:京都で最高に美味しいイタリアンの店を見つけました。元フレンチを修行したシェフがやっている小さな店なんですが、とても上品で、素材の味が生きている。オリーブオイルがこんなに美味しいか、と思ったくらい美味しかったです。今まで食べた中で間違いなくベスト1!!
「The House of HATA」お勧めです。
先日、寶先生の葬儀も終わり、何だか実感も沸かないまま、またいつものあわただしい日常に放り込まれ、日々が過ぎてゆきます。
残された我々はお腹もすくし、喉も渇く。死という厳粛な場面に相対しても、日々の現実から離れる事が出来ません。
 photo MORI Osamu
photo MORI Osamu
父の時もそうだった。父は演奏会の当日、正に演奏しているその瞬間に息を引き取ったので、死に目にも会えず、もうバタバタしているうちに、実感が沸く暇も無く、直ぐに演奏会やらツアーやらが始まってしまった事が思い出されます。
こうして現実は進んでゆくのですね。仏教では愛憎に捉われずに生きるべし、と説いているのですが、現実に生きる我々は、愛憎云々はもちろんの事、もっと目の前の生活が迫っていて、なかなか悲しみに浸る事すら難しいのが現実です。一歩進んで二歩下がりながらも前に向かって歩くしかないですね。
昨日は定例の琵琶樂人倶楽部「SPレコードコンサート~往年の琵琶名人を聞く」がありました。

 この蓄音機は米ヴィクター社製ヴィクトローラ・クレデンザ。昔は家一件分くらいの値段がしたという名器です。手回しでねじを巻き上げ、盤面1枚ごとに針を変えて聞く、まさにアナログの極地。ノイズも多いし、音も小さいけれど、そこからは生々しいほどの音楽が流れていました。今のように録音した部分を繋いだり、エコーをかけたり加工は全く出来ない。まさしく一発勝負という当時の録音現場では、演奏者も本当に実力のある人でなければ務まらなかったでしょう。
この蓄音機は米ヴィクター社製ヴィクトローラ・クレデンザ。昔は家一件分くらいの値段がしたという名器です。手回しでねじを巻き上げ、盤面1枚ごとに針を変えて聞く、まさにアナログの極地。ノイズも多いし、音も小さいけれど、そこからは生々しいほどの音楽が流れていました。今のように録音した部分を繋いだり、エコーをかけたり加工は全く出来ない。まさしく一発勝負という当時の録音現場では、演奏者も本当に実力のある人でなければ務まらなかったでしょう。

これはヴィオロンにあるものと同型のもの。
昨日かけたSP盤からは夫々の演奏家が目いっぱいの技量で張り切っている音が聞こえ、その姿が想像できました。でもやっぱり技術に凝っている演奏よりも、一番古いラッパ録音で録音された永田錦心先生のシンプルな演奏の方が、かえって溢れ出るようなものを感じました。目先の技量を避けて、その想いを内面に秘めてゆくような形は日本人にはぐっくと来るんでしょうね。
寶先生も、SP時代の名人達も、そうした先人が残してくれたものを心に刻んで、胸に秘めて、次の時代を淡々と生きて行く、それが私の役割なんだと、静かに想う日々でした。






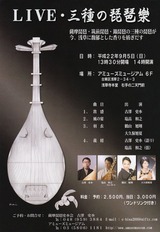

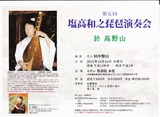












 この蓄音機は米ヴィクター社製ヴィクトローラ・クレデンザ。昔は家一件分くらいの値段がしたという名器です。手回しでねじを巻き上げ、盤面1枚ごとに針を変えて聞く、まさにアナログの極地。ノイズも多いし、音も小さいけれど、そこからは生々しいほどの音楽が流れていました。今のように録音した部分を繋いだり、エコーをかけたり加工は全く出来ない。まさしく一発勝負という当時の録音現場では、演奏者も本当に実力のある人でなければ務まらなかったでしょう。
この蓄音機は米ヴィクター社製ヴィクトローラ・クレデンザ。昔は家一件分くらいの値段がしたという名器です。手回しでねじを巻き上げ、盤面1枚ごとに針を変えて聞く、まさにアナログの極地。ノイズも多いし、音も小さいけれど、そこからは生々しいほどの音楽が流れていました。今のように録音した部分を繋いだり、エコーをかけたり加工は全く出来ない。まさしく一発勝負という当時の録音現場では、演奏者も本当に実力のある人でなければ務まらなかったでしょう。