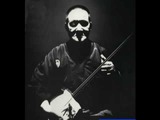世の中、「普通」ということが一番ややこしい。
 これはシルクロードのとある地域の写真ですが、人間の見聞やら常識からすると、自然界の姿はどこへ行っても驚きの連続です。つまり普通だの常識などというものは、所詮人間の考え出した一定の視点でしか無いということです。とすれば、本来人間のあるべき姿とは、社会的常識などの中には無い、と見ても良いかも知れません。
これはシルクロードのとある地域の写真ですが、人間の見聞やら常識からすると、自然界の姿はどこへ行っても驚きの連続です。つまり普通だの常識などというものは、所詮人間の考え出した一定の視点でしか無いということです。とすれば、本来人間のあるべき姿とは、社会的常識などの中には無い、と見ても良いかも知れません。
先週は夏の定例、琵琶樂人倶楽部SPレコードコンサートでした。電気を使わず、手でゼンマイを回して聞くSPの音は、今の耳からすると確かにノイズは多いのですが、何とも生々しい演奏者の姿が浮かび上がってきます。
この名器クレデンザから出てくる音は、今の我々の技術文明がいかに幻想であるかを教えてくれます。そう「ノイズが無いのが良い音」という現代人の常識を覆してくれるのです。毎回せっせと録音した音源のノイズを消したりしてCDを作っている私は、クレデンザを聴く度に納得してしまいます。
こうした現代の世に蔓延する普通=常識を越える音の世界に接することは、私にとって、ともすると凝り固まってしまう自分の感性を解放ししてゆくよい機会なのです。常識のベールを取り払い、存在の根本を認識させてくれるということは、芸術の一番の力なのかも知れませんね。
そしてこういう会には、独自の感性で動き回る仲間がいつも集います。
 右はいつもの古澤さん。左は超感性の三味線語り部 早乙女和完さん。他にも色々な方が今回も来てくれました。
右はいつもの古澤さん。左は超感性の三味線語り部 早乙女和完さん。他にも色々な方が今回も来てくれました。
現在邦楽界がとてつもなく低迷しているのは、邦楽界だけにしか通用しない「普通という常識」に囚われているからに他なりません。精神的解放の無いものからは何も生まれないし、時代とも離れて行くばかり。懐古趣味で成り立っているようなものが、長く持たないのは世の常というものです。しかしそんな中でも面白い連中が少しは居るのです。そういう人と連携と取っていきたいですね。
何事もそうですが、万人受けを意識し過ぎてしまうと、毒も魅力も薄まっってしまいます。それでは一過性の流行になるのがせいぜい。どんなに個性的なものでも売れるものは売れる。逆にどんなに売れているものでも、それを嫌いな人もいっぱい居る。
個性とは本来備わったものなので、奇をてらっていない限り、本人に魅力と器が備わっていれば、その素直な感性の発露は、何かしらの形で世に浸透して行くものだと思っています。でなけりゃ私に仕事が来るはずはない!
日本人のよく使う「普通」という哲学は世界には通用しません。もちろん邦楽界の「普通」はもうどこへ行っても通用しません。皆それが解っていながら、目に見えない「普通」「常識」に囚われている。日本人らしいと言えばそれまでですが、その中からは次世代の音楽はもう生まれないと思うのは私だけではないと思います。私は「とことん自分自身になりきろう」と日々思っています。それが私にとっての「普通」なのです。
昨日、ケイタケイさんの「二つの麦畑」という作品を観てきました。私はこれまで、「かもめ」や昨年ブログに書いた「走る女」など、ケイさんの独舞の舞台ばかり観ていたのですが、今回初めて群舞による作品を観ました。

メンバーはもちろんケイさん率いるムーヴィングアース・オリエンタスフィアの面々です。
ケイさんの舞台はいつも、その場では正直なんだか判らないという感じがするのですが、時間が経つと「こういうことだったのか」、「こういう意味があったのか」とじわじわ感じてきます。そのダンスもいわゆるモダンダンスやバレエのような洗練とは対極にあるようなもので、ダンスという概念を超えています。
私は常々、「舞台は身を晒け出す所」と言っていますが、ケイさんの舞台は、正に嘘偽りの無い自分自身を晒し、そこから表現へ向かうような純粋さを感じます。だから観ているときは内容が良く把握できていなくても、何となく惹きつけられてしまうのです。今回も観終わった後、知人達と色々と話をしながら、舞台が語る意味を噛みしめていました。
![Jimi+Hendrix[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2011/08/0ef71492-s.jpg)

ケイさんの舞台を観ていても、そこには特有の型のようなものは感じません。それに比べ、音楽はどんなジャンルでも一つの定型というものがあります。民族音楽はもちろんのこと、ロックでもジャズでもクラシックでもその定型があるからこそ、ロックはロックとして、ジャズはジャズとして感じるところがあるのです。そして、そのもう一つ先にはそれぞれに特有な「におい」のようなものもしっかりとあります。聴衆はその定型とにおいに強烈に惹きつけられるのです。
一時期、現代音楽の分野では、演奏家の身体性・肉体性を廃するというものが流行っていましたが、結局続きませんでした。やはり音楽には、肉体性がつきものであり、その肉体性の背景には、歴史や宗教・哲学・生活・習慣等の要素が不可欠なのです。
各ジャンル特有の定型もにおいも無くなると、それはもう音楽では無く、音響やサウンドデザインというものになって行きます。もちろんそれも一つの表現と言えますが、無機質なだけの音の塊になるのは否めません。
メシアンは音が色彩となって見える、といわれましたが、結局その色彩を感じる感性も肉体的であり、またその背景にも、その人の負った歴史や宗教・文化が大きく関わっているのです。だから肉体性の無い無機質な音は、すでに「音楽」では無いのです。

かつての人類は雷の音に畏敬の念を感じ、風の音に神性を感じ生きていました。世の中にあるもの全てに生命があるとすれば、当然人間の作り出した音楽にも、大自然が発する音同様に、生きた鼓動が脈打っているはずです。
ケイさんの舞台にはダンスとしての定型は感じませんが、そこにはどうにもならない、拭いきれない肉体というものがいつもあります。そして今回も強烈な「におい」が立ちこめていました。農耕民族特有の「におい」と言っても良いかもしれません。自身を舞台で晒せば晒すほど、自分が背負っているものが出てくるのは当然。その当然を観せているように思いました。
私のやっている音楽には歴然とした定型があります。私は音楽に定型は必要だと思うのですが、型に寄りかからず、そこに日本人としての「におい」、そして個としての「におい」をも感じさせるような、音を出して行きたいものです。

和楽器 ブログランキングへ
ただいま、6枚目となるCDを作っています。
私は舞台に出て演奏したり、レコーディングしたり、作曲したりすることは、面白くてしょうがないですが、自分の録音したものを聞いて編集したりすることは、本当に苦手なんです。まあそれは地獄の攻め苦と言ってもいいくらいで、こればっかりは毎回の大ストレスです。
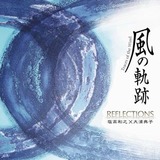 これがただ今作っている作品。9月末の発売です。デザインに関しては、有能なデザイナーに恵まれたので、ストレスは無いのですが、セルフプロデュース故、自分の録音したものを、何度も何度も聞いてテイクを選別し、時に細かな編集もしなければならない。エンジニアさんも大変だろうが、自分の弾いたものを粗探しするのは、かなりつらいものがあります。
これがただ今作っている作品。9月末の発売です。デザインに関しては、有能なデザイナーに恵まれたので、ストレスは無いのですが、セルフプロデュース故、自分の録音したものを、何度も何度も聞いてテイクを選別し、時に細かな編集もしなければならない。エンジニアさんも大変だろうが、自分の弾いたものを粗探しするのは、かなりつらいものがあります。
録音した作品をどのように配し、全体を構成して行くべきか。エコーをかけるべきか、生音で行くべきか、イコライザーをかけるべきか、毎度毎度色々と悩むわけです。今回も、曲そのものをカットすすることを、決断しなければならなかった・・・。
もちろんコンセプトはしっかり持って録音に望むのですが、アルバム全体を作り上げて行く段階で、やればやるほど様々な要因が「生まれいずる」のです。
自分は何をすべきなのか、自分とは何者だ、自分の存在理由は何なのだ・・・。有島武郎とまで行かなくても、多くの事を自分に問いかける。それが私にとって、CD制作というものです。ほんま修行ですわ。

こちらは今回の宣伝用フライヤー。写真は昨年の京都での演奏会の時のものです。今回は楽琵琶のCDですので、こんな楽人装束の写真を採用しました。雅楽をやる時は、こういう堅い衣装も良いのですが、普段はReflectionsのオリジナル作品をやる時がほとんどですので、何か衣装もオリジナルで作りたいと思ってます。一寸シルクロードを感じさせるような雰囲気で・・・。良いアイデアある方はぜひ教えて下さい。


人間どんなことでもそうなのですが、どこを目指しているか、何を考えているか、そこで全く出てくるものが変わっていきます。同じ技術でも平和利用するか、軍事利用するかで、結果が正反対になるように、音楽でも一番大事なのは、何を感じ、何を想って、何を考えているか。そこに尽きるのです。悟りの窓の前に座って、何を想うのか。それで、その人の音楽は決まるといっても過言ではないのです。
しかしそんな事はすっかり忘れてしまって、上手に弾くことや、真面目にお稽古して、流派の優等生や大物になる事に夢中になってしまう。これは音楽とはまた別次元の問題なのですが、それが優先してしまう例が多いですね。
そして、そういった本人にしかない感性を作り上げるのは、自分の故郷の記憶だったり、色々な人との出会いだったり、多くの芸術に触れて得られる感動だったりする訳です。私は毎日富士山を見て育ちました。川も海も近くにあり、雪の全く降らない所で育った事が、私という音楽家を作り上げる重要な要素 なのです。 
和楽器 ブログランキングへ
先週の金曜日から今週火曜日までの五日間は、我が町 阿佐ヶ谷の七夕祭り。毎年この時期は地元でライブをやるのですが、今年は金土と二日間やってきました。


商店街は凄い人出で、歩けないほど。
金曜日は毎年やっているシェ・ルーで弾き語りライブ。土曜日はこのブログでもおなじみの蕎麦処 道心でライブをやってきました。
残念ながら写真を撮っている暇が無かったのですが、道心では先日亡くなった香川一朝さんも吹いてもらった場所なので、演奏しながら一朝さんの音色を想い出しました。
 今の若手が使っている楽器は、同じ尺八といえども、楽器自体がかなり進化していて、音量もバランスも昔のものとはずいぶん違います。加えて皆しのぎを削るように精進していますので、音には力がみなぎっていて、もちろんびっくりするようなハイテクニック。皆さん個性はそれぞれですが、とにかくパワフルな演奏が現代尺八の特徴です。
今の若手が使っている楽器は、同じ尺八といえども、楽器自体がかなり進化していて、音量もバランスも昔のものとはずいぶん違います。加えて皆しのぎを削るように精進していますので、音には力がみなぎっていて、もちろんびっくりするようなハイテクニック。皆さん個性はそれぞれですが、とにかくパワフルな演奏が現代尺八の特徴です。
それと比べると一朝さんの尺八は常に淡々と、静かに演奏するのが持ち味。ちょうど前回まで書いていた木田と竹山の三味線の違いのようです。
太い弦を張り、たたきながら大きな音でパワフルに押しまくる木田のスタイルは正に、今の若手尺八のそれと共通します。一方、一朝さんのスタイルは、竹山のように一見地味ですが、その音色は豊かで、月の光のように静やかに、ゆったりと響いて来ます。
若手でも本曲を熱心に勉強している人もいますが、みなさんやはりパワフルですね。横山勝也先生の影響もあるのでしょうが、一朝さんは横山門下でありながら、パワーに寄りかからない、独自の本曲のあり方を提示したと思います。今日はライブをやりながら、私の記憶の中の一朝さんの音色がまざまざと蘇ってきました。
一朝さんの音色は、音が出ているというより、空間に満ちているようでした。一緒に演奏している頃は、時に頼りなく感じた時もありましたが、今、若手の連中と一緒にやってみて、漂うような、満ちるようなあの音色が、いかに魅力的で素晴らしいものだったか、今更ながら実感出来たのです。

仲間たちと一朝さんの満ちる音について話しましたが、そういう演奏をするには、やはり年季が要るとのこと。当たり前ですね。それを私は今頃になって感じられるようになったのという訳です。本当に情けないですね。いったい何を聞いていたんだ・・・・。

一朝さんのあの淡い月の輝きのような音色はもう響くことはありませんが、きっと若手の連中は次の時代の音色を響かせてくれることだろう、としみじみと想った夏の夜でした。

和楽器 ブログランキングへ
前回のブログで高橋竹山のことを書いたら、結構色々な方からメッセージを頂きました。皆さんやっぱり竹山には関心が高いんですね。
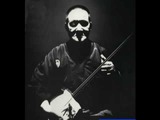
私が竹山贔屓なのには、何かしら自分と共通するところを感じるからです。もちろん私は竹山のような、壮絶な生き方はしていませんし、竹山から比べれば甘っちょろいもいいところなのですが、私も琵琶を始めた頃は、関西のギャラリーやサロン、古本屋さんや、ブティック等々、ライブが出来そうな所を片っ端から回り、月に10本15本と一人で小さなライブをやっていました。
流派には形だけ居ましたが、曲もオリジナルでやっていましたし、弾き方も歌い方も自分で作り出していったので、何となく竹山と似たものを勝手に感じてしまうんです。
私ははこんな具合で活動を開始したので、肩書きの付くような所や、大きな劇場には当然のように無縁で、やれ何とか先生だの、何とか流だの、何とか賞だのというような、いわゆる「邦楽人」とは未だにあまり付き合いがありません。ライブから始めた仲間でも、ある程度の年齢になると受賞歴やら名取やらと肩書き、看板を挙げてそれなりの体裁を繕って先生になりたがる人も多いですが、私はそういう人達とは基本的にタイプが違うのです。
前にもちょっと書きましたが、竹山と同時代には木田林松栄という名人も居ましたが、木田と竹山は、性格も演奏も、何から何まで全く正反対でした。木田はばっちりと組織を作り、弟子をいつも何人も引き連れ、何百万もする三味線を見せびらかして自慢して・・・。まあそれだけ親分肌で面倒見の良い人だったのでしょう。琵琶でしたら、鶴田先生がよく似ていますね。しかし私は、芸はともかく、そういう俗物的な所が、どうも肌に合わないのです。
大きな音で派手なはったりをかまして、ショウビジネスとして、民謡を組織化してやっていた木田と、晩年まで温泉場を回ったりして、あくまで己の音とスタイルを貫いた竹山。良くも悪くもこの差がすべて二人の音色に出ているように思います。

これは竹山の像だそうですが、この表情を見ていると、彼がどれだけ愛されたか判りますね。
そして竹山の素晴らしいところは、最初に歌と三味線を習って、その後三味線に専念したことです。旅の途中に喉を痛めてしまってから、歌うのをやめたそうですが、歌を自分で歌っていた経験があったからこそ、あの絶妙な歌付けが出来、更に三味線に専念していたからこそ、あれだけの歌付け、そして曲弾きが出来たと言えると思います。歌も三味線も両方追いかけていたら無理だったでしょう。
薩摩琵琶や筑前琵琶は常に弾き語りでやりますが、やはり両方をやるとどちらかがおろそかになるものです。どちらかに専念していたら、名人と言われる歌い手も、弾き手ももっと世に出たかもしれない、と思いますね。
永田錦心は新たな感性で、次世代スタンダードとも言えるスタイルを築いたという点で素晴らしい功績がありましたが、弾く方は大したことは出来なかった。雨宮薫水や榎本芝水も、歌の技巧はそれなりにあったけれども、弾く方は通り一遍の平凡なものでしかなかった。今、冷静に見て、琵琶の世界で両方を評価されるのは、水藤錦穣・鶴田錦史くらいだと思います。これからはどうなって行くんでしょうね・・・・。

竹山は弾く事に専念したことで、あの即興曲「岩木」も生まれ、新たな時代を私たちに見せる事が出来たのでしょう。またショウビジネスに寄りかからず、お金を儲けることや、有名ななることにも頓着無かったからこそ、あのスタイルが築けたことと思います。
音楽をやっていれば、誰でも有名にもなりたいし、売れたいと思うもの。竹山にももちろんあったでしょう。でも竹山はそれよりも自分の人生をまっとうに生きたいという気持ちの方が強かった事と思います。上昇志向や自己顕示欲が人一倍強く、ショウビジネスとして活動していった木田とは、その人生も大きく違いました。
自分の音をどこまでも求め、己の分を知り、まっとうに活動し、生きて行く。これらは竹山を通して改めて感じたことであり、私の指針です。

蕩々と広がる雲のように、ゆったりと確実に己の生を歩みたいですね。

和楽器 ブログランキングへ
 これはシルクロードのとある地域の写真ですが、人間の見聞やら常識からすると、自然界の姿はどこへ行っても驚きの連続です。つまり普通だの常識などというものは、所詮人間の考え出した一定の視点でしか無いということです。とすれば、本来人間のあるべき姿とは、社会的常識などの中には無い、と見ても良いかも知れません。
これはシルクロードのとある地域の写真ですが、人間の見聞やら常識からすると、自然界の姿はどこへ行っても驚きの連続です。つまり普通だの常識などというものは、所詮人間の考え出した一定の視点でしか無いということです。とすれば、本来人間のあるべき姿とは、社会的常識などの中には無い、と見ても良いかも知れません。
 右はいつもの古澤さん。左は超感性の三味線語り部 早乙女和完さん。他にも色々な方が今回も来てくれました。
右はいつもの古澤さん。左は超感性の三味線語り部 早乙女和完さん。他にも色々な方が今回も来てくれました。




![Jimi+Hendrix[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2011/08/0ef71492-s.jpg)


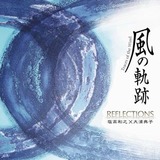 これがただ今作っている作品。9月末の発売です。デザインに関しては、有能なデザイナーに恵まれたので、ストレスは無いのですが、セルフプロデュース故、自分の録音したものを、何度も何度も聞いてテイクを選別し、時に細かな編集もしなければならない。エンジニアさんも大変だろうが、自分の弾いたものを粗探しするのは、かなりつらいものがあります。
これがただ今作っている作品。9月末の発売です。デザインに関しては、有能なデザイナーに恵まれたので、ストレスは無いのですが、セルフプロデュース故、自分の録音したものを、何度も何度も聞いてテイクを選別し、時に細かな編集もしなければならない。エンジニアさんも大変だろうが、自分の弾いたものを粗探しするのは、かなりつらいものがあります。





 今の若手が使っている楽器は、同じ尺八といえども、楽器自体がかなり進化していて、音量もバランスも昔のものとはずいぶん違います。加えて皆しのぎを削るように精進していますので、音には力がみなぎっていて、もちろんびっくりするようなハイテクニック。皆さん個性はそれぞれですが、とにかくパワフルな演奏が現代尺八の特徴です。
今の若手が使っている楽器は、同じ尺八といえども、楽器自体がかなり進化していて、音量もバランスも昔のものとはずいぶん違います。加えて皆しのぎを削るように精進していますので、音には力がみなぎっていて、もちろんびっくりするようなハイテクニック。皆さん個性はそれぞれですが、とにかくパワフルな演奏が現代尺八の特徴です。