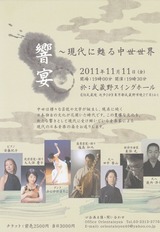邦楽と五線譜というのは、およそ水と油、というのが一般的な見方で、琵琶人にも五線譜を使うことに反対する人が多いです。その気持ちはとてもよく判るのですが、五線譜というものは、様々な情報が書いてあってとても便利。邦楽に於いて五線譜を嫌う人は、そもそも五線譜の捉え方が問題なのです。私はそれを長年訴えてきているのですが、なかなか伝わりません。「五線譜イコール洋楽ではない」これを何とか判って欲しいと思っているのですが・・・。
 雅楽譜
雅楽譜
五線譜は、ご存じの通りクラシックの記譜法ですが、20世紀ジャズの時代になると、五線譜に対する接し方が大きく変わってきます。クラシックでは「ド」と書いてあれば、絶対ドだし、ドミソと書いてあればその通りに演奏しますが、ジャズでは譜面を基にして、自分で音を変化させたりフェイクさせたりして、あくまで自分の考えで表現をします。五線譜はあくまでツールでしかないのです。まあメモ書きのような感じとでも言えば良いでしょうか。
日本はクラシック式の教育を導入したので、ドと書いてあれば、正確なドを弾かなければならないと思い込み、尺八にフルートのようなキーをつけたり、ドレミ調弦のお箏を作ったり、と涙ぐましい改良してきたのですが、それはやっぱり邦楽としてはおかしい。
だからこそ、今でも五線譜に対して強力な反発があるのだと思います。特に子供の頃ピアノやってました、ギター弾いてました、という人は「五線譜はこう弾くべき」という事をクラシック式に洗脳されているので、実にやっかいですね。どうしても一度思い込んだものを解放できない。もっと柔らかく、「ド」と書いてあっても、ドのあたりの音を弾けばいい位に思えればよいのですが、そうはいかない。何度話をしても判らない人が多いですね。
右の写真はオークラウロです。ちょっとわかりにくいが、尺八にクラリネットのようなキーが付いているもので、一時期は結構使われたそうです。
五線譜をジャズ式に捉え、譜面の先に自分の音楽を見て、五線譜を単なるツールと考えると、五線譜は大変便利な機能満載のものになります。五線譜の絶対音程を基本に邦楽器を考えるのでなく、あくまでコミュニケーションツールとして考える。そうすれば、従来のクラシック式のやり方に囚われることは一切無いでしょう。大体クラシックでも五線譜に何でも書き表せるなんて事はなく、皆さんそこから考えて考えて「音楽」を紡ぎ出しているのです。楽譜に書かれている通りに弾いて終わりなんて事はありえないのです。この辺も「楽譜に書いている事を弾いているだけ」なんて具合に、邦楽の人は誤解してますね。あくまで譜面の先に広がる音楽を表現しているのです。
 これは、今度発売したCDの中の曲の譜面。こういう風に、必要とあれば五線譜と明治に出来た琵琶譜を混ぜて書けば良いのです。
これは、今度発売したCDの中の曲の譜面。こういう風に、必要とあれば五線譜と明治に出来た琵琶譜を混ぜて書けば良いのです。
あくまで出て来る音楽の為に譜面はあるのであって、五線譜だろうが琵琶譜だろうが、関係ないのです。素晴らしい音楽であればいいのです。
しかし日本人は本当に本当に本当に舶来コンプレックスが根強く、「そんなこと言っても琵琶は弾けないことがいっぱいあるんですよ」という人も多いですね。よく考えて欲しい。ピアノだって音は伸ばせないし、ヴィブラートすらかけられない。つまりこういう発言をしてしまうのは、「ギターのように、ピアノのように」という具合に、自然と洋楽器を基本という風に感じているからです。ピアノはそんな制約の中で、あれだけ素晴らしい音楽を奏でているのに、琵琶弾く人は「琵琶では無理」という。あれだけ素晴らしい音色と表現力があるのに・・・残念でなりません。こういう硬直した頭はいつになったらほぐれるのでしょうか。若い方が、皆こうやって洗脳されるかのように感性を狭められてゆく姿を見る度に悲しくなります。まあそれがその人の感性の限界かもしれませんが・・・・。
ピアノで指が届かないような譜面を書く作曲家は勉強不足の半人前。同じように五線譜だろうが何だろうが、琵琶で弾けないような譜面を持ってくる作曲家は同じく勉強不足でしかありません。私はどんなベテラン作曲家の作品でも、具合の悪い所があればどんどんと突き返します。それにはちゃんと理由を説明しなければ、相手だって納得しない。全体の構成、琵琶の構造等、色んな事をちゃんと見渡して、作曲家が「確かにあなたの言う通り」と思ってくれればどんどん良い作品になって行きます。
2度3度は当たり前、10回以上突き返したこともあります。演奏家と作曲家は主従ではなく、一緒になってやっていけば良いのです。その為にはこちらにもそれなりの知識、見識、理論を持っていなければいけません。そういう勉強も演奏家に必要なのです。特に琵琶のような特殊とされる楽器の演奏家は、その特殊さを現代の作曲家に説明するだけのものを持っていなければ良い作品は生まれて来ません。そういう勉強はしたくないという人はお稽古で習った曲を楽しんでいれば良いだけのこと。
作曲家とコミュニケーションを取るための共通言語として五線譜を使い、こちらも初見で大体読めれば、曲全体を把握できるし、対等に話が出来るのですが、こちらが中途半端にしか理解できないのでは、どうしても作曲家が主人になってしまいます。こちらに対等の知識があれば、逆に琵琶という専門知識を持っているこちらの方に歩み寄ってくるというもの。
五線譜を自由に使えるようになると、箏や尺八など他の邦楽器とすぐに合奏が出来ます。日本では楽器それぞれに譜面が違うので、やはり国内においても共通言語が必要なのです。
スタジオなどでは勿論五線譜を使うのですが、スタジオに入って、録音が終わり帰るまで、せいぜい30分ほど。それだけプロの現場では五線譜を自在に読めて、且つ音楽として表現出来るスキルが必須条件になっているのです。
 何も洋風にやる事が目的ではありません。邦楽をやれば良いのです。琵琶を琵琶らしく弾けば良いだけの事。
何も洋風にやる事が目的ではありません。邦楽をやれば良いのです。琵琶を琵琶らしく弾けば良いだけの事。
もっとグローバルに琵琶の魅力を聞いて欲しいのなら、色々な人と音楽を分かち合いたいのなら、そんな希望を抱いている人なら、五線譜を自由に使おう。そしてプロで食べて行きたいのなら、初見で読めるようにしよう。只それだけなのですが・・・。プロとしてのスキルを磨くという事を邦楽家はやりませんね。残念ですが・・・。
プロは限られた時間の中でクォリティーの高いものをやらなければならないので、気持ちさえあれば通じ合える、なんて悠長なことは言ってられないのです。
ぜひ頭を柔らかくして、固定概念を捨てて、もっと琵琶が、邦楽器が、そして邦楽という音楽が活躍できる場を演奏家みんなで増やしていきたい。
さて、明日から関西ツアーだ。気合い入れて行こう!!
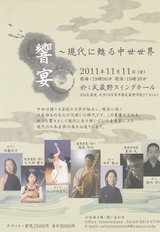

 光悦寺
光悦寺 今月(11月1日)の悟りの窓
今月(11月1日)の悟りの窓




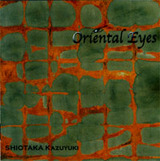 はなかったですね。レーベルもジャズのレーベルだったので、自分の音楽を思う形で世に出すことが出来、本当にただただ嬉しかったという記憶しかありません。沖至、坂田明、小山章太、詩人の白石かずこ、ジャズチェロの翠川敬基・・・こんな凄い音楽家が集うレーベルだったので、今までやってきたジャズがより進化し、私のオリジナルの音楽が、やっと形になり世に現れた、そんな想いでいっぱいでした。若さゆえの稚拙さも多々ありますが、今でもこのCDはお気に入りです。
はなかったですね。レーベルもジャズのレーベルだったので、自分の音楽を思う形で世に出すことが出来、本当にただただ嬉しかったという記憶しかありません。沖至、坂田明、小山章太、詩人の白石かずこ、ジャズチェロの翠川敬基・・・こんな凄い音楽家が集うレーベルだったので、今までやってきたジャズがより進化し、私のオリジナルの音楽が、やっと形になり世に現れた、そんな想いでいっぱいでした。若さゆえの稚拙さも多々ありますが、今でもこのCDはお気に入りです。
 雅楽譜
雅楽譜
 これは、今度発売したCDの中の曲の譜面。こういう風に、必要とあれば五線譜と明治に出来た琵琶譜を混ぜて書けば良いのです。
これは、今度発売したCDの中の曲の譜面。こういう風に、必要とあれば五線譜と明治に出来た琵琶譜を混ぜて書けば良いのです。 何も洋風にやる事が目的ではありません。邦楽をやれば良いのです。琵琶を琵琶らしく弾けば良いだけの事。
何も洋風にやる事が目的ではありません。邦楽をやれば良いのです。琵琶を琵琶らしく弾けば良いだけの事。
 いますが、近頃は関係者以外の人達がわんさか押し寄せているのです。
いますが、近頃は関係者以外の人達がわんさか押し寄せているのです。 今までのものをそのままやっているだけなのですが、雅楽は周りを取り巻く環境がしっかりしているのです。だから凄い集客力があるのです!。そして、最初から最後まで舞台を構成するノウハウが、伝統的に備わっていることも確かな事です。
今までのものをそのままやっているだけなのですが、雅楽は周りを取り巻く環境がしっかりしているのです。だから凄い集客力があるのです!。そして、最初から最後まで舞台を構成するノウハウが、伝統的に備わっていることも確かな事です。
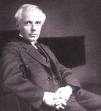 私は自分の器以上には成れませんが、この器でやれるところまでやっていきたい。高いギャラも一流のプロの条件ですが、それ以上に後々までも残って行くような音楽を作り、演奏して、内容充実でやりたいものです。
私は自分の器以上には成れませんが、この器でやれるところまでやっていきたい。高いギャラも一流のプロの条件ですが、それ以上に後々までも残って行くような音楽を作り、演奏して、内容充実でやりたいものです。
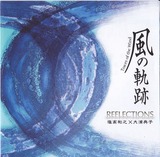 おかげさまで、今回の「風の軌跡」はとても好評を頂いています。自分でも自信作と言えるものが出来上がったので、これからは、この音楽を今までやってきたものと合わせ、どう展開して行くか、これが私の今後の活動となると思います。
おかげさまで、今回の「風の軌跡」はとても好評を頂いています。自分でも自信作と言えるものが出来上がったので、これからは、この音楽を今までやってきたものと合わせ、どう展開して行くか、これが私の今後の活動となると思います。 だから古曲でも新曲でも、常に生き生きした、魅力ある曲として聴衆に聞こえていかなければならない。やっている人が自分の内で感じていても意味は無い。聴衆が感じなければ、消えて行くだけなのです。
だから古曲でも新曲でも、常に生き生きした、魅力ある曲として聴衆に聞こえていかなければならない。やっている人が自分の内で感じていても意味は無い。聴衆が感じなければ、消えて行くだけなのです。