この所ようやく動きが活発になってきました。世に琵琶奏者なんてものはそう居ないので、昔から「三歩歩くと人と知り合う」という感じだったのですが、今年も長い春休みを経て、やっと調子が出てきました。老若男女関係なく、お酒がなくてもコーヒー一杯で盛り上がれるのが私の特徴なので、とにかく人にいっぱい出会うのです。
 演奏の面でも、これから色々なジャンルの方と御一緒出来そうです。ロック・ジャズ・クラシックなど心の広~い方々と演奏出来るのは嬉しいです。琵琶で良かった!!
演奏の面でも、これから色々なジャンルの方と御一緒出来そうです。ロック・ジャズ・クラシックなど心の広~い方々と演奏出来るのは嬉しいです。琵琶で良かった!!
先週はグリンテイルでのサロンコンサート、谷中下町風俗資料館での演奏などがありました。共に写真を撮る暇がなかったので、お見せできず残念ですが、こちらではギタリストのIさん、マドレーヌパテシエを自任するAさんと話がはずみ、気持ちの良い時間を頂きました。

今週は、尺八のクリストファー遥盟さんと久しぶりの再会。クリス宅では、プラハから来たマラック君という青年にインタビューを受け、少し演奏も録音しました。チェコのラジオ番組で流すようです。しかしとっさに英語は出てこなかった。精進足りず・・・。
 オーナーのKさんとは3年ぶりでしたが以前と変わらずノンストップで話が弾み、なかなか止まらない。時間があったらあのまま飲み会に突入しそうな勢いでした。そこではピアニストのNさん、朗読家のKさんと知り合い、突発的に演奏を聞かせることになり、「開経偈」をやってきました。そしてかんげい館では、秋に演奏会が決まってしまいました。
オーナーのKさんとは3年ぶりでしたが以前と変わらずノンストップで話が弾み、なかなか止まらない。時間があったらあのまま飲み会に突入しそうな勢いでした。そこではピアニストのNさん、朗読家のKさんと知り合い、突発的に演奏を聞かせることになり、「開経偈」をやってきました。そしてかんげい館では、秋に演奏会が決まってしまいました。
と、まあこれが私の日常。芸術関係の方が多いですが、とにかく出逢う人皆さんどういう訳か楽しい人達。初対面でもいろんな話が出来るし、面白い事が次々に起こります。
人間は文化があってこそ。文化こそ人間の人間たる基本。ピアニストのNさんとはそんな話をしてきたのですが、音楽を通し人が出逢ってゆくのは、音楽の役割であり、人を惹き付ける音楽の本質なのだと思っています。武満徹さんは「音楽に国境はある」と言っていましたが、人間同士の付き合いに国境はありません。文化は違えど、お互いの音楽を聴いて、ひと時を過ごし、気持ちを分かち合ってゆく事は充分に出来ます。(チェコの方々は私の演奏を聴いてどう思うかな??)
色々な音楽、様々な魅力が集うというのは、何かが生まれる原動力でもあるので、この日常をもっともっと続け、広げて行きたいです。
 葵祭
葵祭
来月は私の第二のホームグランド大阪・京都に行くので、またまた盛り上がりそうです。
それにしても名刺が増えすぎ。稼ぎがあったら真っ先に几帳面なマネージャーを雇いたい!!

和楽器 ブログランキングへ
Met Live Viewing今季最後の作品「椿姫」を観てきました。
泣けましたね~~ドラマですね~~。ヴェルディの作品は、私にはすんなりと入ってくるみたいで、今回も大満足でした。


主演のヴィオレッタ役はナタリー・デセイ。オペラ歌手にしては小柄ですが、PPPまで歌い切る歌唱力が光っていました。迫力系ではなく、どこかはかない感じで、役柄の内面が良く表れていて、役柄と彼女のキャラがぴたりと合っていました。

相手役のアルフレードにはマシュー・ポレンザーニ。この人の声には惚れましたね。リリックテノールといわれる大変艶の有る声質。加えて確かな歌唱力。素晴らしかったですね。久しぶりに声に酔いしれるテノールを聞きました。もう一度聞きたい!

そして、「エルナーニ」でも活躍したディミトリ・ホヴォロストフスキー
相変わらずのずぶといバリトンで、圧倒的な迫力でした。あの声はいったいどうやって出しているんだろう??是非是非生で聴いてみたいです。存在感も十分で、銀髪の髪が今回も決まっていました。
毎度のことですが、とにかくMetは其々の役に合った個性を持つ歌手が揃っている。主演のナタリー・デセイも、ままならぬ運命を生きるヴィオレッタそのものに見えてくるのです。もちろんアリアもたっぷりと楽しめました。定番の「乾杯の歌」はもちろんのこと、中でもホヴォロストフスキーが歌うジェルモンのアリア 「プロヴァンスの海と陸」
「プロヴァンスの海と大地を、誰がお前の心から奪ったのだ?
故郷の輝かしい太陽から、いかなる運命がお前を奪った?
苦しいのなら思い出せ、そこでは喜びに包まれていたことを」
ぐっときましたね。

そして最期にアルフレードの腕の中で息絶えるヴィオレッタの姿を見ていたら、涙がすーと頬を・・・・・。愛とは、人間とは、社会とは・・・・。Metの解説には「ヒロインの悲しい運命に寄り添うカタルシスを味う」とありましたが、、、「泣けるオペラ」でした。
明日は平家物語の「敦盛」を演奏するのですが、このオペラのように、ストーリーを越えて聴く人に何かが伝わるような演奏をしたいものです。
見事な芸も大事ですが、それを見せているだけでは物足りない。その先がなければ!!
邦楽は未だ、見事な練れた芸を見せる聴かせるという所に留まっているような気がしてならないのです。
「おまえは何を描くのか」、そここそ問われていると常に感じるのです。


和楽器 ブログランキングへ
この所何かとあわただしい。忙しいのは結構なことですが、日々が足早に過ぎ去るばかりで・・。もっと物事にじっくりと向き合って生きて行きたいものですね。
良い事、悪い事色々な記憶や想い出は色々とありますが、人間は身勝手なものですから、自分にとって大事な部分は都合よく膨らませて悦に入り、あとはしっかり空の彼方へ押しやって、反省もしない。まあそうでもしないと生きて行けないのが、人の世というものなのでしょうか。

先日は母の見舞いに行ってきました。母は少しずつ認知症が出てきているらしく、何だか会いに行く度にふわっと軽くなっていくように見えます。考えてみれば、年をとって色々な記憶が薄れ、まっさらな状態になって、お勤めを終えて行くのも良いのかもしれないです。「覚えていて欲しい」などというのは、日々カッカして生きている我々の言い分でしかないのだから、人生の重荷を下ろして、身軽になって行くのはむしろ当然の事、そんな風にも思えてきました。
しかしながら私はまだ今生を生きなくてはならない。泣いて笑って、時に戦って、やるべき事を成さなければならない。それはいつしか空に消えて行く小さな出来事であっても、まっさらさらになるまでは、今生を全うしなければならないのです。
だからこそ、何があろうとも、とにかく良い作品を残したいという想いが湧き上がります。しかしそんな想いで作った「作品」は無情なまでに自分の手を離れると独り歩きをし、作品独自の「命」を生きるものです。芸術家はその誕生の時をちょっとお手伝いする事だけしか出来ません。
 個人の想い出や願望など、大自然の中にあっては、うすぼけた空にいつしか消えてなくなってしまうもの。あまりにも小さく、はかなく、刹那な存在でしかないですね。この体もお勤めを終えれば、一物も無く消えてゆきます。それでも、たとえ無記名の作品であっても何か残したいというのが芸術家の最後のエゴなのでしょうね。
個人の想い出や願望など、大自然の中にあっては、うすぼけた空にいつしか消えてなくなってしまうもの。あまりにも小さく、はかなく、刹那な存在でしかないですね。この体もお勤めを終えれば、一物も無く消えてゆきます。それでも、たとえ無記名の作品であっても何か残したいというのが芸術家の最後のエゴなのでしょうね。
 「歩み」佐藤三津江作
「歩み」佐藤三津江作
PS:先週は、よくここで紹介している陶芸家の佐藤三津江さんの展示会があったので行ってきました。作品は相変わらず個性的で生き生きして、静止している作品なのに、そこには「動」を感じます。作品が歩いてきたんじゃないかと思えるような肉感的な「動」が更に強くなったような気がしました。
まだまだしっかり生きて行かんと!

和楽器 ブログランキングへ
先日MET LIVE VIEWING「マノン」を観てきました。マスネ作曲の「マノン」は、アヴェ・プレヴォーの小説「マノンレスコー」の主人公で、フランスを代表する(?)小悪魔的存在の女性として有名ですが、アナトール・フランスはマノンを評し「一生涯恋をして、一週間しか貞節でいられなかった女性」と書いています。

フランスのオペラは、前回書いたヴェルディの「エルナーニ」のようなものとはタイプが違い、どこか滑稽味があって洒落ている。この間観たプーランクのものもそうでしたが、ちょっと軽いコミカルな雰囲気があって、熱狂的声楽ファンには「もっと歌を!」という感じもしないでもないですが、これがフランスオペラの持ち味。今回の「マノン」もそういう意味では歌の魅力満載というのとはちょっと違ったのですが、その分オケは豊饒なまでに鳴り、舞台としての見せ場も結構あり、魅力いっぱいでした。それにマノン役のアンナ・ネトレプコはなかなかの「はまり役」で、ストーリーもオペラにありがちな貴族の物語ではない、我々一般の人間ドラマをたっぷり堪能してきました。
 Metはとにかくキャストが豊富ですね。どの作品を見ても皆キャラにぴたりとはまる人材を選んでいますね。今回の相手役デ・グリューのピョートル・ベチャワもそうでした。マノンに翻弄されるまじめな青年の雰囲気が良く出ていました。
Metはとにかくキャストが豊富ですね。どの作品を見ても皆キャラにぴたりとはまる人材を選んでいますね。今回の相手役デ・グリューのピョートル・ベチャワもそうでした。マノンに翻弄されるまじめな青年の雰囲気が良く出ていました。
「エンチャンテッド・アイランド」でのジョイス・ディドナートも魔女っぷりが板についていたし、ドミンゴなんか登場した時からすでにまんま海神ネプチューンにしか見えませんでした。超一流がしのぎを削って集うだけあって層が厚く、様々なタイプの世界的スターが揃い、まさに煌めくようです。
今回の「マノン」は設定を19世紀にした演出で、より身近な感じがしました。またセリフの中に「神様は幸せをとても軽くつくられた…だからすぐ何処かへ飛んでいってしまいそうで怖いんだ」というデ・グリューのセリフなんかぐっときましたね。オペラは名言の宝庫です。
こういう質の高い舞台は観ていて本当に幸せになります。私は日々色々な舞台を観ていますが、こういう満足度の高いのものは少ないですね。

日本人は素人でも何でも一生懸命やっていると、質に関係なく感動しただの、凄いだのとすぐ言います。いい例がAKBなどのアイドルでしょう。一生懸命は結構なことですが、結局は「姿勢」は求めても「質」を求めていないという事です。
琵琶の世界でも、トップレベルがしのぎを削った、あの勧進帳初演の頃(先日ブログで書いた)は、遥か昔の出来事になってしまったようです。
「日本人は成熟できない国民」という意見をよく聞きますが、音楽界の状況を観ていると、確かにそうだと思えてなりません。個性を殺して、軋轢の無いかの如くに「和」を保っていても、それは本当の「和」でもアンサンブルでもないのです。まず確固とした「個」があり、その上でお互い意見を出し、議論し合い、お互いの違いを認め合い、共生出来て、初めて組織や社会は成り立つもの。それが出来なければ「成熟してない」と言われても仕方がないのです。これでは国力も落ちるわけですね。 
和楽器 ブログランキングへ
ちょっと更新が滞ってしまいました。調子も戻りこれから本腰を入れていきますので、是非また御贔屓に。
 少し前にBoth sides nowというタイトルの記事を書いたら、早速多くの反応を頂きました。皆さん私と同世代かそれ以上の方々ばかりですが、嬉しいですね。このBoth sides nowはジョニミッチェルが歌った曲で、邦題が「青春の光と影」。ジョニミッチェルはジャズミュージシャンとの共演も多い方で、同世代にはぐっとくるんでしょうね。
少し前にBoth sides nowというタイトルの記事を書いたら、早速多くの反応を頂きました。皆さん私と同世代かそれ以上の方々ばかりですが、嬉しいですね。このBoth sides nowはジョニミッチェルが歌った曲で、邦題が「青春の光と影」。ジョニミッチェルはジャズミュージシャンとの共演も多い方で、同世代にはぐっとくるんでしょうね。
それにしても「光と影」なんとも惹きつけられる言葉ですね。誰しも自分の中に光と影を持っていることと思います。私も光と影を持っています。影は普段表に現れませんが、自分の影の部分に対し目をそらさずにしっかりと見つめることは、光の中へと進む事にも繋がると思いますので、影は決して無駄でも、邪魔なものでもないのです。むしろ影があるからこそ、今の私があると思っています。
C.G.ユングは「影は、我々人間が前向きな存在であるのと同じくらい、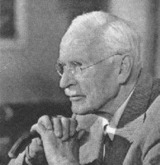 よこしまな存在である。我々が善良で優れた完璧な人間になろうと努めれば努めるほど、影は暗くよこしまで破壊的になろうとする意思を明確にしていく。人が自らの容量を超えて完全になろうとするとき、影は地獄に降りて悪魔となる。なぜならばこの自然界において、人が自分自身以上のものになることは、自分自身以下のものになるのと同じくらい罪深いことであるからだ。」と言っていますが、胸に迫る言葉ですね。ユングに関してはまた機会をあらためて・・・。
よこしまな存在である。我々が善良で優れた完璧な人間になろうと努めれば努めるほど、影は暗くよこしまで破壊的になろうとする意思を明確にしていく。人が自らの容量を超えて完全になろうとするとき、影は地獄に降りて悪魔となる。なぜならばこの自然界において、人が自分自身以上のものになることは、自分自身以下のものになるのと同じくらい罪深いことであるからだ。」と言っていますが、胸に迫る言葉ですね。ユングに関してはまた機会をあらためて・・・。
私が従来の邦楽にどこか距離を置いて、独自の探究をするのは、現在の邦楽に影の部分をあまり感じないからかもしれません。歴史を見てみると、色々な影があったと思いますが、現代の邦楽にはあまり感じません。私は音楽の中に存在する光と影を感じ、見つめていきたい。音楽の中に光と影があることは、人間の営みとして当然だと思いますし、またなくてはならないと思います。
さて、今月はやっと演奏活動も色々と入っています。スケジュールのブログをご参照ください。まずは再びの勧進帳。これは12日に両国でやります。そして7年に渡り毎年恒例で、様々なゲストを迎えてやっているグリーンテイルでのライブが19日にあります。これまで尺八だけでも中村仁樹、岩田卓也、田中黎山、香川一朝の各氏を迎えましたが、皆さん個性が違うので、毎回大変楽しみなのです。
グリーンテイル http://www7a.biglobe.ne.jp/~greentail/ ライブ2というところをクリックしてみてください。今回は新作も演奏予定です。
プラトンの「饗宴」によれば、人は人生において「かたわれ」を求めるといいます。それは人生のパートナーというものだと思いますが、光と影もまた自分の中のパートナーなのかもしれません。

和楽器 ブログランキングへ
 演奏の面でも、これから色々なジャンルの方と御一緒出来そうです。ロック・ジャズ・クラシックなど心の広~い方々と演奏出来るのは嬉しいです。琵琶で良かった!!
演奏の面でも、これから色々なジャンルの方と御一緒出来そうです。ロック・ジャズ・クラシックなど心の広~い方々と演奏出来るのは嬉しいです。琵琶で良かった!!
 オーナーのKさんとは3年ぶりでしたが以前と変わらずノンストップで話が弾み、なかなか止まらない。時間があったらあのまま飲み会に突入しそうな勢いでした。そこではピアニストのNさん、朗読家のKさんと知り合い、突発的に演奏を聞かせることになり、「開経偈」をやってきました。そしてかんげい館では、秋に演奏会が決まってしまいました。
オーナーのKさんとは3年ぶりでしたが以前と変わらずノンストップで話が弾み、なかなか止まらない。時間があったらあのまま飲み会に突入しそうな勢いでした。そこではピアニストのNさん、朗読家のKさんと知り合い、突発的に演奏を聞かせることになり、「開経偈」をやってきました。そしてかんげい館では、秋に演奏会が決まってしまいました。 葵祭
葵祭










 個人の想い出や願望など、大自然の中にあっては、うすぼけた空にいつしか消えてなくなってしまうもの。あまりにも小さく、はかなく、刹那な存在でしかないですね。この体もお勤めを終えれば、一物も無く消えてゆきます。それでも、たとえ無記名の作品であっても何か残したいというのが芸術家の最後のエゴなのでしょうね。
個人の想い出や願望など、大自然の中にあっては、うすぼけた空にいつしか消えてなくなってしまうもの。あまりにも小さく、はかなく、刹那な存在でしかないですね。この体もお勤めを終えれば、一物も無く消えてゆきます。それでも、たとえ無記名の作品であっても何か残したいというのが芸術家の最後のエゴなのでしょうね。

 Metはとにかくキャストが豊富ですね。どの作品を見ても皆キャラにぴたりとはまる人材を選んでいますね。今回の相手役デ・グリューのピョートル・ベチャワもそうでした。マノンに翻弄されるまじめな青年の雰囲気が良く出ていました。
Metはとにかくキャストが豊富ですね。どの作品を見ても皆キャラにぴたりとはまる人材を選んでいますね。今回の相手役デ・グリューのピョートル・ベチャワもそうでした。マノンに翻弄されるまじめな青年の雰囲気が良く出ていました。

 少し前にBoth sides nowというタイトルの記事を書いたら、早速多くの反応を頂きました。皆さん私と同世代かそれ以上の方々ばかりですが、嬉しいですね。このBoth sides nowはジョニミッチェルが歌った曲で、邦題が「青春の光と影」。ジョニミッチェルはジャズミュージシャンとの共演も多い方で、同世代にはぐっとくるんでしょうね。
少し前にBoth sides nowというタイトルの記事を書いたら、早速多くの反応を頂きました。皆さん私と同世代かそれ以上の方々ばかりですが、嬉しいですね。このBoth sides nowはジョニミッチェルが歌った曲で、邦題が「青春の光と影」。ジョニミッチェルはジャズミュージシャンとの共演も多い方で、同世代にはぐっとくるんでしょうね。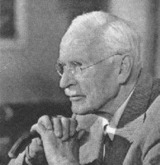 よこしまな存在である。我々が善良で優れた完璧な人間になろうと努めれば努めるほど、影は暗くよこしまで破壊的になろうとする意思を明確にしていく。人が自らの容量を超えて完全になろうとするとき、影は地獄に降りて悪魔となる。なぜならばこの自然界において、人が自分自身以上のものになることは、自分自身以下のものになるのと同じくらい罪深いことであるからだ。」
よこしまな存在である。我々が善良で優れた完璧な人間になろうと努めれば努めるほど、影は暗くよこしまで破壊的になろうとする意思を明確にしていく。人が自らの容量を超えて完全になろうとするとき、影は地獄に降りて悪魔となる。なぜならばこの自然界において、人が自分自身以上のものになることは、自分自身以下のものになるのと同じくらい罪深いことであるからだ。」