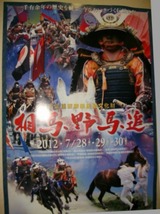滋賀の常慶寺での法要&演奏会の写真が来ました。法要の時は直垂を着て烏帽子をつけていたのですが、その後の演奏会ではREFLECTIONSの定番衣装、白いドレスシャツ姿で演奏しました。この白シャツ、実はファンの方から我々コンビにプレゼントされたものなのです。それ以来いつもこのスタイル。大浦さんは腰に大きなストールを巻いているので、私も今後はベストなんぞを着てみようかと思ってます。


先日のブログでは色々な人からお話を頂きました。日本文化の根幹をどこに観るか。それは日本音楽に携わる人間としては大きな問題だと思います。
チェリストの堤剛さんは「音楽家は史観をしっかりと持つべき」とおっしゃっていましたが、自分の専門とする所だけでなく、自分を取り巻く大きな流れ、歴史にも注目して行きたいと、私は思います。
最近、邦楽家の間で「平均律、純正律、モード、和音」など、そういう言葉を良く意味も判らずに雰囲気だけで使っている例を目にしますが、あまりに情けないです。結局洋楽コンプレックスの塊のようにしか見えません。
洋楽を勉強したから、邦楽がだめになったのか?全くそんなことは無いのです。とある知り合いが「色々な食材や料理が日本に入り、世界各国の料理を食べられるようになったけれど、しっかり和食は基本として残った」と書いていましたが、私もそう思います。
 高野山
高野山
外から入ってきたものを消化、昇華して、新たなものを作り出す、このエネルギーと変遷してゆく過程こそ文化というのです。社会が変わることに伴って、形も質も変わって行く、それこそが文化なのです。
日本という国は、新しいものが入っても、どうにかそれまでのものと共存して、宗教に於いては神仏集合という独特の形を作り、中世前後にはそこから新たな形や文化も創り出してしまう。こういう国は世界でもめずらしい。ちなみに熊野~高野山が世界遺産になった理由は、神道と仏教という事なる宗教が共存している事が世界的に観て極めて珍しい、という理由なのです。
 宮内庁楽部
宮内庁楽部
雅楽を例にしてみても良く判ります。雅楽を知らずに「あれは大陸の音であって日本のものではない」などと知ったかぶりをして決めつける人が居ますが、大きな間違いです。
仏教と共に大陸から輸入された雅楽は、日本の中で日本独自のシステムに作り変えられ、新作も作曲され、日本各地にそれまであった歌を雅楽アレンジにして中に取り入れ、雅楽の中に歌のジャンルも作りました。このようにして日本の雅楽は作り上げられて行ったのです。つまり雅楽は今、日本の音楽であって、大陸の音楽のコピーではないのです。
それはアルゼンチンで生まれたタンゴが、ヨーロッパでコンチネンタルタンゴになったのと同じ事。ジャズもロックもしかり。ただ過去と分断された現代の日本人だけがそれを認めようとしないのです。

文化は常に作られてゆきます。元々日本のものでもない仏教の概念が、鎌倉新仏教という革命を受けて、次の中世には日本文化の屋台骨となって行くように、色々なものが出会い、そして新たなものが出来あがり、それが伝統になって行くのです。
今、邦楽人で洋楽だの、五線譜だの、平均律だのと騒ぎ立てているのは、そういうものを受け入れられない人たちです。鎌倉新仏教の開祖たちも、永田錦心も、そうした新しいものを受け入れることのできない旧勢力に散々圧力をかけられました。
洋楽だけでなく、もっといろいろなものがこれから入ってくるでしょう。でもそれは時を経て、永田錦心や宮城道雄によって新時代の「邦楽」が生み出されたように、次の日本の伝統を生み出して行く事でしょう。私達は日本という国に生き、現代という時間を生きている。今その現場に立たされているのです。

さあ、どこに向かいますか。
少し前後しますが、先週の日曜日は丹沢の水眠亭にて演奏してきました。


水眠亭HP http://www.suimintei.com/
水眠亭は、川辺の廃屋をオーナーの山崎史郎さんがコツコツと自分で直し、自身のアトリエとサロンに作り上げた素敵なスペースです。山崎さんは本職がジュエリーデザイナーですが、万華鏡の作家でもあり、また茶道具も作り、蕎麦も打ち、俳人でもあり、ベースも弾くという実に多彩な方で、その世界はどこまでも広がってゆく方なのです。
私は尺八の中村仁樹君の紹介で行ったのですが、山崎さんとは共通の知り合いも多く、またオーディオにも詳しいし、蕎麦好きだし、もうあまりにかぶりまくっているので、すぐに話が弾み、いきなりビールを飲みながら話し込んでしまいました。
 私は元々、都会よりこうした山の中が好きな方で、ほっておくと鴨長明や西行のような隠遁者なってしまう性質なので、場所からしてすぐになじんでしまいました。次の朝から南相馬に行く予定だったので、夜は最終ぎりぎりで帰りましたが、次は必ず泊りがけでがっつり飲み、語り合いたいです!!
私は元々、都会よりこうした山の中が好きな方で、ほっておくと鴨長明や西行のような隠遁者なってしまう性質なので、場所からしてすぐになじんでしまいました。次の朝から南相馬に行く予定だったので、夜は最終ぎりぎりで帰りましたが、次は必ず泊りがけでがっつり飲み、語り合いたいです!!
今回のプログラムは平家物語の弾き語りでしたが、ここはフリージャズの方もよく演奏している所なので、私の1stアルバムを持って行ったら、ドンピシャ大好評でした。私の原点であるこのアルバムが解ってくれるというのは嬉しいです。特に私の代表曲「まろばし」とチェロの翠川敬基さんが入った「太陽と戦慄 第二章」は、このスピーカーで聴くと素晴らしい迫力で、自分でもちょっとびっくり。次回は中村君も一緒にバリバリセッションしたいと思っています。

山崎さんはじめ、今回のお客様と語っていて思ったのは、音楽がもっと色々なものと呼応すべきではないか、という事。以前、田中眠さんが水眠亭で踊った時、川の中から登場したと聞きましたが、ここには川があり、山があり、そして何よりも闇がある。都会には川や山はもちろんですが、闇というものが無い。街灯が月の明かりを遮り、アスファルトが地の声を絶つ。そう、都会は闇を忘れてしまったのです。闇の無い所に本当の光も、自然の声も無いのです。

水眠亭には闇がある。地、水、月光、そして陽光がある。自然の声に囲まれているのです。ここに集う人々は、肩書きみたいなつまらないまやかしも持っていないし、ネットに振り回され、狭く小さな世界でカッカしている人間も居ない。生身の体から湧き出る音楽があり、言葉があり、触れ合いが溢れていました。
久しぶりに気持ちの良い空間で演奏出来ました。是非また行ってみたいです。
少し御無沙汰です。
南相馬に行ってきました。今回はカメラマン 溝江俊介さんのコーディネートによる旅でした。「現地に行って肌で感じ、現地の方々と話をしてみて欲しい」とのことで、ボランティアに行った訳では無く、彼の地をこの目で見て、その土地の人々とたっぷり話をしてきました。特に相馬野馬追太鼓の方々には、練習も見せて頂き、じっくりと杯を交わしながら話をしてきました。
 飯舘村
飯舘村
二本松インターを降り、全村避難の飯舘村を通って行きました。かつては理想郷として紹介されたこともあるこの村には、今や全く人の気配は無く、田んぼも荒れ放題でした。その後、海に近い小高町にも行きましたがこちらもゴーストタウンとなっており、震災の爪後は今もそのままになっていました。
色々な場所に連れて行ってもらい、津波の考えられないような現状も見てきましたが、そういう事を報告するのはまた次の機会にしようと思います。
 野馬追太鼓の練習
野馬追太鼓の練習
 野馬追太鼓のメンバー達
野馬追太鼓のメンバー達
夜になって相馬野馬追太鼓の迫力ある演奏を聴かせて頂き、体にズンズンその鼓動を感じた後は、居酒屋に移動しメンバー達と飲みながら色々な話を聞きました。もう私などには想像もつかないような話が多かったですが、何よりも笑顔で太鼓を叩き、仕事をして、この地で生きて行こうとする彼らの姿からは、多くの示唆を頂きました。
私のように東京に居る人間は、ネットやメディアで飛び交う情報に操られがちで、勝手に見もしないで考えてしまいます。確かに相馬は今、安全とは言い難いかもしれません。他の多くの問題もあります。しかし相馬で生まれ育った彼らは、相馬で生きるのがごく当たり前で、自然な事なのです。震災後帰ってきた若い人も結構居て、原発を横に見ながらも、彼らは相馬の人として普通に暮らしています。
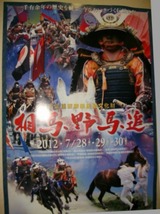
太鼓を叩き、生まれ育った土地に愛情を持ち、熱く地元の祭りの事を語る姿は、日本中の地元を愛する人達と同じだと思いました。私は今年の野馬追祭は行けませんが、是非近いうちに見に行きたいと思います。
震災・津波の爪後は確かに凄まじい。家族を亡くされた話も聞き、未だ放置されている現場も沢山見てきましたが、相馬に彼らが居る限り、相馬にはまた新たな轍が出来て、彼らの作ったその轍が次世代へと受け継がれ、育ってゆくことでしょう。
帰りには小高町から避難している、琵琶の先輩Tさんと会って、話をしてきました。淡々と穏やかに話す中に、しっかりとした視点を持っていて、ここで生きて行こうとする静かな決意を感じました。

私は相変わらず無力です。でも「これからの時代を一緒に生きて行こうぜ!」という方々に出逢えたことは本当に嬉しく思いました。私も彼らと共に、これからの時代を自分の生き方で全うして行こうと思います。
いつか必ず相馬で琵琶のコンサートやるぞ!!
最近親しい友人から良い言葉を教えてもらいました。

「ポジティブに生きるとは、ガツガツと成功や幸福を求めて突き進んでいくことではありません。喜びを持って生きることです。自分のしている仕事、生きている環境、周囲の人々に対して、喜びの心で接することなのです。ただ、自分が好きなことを、喜びを持ってやらせてもらった。だからつらくても頑張れた。そこにまた喜びが生まれた。それだけのこと。喜びがあるから、結果として成功がついてくるのです。成功を求めて、何かをしてきたわけではありません。この順番を間違えてしまうと、人は人生の迷子になってしまいます」
私はどうだろうか。ふと立ち止まって考えました。確かに自分としては、「らしく」生きているつもりでいます。しかし本当に喜びの心で人に接していただろうか。それはどちらかと言えば「我欲」ではなかったか・・・。
先日、石原都知事は「いま日本人が何に胸がときめくかと言えば、ちまちました『我欲』の充実。痩せた民族になってしまった」と発言しましたが、自らを振り返れば確かに言われる通りです。

舞台に立つということは、それ自体が自己顕示欲です。自分の音楽を聴いてもらいたいという顕示する気持ちと、喜びを持って音楽を演奏する気持ち、喜びを持って聴いている人に接するという気持ち、それらが相まっていなければ・・・・。まだまだ私にはバランスが難しい。
どんな形であれ、聴いている人の心を歓喜させるもの、震わせる音楽は、そこに喜びがあるのではないでしょうか。戦記ものなどが古典として残っているという事は、そこに喜びが有ったという事です。人が殺しあう物語は、題材はどうであれ、その物語から湧き上がる人間の姿や根底に流れる哲学、想い等々、何かしら人を震わせ、共感を呼び起こし、歓喜させるものがあるのであって、殺し合いや心中はその舞台設定でしかない。だから表面だけでとらえては、そこに「喜び」は見えてこないと思うのです。奥底から湧き上がるものでなければ!

私はこの夏、北へ向かいます。私の音楽はそんな舞台設定を超えて、喜びを持って聴いて頂けるだろうか。
目の前の我欲に振り回されていたら、そこには喜びは満ちてこない。自分を取り巻く人にも喜びが満ちてくるには、自分が喜びに満ちていなくてはならない。大切な人に喜びを持って接し、喜びを共有する時に、人間は幸せを感じるものだと思います。そんな場所にこそ安らぎがあるのでしょう。私の音楽にはそんな幸せや安らぎがあるだろうか。表面的な薄っぺらい喜びで無く、奥深い所で人を震わせる喜びがあるだろうか。

上記の言葉には続きがあります。
「迷子になったら、もう一度、見守ってくれる父と母を探しましょう。それは甘えることではありません。「天にゆだねる」ということです。自分の力だけでここまで来たのではないのだから、「まあ、いいか」「なんとかなる」と思えるのです。無駄に苦しむことがありません。」
我欲を捨て、この身をゆだねることも時に必要ですね。
喜びにあふれていなければ音楽は響かないのです。
昨日は、琵琶樂人倶楽部第54回目の「語り物の系譜Ⅴ」をやってきました。今回は昨年に引き続き桜井真樹子さんをゲストに迎え、「三五要録」のお話から雅楽~声明そしてヘブライ語アラム語によるユダヤの歌まで、興味深い内容となりました。

桜井さんは音大の作曲科を出た後、雅楽や声明の勉強をして、ユダヤアラブの現地に赴き、ヘブライ語を勉強したり、現地の音楽を研究したりしてきた方です。TOYOと呼ばれるアラブから日本までの大きな文化圏の変遷を常に意識しながら活動している方なので、今回のようなテーマは正に彼女でしか出来ない内容だったと思います。
稽古している以外の音楽をほとんど知らない、という方が多い邦楽・琵琶の世界の中にあって、桜井さんは重衡と千手が五常楽を合奏しながら冗談を言い合うように、私が「嘉辰」を歌い出せば、その場ですぐ龍笛を付けてくる。専門職以外の方でこういう事がすんなりと出来る幅広い見識を持っている人は、いつもの相棒 大浦典子さん位でしょうか。他には知りません。

さて、昨日は嬉しいことに大盛況で客席も満杯でした。この写真で桜井さんと写っている女性は岡庭矢宵さんといって、今年ユダヤのセファルディーという歌のCDをリリースした歌手の方。今日は是非、岡庭さんに聴いてもらいたいと思ってお誘いしました。ユダヤをうたう歌姫達です。

音楽も社会も常に色々なものとの出逢い、接触して形作られてゆきます。TOYOが正にその現場でした。そこに発生するエネルギーは創造力を刺激し、新たなものを生み、育み、一つの形へと洗練を遂げて行きます。しかしその洗練され出来あがったものは、発生時のエネルギーと創造力を失えば、すぐに形骸化し中身の無いものになってしまう。今我々の前にあるものは、そのエネルギーがまだあるからこそ現存しているのです。
今自分のやっている音楽はどこから来たのか。そうしたルーツを知るという作業を、残念ながら近現代の琵琶楽はほとんどしてこなかった。だから薩摩琵琶は今、そのエネルギーを失いつつあるのです。
桜井さんや岡庭さんは自分の音楽のルーツへと向かい実際に勉強研究しながら、最先端の表現者として舞台を張っている。素晴らしい活動ぶりだと思います。

歴史は繋がっている。声明とユダヤの歌は驚くほど近い。TOYOという大きな流れの中には、仏教もキリスト教もイスラム教もある。音楽も文化も人も大いに交流を重ねてきたに違いないと私は思っています。
古から綿々と続く人間の営み。そのTOYOの営みの中から生まれた琵琶を、現代という舞台で演奏したい。桜井さんの声を聞きながらそんな風に想いました。


和楽器 ブログランキングへ


 高野山
高野山 宮内庁楽部
宮内庁楽部







 私は元々、都会よりこうした山の中が好きな方で、ほっておくと鴨長明や西行のような隠遁者なってしまう性質なので、場所からしてすぐになじんでしまいました。次の朝から南相馬に行く予定だったので、夜は最終ぎりぎりで帰りましたが、次は必ず泊りがけでがっつり飲み、語り合いたいです!!
私は元々、都会よりこうした山の中が好きな方で、ほっておくと鴨長明や西行のような隠遁者なってしまう性質なので、場所からしてすぐになじんでしまいました。次の朝から南相馬に行く予定だったので、夜は最終ぎりぎりで帰りましたが、次は必ず泊りがけでがっつり飲み、語り合いたいです!!