先日、パリオペラ座Live viewing「ファルスタッフ」を観てきました。喜劇の面白さを初めてしっかりと味わいました。
「ファルスタッフ」はヴェルディ最晩年の作品で、ヴェルディではほとんど唯一(かなり若い頃に一つ作っているそうです)といっていい喜劇なのです。あのドロドロとした濃~~い愛憎劇ではなく、コミカルでアイロニカル。シェークスピアの「ウィンザーの陽気な女房たち」という作品をを元にしたものだそうで、あのヴェルディが最後の作品として喜劇にたどり着いたというのは興味深いですね。
舞台の最後に、酒飲みで女たらしの老騎士ファルスタッフが放つセリフがなかなか印象的です。
「世界のすべては冗談さ、人はピエロとして生まれる 。頭の中じゃ揺らいでるのさ 。いつでもその理性というやつは 。みんな愚か者!あざけり合うのさ 、お互いを 人間というやつは 。だけど一番沢山笑うのは 最後に笑った者なのさ」
Normal
0
0
2
false
false
false
EN-US
JA
X-NONE
<w:latentstyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden=”true” DefQFormat=”false” DefPriority=”99″
LatentStyleCount=”267″>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Normal”/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”heading 1″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Title”/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtitle”/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong”/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Emphasis”/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Table Grid”/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”No Spacing”/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading”/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List”/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid”/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List”/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading”/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List”/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid”/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 1″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 1″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 1″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 1″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 1″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 1″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”List Paragraph”/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Quote”/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Quote”/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 1″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 1″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 1″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 1″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 1″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 1″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 1″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 1″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 2″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 2″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 2″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 2″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 2″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 2″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 2″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 2″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 2″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 2″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 2″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 2″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 2″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 2″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 3″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 3″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 3″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 3″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 3″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 3″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 3″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 3″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 3″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 3″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 3″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 3″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 3″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 3″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 4″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 4″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 4″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 4″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 4″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 4″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 4″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 4″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 4″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 4″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 4″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 4″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 4″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 4″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 5″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 5″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 5″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 5″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 5″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 5″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 5″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 5″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 5″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 5″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 5″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 5″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 5″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 5″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 6″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 6″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 6″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 6″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 6″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 6″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 6″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 6″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 6″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 6″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 6″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 6″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 6″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 6″/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Emphasis”/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Emphasis”/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Reference”/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Reference”/>
<w:lsdexception Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Book Title”/>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:標準の表;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;
mso-para-margin:0mm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.5pt;
mso-bidi-font-size:11.0pt;
font-family:”Century”,”serif”;
mso-ascii-font-family:Century;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Century;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-font-kerning:1.0pt;}
主演のアンブロジオ・マエストーリは体型からして、正にファルスタッフそのもの。この役では高い評価を受けている人ですが、本当に見るからにぴったり!!写真が見当たらず、お見せできないのが残念です。その他出演者も皆さんレベルが高く 素晴らしかった。左の写真のナンネッタ役のエレーナ・ツァラゴワも、この若さでベテランに引けを取らない充実した歌唱でした。喜劇では演劇的要素がかなり問われるのですが、アルトゥール・ルチンスキ(フォード)、スヴェトラ・ヴァシリエヴァ(アリーチェ)、マリー=ニコル・ルミュー(クイックリー夫人)、ガエル・アルケス(メグ)それぞれ皆さんアリアはもちろんの事、コミカルな演技も歌のアンサンブルも素晴らしかった。
素晴らしかった。左の写真のナンネッタ役のエレーナ・ツァラゴワも、この若さでベテランに引けを取らない充実した歌唱でした。喜劇では演劇的要素がかなり問われるのですが、アルトゥール・ルチンスキ(フォード)、スヴェトラ・ヴァシリエヴァ(アリーチェ)、マリー=ニコル・ルミュー(クイックリー夫人)、ガエル・アルケス(メグ)それぞれ皆さんアリアはもちろんの事、コミカルな演技も歌のアンサンブルも素晴らしかった。
歌とオーケストラとの息もしっかりと合っているし、全体に大雑把なところが無いのです。Metのような派手な演出は全くないのですが、調和が取れていて、コミカルなその演出はかえってストーリーをしっかりと浮かび上がらせて、とても判りやすい充実の舞台でした。
勿論今回もオーケストラのサウンドがいいのです。指揮はダニエル・オーレン。パリオペラ座ですから当たり前なんですが、一流の音は実に気持ち良い!!
欧米は生活の面では個人主義の国ですが、音楽や舞台でのアンサンブルが実に緻密で構築的。日本は社会の中では調和を重んじる国ですが、舞台芸術の分野に於いて、大人数でのアンサンブルの力がはっきり見えるのは歌舞伎位のものでしょうか。面白いですね。個人主義とは個人の責任で生きるという事なので、基本的に自分で責任を取り、自立して生きるという事。こういう個として自立した国民性があってこそ、オペラのような舞台を生むのでしょうね。そして個から世界を見渡すような視野が大切なのだと思います。その美意識や感性にも、現代社会に於いては、「世界の中の個」、「世界と共に生きる」というような視点が必要ではないでしょうか。日本でもこの辺りの感覚はこれから大いに求められることだと思います。世界がつながっている現代に、己の道なんて言って閉じこもっている訳にはいかないのです。
染色の志村ふくみさんも、我々は常に前衛なんだとおっしゃっていましたが、素晴らしいものを現代に、そして次世代に残すことは、常に最先端の感性を持ち続ける事でもあります。人間は頑張っている人ほど、その渦中にあってなかなか客観的に自分のやっているものが見えていないもの。音楽に於いても、ドビュッシーやラベルの例を挙げるまでもなく、社会は難なく新しいものや変化を受け入れても、本職の音楽家の方が色々なこだわりを身にまとってしまっていて、新しいものをなかなか受け入れることが出来ない。人間は自分の勉強したもの、築き上げてきたものにいつしか囚われてしまうものですが、それを乗り越えて次の時代に行けるかどうか、その人の器というものが問われますね。
生誕200年のヴェルディの作品が、現代にこうして最先端の感性と演出と技術で素晴らしい舞台となって表現される、これこそ芸術の力ですね。日本の音楽も、形を守るだけでなく、最先端の表現として、古典を世界に発信出来る器が欲しいですね。そんな若者もぼつぼつ出てきたように思います。
元気が湧いてきます!!

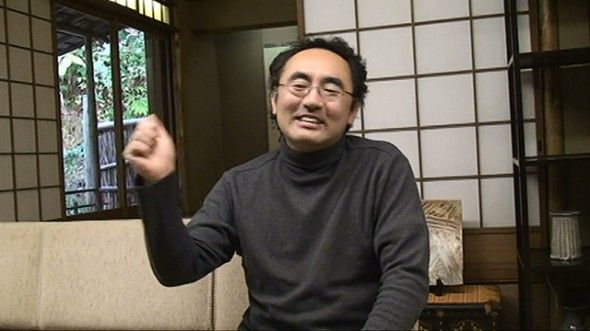 こちらが河村さん。音楽、特に現代音楽にとても造詣が深く、話が弾みました。
こちらが河村さん。音楽、特に現代音楽にとても造詣が深く、話が弾みました。







 今、世の中のもの大半が、強く、早く、軽く、と便利で刹那的な方向にどんどんと向い、そのために知識や理論が費やされ、社会全体が生き急いでいるかのように私には思えます。音楽も、どんどんこの調子でスピードやパワー重視の表面的なものになってきているような気がしてなりません。
今、世の中のもの大半が、強く、早く、軽く、と便利で刹那的な方向にどんどんと向い、そのために知識や理論が費やされ、社会全体が生き急いでいるかのように私には思えます。音楽も、どんどんこの調子でスピードやパワー重視の表面的なものになってきているような気がしてなりません。


 素晴らしかった。左の写真のナンネッタ役のエレーナ・ツァラゴワも、この若さでベテランに引けを取らない充実した歌唱でした。喜劇では演劇的要素がかなり問われるのですが、アルトゥール・ルチンスキ(フォード)、スヴェトラ・ヴァシリエヴァ(アリーチェ)、マリー=ニコル・ルミュー(クイックリー夫人)、ガエル・アルケス(メグ)それぞれ皆さんアリアはもちろんの事、コミカルな演技も歌のアンサンブルも素晴らしかった。
素晴らしかった。左の写真のナンネッタ役のエレーナ・ツァラゴワも、この若さでベテランに引けを取らない充実した歌唱でした。喜劇では演劇的要素がかなり問われるのですが、アルトゥール・ルチンスキ(フォード)、スヴェトラ・ヴァシリエヴァ(アリーチェ)、マリー=ニコル・ルミュー(クイックリー夫人)、ガエル・アルケス(メグ)それぞれ皆さんアリアはもちろんの事、コミカルな演技も歌のアンサンブルも素晴らしかった。



 音楽を高らかに発信しているのに、「格」をぶら下げて舞台に上がっても、世間の人にほとんど受け入れらないのは当たり前。つまり音楽をやっている訳ではないという事です。聴衆は音楽を聴きに行っているのですがね・・・・。これでは当然著作権の意識など生まれようがありませんね。
音楽を高らかに発信しているのに、「格」をぶら下げて舞台に上がっても、世間の人にほとんど受け入れらないのは当たり前。つまり音楽をやっている訳ではないという事です。聴衆は音楽を聴きに行っているのですがね・・・・。これでは当然著作権の意識など生まれようがありませんね。 私は欧米のような著作権のあり方が良いとは決して思っていません。ショウビジネスを基本に整えられた現在の著作権法には様々な矛盾があると考えています。ネット上に出している以上、コピーもされるだろうし、研究対象にもされるでしょう。時に勝手に使われることも覚悟の上です。どんどん聞いて分析して、肥やしにして、部分をパクリながら自分のオリジナルに仕立てて結構だと思います。今までの全てのジャンルの音楽家も皆そうしてきました。
私は欧米のような著作権のあり方が良いとは決して思っていません。ショウビジネスを基本に整えられた現在の著作権法には様々な矛盾があると考えています。ネット上に出している以上、コピーもされるだろうし、研究対象にもされるでしょう。時に勝手に使われることも覚悟の上です。どんどん聞いて分析して、肥やしにして、部分をパクリながら自分のオリジナルに仕立てて結構だと思います。今までの全てのジャンルの音楽家も皆そうしてきました。


 こういう演奏を聴くと、やはり薩摩琵琶にも器楽的な分野はぜひとも欲しいと思ってしまいます。私は琵琶の分野で、多分一番器楽的な演奏をして、作品も作ってきた一人だと自負していますが、まだまだ曲が少ないと思っています。琵琶のこれまでの伝統がどうであれ、現代人は琵琶の楽器としての音色を求めている方も多いのですから、これから現代、次世代の聴衆に向けて、器楽としての琵琶楽を確立する人もどんどん出るべきだと思っています。津軽三味線も唄と切り離されたからこそ、ポピュラリティーを得た事実を観ればそれは明らかでしょう。民謡という事でなく、津軽三味線という楽器を聴きたいという聴衆が沢山居たということです。こだわりや習慣、伝統などをいかに超えてゆくか、次世代を目指してゆけるか。今、薩摩琵琶の器の大きさが問われているような気がします。
こういう演奏を聴くと、やはり薩摩琵琶にも器楽的な分野はぜひとも欲しいと思ってしまいます。私は琵琶の分野で、多分一番器楽的な演奏をして、作品も作ってきた一人だと自負していますが、まだまだ曲が少ないと思っています。琵琶のこれまでの伝統がどうであれ、現代人は琵琶の楽器としての音色を求めている方も多いのですから、これから現代、次世代の聴衆に向けて、器楽としての琵琶楽を確立する人もどんどん出るべきだと思っています。津軽三味線も唄と切り離されたからこそ、ポピュラリティーを得た事実を観ればそれは明らかでしょう。民謡という事でなく、津軽三味線という楽器を聴きたいという聴衆が沢山居たということです。こだわりや習慣、伝統などをいかに超えてゆくか、次世代を目指してゆけるか。今、薩摩琵琶の器の大きさが問われているような気がします。 西洋音楽とは違う別の形、概念でのアンサンブルは、充分に可能だと思います。日本では既に雅楽をはじめ、長唄囃子や能囃子が素晴らしいアンサンブルを完成させていますが、琵琶楽に於いても、アンサンブル作品の充実は、これから大変重要だと思っています。
西洋音楽とは違う別の形、概念でのアンサンブルは、充分に可能だと思います。日本では既に雅楽をはじめ、長唄囃子や能囃子が素晴らしいアンサンブルを完成させていますが、琵琶楽に於いても、アンサンブル作品の充実は、これから大変重要だと思っています。