先日、久しぶりに劇団アドックの公演を観てきました。
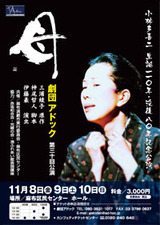
原作は三浦綾子。小林多喜二の母セキの事を描いたものです。アドックにとってこの作品は、旗揚げの時に上演した作品でもあり、何度となく上演しているものですが、実は来年の1月26日、川崎能楽堂にて、「アドック」と私がやっているアンサンブルグループ「まろばし」の共同企画として、この「母」を琵琶をバックに、主演の三園ゆう子さんの一人語りでやってもらうという企画がありまして、今回はいつになく大変興味を持って観てきました。
アドックの舞台はもう何度も見ているし、以前にも「母」は観たことがあるのですが、今回は実によく洗練されていて、役者たちもこなれ、効果音など細かな部分が整理され、素晴らしい舞台となっていました。途中、何度も涙を抑えるのに大変でした・・・。三園さんがにこやかに語っているシーンでも、その言葉の裏側までもダイレクトにこちらに伝わって来るようで、そのレベルの高さを思い知りました。
 こちらは来年のチラシ表。
こちらは来年のチラシ表。
来年の趣旨は、「語り合うという事の意味を今こそ問う」というテーマで、古典からは忠度と俊成、そして千手と重衡の物語を通して語り合う姿を聴いていただき、現代作品からは、「母」を取り上げ、セキが現代の人に語りかける姿を通して、「語り合う時代」を表して行こうと思っています。
アドック主宰の三園さんと演出脚本の伊藤豪さんは、舞台にかける姿勢が大変真摯で、私には共感する部分が沢山あります。このショウビジネス全盛の時代に、かたくななまでに社会派を貫き、鋭く人間の姿を描いてゆくアドックの姿勢に私は大変惹かれるのです。今はどんな分野でも売れるかどうかが最優先という時代。その路線を取るのは別に悪い事ではないし、それはそれで高いクオリティーを求められることと思いますが、邦楽の分野でここまで貫いている方は少ないですね。邦楽器の珍しさがどうしても売りになってしまいますし、結局有名作曲家の作品も、ステイタスとしてやっているだけなんだ、と思ってしまうものも少なくありません。
アドックの舞台はショウビジネスに色気を出したりしない。姿勢にブレが全く無いのです。どこまでも自分たちのスタイルを貫いている。だから毎回深く深く心に刺さってくるのだと思います。以前私も参加した芥川龍之介原作の「雛」や、三浦綾子原作の「壁」もそうでしたが、とにかく重過ぎる程に深くこちらの心に呼びかけるものがあります。またそこには多くの示唆があり、こちらの創造力と舞台とが一体となった記憶が、私の心の中に残っています。
今、邦楽に於いてこんな舞台はなかなかないですね。 古典であろうが新作であろうが、それを通して自分の音楽性や哲学を表すのが演奏家の在るべき姿だと思います。音楽は社会と共に生き、社会との関わりの中で成立して行くもの。舞台に立つ以上は、自分又は自分達の表現をしていかないと、誰も聴いてくれません。聴衆は流派の曲を聴きに来るのではなく、演奏者の音楽を聴きに来るのです。アドックも三浦作品をアドックのやり方で舞台にかけるからこそ、人々がその舞台に集うのです。邦楽人も自らの音楽を高らかに歌い上げなくては!!
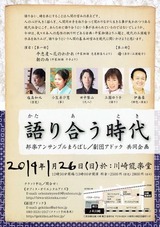 来年のチラシ裏
来年のチラシ裏
「母」を観ていて、明治から大正、昭和へと日本がどんな道を辿り、そこにどんな人間の姿があったのか、見えてきました。私は平和な時代にたまたま生まれ生きてきましたが、そこに至るには壮絶なまでに生きる事への人間の戦いがあり、その上に現代のこの世の中が出来上がっている事を思い知りました。この歴史を忘れてはいけない。私はそう感じました。
たとえショウビジネスに乗らなくても、自分の行くべき道を行く。これは良寛の姿勢などとも相通じるものがあると思います。現代は何事においても利を求めすぎる。その利を求めるあまり、色々なひずみが出てきています。中身よりも外見を派手に奇抜にしたり、誇大な宣伝をかけたり、果ては偽装も平気でやってしまう。邦楽も、世の中全体も、本来求めるべきもののポイントがかなりずれているように思います。時代を見据え、時代と共に歩むのは結構。しかし時代に流されてはいけない。新しい時代を作る位でなくては!!
来年、どうやってこの「母」に関わろうか。今色々なアイデアが湧き上がっています。
来年の公演が楽しみです。
先日、江戸手妻の藤山大樹さんの出世披露公演を観てきました。
 出世披露の口上
出世披露の口上大樹さんは高校生の頃より藤山新太郎先生の手伝いを始め、大学でもマジック研究会に所属。卒業後は内弟子に入り4年間の修業期間を経てこの程、藤山大樹の名前を頂いたのですが、新太郎師匠に就いてコツコツと練習をする真面目な人柄ゆえ、その技は驚くほどの完成度を持っています。まだ25歳。すでに新太郎師匠の所でもソロで演目を任されているし、個人としても色々な場所で仕事をしているので、知っている方も多いと思いますが、これから花開く、正に逸材!今回は素晴らしい門出となりました。
 七変化
七変化これからは独立して旺盛な活動をして行くと思いますが、彼なら十二分な技量と芸に対する謙虚さを兼ね備えているので、今後に大きな期待を持てます。いつか一緒に仕事が出来るといいですね。
左の写真は大樹さんの十八番「七変化」。これは是非皆さんに観てもらいたい演目です。凄い技ですよ。そして舞台としての完成度が高い。ただ上手なだけでなく、舞台全体を務め上げるその力量は大したものです。新太郎師匠の所では、門下全員に日舞・長唄を習わせ、所作や日本の文化そのものを体現させています。今回も長唄囃子 杵家七三社中の演奏で、新太郎師匠も唄で参加して、大樹さんによる舞踊「雨の五朗」が披露されました。こういう素養が、舞台運びや演目の中での話し方、身のこなし方すべてにものを言うんです。舞台全体に日本文化としての世界観がある。これが素晴らしいのです。舞台そのものを張れるような、実力と日本文化の素養を身に付けた若手が琵琶の世界にぜひ出てきて欲しいものです。
藤山大樹HP http://www.japanesemagic.jp/
次の日は私が敬愛する田原順子先生の会「糸遊び」を観てきました。さすが田原門下!自由自在な発想と演奏が縦横無尽に展開されていました。そしてこれだけの個性を束ねる田原先生の器の大きさにも感服。弟子達皆が田原先生の思考や哲学を自分なりに継承していて、観ていて大変可能性を感じました。
これだけ思いっきり個性を爆発させて、展開させているのは、現在琵琶の世界では田原門下が唯一です。他には観たことがありません。田原門下の中から、藤山大樹さんのような本当のプロが今後出て来るかどうかは、判りませんが、この自由な土壌はきっと何かを生み出してゆく事でしょう。
 煌めく才能は、現代社会の中にもしっかりとあります。その才能が更に煌めくには、大きな視野が必要です。自分のやっている事だけに興味を持つようなオタク目線では、何事もレベルは上がりません。「那須与一」や「壇ノ浦」のような流派の曲も勿論良いのですが、おさらい会と変わらないのでは、せいぜい関心しかしてくれません。聴衆を虜にするような独創性、そして魅力がなければ!更に世界に通用するレベルが無ければ!
煌めく才能は、現代社会の中にもしっかりとあります。その才能が更に煌めくには、大きな視野が必要です。自分のやっている事だけに興味を持つようなオタク目線では、何事もレベルは上がりません。「那須与一」や「壇ノ浦」のような流派の曲も勿論良いのですが、おさらい会と変わらないのでは、せいぜい関心しかしてくれません。聴衆を虜にするような独創性、そして魅力がなければ!更に世界に通用するレベルが無ければ!
プロとして舞台で琵琶を弾くというのは、日本の文化を弾くという事でもあります。習ったものを得意になって弾いているのはアマチュアでしかないのです。独創性は勿論の事ですが、日本の文化をどう捉えているか、そこが問われます。邦楽の根底には先ず日本の風土があり、仏教があり、文学も歴史も深く関わって邦楽が出来上がっています。短歌を詠んだり、お茶を点てたり、歌舞伎や能を論じたり・・・。それらに関係なく琵琶だけ弾こうとしても、それは洋楽が席巻している現代に於いては、もはや日本の音楽ではないのです。フォーク、ロック、ブルーズが形を変えたに過ぎない。琵琶楽は千年以上の歴史があるのです。自分が興味のある所だけ、見えているところだけを見て、音楽や文化を断片的にしか見ていないようでは、とてもプロの舞台人には成れません。すぐ底が知れてしまう。
是非大樹さんのような日本の文化を表現できる舞台人が琵琶の世界にも出てきて欲しいですね。煌めく才能を観て聴いて、すがすがしい気持ちで週末を過ごしました。
先日、新宿のエルフラメンコで催された、川崎さとみ芸歴30周年記念リサイタルにて演奏してきました。
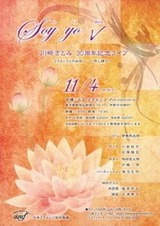

エルフラメンコは日本におけるフラメンコの中心基地。スペインの一流のダンサーが来日して公演をする唯一の本格的なフラメンコのお店です。ジャズで言えばブルーノート東京みたいな所。ここで樂琵琶を弾いたのは私が初めてかもしれませんね。
いや~~楽しかったですよ。リハーサル時から、メンバーの皆さんとは話もはずみ、且つ色々と勉強になりました。
今回は現代日本のフラメンコ界を代表するトップレベルのメンバーが揃いました。男性のバイラオール(踊り手)が伊集院史朗、カンテ(歌)が川島桂子と石塚隆充、ギターは柴田亮太郎と内藤信、パーカッションに海沼正利、それに私と笛の大浦典子という布陣!私の作曲したSiroccoもダイナミックな展開にアレンジされ、新たな命が宿りました。
 これは楽屋の風景。何しろ皆さん居るだけで楽しい。この自由さは邦楽には無いですね。左からPerの海沼さん、ギターの内藤さん、カンテ(歌)の石塚さん、ギターの柴田さん。私は海沼さん、柴田さんと一緒に演奏しましたが、とにかくご機嫌でした。
これは楽屋の風景。何しろ皆さん居るだけで楽しい。この自由さは邦楽には無いですね。左からPerの海沼さん、ギターの内藤さん、カンテ(歌)の石塚さん、ギターの柴田さん。私は海沼さん、柴田さんと一緒に演奏しましたが、とにかくご機嫌でした。
 プログラムより
プログラムより
そしてこちらが今回の主役、川崎さとみさん。エネルギッシュで頑張り屋の彼女らしい、気持ちの良い舞台でした。
しばらく私自身がフラメンコと離れていたので、川崎さんとはあまり連絡を取っていなかったのですが、今年に入って、バレエの雑賀淑子先生の夏の公演の事で連絡を取り合ったのがきっかけでまたやり取りを始め、今回のリサ
イタルに至りました。縁というものは面白いですね。何かに手繰り寄せられるかのように繋がって行きます。これを「はからい」というのでしょうか。
川崎さんと最初に知り合った頃、私はパコデルシアに憧れフラメンコギターをちょっとかじっていたのですが、それがもうかれこれ25年程前。月日の経つのは早いものですね。
それにしてもフラメンコの自由な雰囲気は楽しいのです。やっている人も聴いている人も、魂が高鳴ります。全体の雰囲気はいい感じでゆるいのですが、こと演奏、そして舞台にはとても厳しい。特にリズムに関しては、大変なこだわりと意識を皆さん持っていますね。
邦楽は全く逆。しきたりや序列にはやたらと厳しいけれど、音楽にはゆるい。実力よりも流派や団体内での力関係優先の人が多いのも邦楽の特徴です。
プロとアマがはっきりとしていて、タブラオと呼ばれる小さなスペースでも真剣勝負で命のほとばしりを舞台で聞かせるフラメンコと、大そうなホールを借りておさらい会と同じ事をやっている邦楽では、聴衆はどちらに魅力を感じでしょうか・・・・。
 実はフラメンコギターと薩摩琵琶は共通点がとても多いのです。
実はフラメンコギターと薩摩琵琶は共通点がとても多いのです。 薩摩琵琶を弾きだした頃すぐにそれを感じましたが、特に演奏技術の面で、右手首の使い方などが大変似ています。また音階も似ているし、崩れの部分の感情の出し方などにも、一つの通奏低音を思わずにはいられません。哀調を帯びた音楽という所でも、繋がりを感じます。それゆえ私には両方を行き来しても
薩摩琵琶を弾きだした頃すぐにそれを感じましたが、特に演奏技術の面で、右手首の使い方などが大変似ています。また音階も似ているし、崩れの部分の感情の出し方などにも、一つの通奏低音を思わずにはいられません。哀調を帯びた音楽という所でも、繋がりを感じます。それゆえ私には両方を行き来しても
ほとんど違和感が無いのです。今回は樂琵琶でしたので、薩摩琵琶よりも更に音階やリズムに全くストレスが無く、ギタリストの一人のような気持ちで演奏してきました。
フラメンコと邦楽それぞれに深い文化があることは、皆さんよくお判かりだと思います。音楽という具体的な形も勿論ですが、その根底に流れる文化こそ、大事にしていくべきだと思います。フラメンコの演奏家と一緒に居て思うのは、想いの情景がはっきりと見えて来る事です。
目の前で売れる売れない、という価値観だけでは文化は失われてしまいます。残念なことに、最近の邦楽の演奏を聴いていると、売れるかどうかが最優先で、「秘める」というような日本独自の崇高な表現や文化をほとんど感じません。世の中を見渡しても、同じように想いを秘めて行くような感性がどんどんと無くなってきていると感じます。日本のジプシーよろしく、放浪の琵琶法師を気取って演奏しても、思い入れだけでは伝わりません。外見のはったりや単なるスキルの部分で演奏されるようになったら、もう音楽としてお終いなのです。
どんな演奏でも、その先に何を想い、何を語りたいのか・・。そこがが一番大切なのではないでしょうか。そこに日本の文化が無ければ、いくら琵琶を弾こうが、それは日本音楽ではないのです。逆に何を弾こうと、自分の中にしっかりとした想いと文化を持っていれば、おのずからその姿は新しい日本音楽となって行くでしょう。邦楽はよくよく考えなければいけない時期にあると思います。
「敦盛」や「那須与一」をやるのは何故なのか、その先に何を語り伝えようとして、それらの曲を演奏するのか。ただお稽古の成果を披露するのなら身内のおさらい会でやれば良い事。お金を取る演奏会でやるのだったら、その先に想いがあり、それが確実に表現されていなければ人は聴いてくれません。お上手を披露しても感心されるだけです。
もう10年以上前、とある著名な音楽家の方に「もう薩摩や筑前の琵琶は、このままいくと歴史資料のようになって消えて行くと思うよ」と言われましたが、今になってみると、私も同じ事を感じます。
 うちあげにて
うちあげにてほとばしるような想い、魂の煌めき、民族の心・・。今邦楽に一番求められていることをフラメンコから学びました。

和楽器 ブログランキングへ
戯曲公演「越の良寛」をやってきました。
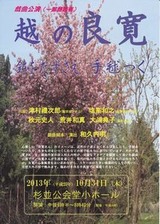 今回は書き下ろしの新作ですし、能シテ方の津村禮次郎先生との共演でもあったので、戯曲に対し、どう音楽を付けて演奏したらよいか迷うところもありましたが、とにもかくにも私にとってこの舞台は、良寛という人物に出逢えた貴重な体験となりました。良寛は今後私の中で、永田錦心とともにとても大きな存在となって行くと思っています。
今回は書き下ろしの新作ですし、能シテ方の津村禮次郎先生との共演でもあったので、戯曲に対し、どう音楽を付けて演奏したらよいか迷うところもありましたが、とにもかくにも私にとってこの舞台は、良寛という人物に出逢えた貴重な体験となりました。良寛は今後私の中で、永田錦心とともにとても大きな存在となって行くと思っています。
舞台そのものは、個人的にも色々と反省点もあるし、舞台全体としても未消化な部分も多かったと思いますが、本番で印象的だったのは、樂琵琶独奏と舞だけのラストシーンでした。津村先生は僧籍を持っている方でもあるのですが、劇中、良寛を演じている時には、実際に自分が修業時代に来ていた墨染めの衣を着て演じていました。しかしラストシーンでは面を付けて、少しだけ華やかな衣装で舞われました。私はその時「春陽」という曲を弾いたのですが、そこにはすでに言葉は無く、春の景色が描かれた扇を持ち、春の陽光に包まれるが如く、時を愛おしむように舞う姿だけがありました。良寛や彼を取り巻く人々の、次代へのあたたかい想いが昇華して、その数々の想いが津村先生の舞姿となって、戯曲の最後を締めたのです。その姿は良寛でもあり、維馨尼でもあり、貞心尼でもあり、また文台でもあった事と思います。私はあの姿を見ながら、個々の人物を超えた、肉体を超えた、時間をも越えた存在になっていると感じました。
あの何とも言えない空気は忘れられないですね。会場が澄み切った湖面のような雰囲気になり、弾いていて、私自身が湖面に漂っているような気がしました。

良寛に関しては、これまで子供と毬をつく優しいお坊さんという位のイメージしかなかったのですが、それは今回良寛を追いかけてみて、全く変わりました。今では自分と共通する部分を多く感じますし、大変に魅力的な人物に思えてなりません。
良寛は自分の人生を生きてゆく中で、自分の無力さを痛烈に感じていたのだと思います。自らの無力を知ったからこそ、大きな「はからい」によって生かされている命を自らの中に感じたのではないでしょうか。そしてその上で世の中としっかりと関わりを持って生き抜いた。決して隠遁生活をしていたのではなく、堕落した宗門から離れ、何を言われても最後まで己のやり方で慈悲慈愛の志を貫き、己の姿をどこまでも見つめ、自分の行くべき道を歩んだその人生に魅力を感じます。
書や詩に関しても、良寛のそれは定型というものが無い。勿論流派も肩書きも何も無い。子供のころから良い教育を受けていたので、学問や教養の素養はかなり高いレベルで持っていたようですが、そういう身に付けた知識や常識、権威のようなものに全くおもねることなく、どこまでも自由に感性を開き独自の道を通した。こういう部分に私は激しく惹かれるのです。
 出雲崎
出雲崎
私も流派や組織とは離れ、全て自分が作った音楽作品を聴いてもらっているので、そんな意味でも良寛の生き方には感じるものがあります。今回の舞台をきっかけに、良寛の姿が一つの目標のように思えてきました。
私は、豊かな知性があってはじめて、想いも行動も実を結ぶと思っています。いくら独創的であっても、その土台となるものが無くては、独創性もただのアイデアで止まってしまいます。良寛の姿はそれを正に証明してくれたように思っています。その土台とは単なる知識とかではなく、物事をしっかりと見抜く本物の知性、そこを持っているかどうかです。良寛は一見自由に、気ままに生きていたように見えますが、そこに土台となる豊かな知性があったという事が、何よりも素晴らしいのです。
そういう本当の知性を持つことはなかなか大変です。人間は小賢しい知識など持っていると、かえってものが見えなくなるものです。自分の小さな頭だけで考え、頑張っている事に満足し、我流でただ気合入れてやっているだけに終わってしまう事が多い。それは自己満足の世界でしかない。積極的に学び、自分の無力さを感じ、「はからい」によって導かれている自分を感じてはじめて、自分の道を見出す。これが知性というものではないでしょうか。
良寛は、知識や技術、常識、権威・・そういうものに寄りかからず、そこを乗り越えて自ら歩むべき道を歩んでいきました。そして後世の我々に多くのものを残してくれました。そういう良寛に、私は共感と感謝を感じずにはいられません。
邦楽も今、自らの姿を見つめ直すことをすべき時期だと思います。都合よく流派や肩書きをひけらかしているようでは・・・・。まともな知性を持つべきだとだと思います。
良寛の無一物で生きた姿は我々に大きな示唆を与えてくれます。そしてその姿は実にすがすがしく思えるのです。
 五合庵
五合庵良寛は生き方に関して矛盾が無いのだと思います。常に淡々と自分の行くべき道を歩む。批判されようが、何されようが自分自身に対し矛盾を許さない。徹頭徹尾純粋だったのではないでしょうか。そこには深い慈悲や慈愛の想いがあったればこそ、何者にも囚われない大きな世界を得、それが書や詩などのかたちで残ったのでしょう。我々はそれを見て、我が身を振り返り、良寛の大きな世界を前にして、ただ頭を垂れるばかり・・・。
 現代人は「私」というものが良くも悪くも強い。強すぎる。だからどうしても物事に対し、自分が見えている所だけを見て、小さな自分の頭で判断を下してしまう。全てにおいて自分の感情が最優先で、己の世界が全てになっているのが現代人です。自分が見ている以外の所、自分の興味ないものに価値を見出さない。別の角度から物事を見て判断し、自らを振り返るという能力が著しく欠けている。自分自身もそういう所を自らの中に感じているので、良寛の常識や知識や権威等の一切のものに囚われない純粋さ、自分の無力を徹底的に感じている姿は、私に多くの事をもたらし、私の目を開いてくれるのです。
現代人は「私」というものが良くも悪くも強い。強すぎる。だからどうしても物事に対し、自分が見えている所だけを見て、小さな自分の頭で判断を下してしまう。全てにおいて自分の感情が最優先で、己の世界が全てになっているのが現代人です。自分が見ている以外の所、自分の興味ないものに価値を見出さない。別の角度から物事を見て判断し、自らを振り返るという能力が著しく欠けている。自分自身もそういう所を自らの中に感じているので、良寛の常識や知識や権威等の一切のものに囚われない純粋さ、自分の無力を徹底的に感じている姿は、私に多くの事をもたらし、私の目を開いてくれるのです。
良寛の志は後に、鈴木文台、長谷川泰、吉岡弥生、野口英世ら多くの人々に受け継がれて行った事を初めて知ったのですが、やはり高い志、精神はどこかで必ず受け継がれてゆくのだな、と思いました。隠遁した坊さんなんて思っていた自分が恥ずかしくなりました。
 良寛役の津村先生と
良寛役の津村先生と良寛自身も「はからい」によって導かれ、後にまた多くの人が良寛を通じて導かれた。今回私もまた導かれたように思います。
来年は良寛の事を琵琶唄にしてみようと思っています。どういう形になるか判りませんが、取り組むべき題材だと感じています。
今回の舞台は、音楽をやっていく上で良い機会となりました。
先日、新潟六日町のお寺 雲洞庵にて演奏してきました。
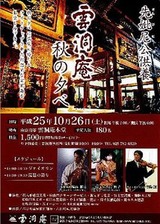 雨にもかかわらず大勢の方にお越しいただき、とてもいい雰囲気で演奏出来ました。このお寺はもう5、年ほど前に、六日町のイベントで演奏した帰りに連れてきてもらったところで、「いつかここで演奏会をやれたらいいですね」と言っていたのが、ここにきて実現したのです。ちょうどこの雲洞庵が大河ドラマ「天地人」の舞台となった頃に、主人公の直江兼続の曲を作って欲しいと六日町の方からいわれ、作詞作曲した曲があったのですが、今回もその曲「寒月の教へ」をメインに演奏してきました。
雨にもかかわらず大勢の方にお越しいただき、とてもいい雰囲気で演奏出来ました。このお寺はもう5、年ほど前に、六日町のイベントで演奏した帰りに連れてきてもらったところで、「いつかここで演奏会をやれたらいいですね」と言っていたのが、ここにきて実現したのです。ちょうどこの雲洞庵が大河ドラマ「天地人」の舞台となった頃に、主人公の直江兼続の曲を作って欲しいと六日町の方からいわれ、作詞作曲した曲があったのですが、今回もその曲「寒月の教へ」をメインに演奏してきました。
 photo 酒井建
photo 酒井建
この雲洞寺は中越では一番大きなお寺で、タイトルの「雲洞庵の土踏んだか」という言葉は、修行者がこの雲洞庵の道場で学ばなければ、一人前の禅僧とは言えぬ、という所から出て来た言葉だそうです。それくらい大きなお寺だったという事ですね。
禅宗のお寺らしく、派手さは無く、しっとりと落ち着いた感じのするお寺さんでした。 ご住職も地味で、且つにこやかで気持ち良く迎えてくれたのが嬉しかったです。今回は通常の演目の他、雲洞庵の縁起を琵琶唄と朗読に仕立てて、地元のFM局 FM雪国の岡村アナウンサーと共にやってきました。
ご住職も地味で、且つにこやかで気持ち良く迎えてくれたのが嬉しかったです。今回は通常の演目の他、雲洞庵の縁起を琵琶唄と朗読に仕立てて、地元のFM局 FM雪国の岡村アナウンサーと共にやってきました。
新潟にはもう10年以上前からご縁を頂いていて、特に湯沢、六日町ではどんどんと縁が繋がって行きます。今回も地元の方の集まりである「にいがた山賊の会」に急遽おじゃまして熊汁を食べてきました。またこの辺りは何と言ってもコシヒカリの産地ですから、皆さん米に対するこだわりと誇りが半端なかった。素晴らしい!。旅はなんといってもこういう出会いが楽しいのです。ただ演奏してくるだけではなくて、その土地の食べ物、酒、そして人々と関わって行く事が私の仕事なのです。


 龍言の庭
龍言の庭
そして今回泊まらせてもらったお宿はこちら。「温泉御宿 龍言」という古民家を移築して作った素敵なお宿でした。周りが木々に囲まれ、大きな池があり、滝もある素敵な場所で、心も体も癒されました。お世話になりました。
土地に触れ、人々と交わり、琵琶を聴いてもらって…、私は本当に面白い仕事をしているな、と実感した演奏会でした。
 さて、のんびりとはしていられません。今週は31日の木曜日に戯曲公演「越の良寛」が控えています。脚本は和久内明先生、そして能シテ方の津村禮次郎先生との共演です。只今朝から晩まで稽古の真っ最中です。
さて、のんびりとはしていられません。今週は31日の木曜日に戯曲公演「越の良寛」が控えています。脚本は和久内明先生、そして能シテ方の津村禮次郎先生との共演です。只今朝から晩まで稽古の真っ最中です。
杉並公会堂小ホールで18時30分開演です。ぜひぜひお越しくださいませ。
秋は毎年、良いお仕事をたくさん頂いて、本当に充実しています。年末からはまた創作の時期に入りますが、年明けにも一つ大きな舞台が決まりまして、なかなかゆっくりしてはいられません。まだまだ私の旅は続きそうです。
是非是非ご贔屓に。
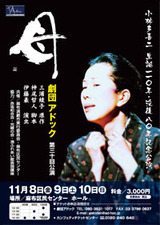
 こちらは来年のチラシ表。
こちらは来年のチラシ表。
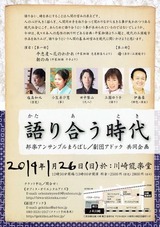 来年のチラシ裏
来年のチラシ裏




 七変化
七変化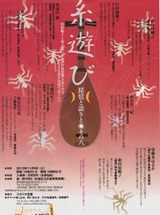
 煌めく才能は、現代社会の中にもしっかりとあります。その才能が更に煌めくには、大きな視野が必要です。自分のやっている事だけに興味を持つようなオタク目線では、何事もレベルは上がりません。「那須与一」や「壇ノ浦」のような流派の曲も勿論良いのですが、おさらい会と変わらないのでは、せいぜい関心しかしてくれません。聴衆を虜にするような独創性、そして魅力がなければ!更に世界に通用するレベルが無ければ!
煌めく才能は、現代社会の中にもしっかりとあります。その才能が更に煌めくには、大きな視野が必要です。自分のやっている事だけに興味を持つようなオタク目線では、何事もレベルは上がりません。「那須与一」や「壇ノ浦」のような流派の曲も勿論良いのですが、おさらい会と変わらないのでは、せいぜい関心しかしてくれません。聴衆を虜にするような独創性、そして魅力がなければ!更に世界に通用するレベルが無ければ!
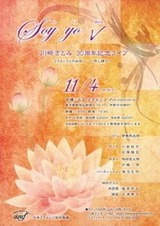
 エルフラメンコは日本におけるフラメンコの中心基地。スペインの一流のダンサーが来日して公演をする唯一の本格的なフラメンコのお店です。ジャズで言えばブルーノート東京みたいな所。ここで樂琵琶を弾いたのは私が初めてかもしれませんね。
エルフラメンコは日本におけるフラメンコの中心基地。スペインの一流のダンサーが来日して公演をする唯一の本格的なフラメンコのお店です。ジャズで言えばブルーノート東京みたいな所。ここで樂琵琶を弾いたのは私が初めてかもしれませんね。 これは楽屋の風景。何しろ皆さん居るだけで楽しい。この自由さは邦楽には無いですね。左からPerの海沼さん、ギターの内藤さん、カンテ(歌)の石塚さん、ギターの柴田さん。私は海沼さん、柴田さんと一緒に演奏しましたが、とにかくご機嫌でした。
これは楽屋の風景。何しろ皆さん居るだけで楽しい。この自由さは邦楽には無いですね。左からPerの海沼さん、ギターの内藤さん、カンテ(歌)の石塚さん、ギターの柴田さん。私は海沼さん、柴田さんと一緒に演奏しましたが、とにかくご機嫌でした。
 実はフラメンコギターと薩摩琵琶は共通点がとても多いのです。
実はフラメンコギターと薩摩琵琶は共通点がとても多いのです。 薩摩琵琶を弾きだした頃すぐにそれを感じましたが、特に演奏技術の面で、右手首の使い方などが大変似ています。また音階も似ているし、崩れの部分の感情の出し方などにも、一つの通奏低音を思わずにはいられません。哀調を帯びた音楽という所でも、繋がりを感じます。それゆえ私には両方を行き来しても
薩摩琵琶を弾きだした頃すぐにそれを感じましたが、特に演奏技術の面で、右手首の使い方などが大変似ています。また音階も似ているし、崩れの部分の感情の出し方などにも、一つの通奏低音を思わずにはいられません。哀調を帯びた音楽という所でも、繋がりを感じます。それゆえ私には両方を行き来しても


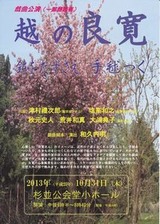 今回は書き下ろしの新作ですし、能シテ方の津村禮次郎先生との共演でもあったので、戯曲に対し、どう音楽を付けて演奏したらよいか迷うところもありましたが、とにもかくにも私にとってこの舞台は、良寛という人物に出逢えた貴重な体験となりました。良寛は今後私の中で、永田錦心とともにとても大きな存在となって行くと思っています。
今回は書き下ろしの新作ですし、能シテ方の津村禮次郎先生との共演でもあったので、戯曲に対し、どう音楽を付けて演奏したらよいか迷うところもありましたが、とにもかくにも私にとってこの舞台は、良寛という人物に出逢えた貴重な体験となりました。良寛は今後私の中で、永田錦心とともにとても大きな存在となって行くと思っています。


 現代人は「私」というものが良くも悪くも強い。強すぎる。だからどうしても物事に対し、自分が見えている所だけを見て、小さな自分の頭で判断を下してしまう。全てにおいて自分の感情が最優先で、己の世界が全てになっているのが現代人です。自分が見ている以外の所、自分の興味ないものに価値を見出さない。別の角度から物事を見て判断し、自らを振り返るという能力が著しく欠けている。自分自身もそういう所を自らの中に感じているので、良寛の常識や知識や権威等の一切のものに囚われない純粋さ、自分の無力を徹底的に感じている姿は、私に多くの事をもたらし、私の目を開いてくれるのです。
現代人は「私」というものが良くも悪くも強い。強すぎる。だからどうしても物事に対し、自分が見えている所だけを見て、小さな自分の頭で判断を下してしまう。全てにおいて自分の感情が最優先で、己の世界が全てになっているのが現代人です。自分が見ている以外の所、自分の興味ないものに価値を見出さない。別の角度から物事を見て判断し、自らを振り返るという能力が著しく欠けている。自分自身もそういう所を自らの中に感じているので、良寛の常識や知識や権威等の一切のものに囚われない純粋さ、自分の無力を徹底的に感じている姿は、私に多くの事をもたらし、私の目を開いてくれるのです。
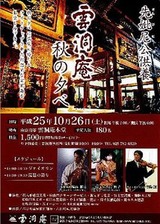 雨にもかかわらず大勢の方にお越しいただき、とてもいい雰囲気で演奏出来ました。このお寺はもう5、年ほど前に、六日町のイベントで演奏した帰りに連れてきてもらったところで、「いつかここで演奏会をやれたらいいですね」と言っていたのが、ここにきて実現したのです。ちょうどこの雲洞庵が大河ドラマ「天地人」の舞台となった頃に、主人公の直江兼続の曲を作って欲しいと六日町の方からいわれ、作詞作曲した曲があったのですが、今回もその曲「寒月の教へ」をメインに演奏してきました。
雨にもかかわらず大勢の方にお越しいただき、とてもいい雰囲気で演奏出来ました。このお寺はもう5、年ほど前に、六日町のイベントで演奏した帰りに連れてきてもらったところで、「いつかここで演奏会をやれたらいいですね」と言っていたのが、ここにきて実現したのです。ちょうどこの雲洞庵が大河ドラマ「天地人」の舞台となった頃に、主人公の直江兼続の曲を作って欲しいと六日町の方からいわれ、作詞作曲した曲があったのですが、今回もその曲「寒月の教へ」をメインに演奏してきました。
 ご住職も地味で、且つにこやかで気持ち良く迎えてくれたのが嬉しかったです。今回は通常の演目の他、雲洞庵の縁起を琵琶唄と朗読に仕立てて、地元のFM局 FM雪国の岡村アナウンサーと共にやってきました。
ご住職も地味で、且つにこやかで気持ち良く迎えてくれたのが嬉しかったです。今回は通常の演目の他、雲洞庵の縁起を琵琶唄と朗読に仕立てて、地元のFM局 FM雪国の岡村アナウンサーと共にやってきました。


 さて、のんびりとはしていられません。今週は31日の木曜日に戯曲公演「越の良寛」が控えています。脚本は和久内明先生、そして能シテ方の津村禮次郎先生との共演です。只今朝から晩まで稽古の真っ最中です。
さて、のんびりとはしていられません。今週は31日の木曜日に戯曲公演「越の良寛」が控えています。脚本は和久内明先生、そして能シテ方の津村禮次郎先生との共演です。只今朝から晩まで稽古の真っ最中です。