先日、オペラシティーで行われた、コンポージアム2015武満作曲賞の本選会を聴いて来ました。今年はカイヤ・サーリアホ氏を審査員に向かえての開催とあって、サーリアホ作品に関心のある私としてはぜひとも聞いてみたいと思っていました。
HP:http://www.operacity.jp/concert/compo/2015/schedule/150531.php

私は現代音楽分野の専門家ではないので、評論は出来ませんが、現代音楽も含め音楽に携る演奏家作曲家として、色々と想う所がありました。この武満作曲賞は毎回審査員を一人だけ招き、最初の選考から最後の本選までをゲスト審査員一人でやるというユニークなもので、審査員の器も試される、結構難しいコンクールなのです。したがって毎年審査員の好みも反映されるし、過去には電子音楽の作品が出たり、エレキギターやターンテーブル、サンプラーまで入った作品もあったそうです。
今回ファイナリストに残ったのは80年代90年代生まれの若い海外の作曲家4人。皆力作で、個人的にはトルコの作曲家イーイト・コラット氏の作品「difeʁãs」が気に入りました。一度聞いただけでは細かな手法やアイデアは読み取れませんが、オーケストラの響かせ方に独自のものを感じました。皆さん色々な手法を駆使しているし、感覚的にグローバルな感じで、民族性に拘ったりするものはありませんでした。6月21日と28日の朝8時10分からFMの「現代の音楽」で放送されるとの事ですので、是非興味のある皆様には聞いて頂きたいと思います。
 ウズベキスタン イルホム劇場 現地の現代音楽グループとの共演
ウズベキスタン イルホム劇場 現地の現代音楽グループとの共演
作曲というものを論じる程の技量と知識を私は持っていませんが、複数の要素を構築して建築物のように創り上げて行くヨーロッパ的な手法は、そろそろ卒業しても良いのではないかと、個人的に思っています。別に民族的な手法に戻れという事ではありませんし、ジョン・ケージを賛美している訳でもありません。積み上げて創り上げて行くという考え方ではなく、人工的な構築とは別の方向で作曲しても良いのではないかと思うのです。勿論昨今の作曲家がマーラーやシェーンベルクのような論理の所で留まっている訳ではないし、今回の作曲家たちを見ても大変アイデアに富んでいます。しかし要素を構成し、積み上げるようにして曲を構成して行くという点では以前と変わらない。オーケストラを使う以上、秩序が必要ですし、法則も無ければ音が鳴りません。これまでも12音やセリーの技法などあらゆる考え方や手法が出ては消え繰り返されてきましたが、アイデアの果てに何が生まれたのだろう?というのが正直な所です。
トルクメニスタンでの演奏会にて
今回はグローバルな感じと共に、どれもがいわばヨーロッパ的でもありました。元々経済力、政治力、軍事力などで世界を制覇したヨーロッパの文化がグローバルという名の下で世界の基本として広まった訳だし、日本もそれを取り入れて、世界の一員となって行った訳ですから、とにかくヨーロッパが中心なのは当たり前でしょう。しかしもうこれからは経済も政治も何もヨーロッパの時代は過ぎ去る事も見えてきました。それを考えると世界音楽としてのクラシック音楽はそろそろ終焉を迎えているとも考えられます。クラシック音楽がグローバルな視点をこれ以上拒否するのであれば、それはそれで良いでしょう。ただクラシックの奔流がこれからも続いて行くためには、新しい概念が必要なのは目に見えているのではないでしょうか。
時代はどんどん動いて行きます。次の時代を感じさせるような視点をもう少し聴きたかったですね。
現代音楽について、ここ20年程思っていたのですが、生っぽい感じがあまりにも無いのです(ポップス分野でも感じますが)。一時は肉体性を排すなどというものが流行った事もありました。洗練と言ってしまえばそれまでなのですが、クラシック音楽の延長である現代音楽が、どこか地に足がついていないと思うのは私だけではないでしょう。論理や構成こそはクラシックのクラシックたる所だと思いますが、そろそろそこを乗り越え、もっと人間の生を謳歌して良いのではないでしょうか・・・・・。私の個人的な意見でしかありませんが、ずっとそんな感じを持ち続けています。
郡司敦作品演奏会、Violin、Cello、Piano、合唱、尺八、筝、琵琶
邦楽でもクラシックでも、何か大きな概念の転換が必要な時期に来ていると思います。日本も世界もこれから10年で大きく変わって行くでしょう。テクノロジーももっともっと進んで、これまでの哲学が通用しなくなるところに行くと思います。アジアが世界の中心になるとは私は思っていませんが、欧米中心の世の中はもうこれ以上続かないと思います。アジア圏だけでなく、。アラブ圏やアフリカの情勢もこれから刻一刻と変化して、それに伴い時代の価値観、センスはこれから目まぐるしき勢いで変わって行くでしょう。音楽はそれに就いて行けるだろうか・・・・?

和楽器 ブログランキングへ
先日、能楽師 津村禮次郎先生のドキュメンタリー映画「踊る旅人」の試写会に行ってきました。
http://www.nohgakutimes.jp/archives/308
津村先生とは戯曲公演「良寛」では三度共演させてもらって、本当に素晴らしい時間を共有する事が出来ました。特にラストシーンでの樂琵琶と先生の舞だけの8分間は忘れられないですね。そんな津村先生のあくなき追求が良く判る映画になっていると思います。6月27日新宿ケイズシネマにて上演されるとの事ですので、是非観て頂きたいと思います。
 「良寛」ラストシーン
「良寛」ラストシーン
それにしてもドキュメンタリー映画が出来るというのは凄い事ですね。つまりそれだけの充実した仕事をしてきたという事なのでしょう。実は、先日このブログに書いた灰野敬二さんも昨年ドキュメンタリー映画が公開されました。凄い人に囲まれて幸せです。
お二人に共通している事は、目先の売れ線に絶対に行かない事です。あくまでもどこまでも己のやるべき事を貫いている。何を言われようと自分の価値観と美学を信じて、己の求める所に向かって活動をしている。お二人のこういう部分には心底惚れ込んでしまいます。そして大きな力と刺激を私に与えてくれます。私もこういった人生を歩みたい。経済的な事も含め、多くの困難もあると思いますが、自分の行くべき道を只管歩んで行きたいと思います。
歌手のバックバンドをやって喜んでいる人も多いし、タレントのような活動に傾倒して行く人も居ますが、そういうものは私のやるべきものではない。私には私のやるべきものがある。それをどこまでもやって行きたい。
「良寛」公演にて
音楽以外の所で注目されても仕方がないと私は思います。奇抜で珍しいパフォーマンスで売ったり、肩書きに寄りかかってその力で舞台を張るような、そんな人生は送りたくないですね。琵琶がただの物珍しさで聴かれ、琵琶=耳なし芳一みたいに聴かれるという事はイメージだけで聴かれているという事。音楽を聞いてくれている訳ではないのです。そんなものは誰がやってもいいのです。
パコ・デ・ルシアは、フラメンコという民族色の強い音楽を世界のスタンダード音楽にのし上げました。何故琵琶でそれが出来ないのでしょう?????。意識も知識も技術もまだまだ小さすぎるのではないでしょうか。私は薩摩琵琶でも樂琵琶でも、「こうでなければ琵琶じゃない」という凝り固まっている概念そのものを乗り越えて行きたいのです。
 「良寛」公演にて
「良寛」公演にて
日本人は個としての自立が出来ていないと言われますが、邦楽でもジャズでもみな、自分がどのグループに所属しているかという事で自分を保っている人があまりにも多すぎる。私は私、あなたはあなた。どんな場に行っても、自分のやるべき事をやればよいし、コンプレックスを持つ必要もない。
音楽家なら音楽で勝負するのが真っ当なのです。それが出来ないから余計な尾ひれで自分を飾るのです。だから私はそういう尾ひれを付けた人とは付き合わない。私がお付き合い頂いている方々は皆さん、何かしら賞も取っているだろうし、名前もあると思いますが、絶対にそういう事で自分を売ろうとしないし、口にも出さない。津村先生も灰野さんも対等の音楽家として常に接してくれます。舞台人はそうでなくては!!。周りの方が、色々はやし立てるのは結構ですが、自分から学歴やらキャリアを口にするのはどう考えても、どんな分野でもおかしいし、そういう輩はろくでもないのは世の常です。

兎にも角にも、自分の求める所を只管進み、良い仕事をしたいものです。良き先輩達を持って幸せです。
 城ケ島
城ケ島もう毎日半袖で過ごすようにになりましたね。季節の移り変わりの速さが身に沁みるこの頃です。日々なるべく色々なものに囚われないように生きたいと思うのですが、社会と共に生きざるを得ない人間としては、世の流れには関わらずにはいられません。致し方ないですが、だからこそそこから音楽も生まれてきたのでしょうね。
最近よく「けれん」を感じる舞台に出会う事が多くなりました。この「けれん」という言葉は、高田栄水先生の所で琵琶の稽古を始めた時に聞いたのですが、一般的には、ある程度上手な方が、もっと上手に見せようとして、余計な装飾をしてしまったり、極端な表現をした時に言われます。自分の演奏にもこの「けれん」をどこかに自ら感じているからこそ、気になるのでしょう。
 人間は何かの枠の中で自分というものを認識する生きものですが、それ故どうしても枠の中での自己顕示、優劣の感覚等々様々な意識が湧き上がります。「けれん」は正にそうした「枠の中での自分」という意識から生まれてきます。そんな心は誰にも少なからずあるものですが、それに振り回されてしまった時、自分自身を失ってしまいます。そういった所にこそ、その人の器が試されるというものですね。
人間は何かの枠の中で自分というものを認識する生きものですが、それ故どうしても枠の中での自己顕示、優劣の感覚等々様々な意識が湧き上がります。「けれん」は正にそうした「枠の中での自分」という意識から生まれてきます。そんな心は誰にも少なからずあるものですが、それに振り回されてしまった時、自分自身を失ってしまいます。そういった所にこそ、その人の器が試されるというものですね。
「けれん」は、ある程度技量が無いと出て来ません。上手で、ある程度の事が
出来てしまうからこそ、やらなくてもいいようなコブシを回してみたり、極端な表現をしてみたくなってしまうのでしょう。何か一ひねりして、目の前の枠の中で自分の存在を知らしめようとする小さな心が「けれん」を生むのです。つまり上手に成ればなる程、高く深い精神を伴わなければ、良い音楽は響かないのです。派手な格好をして、調子っぱずれの歌を歌っている内は「しょうがねえな」で済みますが、一見ベテランのような顔をしていて、そこに「けれん」が見えてしまうと、かえってその質に疑問を持たれてしま
う。
問われるのは、技量ではなくて器であり、精神なのです。
けれん無き姿をしているか?
「けれん」が見える内は、多少の技量があっても結局そこまでしかないという事。その先にヴィジョンも無ければ、音楽の喜びも無い。自己顕示欲だけが聞こえてく
る。しかし「けれん」がまとわりついている人は、ひとたび想う所、見ている所が変わると演奏ががらりと変わります。技量も無く、勘違いしたプライドで固まっている人は論外として、心の持ち方一つで何もかもが変わるのです。それは元々ある技量が、ちゃんと理由を持ち始め、それら一つ一つが表現のスキルになるからです。音楽は結局の所、何を考えているかという所で成り立っています。技術で成り立つものではありません。その心が音楽という形になるだけなのです。ただその心を開いて行くのが一番難しい。練習したところで凝り固まった心や偏狭視野は変わらない、更に凝り固まって行くばかり。大きな世界を見て心を開けるかどうか。もうその人の器でしかありません。
ヴィジョンが定まって、柔軟な心と視野を持っている人は、そのヴィジョンを実現するための技量がどんどん身に付いて来ます。知識や技術に意味を感じているからです。最初はがむしゃらにやっても結構だと思いますが、自分が何をやりたいのか、何故それが必要なのか、何故やるのか。そうしたものがはっきりと見えた時に、勉強してきた技術や知識が自分の中で意味を持ちはじめます。
そしてある程度来た時にまた更に先の大きなヴィジョンを持てるかどうか。こうして段階を一つ一つクリアできる人は成長して行きますが、ある所で止まってしまう例が多いですね。私自身も常に柔軟な心でいたいと思っていますが、自分では自分の事はよく見えないので、多くの友人達と関わり話をすることで、様々な示唆や気付きを頂いています。何かをやり続けるには大切な部分ではないでしょうか。
いつまでも大きな視野、ヴィジョンを常に持ち、柔軟な心で居たいものです。「こうでなくてはならない」「こういうものだ」という狭く小さな感性、硬直した心では何も生み出せない上に、次世代へとつなげて行く事も出来ない。
魅力ある音楽を創りたいのです。それを更に良きものに、そして更に次世代へ。そんな想いが年を重ねるごとに増してきました。
先日は、日経新聞の記事に沢山のエールを頂きまして、誠にありがとうございました。大変反応が大きく、私もちょっとびっくりしました。この場をもってお礼に代えさせて頂きます。これからもどんどんと活動を展開して行こうと思っていますので、是非とも御贔屓にお願い申し上げます。
記事では樂琵琶の事ばかり書いてありましたが、薩摩琵琶もどんどん弾いて行きますよ。ただいわゆる従来の弾き語りのスタイルは少なくなって行くと思います。弾き語りはやるべき人がやって行くでしょう。私は私の音楽を追求します。薩摩琵琶では現代音楽的なアプローチや、声や唄を使った今までに無い形をもっとやって行きたいし、独奏曲も更に作りたい。樂琵琶の方も雅楽という枠ではなく、汎アジアという視点を持って色々な作品を作って行きたいと思います。
 若き日
若き日
私は有難い事に、15年ほど前から色々とメディアには取り上げて頂いていたのですが、今回ちょっと整理する意味で、以前のインタビューや掲載記事等読み返してみました。
昔から言いたい事を吠えてますね。言ってる内容も今と同じ。雑誌的には私のような反乱分子は面白いのでしょうが、30代の頃邦楽ジャーナルに書いた長文など、ここまで言っていいんだろうか?という位言いたい放題。
ジャズから始まった私の音楽人生ですが、邦楽の世界に入ってみて、これほどまでに名前や肩書きにすり寄る人がいるとは思いもよりませんでした。また邦楽界の低迷がそこにある事も痛感しました。そんな想いを吠えまくっていたんでしょうね。
それにしても邦楽はこれから変わって行くのでしょうか。本当に音楽をやる事が出来るのでしょうか・・・・・・?。
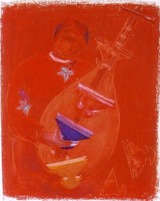
この絵を書いてくれたのは鈴田郷さんというおばあちゃまです。私のCDジャケットにも使わせてもらいましたが、今は毎月の琵琶樂人倶楽部の看板にさせてもらってます。実に自由に感じたままを書いてくれている。良い絵だと思います。私はこの素直な感性を大変気に入っているのです。
今邦楽にはこの素直さがあるとは思えません。我々は舞台が全てなのです。偉い先生でもお名取さんでも、大学の先生でも、はたまた私のように何にも書くことが無い人でも、舞台に立ったら皆同じ演奏家です。とにかく舞台がつまらなければお客様は二度と来てくれない。音楽は一般の方が聴くものなのだから、現代に生きる人々の感性に訴える力の無いものは、すたれて行っても仕方がない。解りやすくするというのでなく、何か魅力を感じさせることが必要なのです。
皆さんはお上手なものではなくて、素敵なものを聴きに来ているのです。核心を伝えながらも、感性は柔軟に時代に対応して行かないと伝わりません。村の中の価値観やお上手さは、現代社会に生きる一般の人には通用しないのです。仲間内にしか見えない重い幻想の鎧はもうそろそろ脱ぎ捨てて、素敵な舞台をやろうじゃありませんか!!!
とにかく素敵な琵琶の音を聴かせたいのです。かつて私はジミヘンやヴァンへイレンに衝撃を受け、ジェフベックに涙し、マイルスやコルトレーンにやられ、ウエスやジムホールに心酔し、青春時代を過ごして来ましたが、いつか次世代の若者が、純粋に音楽として私の残した作品を聴いて何かを感じてくれたら本望です。
まだまだ長い旅は続きそうです。
今月は刺激的な演奏を何度も聴かせて頂いたせいか、何だか気分が興奮気味だったのですが、やっと魂が落ち着き(?)家でゆっくり琵琶を弾けるようになりました。今月は灰野さん、中島さんのコンサートの他に、箱根のサロンコンサートも面白かったし、手妻の藤山新太郎師匠の公演にも毎週参加しましたが、本当に刺激の多い半月間でした。
良いものを聴くのは素晴らしい事ですが、興奮状態では自分の仕事が出来ません。落ち着いて我が身を振り返り、自分のやるべき事をしっかりと見据えないといけませんね。
先日、樂琵琶の事で取材を受けたのですが、その時に主に話したのが、樂琵琶に対する私の視点です。私が見ているのは雅楽の琵琶という事でなく、もっと汎アジア的な弦楽器という所。記者の方は充分に判ってくれたようなので嬉しかったです。私は雅楽もそれなりにやるけれども、雅楽師ではないのです。現行の雅楽も含め、樂琵琶はその歴史にアジア全般を背負っています。私は樂琵琶やそれ以前の弦楽器達の辿った歴史に興味がありますので、雅楽という限定された中で樂琵琶を見てはいません。
以前からシルクロードを視野に於いて樂琵琶を弾いて来ましたが、樂琵琶で秘曲や、古典曲のアレンジ物などオリジナルのCDを3枚出してみて、更にその想いは強くなったと思います。薩摩琵琶は日本で生まれたものですから、現代日本の音楽を高らかに歌い上げるべきだと思いますが、樂琵琶はどんどん国境を超え、時代を超え音楽を奏でるべきと思っています。
 やっとゆっくり琵琶を向き合う時間が訪れ、ここ数日は改めて琵琶楽に対するアプローチを考える良い機会となりました。
やっとゆっくり琵琶を向き合う時間が訪れ、ここ数日は改めて琵琶楽に対するアプローチを考える良い機会となりました。
私が樂琵琶に取り組むきっかけとなったのは、「殿上人の秘曲」というCDです。多忠輝さんの演奏する「啄木」をじっくり聴いてみて、やっぱり「これだな」っとあらためて頷いてしまいました。この演奏は家元や樂家に良くある、「確かに間違いのない伝承だけれども、どうも腑に落ちない」という所を全く感じない。弦楽器をあるべき姿に豊かに鳴らし、歌わせている。多彩なタッチも素晴らしい。実は私が、雅楽や邦楽で一番腑に落ちないのが、ぶっきらぼうとも言えるヴァリエーションの無いタッチなのです。そこに豊かな感性は感じられないですね。
この多先生のタッチは実に繊細で、表情がある。樂琵琶を大きく歌わせている。もしこの演奏に出逢わなかったら、私は樂琵琶を弾いていなかったでしょう。機会は無いと思いますが、一度多先生にお目にかかってみたいものです。
中でも「啄木」は今聞いてもモダンな感じで、古臭いという所がみじんも無いですね。一番好きな曲です。おおらかで明るく、大陸の風を感じます。樂琵琶の音色は全体にこのイメージがあるのですが、「啄木」は特にこうしたイメージを喚起させますね。薩摩琵琶は逆にあの何とも言えない湿った暗さが一つの魅力なのですが、携わる人の感性が変わると、同じ琵琶でもここまで変わるんですね。
また「啄木」が時代を超えて魅力を放つのは器楽という所が大きな要因だと思います。例えば新古今のような和歌だったら、古風な言葉でもその感性は今でもそのまま通じるものがありますが、歌詞の入った曲は、時代が変わってしまうとどうにも感覚的に判らないというものも少なくないです。特に近代の曲は時代が近いだけにかえって判らないものが多いような気がします。例えば「石堂丸」や「戦艦大和」等はどうにも解せない部分が多々あります。明治以降、時代と共に人々の感性が大きく変化したのですから、これは致し方ないですね。
「啄木」は器楽だからこそ、色々な時代の感性に晒されても、魅力を感じてもらえたのではないでしょうか。筝曲の「みだれ」もそうですが、現代音楽とも言えるようなモダンを感じます。武満徹は「音楽には国境がある」といいました。確かに武満の言葉は十二分に頷けるものがありますが、私はそれを判った上で、あえて音楽は時代も国境も越えると言いたい。
そして改めて感じたのは伝統を守る最前線にいる人と、次世代の日本音楽を創ろうとする私とでは、同じものを同じように弾いても違うんですね。表面上は同じです。そっくりそのままコピーしましたから、さらっと聞く分には同じに聞こえるかもしれませんが、確かに違う。その違いは是非先入観を取り払いお聴きになって感じて頂きたいと思います。
しかし継承という部分と、ある意味真逆な創造という二つの両輪が「啄木」という曲で繋がっているというのは面白いじゃないですか。それだけこの曲には大きな器や懐の深さがあるという事だろうし、だからこそ今聞いてもとても新鮮な魅力が溢れていると思います。
樂琵琶の魅力をどんどん聞いてもらいたいですね。

 ウズベキスタン イルホム劇場 現地の現代音楽グループとの共演
ウズベキスタン イルホム劇場 現地の現代音楽グループとの共演










 人間は何かの枠の中で自分というものを認識する生きものですが、それ故どうしても枠の中での自己顕示、優劣の感覚等々様々な意識が湧き上がります。「けれん」は正にそうした「枠の中での自分」という意識から生まれてきます。そんな心は誰にも少なからずあるものですが、それに振り回されてしまった時、自分自身を失ってしまいます。そういった所にこそ、その人の器が試されるというものですね。
人間は何かの枠の中で自分というものを認識する生きものですが、それ故どうしても枠の中での自己顕示、優劣の感覚等々様々な意識が湧き上がります。「けれん」は正にそうした「枠の中での自分」という意識から生まれてきます。そんな心は誰にも少なからずあるものですが、それに振り回されてしまった時、自分自身を失ってしまいます。そういった所にこそ、その人の器が試されるというものですね。



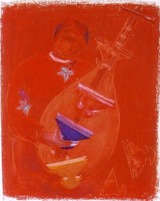


 やっとゆっくり琵琶を向き合う時間が訪れ、ここ数日は改めて琵琶楽に対するアプローチを考える良い機会となりました。
やっとゆっくり琵琶を向き合う時間が訪れ、ここ数日は改めて琵琶楽に対するアプローチを考える良い機会となりました。