先日、「弦流」の演奏会を無事終えました。とても充実した内容になって嬉しかったです。「平成絵巻方丈記」もそうでしたが、今回も日野さん、常味さんというベテランと共に演奏して、つくづくベテランと言われる人達の充実した演奏に感服しました。こういう機会を持てたことは大きな収穫でしたね。
この演奏会を持って年内の演奏活動を締めくくりました。新年は10日のMjamでの演奏からスタートいたします。来年も引き続きよろしくお願い申し上げます。

9月 尾形光琳「菊花屏風図」前での演奏 箱根岡田美術館
今年一年は、私の音楽活動の中でもとりわけ充実した一年となりました。日経新聞の文化欄で紹介して頂いたことが大きかったですが、そこから色々な出会いが繋がりました。初めての場所での演奏会にも沢山恵まれました。やはりメディアに載るということは広告的な効果が高いですね。
年始めからは、今迄の作品がネット配信となり、世界中の方が聴いてくれたということも嬉しい事です。特に台湾での売り上げが突出していたのが自分でも面白いと思いました。
音楽家なら誰しも純粋に音楽だけやっていたい、と誰しも思うことでしょう。しかしプロという立場になったら、どうしても売って行かなくてはいけない。ここが一番難しい所です。売れている自分に満足という方も居るので、そちらに比重が大きい人は、また違うと思いますが、私はどこまでも自分が納得する音楽をやりたい。かといって人から支持されない音楽をやり続けても食べていけない。厳しい所ですが、ここを何とかクリアしなければ成り立たないのです。演奏家とリスナーにはいつの時代も距離と溝があるもの。自分がリスナーに回ってみると良く判ります。踏ん張り処ですね。
邦楽には、音楽以外の仕事をしながらやっている人も多いですが、お金の面を考えないでやっている人は、やっぱりレベルも意識もアマチュアのそれを越えられないと感じます。常に舞台に立って、清濁ギリギリのところで勝負してこそ、魅力ある音楽は生まれて行くものではないでしょうか。
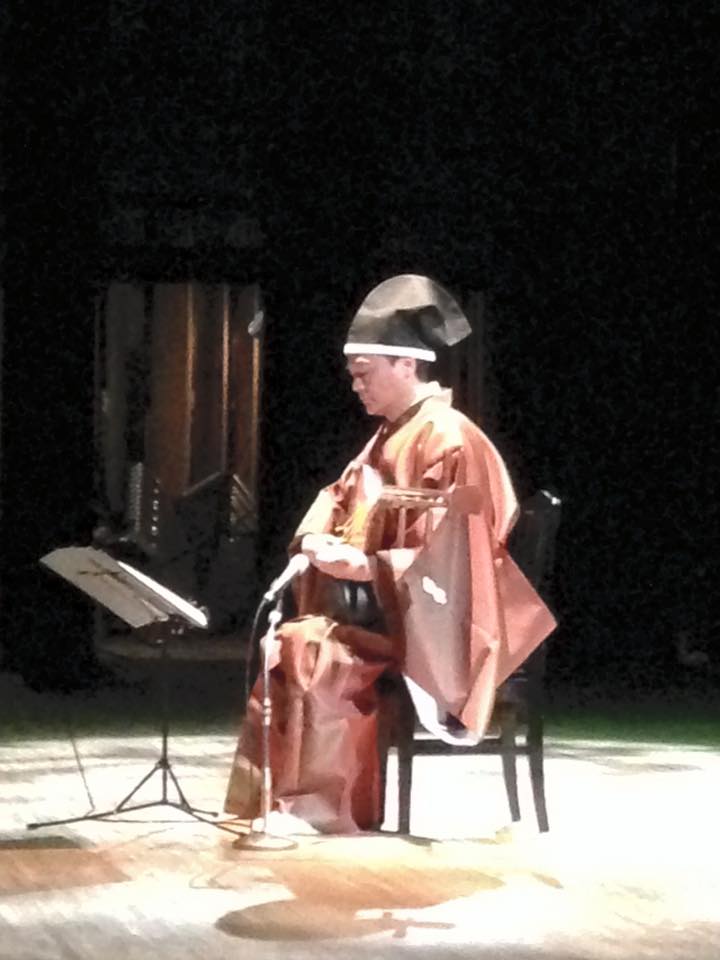 9月山科文化会館
9月山科文化会館
ここまでやって来て、私は私のやり方をするのが一番だし、まあそれしか出来ないな、という実感があります。20代の頃とは随分考え方も変わってきているし、売る事よりも、素晴らしい作品を残すことの方に喜びを感じます。薩摩琵琶のように古典というものがほとんど無いジャンルに転向したのは私にとっては良かったと思います。薩摩琵琶だったからこそ、旺盛な創作活動が可能であったと思います。これが能や雅楽では難しかったでしょうね。
樂琵琶も雅楽とは距離を置いて接していることが自分にとって大事なことだと思っています。ちょうどメセニーが独自にオーネットを研究しているような感じです。
他にない独自のスタイルとオリジナルな音楽は、琵琶という楽器に出会った事で具現化したと思っています。
かの武蔵は「神仏を尊び、神仏に頼まず」と書き残していますが、私もそんな心境で居たいと思っています。何かに寄りかかって生きて行くのは私の性に合いません。大学や流派協会、肩書き受賞歴など余計なものがないからこそ、しがらみも無く自由に動けるのです。これからも思うように活動して行きたいと思っています。その活動がどれだけの支持を得るのか私には判りませんが、ビジネスとして捉えるのでなく、あくまでも芸術活動として、どこまでも意志を貫いて行こうと思います。
1月戯曲公演「良寛」
来年も色々舞台が目白押しです。戯曲公演「良寛」、平成絵巻「方丈記」はシリーズ化して行きますし、何時ものReflectionsも勿論、薩摩琵琶でのソロ公演の活動も旺盛に展開して行く予定です。まだまだ旅の途中、歩みは緩めませんよ!!
来年もよろしくお願い申し上げます。
世はクリスマス一色ですね。今年は明日25日に演奏会を控えているので、時間を取ってゆっくりのんびりは出来ませんが、一年の締めくくりの時期ですし、色んな人と会い杯を交わす時期でもありますので、この一年を振り返り、来年の方向性を静かに考えて過ごしています。
先ずは25日の演奏会のお知らせを!
ペルシャ辺りからがじまった弦楽器にバルバッドというものがあるそうで、それが今日の琵琶の起源という説をよく耳にします。そのバルバッドがアラブではウードになり、西に行けばリュート、ギターになり、東に行けばシタールや琵琶になったそうです。その歴史は正にシルクロードを経て各地に伝わったということを考えると、各地の楽器にも文化にも親戚のよしみを感じます。
以前も書きましたが、バグダッドが栄えていた頃、シリアブという人物が当時最先端の文化音楽をイベリア半島に伝えたことで、現在のフラメンコの基礎が出来上がっていったようです。そんな事を思うと、シルクロードがイベリア半島まで延長していたかの様な想いにもかられますね。
という訳で、12月25日 夜7時開演です。
場所は参宮橋の小さな音楽サロン
リブロホール http://libromusic.co.jp/librohall/hall.html
出演は,ウード:常味裕司、 フラメンコギター:日野道生、 樂琵琶・薩摩琵琶:塩高和之です。各人のソロ、デュオ、最後はトリオによる合奏等々バリエーション豊かに演奏します。是非お越しくださいませ。
トルクメニスタンのアシュカバッドでの演奏会にて
年末に、一年間良い仕事をさせてもらった事を感謝できるというのは嬉しい事です。毎年毎年内容も良くなってきて、紆余曲折しながらも活動が充実してきているという実感もあります。こうした実感の根底に感じるのは、仲間達の存在ですね。先輩後輩、師匠、友人知人・・。本当に素敵な方々に恵まれているという想いが年を追うごとに増しています。勿論折り合いの上手く行かない人もいますが、そういう人こそ、何かを教えてくれるものです。また一緒に仕事をしたり、常にいろんな話をしたりするごく身近な相棒には本当にお世話になっていると思っています。数多くの出逢いは勿論ですが、身近な仲間や相棒と常にいろんな意見を交わしていることが、私にとって大きな糧ですね。
私の中の思考や哲学が毎年少しづつでも深化しているとしたら、それは仲間のお蔭です。琵琶は基本が独奏なので、自由に何でもできる反面、とかく小さな世界に籠りがち。自分の中の価値観でしかものを見なくなったらろくなものは出来ません。自分の知らないことや、一見「たいしたことないな」なんて思うことにこそ、別の価値があり、豊かな世界があるものです。自分の経験からしかものを見ず、興味のある分野にしか価値を見いだせなくなったら音楽家としてはお終いです。
だからこうして様々な分野で仕事をして行けることは本当に幸せですね。
来年からは、戯曲「良寛」や平成絵巻「方丈記」がシリーズ化して行く感じですし、明日演奏会の「弦流」もこれから続いて行きそうなトリオです。来年2月には恒例のREFLECTIONS演奏会がまた近江楽堂で控えていますので、また来年が楽しみになってきました!!。
先日、平成絵巻「方丈記」をやってきました。
伊藤哲哉さんの語りを中心に、水野俊介さんの5弦コントラバスと私の樂琵琶。それにヒグマ春夫さんの映像が我々を包み込むという異次元空間がなかなかに面白かったです。会場となった六本木のストライプスペースもお客様で満杯という嬉しい公演でした。
「方丈記」を書いた鴨長明は、来年が没後800年ということで、来年3月26日にはルーテルむさしの教会、命日が6月ということで、6月10日には相模原南市民ホール、6月30日には兵庫芸術文化センターホールにて公演が決まっています。まだまだ面白く練れて行く舞台ですので、今後の展開が実に楽しみです。
 それにしても皆さんそれぞれの世界の大ベテラン。豊富な経験と技術があるということは、良いものを生み出す土壌があるということですね。こういうものは若手では出来ません。それだけ充実したものを感じました。そして皆さん素晴らしいキャリアがあるにもかかわらず大変に気さくな方々。どの世界でもまともな人はどんなにキャリアを積んでも、そんなものに寄りかかったりしませんが、今回のメンバーは本当に皆が対等なのです。器がでかいな。
それにしても皆さんそれぞれの世界の大ベテラン。豊富な経験と技術があるということは、良いものを生み出す土壌があるということですね。こういうものは若手では出来ません。それだけ充実したものを感じました。そして皆さん素晴らしいキャリアがあるにもかかわらず大変に気さくな方々。どの世界でもまともな人はどんなにキャリアを積んでも、そんなものに寄りかかったりしませんが、今回のメンバーは本当に皆が対等なのです。器がでかいな。
私は若いころからジャズ仲間に囲まれていたせいもあって、邦楽人の肩書きを常に看板にする姿は今でも馴染めません。特に若手から肩書きだの格だのという発言が聞こえてくるのは残念で仕方がないですね。まあ小さな世界に入って、そこの常識に染まってしまうのは人間仕方がないですが、こと音楽や芸術に関しては、浮世の垢にまみれたくはないですね。

Metのオペラ「テンペスト」(作曲トマス・アデス)のラストシーンで、主人公プロスペローが「人間は自尊心で死ぬのだ」と弟に対し言い放つ所がありましたが、人間は自分の持っているプライドというもので、自分自身を振り回してしまいますね。小さな村社会しか見ていない人と、世界を視野に入れている人では全く違うプライドを持つでしょう。また信仰によっても変わってくるかもしれません・・・・。人間という存在の危うさを感じます。
私にはプライドというよりは、まあ意地と言う方が合ってますでしょうか。言葉はどうであれ、とにかく自分の奏でる音楽が「愛を語り届ける」ものでありたいということは一貫しています。まあ人それぞれだと思いますが、音楽より先に肩書きぶら下げて見栄を切って闊歩しているより、聞いてくれる人や出会う人に感動を持って接してもらえるような人生の方がいいじゃないですか。
私はこれまで多くの先輩や先生に恵まれたと思っています。直接指導を受けた先生は勿論、何時もの相方や後輩達からも常に多くの気づきを頂いています。「上手くなりたい」とは楽器をやっている人は誰でも思うと思いますが、そんな程度の意識ではとてもプロの舞台には立てないのだ、ということも教わりました。音楽家は音楽をやることが目的。何を表現するか、それが問われているのです。上手も結構、偉いも結構ですが、その先にある魅力ある音楽に意識が行っていなければ、ただのお稽古事でしかありません。逆に上手などというものは仇にもなります。いわんや偉いかどうかなんて・・・。
 ジョンレノンやボブディランの歌に対して音程がどうの、発声がどうのという人はいませんね。マイルスもジミヘンも同様、リスナーはその音楽を評価しているのであって、技でもなんでもないのです。そんなことは誰もが当たり前に思っていることが、当事者になると見えなくなってしまう。まあこれが業にまみれた世の中というものですが、その中でうごめいて終わるか、それともその先に行って音楽を創造するか、結局はその人の器でしかないですね。
ジョンレノンやボブディランの歌に対して音程がどうの、発声がどうのという人はいませんね。マイルスもジミヘンも同様、リスナーはその音楽を評価しているのであって、技でもなんでもないのです。そんなことは誰もが当たり前に思っていることが、当事者になると見えなくなってしまう。まあこれが業にまみれた世の中というものですが、その中でうごめいて終わるか、それともその先に行って音楽を創造するか、結局はその人の器でしかないですね。
自然は何よりも美しいですが、人間のようなつまらないプライドは持っていません。人間だけが小さなプライドというものに振り回されうごめいているのです。これだけ綺麗な紅葉も、ただ自然のまま、ありのままの姿でしかないのに、人間はどこまでもあれやこれやと画策し、追い求め論争を繰り返し、挙句の果てに優劣や格式を創り出し、それにまた振り回され、結局は本来の在るべき姿も判らなくなり、ありのままで生きるという生物としての本質的な生き方すらも忘れたまま生を終えてしまう。
音楽や芸術は、そんな俗世の中に生きる人間に、本来の姿を感じさせ、無垢な感性を呼び覚ますものであって欲しい、と私は思っています。黛敏郎さんは「音楽は祈りと叫びである」と言っていましたが、人間の存在の根源に至るのが音楽や芸術ではないかとも思います。
今、不安定な世の中に在って、音楽は何を奏でるのか・・・・?。「愛」なんて言うのはゆめゆめしいだけの、平和ボケで理想主義的なおめでたい感覚でしかないでしょうか?。少なくとも肩書きでけん制し合っているよりは美しい。
私は音楽家でありたいのです。
年末になると、普段飲み歩いている仲間からも「正月は実家に帰るよ」なんて声が良く聞かれます。なんだかいいな~~。暖ったかい感じがしますね。私は既に実家というものが無くなってしまっていて、地元静岡に行っても泊まる所も無いので、都会でのんびり(していられないですが)してます。以前は介護施設に入所していた母の所に年末から正月過ぎまで泊り込むのが毎年恒例で10年程そんな調子だったのですが、今考えると、世話に行っているつもりで、甘えに行っていたのかもしれないですね。
富士山の日の出も久しく見ていないです
音楽家にとって、帰るべき場所や自分が何者であるのかという認識は音楽活動をしてゆく上で、大きな指針となるし、これを認識しない訳にはいきませんね。まあアイデンティティーと言えば良いのでしょうか。
自分が何者であるかが判るということはなかなか難しい問題ですが、それを追求し、感じて行く姿勢が薄いとしたら、それは本当の意味で音楽はやれてない、とも言えます。自分が演奏するものがたとえ伝統音楽であったとしても、それは本当に自分の音楽なのか?。常に我が身に問いかけ、追求する姿勢を持たないと、振り回されて終わってしまいます。
人間は得てして環境に影響され本来の自分を見失うものです。先生と言われたり、肩書きが付いたり、多少の収入を得ることで満足し、音楽以外のものを基準にするようになってしまう。もうそこからは音楽は響かない。何者でもないありのままの自分自分から発してこそ、音楽は「祈りと叫び」になるのです。そしてその音楽には、格好つける必要も無く、素のままで身を委ねられる、自分の帰るべき場所があるはずです。
小さな村の中に居て、虚勢を張っていても、誰も聴いてはくれない。知り合いと褒め合っていても音楽は世に響かないのです。邦楽にはそんな残念な例が多過ぎます。せめて若い世代だけでも音楽にもまともな眼差しを向けて、取り組んで行って欲しいものです。
 30代の頃の私はこんな目付きをしていました。とにかくすべてが音楽という感じで、良くも悪くも純粋過ぎましたね。
30代の頃の私はこんな目付きをしていました。とにかくすべてが音楽という感じで、良くも悪くも純粋過ぎましたね。
まあ反省はともかくとして、この頃はまだ自分の姿が、本当の意味で自分で見えていなかったと思います。ただ自分のやるべき音楽はジャズではない、という気持ちは強く持っていました。もう既にこの頃から独自の塩高モデル(六柱)に改造していたのを見ると、すでに組織には組しない「俺流」を貫いていたようですが・・・・。しかしながら、必死で自分の居るべき場所、帰って行く家を探していた時期だったとも言えますね。
そして今、まだ旅の途中ではありますが、道は見えてきました。現実生活はともかくも、芸術的精神に於いて自分が帰って行く所も強く感じるようになりました。年を追うごとに視野が開け、心も体も柔軟になって来るのを感じます。まあこれが年を取るということでしょうが、色々なものから解放されて行くこの感触はいい感じです。やはり帰るべき所は誰にも必要ですね。心の部分だけでも。
さて、明日は平成絵巻「方丈記」の初演です。
六本木芋洗坂沿いにある、ストライプスペース http://striped-house.com/stripe-space.html
にて19時の開演です。是非お越しください。
日本人の帰るべき所、根幹の感性が見えるかもしれません。乞うご期待!!






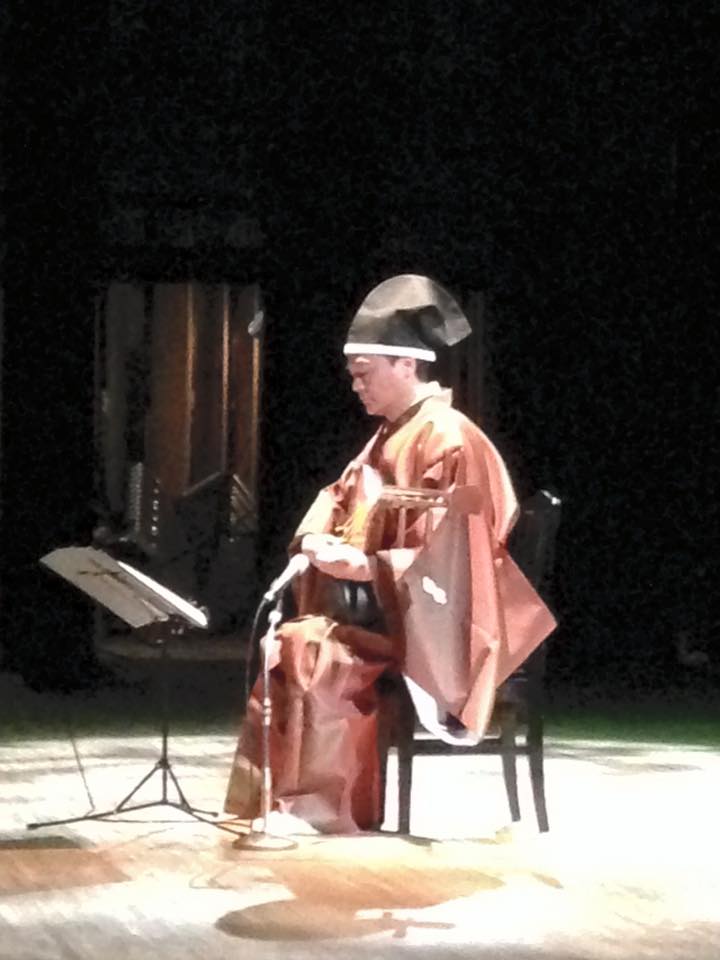






 それにしても皆さんそれぞれの世界の大ベテラン。豊富な経験と技術があるということは、良いものを生み出す土壌があるということですね。こういうものは若手では出来ません。それだけ充実したものを感じました。そして皆さん素晴らしいキャリアがあるにもかかわらず大変に気さくな方々。どの世界でもまともな人はどんなにキャリアを積んでも、そんなものに寄りかかったりしませんが、今回のメンバーは本当に皆が対等なのです。器がでかいな。
それにしても皆さんそれぞれの世界の大ベテラン。豊富な経験と技術があるということは、良いものを生み出す土壌があるということですね。こういうものは若手では出来ません。それだけ充実したものを感じました。そして皆さん素晴らしいキャリアがあるにもかかわらず大変に気さくな方々。どの世界でもまともな人はどんなにキャリアを積んでも、そんなものに寄りかかったりしませんが、今回のメンバーは本当に皆が対等なのです。器がでかいな。
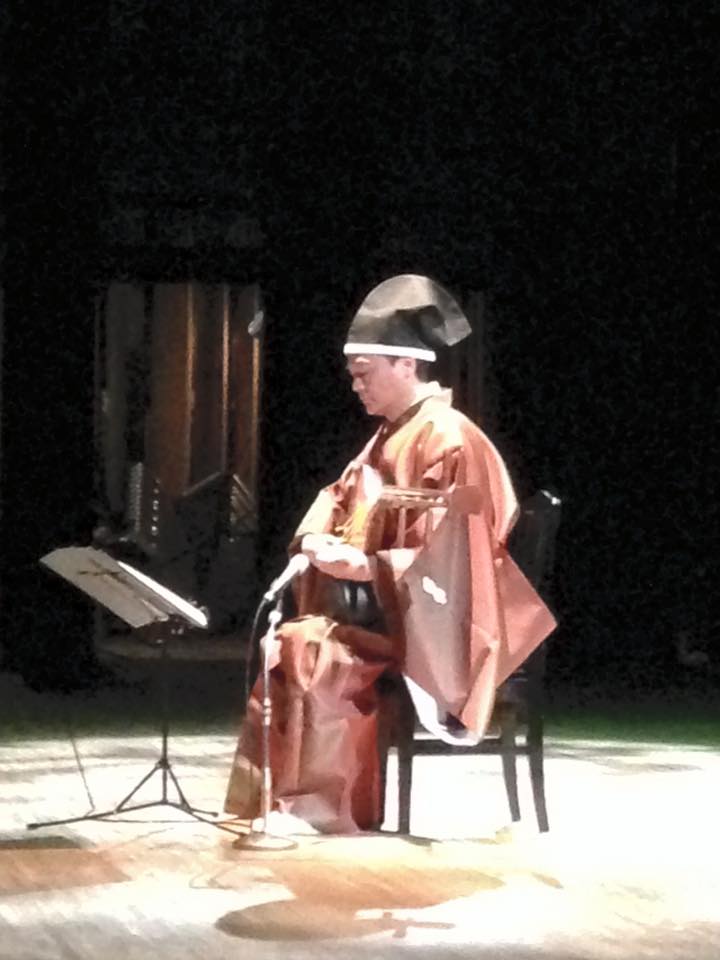
 ジョンレノンやボブディランの歌に対して音程がどうの、発声がどうのという人はいませんね。マイルスもジミヘンも同様、リスナーはその音楽を評価しているのであって、技でもなんでもないのです。そんなことは誰もが当たり前に思っていることが、当事者になると見えなくなってしまう。まあこれが業にまみれた世の中というものですが、その中でうごめいて終わるか、それともその先に行って音楽を創造するか、結局はその人の器でしかないですね。
ジョンレノンやボブディランの歌に対して音程がどうの、発声がどうのという人はいませんね。マイルスもジミヘンも同様、リスナーはその音楽を評価しているのであって、技でもなんでもないのです。そんなことは誰もが当たり前に思っていることが、当事者になると見えなくなってしまう。まあこれが業にまみれた世の中というものですが、その中でうごめいて終わるか、それともその先に行って音楽を創造するか、結局はその人の器でしかないですね。
 30代の頃の私はこんな目付きをしていました。とにかくすべてが音楽という感じで、良くも悪くも純粋過ぎましたね。
30代の頃の私はこんな目付きをしていました。とにかくすべてが音楽という感じで、良くも悪くも純粋過ぎましたね。