梅雨が明けましたね。夏の耀くような日差しは見ているのは好きなのですが、暑さにはとにかく弱いので、昼間は部屋の中から眺めています。

梅雨明けの江の島
先日は久しぶりに、福原百七さんが同人として頑張っている「長唄五韻会」に行ってきました。皆さんその道の玄人さんなので、さすがのレベルでした。
私はこの会や他の会でも出演させてもらっているのですが、やる度に家元のもとで修行してきた邦楽の演奏家と自分とは、雰囲気が随分違うなと思っていました。こうして少し離れた所からじっくり聞いてみると、と改めてその違いを実感しました。
 郡司敦作品個展にて
郡司敦作品個展にて
御存じのように薩摩・筑前の琵琶は歴史が浅く、組織が出来上がってまだ100年程。特に私の弾いている錦琵琶は昭和になってから楽器が出来上がり、流派として創流され、その錦琵琶の中でも私が少しばかり習った鶴田流は、「流」と言われ出したのが80年代以降ですから、何百年と組織を維持してやってきた長唄とは、もう歩く姿から何から何まで違って当たり前なのです。
それにしても五韻会の皆さんは所作が良いですね。若き家元のHさんも落ち着いた、「らしい」風情になっていました。そして面白いことに、彼らの風情は能や雅楽の人ともまた違うのです。実に興味深いですね。
私は小学生の頃からギターを弾いているので、作曲したり演奏したりする時にギターの知識と経験がとても役にたっていますが、そういう所も一つの私の風情となっているんでしょうね。先日の神戸の方丈記公演の時なども、美術評論家のMさんが「塩高さんはロックですね~~~」と言ってくれましたが、それが私という人間なのだと思います。最近はそういう自分の風情をすんなりと受け入れることが出来るようになりました。また本来の自分のありのままに生きることは年齢を重ねれば重ねる程に、大事なことのような気もしています。
私のこういう風情は、やればやる程、どんどんと邦楽の型や枠から外れて行きます。普通にやっているつもりでも、人から見るといつも俺流という風に見えるようです。こんな感じで常にno borderであるのが私の姿です。このスタイルですから。お付き合いする人も皆、枠に収まるような人は居ないですね。外国人のお客様が多いのもまあ私らしいですね。


阿佐ヶ谷ジャズストリートにて 最近は相棒がepiphoneに変わりました
最近ギターを弾くのも良いなとよく思います。毎年出ている阿佐ヶ谷ジャズストリートには今年も出ますが、とにかく思うことは、何をやろうが自分の中で繋がっているのだから、外側の目を気にすることはないということです。どこまでも自分らしく生きることに尽きると思います。今自分が感じることは何かのきっかけと必要があってこそなのだから、素直に身を委ねれば良いのです。だからこそ自分の音楽が具現化されるのです。
最近はよくブログにも書いていますが、歌に関して本当に色々と感じることが多く、弾き語りに於いては自分の歌を歌いたいという想いがとても強くなりました。「経正」「敦盛」は自分の歌として作詞の森田亨先生と創り上げましたので確かに申し分ないのですが、これだけでは足りない。歌や声をメインにしていこうとは思っていませんが、声や歌を一つの表現の形として行くのは、自分の音楽に必要だと感じていますので、もっとレパートリーに歌が欲しいのです。歌に限定しなくても語りでも、別の形でも良いのです。
 岡田美術館にて
岡田美術館にて
単に得意な曲ではなく、自分が人生賭けて歌いたい歌。そんなものを歌いたい。自分の中からそのまま出てきた歌を歌いたいのです。一人一人顔も声も違うように、自分だけの歌を歌いたいのです。借り物の歌では何も届かない。どんな名曲も、自分の懐に入って来て、尚且つもう一度私の中から歌が湧き上がって来ない限りは演奏は出来ませんね。
やっぱり私は創るしかないですね。まだ薩摩琵琶には古典というものが無いのですから、創るしかないでしょう。
果てしないですね、音楽は。
夏の日の徒然に・・・・・・、。
ちょっとご無沙汰してしまいました。先日のフラメンコギタリスト日野道生さんとのライブを最後に一連の連日演奏会が一段落ついて、のんびりさせてもらってます。こういう時期は良くしたもので色々なお客様が来たり、会いに行ったりして毎日楽しく過ごしています。演奏会が続いていると気持ちも張って、目付きも鋭くなってゆく感じなのですが、今は随分と気分も落ち着いてきたので、この夏は涼しい所で、ゆっくりお散歩でもしながらお茶(?)飲んで、おしゃべり三昧で英気を養いたいですね~~。
先月はバークレーで作曲を勉強中のジポーリン・ジョシュ君が、ICJCのジョセフ・アマトさんの紹介で何度も訪ねて来てくれて、演奏会のお手伝いまでしてもらい、これからの作曲作品について熱く語って行きました。日本に居る間、琵琶を貸してあげたのですが、随分と発想を得たようなので、何が出て来るかとても楽しみです。
ちょうど同じ頃、尺八のグンナル・リンデルさんがスウェーデンからやってきたので、久しぶりにゆっくりと話が出来ました。今後は一緒にヨーロッパでの演奏の機会もありそうです。彼とは琵琶での活動の最初からコンビを組んで頑張ってきた相棒なので、本当に話が尽きないのです。
そのすぐ後には、ハワイ大学のクリス・モリナ先生が焼酎を持って我が家に遊びに来てくれまして、日本の古典芸能の話や古武術の身体性、オペラ、バレエ、クラシック、現代音楽、そして現代社会の行方までたっぷりと話を交わし合って、久しぶりに芸術家と充実した時間を持つことが出来ました。
皆さん本当に情熱が溢れるようで、話していてこんなに気持ちの良い人達は他にないですね。日本の音楽・芸術家は自分を売り込むことに熱心な方ばかりで、あまり芸術を語る人がとても少ないので、こうしてゆっくりじっくり芸術に付いて話が出来るというのは本当に幸せを感じます。
来月頭には、台湾の琵琶 奏者 劉芛華さんがリサイタルの報告をしに来てくれることになっています。今年5月の彼女のリサイタルでは、二胡の林正欣さんと拙作の「塔里木旋回舞曲」「Sirocco」を取り上げてくれました。嬉しいですね。劉さんとはもう結構長いお付き合いで、リサイタルで私の作品を演奏してくれたのもこれで2回目です。彼女が最初に我が家に遊びに来た頃は、まだ勉強中という感じでしたが、ここ5,6年の演奏活動の充実ぶりには目を見張るものがあります。特に最近は活動がかなり展開しているようで、彼女が年々音楽家として充実して行く姿は、見ていて頼もしいの一言!。応援せずにはいられませんね!!
奏者 劉芛華さんがリサイタルの報告をしに来てくれることになっています。今年5月の彼女のリサイタルでは、二胡の林正欣さんと拙作の「塔里木旋回舞曲」「Sirocco」を取り上げてくれました。嬉しいですね。劉さんとはもう結構長いお付き合いで、リサイタルで私の作品を演奏してくれたのもこれで2回目です。彼女が最初に我が家に遊びに来た頃は、まだ勉強中という感じでしたが、ここ5,6年の演奏活動の充実ぶりには目を見張るものがあります。特に最近は活動がかなり展開しているようで、彼女が年々音楽家として充実して行く姿は、見ていて頼もしいの一言!。応援せずにはいられませんね!!
こうして日本音楽が色々な視点で語られて、新たな展開が出て来るのは何とも頼もしく、嬉しいものです。まあアプローチしてくれるのが全て外国人というのも何なのですが・・・。
ともあれ様々な国の人が色んな視点で日本音楽を見つめ、私の曲も独自の解釈を持って取り組んでくれるなんてことは、嬉しいじゃないですか。ウズベキスタンのアルチョム・キムさんなんかも民族音楽の新たな世界をヨーロッパに於いて創造していているので、期待は膨らみますね。以前タシュケントにあるイルホム劇場で演奏した、キムさん編曲の拙作「まろばし」も是非再演してみたいものです。
アルチョム・キムさんとイルホム劇場公演後に ジョセフアマトさんとICJCにて
横浜インターナショナルスクールや併設のICJC(International center of japanese culture)でもここ何年か演奏やレクチャーを重ねていますが、ここから以前紹介したレオ君やゆーじ君など、ずば抜けた才能あふれる演奏家も出て来ていますし、これから海外の作曲家が邦楽器の為の新たな曲を作り、今迄に無い世界がきっと展開されて行く事と思います。
そして今週は、久しぶりにオランダ在住のソプラノ歌手 夏山美加恵さんにもお会いして、同じくオランダ在住の笙奏者 佐藤なおみさんともお話しが出来、美味しいランチを食べながら楽しい時間を頂きました。お二人共それぞれに独自のスタイルを持ち、確固とした意見も持って音楽に取り組んでいる。今や日本人がヨーロッパで日本の楽器を演奏し、活躍している時代なのです。時代はどんどん展開して行くのですね。彼らとは、話しているだけで新たな目が開かれ、発想も湧き、実に楽しいのです。
一番最初にグンナルさんとレコーディングしたCDのジャケット (筝はカーティス・パターソンさん。皆若い!!!!!)
今、邦楽人以外の多くの人達が日本文化の深淵な魅力を感じて動き出しています。しかし当の邦楽人はどうでしょうか・・・・?音楽の外側の部分に目を奪われて、その魅力に実は気付いていないのかもしれません。雄大にして底知れぬ魅力に溢れた日本の音楽の歴史に包まれながら、霧の中を彷徨って、目の前すら見えなくなっているのではないでしょうか???。
外側から見ていると霧に包まれた風景は幻想的でとても美しい。実に魅力的です。しかしその中に居ては何も見えず、ただ流されるままに彷徨うばかり。今、邦楽に新たな視野や感性、柔軟な姿勢が備わってきたら、きっとこの霧も晴れて、そ
の姿がまた輝きだすように思えてなりません。
もう気分は夏ですね。ここ数日は昼間で歩くのに躊躇する程の陽射し。先日の関西も30度を超えていて、歩いて廻るにはかなり厳しい陽気でした。明日からまた金沢に行くのですが、少しでも陽射しが和らぐことを願っています。
そんな慌ただしく暑苦しい日々が続く中、友人から虹の写真が送られてきて、何だか気分がゆるみ安らぎました。虹というものは何ともさわやかで、からりとしていい気分にさせてくれますね。
虹には大きなロマンがあって、希望が湧いてくるような幸せな感じがする一方、彼方という思考も湧いてきます。人生生きていれば、色々な事情で離れたり別れなければならなくなった人もいますし、現世を旅立って行った知人も多くいます。ちょうどこの7月頭は尺八の香川一朝さんが旅立ったこともあって、私にはそれら幾多の別れに、虹のイメージが重なるのです。此岸から彼岸までを繋いでいる虹の、この両端の果てしなく遠い、辿り着けない程の距離は、現世に生きる我々には乗り越えられない、いや乗り越えてはならない距離のように思えてしまうのです。
拙作「虹の唄」もそんな彼岸へと行ってしまった人達への想いが曲となって、す~~と心の中に降りてきた時に出来上がりました。そして何年も弾いている内にまた多くの想いが曲に乗り、自分の中でどんどんと意味を持つ曲となって行きました。あまたの別れの中にある未練や、悲しさ、感謝、希望・・・・等々あらゆる心の風景が、この曲に乗って私の中を巡って行くのです。
私は作曲する時にはいつも譜面を書きながら作るのですが、この曲だけはふわっと降りて来るように勝手に指が弾き出して、修正することも無くそのまま最後まで湧き出て来たのです。こんな曲は今迄無いですね。大概は構想を元にモチーフを作ったり、色んなパーツをくっつけたり外したりして、推敲に推敲を重ねて作るのですが、この曲だけは全くそういう作業がありませんでした。未だに不思議な感じです。
 ルーテルむさしの教会にて
ルーテルむさしの教会にて
人間色々な時がありますが、自分がやりたい事をまともにやっている時は一番幸せを感じますし、周りにも幸せをもたらすのではないでしょうか。周りを見ても、心底自分に向き合い、やりたいものをやっている人は魅力的です。
私は琵琶で活動を始めた最初から先鋭的だと評され、自分自身でも先鋭的且つ最先端でありたいと願い、従来のルールが何であろうと、誰が何と言おうと自分のやりたい事をやりたいように実現して来たつもりですが、この所御縁がある灰野敬二さんのような超前衛を突っ走ってきた先輩と一緒に居ると、自分の詰めの甘さがよく見えて来ます。知らない内に色々なものに振り回され、本来の自分の生き方が歪んでしまっている部分があるのでしょう。だからこそ事あるごとに、更に更に自分自身であろうとする気持ちが旺盛に湧き上がります。言い換えれば、まだまだ自分本来の生き方には至ってないということなのかもしれません。
そんなことをつらつら考えていると、虹の彼方へ旅立つというのは、ある意味で自分の本来の人生へと向かう、一番解放された瞬間なのかもしれない、なんてことも思うことが多くなりました。
カリブの夕暮れ
人は、何事も手が届かないからこそ求めるのです。これを業というのかもしれないし、宿命ともいえますね。私はいつも常に「もっともっと作曲しなければ」「もっと自分のスタイルを明確にしたい」と同じことばかり何十年も言い続けて今に至ります。聴いている周りの人はさぞかし迷惑だろうとも思うのですが、本当にもっともっとという想いが消えることはないのです。まあここが無くなったら音楽家としてお終いかもしれませんが・・・・。
上手かどうかなんてのは、私にとっては面白くないのです。そんな感覚はアマチュアと同じ視点でいるということです。舞台に立つ人間は圧倒的であり、それを舞台の上で具現化ですることが出来なくては舞台人とは言えないのです。出来上がっているスタイルの中で「お上手」にやっても、それはお稽古事という所から何も抜けていない。そういう感覚を捨てられない人は、せいぜい肩書き並べて、先生と言われご満悦なのでしょう。
今迄に無いものを創り出し、それを舞台の上で具現化しないと気が済まないのが、私という人間です。永田錦心、マイルス、ドビュッシー、ジミヘン、パコデルシア、魯山人、、、、私が憧れてやまないこういう人達は当時の世間の常識やセンスを飛越え、ぶち壊し、世に自分の創りだしたものを示し、それを認めさせました。だから次の時代が見えてきたのです。
 私のような人間は、もっともっとと言い続けながら虹の彼方へと旅立ってしまうのかもしれませんが、こういう生き方も自分らしければ良いのではないかと思います。時に悲しいこともあるでしょうし、落ち着かない人生とも言えますが、スリルに満ちた日々は私をワクワクさせてくれます。
私のような人間は、もっともっとと言い続けながら虹の彼方へと旅立ってしまうのかもしれませんが、こういう生き方も自分らしければ良いのではないかと思います。時に悲しいこともあるでしょうし、落ち着かない人生とも言えますが、スリルに満ちた日々は私をワクワクさせてくれます。
私が虹の彼方へと行く時がいつかは判りませんが、私は私の人生を淡々と歩んで行きたいですね。喜びも悲しみも包み込んで・・・。
先週、兵庫県芸術文化センターホールで、「秘曲でつづる平成絵巻 方丈記」の公演をやってきました。
役者の伊藤哲哉さんと方丈記に取り組み始めたのが1年前、それから仲間も集まり、色々な場所でやらせて頂きましたが、今回の公演はその集大成とも言うべき実に充実した公演となりました。




バックには映像作家のヒグマ春夫さんがインパクトのある映像を映し出してくれて、舞台はこんな感じになりました。
音響、照明もバランスよく、久しぶりに良い舞台で気持ち良く演奏することが出来ました。大きなホールでしたが、お客様もたくさん来て頂きまして、ありがたかったです。やはり大勢のお客様の前でやると、きりりとしますね。
 左から照明の早川さん、芸術評論家の宮田さん、映像のヒグマさん
左から照明の早川さん、芸術評論家の宮田さん、映像のヒグマさん
鴨長明:伊藤哲哉 5弦ウッドベース:水野俊介 樂琵琶:塩高和之
映像:ヒグマ春夫 照明:早川誠司 舞台監督:菊池廣
主催:YUKIプロデュース
このメンバーに加え、第一部に方丈記についての解説を服部祥子、小林一彦両先生に話して頂き、方丈記の魅力を語ってもらいました。
大きな公演をやるには資金も必要ですし、ショウビジネスでない我々のような演目では、そういくつも大きなホールでやる事は出来ませんが、これはぜひ今後も続けてやっていきたいと思っています。
そしてその後は、京都桃山にあるアートサロン ラ・ネージュにて朗読の馬場精子さんとの初共演をしてきました。
ここは打って変わって50名程のサロンで、お客様も満杯。眼の前にお客様が居るような状態でしたので、ホールとは全く雰囲気は違ったのですが、天井が高く、とても響きの良いスペースなので、こちらも琵琶の音が良く響き、気持ち良かったです。
そして「方丈記」が原文のままなら、こちらも平家物語の「敦盛最期」を原文のまま朗読して頂くという珍しい企画!。伊藤哲哉さんの舞台が豊かなキャリアに裏打ちされたベテラン俳優の充実した圧巻の一人語りなら、馬場さんは女性らしい柔らかく、ノスタルジックな雰囲気に包み込まれるような、爽やかな語り口でした。

馬場さんとはもう何年も前からやり取りがあって、いつか一緒にやる機会を持ちたいと話していたのですが、ここに来てやっと実現したという訳です。また9月には東京のキッドアイラックアートホールでも再共演がありますので、ぜひぜひお越し頂きたいと思います。
この所、様々な語り部さんと一緒にやることが多くなりました。それぞれ違った個性とスタイルを持っていて、なかなか面白いです。
私自身が弾き語りというスタイルを脱しつつあるので、こうして声を操る方々と組むことが多くなるのは当然の流れだと思います。今後私が声というものとどう向き合て行くか、音楽家として大きな選択であり課題ですね。
さて旅はこれだけでは終わりません。今回は奈良に3泊して、演奏会の跡は奈良周辺を散策してきました。中でも久々に行ったのが大宇陀。もう15,6年も前、まだ私がぎりぎり若手なんて言われていた頃に、大宇陀の古い町並み沿いにあるカフェで演奏した事があり、いつかまた行ってみたいと思っていました。そのカフェは既にオーナーも変わっているようでしたがまだお店は健在でした。残念ながら開店が11時ということで、ちょっと早過ぎて入ることが出来ませんでした。しかし近くの通り沿いの休憩所で、地元のおばちゃんとのんびりと話が出来て、楽しい時間を過ごすことが出来ました。
この辺りは万葉の郷なので、「かぎろひの丘」にも馳せ参じ人麻呂さんに想いを馳せ、阿紀神社などもに足を向けて、万葉の風に浸りのんびり歩いて来ました。
そして奈良に行ったら、美味しいものもしっかり頂くのがいつもの習わし。今回もビストロ・プチ・パリにて楽しんで来ました。鮎旨かったな。自家製のソーセージも・・・・。
古典の世界は魅力的なのです。良い仕事をさせて頂きました。
昨日は、北鎌倉の其中窯サロンにて演奏してきました。
其中窯入口
数年前にもここで演奏をやってきたのですが、ここはかの北大路魯山人が築いた窯。現在は陶芸家の河村喜史さんが引き継いで作陶をしています。
前回は窯をゆっくりを拝見する事が出来なかったので、今回はゆっくり拝見させてもらいました。結構広い敷地があるので窯も大きく、焼き上がったばかりの作品や焼成前の乾かしてある作品など陶芸に関わる色々なものが至る所に有って、興味のある人にはワンダーランドです。
 窯の様子
窯の様子
私の母が元気な頃は陶芸にはまっていて、家でしょっちゅうろくろを回してましたが、私も小学生の頃には陶芸倶楽部に入っていましたので、陶芸はずっと身近なものでした。私は陶芸をやらないのですが、よく地方での演奏の後には、打ち上げなどでその土地の陶芸家とよく知り合い、作品を頂くことも多く、我が家には作家ものの陶器が結構沢山あります。また普段から集まる仲間には、このブログにも時々登場する佐藤三津江さんはじめ、陶芸をやっている人もけっこう居て、陶芸はいつも私の周りにあるものなのです。
河村喜史さんは代々続く陶芸家の家系に生まれ、祖父喜太郎さんは当時「陶工」という言葉しかなかった時代に、陶芸を芸術として認知させた一人だったそうです。「陶芸家」という呼び方もここから始まったそうで、その意思を受け継ぎ、喜史さんの父又二郎さんも色々な芸術家と交流し、この北鎌倉の地でサロンを展開したそうです。喜史さんも音楽に大変造詣が深く、現代音楽の作曲家とも交流を持っているので、色々と話を聞くだけでも面白いのです。今回は又二郎さんの奥様もサロンに来られて、お会いすることが出来ました。立派な作品集を頂いてしまいました。
更に今回は、ドキュメンタリー映画を作っている川瀬美香さんにもお越し頂いて、話が湧きました。もっとゆっくり時間があったら良かったのですが、まあこれも次回のお楽しみですね。

映画監督の川瀬美香さんによる撮影
 画家のゼノビッチ美奈子さん、ブルースマンのホセ有海さん、古澤ブラザース、琵琶制作修行中のIさんらとの今年のお花見
画家のゼノビッチ美奈子さん、ブルースマンのホセ有海さん、古澤ブラザース、琵琶制作修行中のIさんらとの今年のお花見
琵琶などやっておりますと、音楽・美術・演劇など、色んな分野の芸術家と自然と知り合います。そんな芸術家たちと話をするのは、とても楽しく面白いのです。芸術家だけでなく、ものつくりをしている人は職人さんでも、農家の親父さんでも皆さん話が面白いですね。私はそんな人たちと常に接しているのがとにかく好きなんです。
私が主催する琵琶樂人倶楽部や日本橋富沢町樂琵会も音楽家だけでなく、音楽に関心のある方が気軽に集まれる所として発足しましたので、毎月色々な人が集ってくれて実に面白いのです。
こうして機会を頂くのは本当に嬉しいです。これからも良い仕事をどんどんとやって行きたいですね。
さて明日からは神戸の芸術文化センターホールで「方丈記」公演の為に行ってきます。その後京都桃山のラ・ネージュというサロンで、朗読の馬場精子さんとの企画、そのまたすぐ後には金沢から少し行った所にある白山の望岳苑にてディナーコンサートと続いています。もう一頑張り!
多くの人に琵琶の音と私の音楽を聴いてもらいたい。地味なものですが、是非是非聞いていただきたいのです。

 郡司敦作品個展にて
郡司敦作品個展にて

 岡田美術館にて
岡田美術館にて




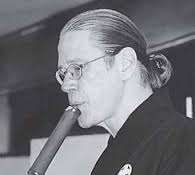
 奏者 劉芛華さんがリサイタルの報告をしに来てくれることになっています。今年5月の彼女のリサイタルでは、二胡の林正欣さんと拙作の「塔里木旋回舞曲」「Sirocco」を取り上げてくれました。嬉しいですね。劉さんとはもう結構長いお付き合いで、リサイタルで私の作品を演奏してくれたのもこれで2回目です。彼女が最初に我が家に遊びに来た頃は、まだ勉強中という感じでしたが、ここ5,6年の演奏活動の充実ぶりには目を見張るものがあります。特に最近は活動がかなり展開しているようで、彼女が年々音楽家として充実して行く姿は、見ていて頼もしいの一言!。応援せずにはいられませんね!!
奏者 劉芛華さんがリサイタルの報告をしに来てくれることになっています。今年5月の彼女のリサイタルでは、二胡の林正欣さんと拙作の「塔里木旋回舞曲」「Sirocco」を取り上げてくれました。嬉しいですね。劉さんとはもう結構長いお付き合いで、リサイタルで私の作品を演奏してくれたのもこれで2回目です。彼女が最初に我が家に遊びに来た頃は、まだ勉強中という感じでしたが、ここ5,6年の演奏活動の充実ぶりには目を見張るものがあります。特に最近は活動がかなり展開しているようで、彼女が年々音楽家として充実して行く姿は、見ていて頼もしいの一言!。応援せずにはいられませんね!!

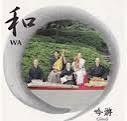



 私のような人間は、もっともっとと言い続けながら虹の彼方へと旅立ってしまうのかもしれませんが、こういう生き方も自分らしければ良いのではないかと思います。時に悲しいこともあるでしょうし、落ち着かない人生とも言えますが、スリルに満ちた日々は私をワクワクさせてくれます。
私のような人間は、もっともっとと言い続けながら虹の彼方へと旅立ってしまうのかもしれませんが、こういう生き方も自分らしければ良いのではないかと思います。時に悲しいこともあるでしょうし、落ち着かない人生とも言えますが、スリルに満ちた日々は私をワクワクさせてくれます。











