琵琶樂人倶楽部は、お陰様で今月9日(水)の開催で15周年となります。
あっという間の15年間というのが正直な所ですが、この琵琶樂人倶楽部は毎回集客を気にせずにやって来たので、運営に当たってのストレスが無く、毎月やりたいようにやらせて頂き、本当に楽しく続けて来れました。名曲喫茶のスペースを借りてやっているので会場は小さいですが、最近は毎回満席のお客様に恵まれまして、本当に感謝しております。
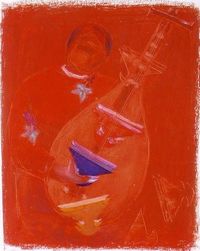
日本は、その歴史自体が世界一の歴史を誇る国家であり、雅楽や能などは世界に例を見ない歴史の長さを誇る音楽芸術が、未だに現役で受け継がれている国です。その中で琵琶樂は平安時代から様々な形で続いて、その魅力を今にかろうじて伝えています。薩摩・筑前の琵琶は明治後期に初めて流派が出来た日本の若い琵琶樂ですが、明治には、永田錦心を筆頭としてエネルギーも創造性も旺盛に溢れ出ていて、大衆芸能としても人気を博しました。高度成長期には上記したように鶴田錦史による現代音楽分野への進出が、世界的にも大きな話題となりました。
しかしながら琵琶樂人倶楽部発足前夜の1990年~2000年頃の琵琶樂の現状は、過去の焼き直しに終始し、更にはその正統性を主張しようとして、古典だ伝統だと吹聴していて看板を挙げて虚勢を張っている有様でした。私はそういう琵琶樂の姿が何とも悔しかったのです。世界を視野にして琵琶樂を考えていた永田錦心の志を受け継ぐ人は誰もおらず、創造的な音楽としての魅力を発信する人も皆無でした。
 2011年1月、毎年恒例だった「薩摩琵琶三流派対決」
2011年1月、毎年恒例だった「薩摩琵琶三流派対決」発足時に一緒に立ち上げをやってくれた古澤月心さん、琵琶製作者でもる石田克佳さんと
当時の私は、まだまだ自分自身が発展途上でありましたが、とにかくこの現状に甘んじていたらどうにもならないと思い、自分自身の演奏活動と並行して、琵琶樂をもっと知ってもらおうと思い、雅楽・平家・薩摩筑前、そして現代の琵琶樂の紹介をする場として琵琶樂人倶楽部を設立したのです。最初は古澤月心さんが薩摩四絃と平家、私が薩摩五絃と樂琵琶の演奏を担当し、レクチャーは私がやりました。
全ての企画は最初から私がしていましたが、多々失敗もありました。会の趣旨に合わない人を呼んでしまったり、勉強不足でレクチャーの内容が中途半端に終わってしまった事もありました。しかし私自身はそんな毎回の企画やレクチャーなどを通して、多くの勉強をさせてもらったのです。
実はもう20年程前から大学や市民講座などの特別講座をほぼ毎年、あちこちでやらせて頂いていますが、ネタは造りは皆この琵琶樂人倶楽部の企画内でやっていたと言っても過言ではありません。先月も東洋大学文学部でお話させたもらいましたが、私のレクチャーも随分とこなれて来ました。琵琶樂人倶楽部をやっていたお陰ですね。
今年から、琵琶樂人倶楽部専用のブログページも出来ました。
ゲストの方の写真も了解を得ている方については載せるようにして、15年経ってやっと恰好がついてきた感じです。ここ数年は毎回誰かゲストを迎えていますが、私の作曲活動も少しづつ進んでいますので、それに伴ってゲストも色々と変化しています。今月は、すでに相方と言っても良いコンビネーションを築いているVnの田澤明子先生に加え、AsのSOON・KIMさんが初登場します。キムさんは20歳頃からNYに渡り、あのオーネット・コールマンの下で研鑽を積んできた稀有な方で、主にヨーロッパで活躍されていました。8年程前にキムさんが日本に一時戻ってきた頃からのお付き合いですが、また今年中にもヨーロッパに行ってしまうとの事ですので、その前に声を掛けさせていただきました。常に世界が視野にあり、それに伴ってジャンルを軽々と飛び越えて音楽を創り出す姿勢が素晴らしいミュージシャンです。琵琶人にも、かつての永田錦心や鶴田錦史のように、ジャンルを越境して音楽を創り出し、活躍するような人がそろそろ出てきて欲しいですね。
以下は渋谷クラブクアトロで行われたオーネット・コールマン追悼公演の模様です。キムさんとカルヴィン・ウエストン、バーノン・リード、アル・マクドウェルという世界で活躍するオーネットスクールのトップメンバーによるライブは凄まじいものでした。Tower of Funk in Japan 2015-2 – YouTube

琵琶樂人倶楽部は、とにかく様々な人とのつながり、関わりの中でこれまでやって来れました。私は琵琶を弾く事で人と繋がり、今生かされているといつも感じていまして、音楽活動をするという事は縁を繋ぐ事だとずっと感じています。
琵琶というと放浪芸人のような琵琶法師や耳なし芳一というイメージだけを利用して見せる例も多いですが、何となく和風というような目の前だけを楽しませる安手のエンタテイメントではなく、またお稽古事
のようなものでもなく、世界に飛び出して、他のジャンルと同じ芸術音楽として聴いてもらえる琵琶樂を、これからも微力ながら紹介して、私自身も演奏・作曲活動を展開して行こうと思っています。これからも是非御贔屓を。



