湿度が増してきていますね。早目の梅雨という感じになるのでしょうか。琵琶にはつらい季節です。
それにしても世のうつろいは本当に早く、自分だけは変わらないつもりでも、自分を取り巻く状況はもう去年とは違うし、社会の流れそのものも変化しています。まあ平安時代にすでに在原業平が「月やあらぬ 春や昔の春ならぬ 我が身ひとつはもとの身にして」と詠んでいる位ですから、世というものはどんな時でも変わらずうつろうものなのでしょう。

お陰様で私はそこそこ仕事を頂いていますが、内容はコロナ前とは随分様変わりしています。今後ももっと変化して行くと思っています。私がここ数年間何とかやって来れたのは、毎月定例の琵琶樂人倶楽部を続けていた事と、レクチャーなどの仕事がずっと入っていた事、それから急に琵琶を習いたいと言って来る若者が次々にやって来たのも良いモチベーションとなりました。収入は残念ながら下降気味なのですが、モチベーションが下がらずに、相変わらずの感じで作曲したり演奏したりしてやって来れました。
私には相変わらずエンタテイメントには程遠い所に居ます。私自身がエンタメには興味が薄いですし、普段からそういう顔をして、非エンタメのオーラを発しているのでしょう。今後もやりたいとは思っていないですが、世の中はエンタメ寄りの方が本当に多いですね。よくもまあそんな世の中で「我が身一つはもとの身にして」なんていいながら、これ迄生きて来れたと思います。本当に有難い事です。随分昔には演歌歌手の録音など何度かやったことがありますが、あれは私の仕事ではないですね。まあ映画音楽で映像と音楽が切り離せない程に作品として成立していて、一緒に作品を創り上げるようなものならやってみたい気もありますが、「ベニスに死す」や「ニューシネマパラダイス」のような作品は、この所とんと見たことがありません。見たいなと思う映画も減ってきました。
音楽家は油断すると、直ぐいいように使われて何でも屋になってしまいます。特に琵琶は珍しいので、飛び道具的に珍しさを前面にした形で技の切り売りをさせられがちです。そこには音楽は無い。ただの体の良い便利屋になっているだけです。そうして食って行く為の芸に落ちたら、もう音楽家としてお終いだと私は思っていますので、自分のやりたいものを、これまで通りに地道にやって行きますよ。

最近建築家の安藤忠雄さんがインタビューで、「働く事は夢中になる程楽しくなければいかん」と言っていましたが、激しく同意しますね。昔は「辛い事をやるからこそ金がもらえるんだ。好きな事をやるんだったら金はもらえない。そんなものは仕事ではない」等と上から目線で説教する大人が大勢居ましたが、辛い・大変と思ってやっている仕事で、クオリティーの高い仕事が出来る訳がない。誰が考えても当たり前だと思うのですが、そんな根性論的な感覚が、以前はまるで主流のように社会の中にありました。
今はエンタテイメントが全てに渡って蔓延っていますが、実は日本人はエンタテイメントを本当に楽しんでいないのかもしれません。もう少し言い方を変えると、楽しむことがとても下手と言えるかと思います。仕事でも表面を楽しんでいるようにしているだけで、とことん夢中になる程楽しんでいない。私にはそう思える事がよくあります。上記のような根性論的な感覚がまだ抜けないのかもしれませんし、音楽や芸術に関しても、どこかで仕事と思う事が出来ないのかもしれません。まあ日本がここ30年で衰退したのは、そんな大人達の旧態然とした根性論的感性ゆえかもしれませんね。

楽琵会にて、Vn:田澤明子先生、笙:ジョウシュウ・ジポーリン君と
photo 新藤義久
私は最近は洋楽器を取り入れた作品を色々と創っています。演奏会のパートナーにもヴァイオリンやフルートを入れる事が多くなりました。邦楽器では実現し得ない世界が視野に入ってきたという事です。
少し前にお知らせしましたが、Vnの田澤明子先生との録音が編集作業を経て、今月末~来月初め辺りには配信される見込みです。その他フルートやメゾソプラノを入れた作品なども色々と出来上がっていますので、順次録音・配信をして行きたいと思っています。
邦楽器同士でなければ表現できない世界は確実にあります。しかし逆に邦楽器のみでは実現できない世界もあります。現代における楽曲リリースは、一瞬でドメスティックな世界を越えて世界に向けて発信されます。そう考えれば、その感覚も小さな枠の中に囚われているようなものは世に響きません。世の動きとの密接な関わりは、芸術活動に於いてとても重要な事なのです。これだけ世界が経済・政治から繋がって身の回りの生活にも大きく関わっている現代において、洋楽器を排して考えるのは、世の中と矛盾しているような気になるのです。日本の中ではなく、世界の中での琵琶樂というセンスはこれから是非とも主軸にしたい感覚です。そう考えれば琵琶でもっと自分の思う表現を実現する為には、洋楽器との組み合わせは今後、とても重要になって来る感じていて、表現領域を広げる過程で洋楽器とのコンビネーションが多くなって行ったのです。これからは世の中とどのように関わって行くか、そこにセンスと器が問われます。
世の中に沿う事はとても大事な事ですが、迎合する事と沿う事をはき違えないようにしています。先ずは私は日本の音楽をやっているのですから、日本の歴史や古典を知らない訳には行きません。これはクラシックでも同じでしょう。クラシックを演奏していてキリスト教を知らないなんてのは偽物と言われても仕方がないように、音楽は常に歴史や宗教、そして社会と共に成立するものです。
世のセンスはどんどんと移り変わります。価値観も形もどんどんと変わります。その中で変わらないものは何なのか。そこを見極める目がある人だけが仕事をして行けます。少しばかりの知識や経験に寄りかかって、小さなプライドを持ってしまうような人は、ほどなく仕事もやって行けなくなるのはどの分野でも同じ事。どれだけやっても、まだ自分には計り知れない世界がある事を感じている人は、視野も行動もどんどんと広がり、時代に合った形で自分の求める仕事が出来て行くと思いますが、現代ではなかなかそんな人に出逢うのが稀になりました。
幸い私の周りには、自らの根幹や核を見失う事の無い本当に尊敬すべき人が居ます。これも運命というものでしょうか。ありがたいですね。何かとふらついてしまう私にとって、そういう方は私の指針となっています。私は到底その域に到達は出来ないまでも、私も移りゆくものと変わらないものを見極める人でありたいと思います。
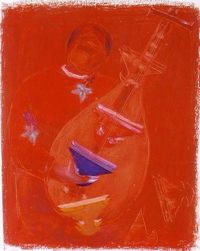
さて今週は第174回の琵琶樂人倶楽部「琵琶を巡る三種の声」と題しまして、私の弾き語り、メゾソプラノの保多由子先生、舞台女優の佐藤蕗子さんの声で琵琶樂の様々な形をお聞きいただきます。エンタテイメントには程遠い、重く、長い作品が3つ続きます。でもとても興味深い内容になると思っています。目先の楽しさを追いかけて、いつしかこの風土から紡ぎ出された音楽を忘れてしまった現代人にこそ聴いて頂きたいと思っています。是非お越しくださいませ。




