東京では天気の良い日が続いてます。そのせいか今年は昨年に比べ緊張感がありませんね。しかしながら今後、演奏会をこれ迄の形で開くことが出来るようになるのでしょうか。それとももう舞台は違う形に変化して行くのでしょうか。舞台人としては、そこが心配です。
今私は毎日のように譜面を眺めて暮らしています。その位しか今のところやることもないので、のんびりと色々と見直すにはちょうど良い機会だと思っていますが、ちょっとのんびりし過ぎで、ゴロゴロしていることも多いですね。贅沢な日々です。譜面は以前創った私のオリジナルをいじっていることが多いのですが、洋楽器とのデュオ作品は今までにない形にしようと思って奮闘中(?)です。まあアイデアが湧き上がってくるまでの「而」の魔術的時間を楽しんでいるという訳です。
また以前私がロンドンで初演した石井紘美先生の曲「HIMOROGIⅠ」も見直しています。石井先生は現在ドイツにお住まいなのですが、先生から「少し手を入れたい」とのことで連絡が来て、メールでデータのやり取りなどをしながら、久しぶりに聴き直しているのですが、琵琶の音と電子音が、今聴いてもとても新鮮で、あの頃を想い出します。

あの頃
この曲を初演したのは2003年の5月、ロンドンシティー大学でした。もう18年前なんですね。時の流れがこんなに早いとは・・・。私にとっては初めての海外公演で、スウェーデン人尺八奏者グンナル・リンデルさんと二人で、一週間程ストックホルム大学、スウェーデン国立民族博物館ホール、他地元のサロンコンサート等をやって、次の週はロンドンに渡り、ロンドンシティー大学で演奏してきました。当時BBCオケのフルーティストだったR・Sさんの家に居候させてもらって、そこからロンドンシティー大学でのリハーサルに3,4日通い、初演にこぎつけました。演奏会当日は、昼間、世界各国から集まった若き作曲家たちに向けてのレクチャーをやり、夜が演奏会。英語もしゃべれない奴が、半月ほどのツアーをよくぞやり遂げました!!。R・Sさんの奥様(ピアニストで日本人の方)が「あなたじゃ外でランチも注文できないだろうから」とお弁当を作ってくれて、それを背負ってロンドンシティー大学に出かけたのが懐かしいです。今思うと何かに突き動かされていたようなツアーでしたね。
この時の演奏は私の2ndCD「MAROBASHI」に収録され、その後、石井先生がドイツの現代音楽のトップレーベルWergoから出した作品集「Wind Way」にも収録され世界発売となりました。また少し後にナクソスレーベルからもリリースされました。
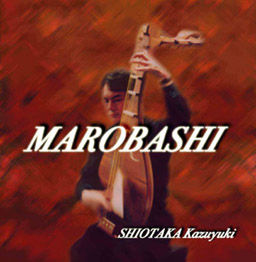
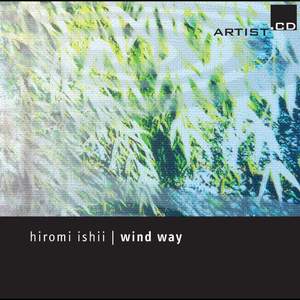
この曲は、自分の演奏が世界に発表された最初でしたので、本当に嬉しかったです。
「HIMOROGI Ⅰ」は、私の代表作である「まろばし」と共に琵琶弾きとしての私を形作った重要な曲なのです。
「HIMOROGI Ⅰ」は石井先生の作曲の準備期間を考えると、約20年程の時を生き続けて、20年経って更にまた先へと進化しているという訳です。曲は常に演奏されるからこそ命が宿るのであって、その命が次世代へと繋がって行くもの。それは古典文学が時代によって様々な視点で読まれ、解釈されて行くのと同じ事です。今回は石井先生と、「我々が今生から居なくなった後の事」も考えて、後々の演奏家も演奏が可能なようにしようと話し合っています。
石井先生から教えてもらったことはとても沢山あるのですが、中でも一番覚えているのは「実現可能な曲を創りなさい」という言葉。それは技術的な面だけでなく、経済的な面にも言える事で、無理な編成や、お金のかかり過ぎる設定のものなど、譜面を書いただけで演奏されないままの曲が、世の中には沢山あるのです。今私が創っている曲は、カルテット止まりで編成が小さい曲が多く、必ず自分が弾くという事を前提にしていますが、これは琵琶という楽器の特殊性を考え、「実現可能」という石井先生の教えによることが大きいですね。
私の曲は少々難しいと、琵琶製作の石田克佳さんから時々言われるのですが、これについては、ちょっと視点を変えたり邦楽の枠を取り払うと割と簡単維解決できます。私の場合、発想の根本が弾き語りでは無いので、他ジャンルから琵琶に転向した人には判りやすいんですが、いわゆる流派でお稽古をしている人には、いきなり違う言語で喋りかけられているような感じなのでしょう。かつて私に習いに来ていたイスラエルのミュージシャンや、アメリカの某音大を出た方(共にギタリスト)は、私の創った独奏曲などを、短期間でそれなりに弾きこなしていました。きっと次世代の琵琶弾きにとってはさほど難しい曲ではなくなるだろうと考えています。また樂琵琶の作品も古典雅楽の発想で創っていないので、雅楽を勉強している人より他ジャンルの人の方が入りやすいですね。以前台湾の二胡と琵琶(pipa)の奏者がちょっとアレンジを施して、リサイタルで何度か取り上げてくれました。
自分が作り出した曲が受け継がれ、その魂が様々な形に進化して行く様は興味深いです。この曲が台湾で再演された時は本当に嬉しかったです。
日本では琵琶のような伝統的なものは、流派で形を教え込まれるので、なかなか別のアプローチというものが発想しづらいのですが、今は伝統曲だろうと最新の曲だろうと、ネット配信を通じ、世界に飛び立って行く時代です。世界中で面白いと思った人が、流派とは全く違うやり方で曲にトライしたり、作曲者とは別の意味合いを持たせて、アレンジして演奏する人なんかがどんどん出てくるでしょう。家元にお伺いを立てなくてはい
けないなどという村社会的なルールは、もはや通用しません。
けないなどという村社会的なルールは、もはや通用しません。
そんな次世代に向けた視線も踏まえて作曲活動をしてゆくことは、とても大事なことだと思います。私の創り出したものが、世界の誰かによって、新たな形になって、新たな命を吹き込まれて、その魂を進化させて行く。ロマンあふれる素晴らしい物語じゃないですか。

赤坂ゆううんにて 尺八の藤田晄聖君と
ネットで世界が繋がっているこの時代には、魅力ある音楽だったら必ず、世界の誰かが、その精神や魂を彼らなりのやり方で受け継が出で行くでしょう。レコードの時代ですら、ジミヘンやマイルスのレコードをかじりつくように聴いて、その魂を受け継ぎ、次世代の音楽を創造していった人が世界には山のようにいるのです。
欲をかくのはよくないかもしれませんが、私の創った音楽が、世界中の多くの人の手に渡り、更なる魂の進化を遂げて行って欲しい、と願うばかりです。
欲をかくのはよくないかもしれませんが、私の創った音楽が、世界中の多くの人の手に渡り、更なる魂の進化を遂げて行って欲しい、と願うばかりです。

琵琶樂人倶楽部にて photo 新藤義久
琵琶樂にも、型や流派のような目に見える形に囚われず、永田錦心の、そして鶴田錦史の魂を受け継ぐ若者がもうそろそろ出てきていいんじゃないかな。私はそう思っています。そしてなにより私自身が、囚われることなく次世代の琵琶樂をもっと創って行きたい。それが例え評価されずとも、その志と魂だけは無くしたくないですね。



