
琵琶樂人倶楽部にて、安田登先生、名和紀子さんと
先日の琵琶樂人倶楽部は、沢山の方にお越しいただいて、大変充実した会となりました。小さな会場ですし、こういう時期でもありますので、何人かお断りをするような形になってしまいましたが、これからも内容充実でやってまいりたいと思います。今後共宜しくお願い申し上げます。



左:浄瑠璃寺、中:高天彦神社参道。右:高鴨神社

琵琶樂人倶楽部にて photo 新藤義久
私はあまりデジタルが得意でなく、SNSも一切やっていないし、せいぜいこのブログとメールを書く程度の、超アナログ派なので、何とか時代にへばりつきながら生きて行くしかないだろうと思っていますが、PCやデジタルツールなどの生活システムという部分よりも、一番心配しているのは、現代人の「想像力の欠如」です。
ネットの記事や書き込みなどを見るにつけ、いつもその「想像力」の無さに残念な思いを感じてしまいます。プロであるはずのライターでさえ、物事の背景や裏側への視野にかけるような文章を書いている例が多いように思います。自分と違うレイヤーに生きる人が居て、全く違う生き方があり、感性があるという事が理解できないのでしょうか・・・。世の中に起こる事件などを見ても、自分の世界以外の物を想像出来なくなっているような、痛ましいものが大変多いように思います。またそれに対する意見を見聞きしても、もうこの国は終わりか、と思えるような言葉ばかりが並んでいますね。今、心が失われてきている。私には、そうとしか思えません。こうした現代日本人の姿はかなり深刻な問題ではないかと思えて仕方がないのです。
世の中の流行りを見ても、目の前が楽しいものが全てになりつつありますね。じっくり考え、味わうものは大変少ないです。日本は、江戸時代から歌舞伎に代表されるように、何でもありの目の前を楽しませるエンタメが大流行ですが、そういうものと同時に、深く感じ、想いを馳せるような芸能も、かつては沢山存在していました。
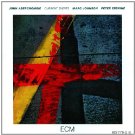 ジョン・アバークロンビー「Current Events」
ジョン・アバークロンビー「Current Events」現代の音楽家は、喜怒哀楽の感情を歌い上げるのが「表現する」事とばかりに、声を張り上げているものが多いですが、哀しみの裏側にある心、喜びの背景にある情景等々、何か喜怒哀楽のもっと奥深い所が忘れ去られているような気がしてなりません。表層の感情ばかりでは味わいは感じませんね。
70年代、80年代辺りまでは、そんな流行りのポップスと同時に、リスナーの想像力を刺激するような音楽を創るレーベルがまだ頑張っていてリスナーもそういうものを求める人が多く、結構世界に受け入れられ、CDやレコードの売り上げも大きかったように思います。私の世代だとECMレーベルなどはその筆頭でしょう。キース・ジャレットの「ケルンコンサート」等はもの凄いセールスを記したし、アルヴォ・ペルトの諸作品は、現代音楽の新たな分野を世に紹介し、これもまたかなりのセールスを実現しました。私はラルフタウナーの「ソロコンサート」、ジョン・アバークロンビーの「Current Events」などの作品等々、ECMレーベルの作品から、かなりの影響を受けました。これらの音楽は聴くと同時に、感じる音楽でした。

琵琶樂人倶楽部にて、安田登先生、名和紀子さん、晄聖君
世の中のものは、どんなものでも様々なタイプのものが溢れているのが無理の無い状態だと常々思っていますが、今では、どんなものでも感じる事よりも楽しむことが優先というものが多いですね。生活すべてがあまりに便利になってしまって、想像力をさして使わなくても生きて行けるようになってしまったので、周りの物や人と関わるという、人間の基本が崩れてきているように感じるのは私だけではないと思います。何か根幹が危うくなっていると感じられて仕方がありません。
その反面、表面の体裁やルールは取り繕おうとして、自粛〇〇の様に、中身より目に見えるルールを守る事で満足し、またそれを盾に攻撃することで、自分は正当だと思い込む。何故そういうルールなのか、どうして行けば、皆が気持ちよくウェルビューイングで暮らして行けるのか、そういう事に想いを馳せることをしないですね。近視眼的で表面的な思考は、対立とトラブルをどんどん生んで行くように、私は思えて仕方がないのです。


ヴィオロンにて、朗読の櫛部妙有さんと photo 新藤義久
寄ってかかるものを見つけ、そこに身を寄せている事で安心し、中身を考えようとしないのは、日本人の特性なのでしょうか。想像力は人間の生きる術の最たるもの。月を見て、歌を詠むこともなくなった日本人に、明日はあるのでしょうか。
豊かな音楽を創って行きたいものです。



