今月は琵琶樂人倶楽部が、何と14周年を迎えます。開催回数も155回となり、気持ちも新たに、更なる気合も入ってきました。HPの琵琶樂人倶楽部のコーナーには、この13年間の軌跡が残っていますので、是非ご覧になってください。
今でも色々と試行錯誤をしながらやっているのですが、とにかく流派や協会、ジャンル関係なく、琵琶樂に関することを考え付く限りやってきました。この13年間は、自画自賛ではありますが、回を重ねるごとに充実してきたと思っています。
私は樂琵琶と薩摩琵琶(あと少しばかり平家琵琶)を弾きますが、樂琵琶が千数百年という長い歴史を誇るのに対し、薩摩琵琶は、流派というものが出来てまだ100年。その源流を辿ってもせいぜい150年。また私が最後に習ったT流は1970~80年に流派として成立した若い流派です。私が使っている錦琵琶も開発されたのが昭和に入ってからですので、正に現代の音楽であり、楽器なのです。
今でもイメージだけで琵琶が捉えられ、演奏する方も、ろくに歴史認識が無いままに広報している例が多く見受けられます。私は自分の演奏だけでなく、演奏者、リスナーの意識も変えて行くべきだと思い、琵琶樂の確かな歴史と知識を広めるという志の元に、琵琶樂人倶楽部を発足しました。

100回記念演奏会 リブロホールにて古澤月心さんと
琵琶樂人倶楽部では、Vnの田澤明子先生やメゾソプラノの保多由子先生など、洋楽の大ベテランを呼ぶこともよくありますが、基本的に若い世代の方に声をかけています。協会や流派という枠を外してみると、良いものを持っている琵琶人・音楽人は結構居るんです。琵琶樂人倶楽部では、そんな面白い魅力を持った人にどんどんと声をかけていますが、永田錦心や鶴田錦史が実践してきたように、新しい時代には、新しい感性を持った人がどんどんと活躍して行くと確信しています。受賞歴など並べて満足しているような旧来の感性では、次の時代は見渡せません。明日の琵琶樂を担って行く為にも、自分自身の精進と共に、旧来の常識や因習に囚われることなく、魅力的な人材にどんどん声をかけて、明日の琵琶樂を共に盛り上げて行きたいと思っています。

当時の私、高野山常喜院にて
この写真は発足して一年後、高野山常喜院にて開催した独演会の時のものです。琵琶で演奏活動を始めて、もう随分と経ちますが、琵琶樂人倶楽部を発足してからの、この13年間は本当に良い仕事をさせてもらいました。シルクロード各国へのコンサートツアーや高野山公演をはじめ、今振り返っても、よくやったなと感心するようなものばかり。とにかく琵琶弾きとして本当に良い仕事に恵まれました。
またリーダーアルバムCDも8枚(+ベストアルバムが2枚)をリリースして、邦楽では世界へ一早くネット配信も開始して、充実の13年間だったと思っています。
これも皆、良き先輩方々や良き仲間が居て、聴きに来てくれる人、応援してくれる人が居たからこその賜物であって、今更ながら、多くの人に支えられたと感じています。私は、いわゆる世間でいう所の芸人には程遠いタイプです。とてもじゃないけどエンターティナーには成れません。気の利いたことを言える訳でなし、愛想を振り撒くどころか、舞台に出ても仏頂面しか出来ません。スター性などというものからは全く持って程遠いのですが、そんな私がこうしてやって来れたことは、御縁に包まれていたからだと、心から感謝しております。この御縁こそが私の音楽であると思っています。

今年の7月琵琶樂人倶楽部にて photo 新藤義久
今月の琵琶樂人倶楽部は原点に立ち返り、薩摩琵琶の変遷をレクチャーします。ゲストには尺八の吉岡龍之介君を迎え、「今」の琵琶樂を演奏いたします。
11月11日(水)
場所:ヴィオロン(JR阿佐ヶ谷駅北口徒歩5分)
時間:19時30分開演
料金:1000円(コーヒー付)要予約
出演:塩高和之(レクチャー・琵琶) ゲスト吉岡龍之介(尺八)
演目:風の宴 まろばし 西風 他
問い合わせ:琵琶樂人倶楽部 orientaleyes40@ yahoo.co.jp
時間:19時30分開演
料金:1000円(コーヒー付)要予約
出演:塩高和之(レクチャー・琵琶) ゲスト吉岡龍之介(尺八)
演目:風の宴 まろばし 西風 他
問い合わせ:琵琶樂人倶楽部 orientaleyes40@ yahoo.co.jp
是非是非お越しくださいませ。尚、このような時期でもありますので、完全予約制とさせていただきます。 orientaleyes40@yahoo.co.jp 迄ご一報くださいませ。
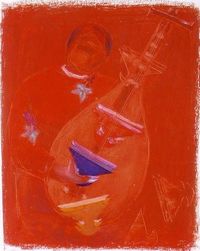
最期に。琵琶樂人倶楽部の看板絵として、いつも掲げているこの赤い絵は、長崎の鈴田郷さんという方が書いてくれました。私がまだかろうじて若手と呼ばれていた頃、大阪で小さな演奏会をやり、そこに娘さんと来てくれた鈴田さんが、私をスケッチして書いてくれたものです。残念ながら鈴田さんはもうお亡くなりになってしまいましたが、この絵だけは、これからも琵琶樂人倶楽部の看板として掲げて行こうと思っています。
今後共宜しくお願い申し上げます。



