世の中が動き出しましたね。これから世界が、そして日本がどう舵を取るのか。今私たちは岐路に立たされていますね。
 先日、ルーテル大阪教会の大柴譲治牧師と一年ぶりに電話でお話しさせていただきました。大柴牧師は2016年迄阿佐ヶ谷のルーテルむさしの教会にいましたので、私はイースターコンサートやらクリスマス礼拝など、事あるごとに教会に行って牧師の説教を聴いていました。また教会では何度も演奏をさせていただき、大阪教会へ移る時には「方丈記」の公演までさせていただきました。
先日、ルーテル大阪教会の大柴譲治牧師と一年ぶりに電話でお話しさせていただきました。大柴牧師は2016年迄阿佐ヶ谷のルーテルむさしの教会にいましたので、私はイースターコンサートやらクリスマス礼拝など、事あるごとに教会に行って牧師の説教を聴いていました。また教会では何度も演奏をさせていただき、大阪教会へ移る時には「方丈記」の公演までさせていただきました。ちょうど一年前、私は突然、大柴先生に会いに行きたいなと思って、関西に用事があったついでに、何のアポも無く飛び込みでルーテル大阪教会に行ってみました。今思うときっと何かに導かれたのでしょう。その時本当に絶妙のタイミングで牧師に会う事が出来、楽しいひと時を過ごさせていただいた記憶がしっかり残っています。
先日、昨年の再会の事を大柴牧師が想い出してくれて、Facebookで一年前のこの記事を取り上げてくれたそうです。道理でこのところPVが上がっているなと思っていましたが、そういう事だったのですね。私はSNSを一切やっていないので判らなかったですが、ちょうど一年経って、お互いに色々と想い出すというのも何かの縁かなと思います。事実大柴牧師とはそういう繋がりと感じることがとても多いのです。
ルーテル大阪教会では、今ネット礼拝をやっているので早速Youtube で拝見しました。沢山出ていますので、ご興味のある方は是非観てください。大柴牧師の言葉は、神も仏も判らない私に、どういう訳かすっと入って来て、多くの気づきを与えてくれます。このブログにも色々とその時々での勝手な感想を書いたりしていますが、久しぶりに聴いてまた色々と感じるところがありました。
いくつか聞いた中に、「人が一つ場所に集まるというのは、当たり前の事ではないのです。恩寵なのです」(5月24日の説教)という言葉を聞いて、私の中にすとんと落ちるものがありました。
私が普段やっている小さな演奏会も、規模は小さいけれども、それでも特別な時間なんだという事を改めて思いました。集客が出来ない等といつもそんなことばかりを考えていましたが、あまりにも心が小さくなっていましたね。確かに私は宣伝も上手くできないし、エンタテイメントの音楽でもないし、人脈も人望もさしてないので、集客はいつも少ないのですが、この場を持たせていただいて、存分に自分の思う音楽を妥協せずにやれるという事への感謝をいつしか忘れていたのかもしれません。私はすべての演奏会で自分の作曲したものをやらせていただいています。そんな人は琵琶でも邦楽全体でも他に居ないでしょう。そういう機会を与えられていたという事です。その与えられたものをもっと考えるべき時が、今だと感じました。

経正熱唱中 箱根岡田美術館にて
私がレパートリーにしている数少ない弾き語りスタイルの曲に「経正」があります。経正は音楽家として生きたかったけれど、自分に与えられた運命は平家の武将でした、霊となって表れた経正は、ラストシーンでそんな自分に与えられた運命を悟り、受け入れて、自らろうそくの灯を消して成仏して行きます。私も今生で、悟らぬとまでいかなくても自分に与えられた運命を少しは理解し、その意味をあらためて考えていきたいですね。
ちょうど一年経って、大柴牧師と電話で再会を果たすというのも何かの意味があったのでしょう。牧師は「この時間を大切な時間として過ごしましょう」と電話口で言ってくれましたが、コロナウイルスがもたらしたことは、悪い事ばかりではないですね。
ソーシャルディスタンスがこれから定着することを考えれば、大柴牧師の言われたように「皆が集まってくるのが当たり前」ではない時代になったのです。この岐路に立たされたとも言える、動きの止まった数か月を大切な時間として思えるような心を持ちたいものです。
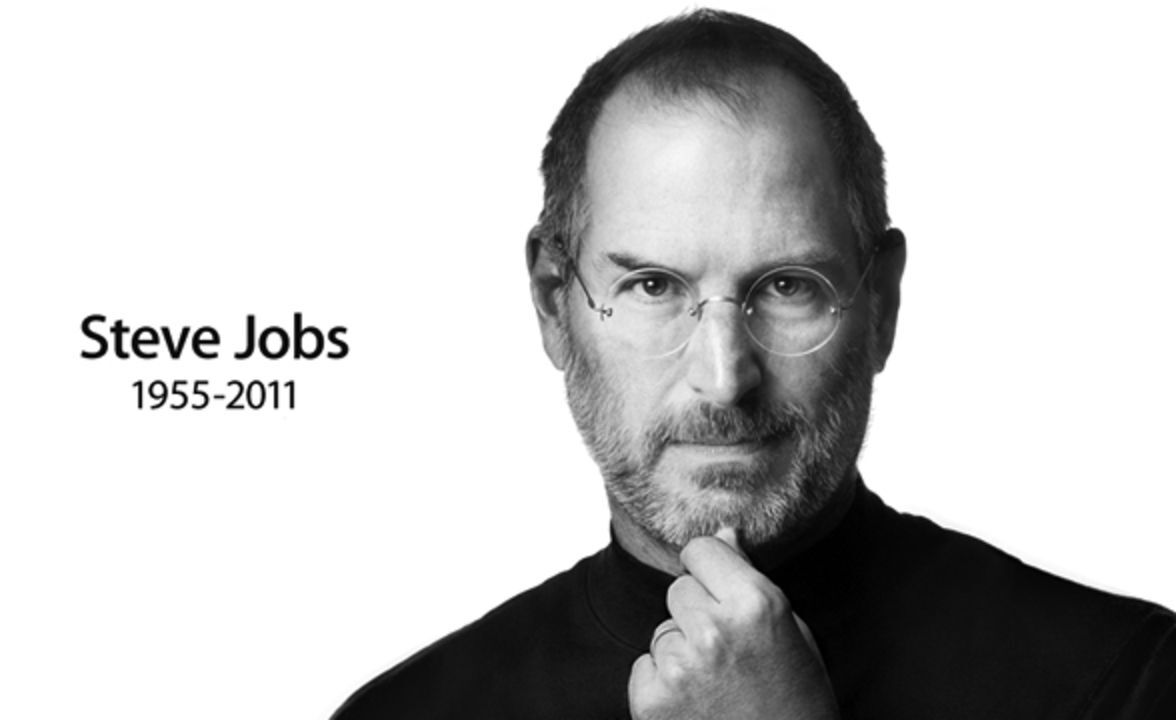 私は今のこの状況を、日本全体が変わるべき時に来た、そういう運命と試練を与えられた、という風に考えているのですが、ビジネスの分野でも色んな話が出て来ていますね。私はビジネスセミナーなどにも少し顔を出すこともありますので、これ迄いろんな話を聞いていたのですが、もう日本の経営のやり方では10年も持たない、という話が多いです。未だに年功序列の考え方が蔓延し、スキルのある若手が収入を得ることが出来ないとの事。だからAiなどの最先端の研究部門はシリコンバレーやバンガロールにあるそうです。新しい感覚とスキルを持ったビジネスの最先端にいる若者は、日本では正当な収入を得ることは出来ないし、日本の経営陣特有の、失敗を恐れて無難に体裁を取り繕おうとする考え方が、若手のチャレンジを妨害して何もできない、という話を何度も繰り返し経営学の先生方から聞きました。
私は今のこの状況を、日本全体が変わるべき時に来た、そういう運命と試練を与えられた、という風に考えているのですが、ビジネスの分野でも色んな話が出て来ていますね。私はビジネスセミナーなどにも少し顔を出すこともありますので、これ迄いろんな話を聞いていたのですが、もう日本の経営のやり方では10年も持たない、という話が多いです。未だに年功序列の考え方が蔓延し、スキルのある若手が収入を得ることが出来ないとの事。だからAiなどの最先端の研究部門はシリコンバレーやバンガロールにあるそうです。新しい感覚とスキルを持ったビジネスの最先端にいる若者は、日本では正当な収入を得ることは出来ないし、日本の経営陣特有の、失敗を恐れて無難に体裁を取り繕おうとする考え方が、若手のチャレンジを妨害して何もできない、という話を何度も繰り返し経営学の先生方から聞きました。かのスティーブン・ジョブズは今見るととんでもないものを色々作り、大失敗を繰り返して、失敗しながら成功もしてきたそうですが、かつての日本企業も敗戦というどん底から発展をしてきましたことを考えれば、この時代に、今一度かつて熱くほとばしった創造する心を取り戻して欲しいものです。

日本橋富沢町楽琵会にて。能楽師 津村禮次郎先生と
日本には良いものが沢山あります。文化も精神も世界に誇るものが沢山あります。しかし無情にも世の中というものは留まることがないのです。「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」がこの世というもの。過去に固執して「今あるものを守っていれば何とかなる」という事は、あり得ないのです。常に創り出して行くからこそ文化として成り立ち、その精神が社会を発展に導き、文化として受け継がれてゆくのです。永田錦心や高橋竹山が居なかったら、今津軽三味線も薩摩琵琶も無かったでしょう。
人と距離を取り、群れないで個人として生かざるを得ない時代になると、これまでのやり方も考え方も通用しません。しかし人間としての核の部分は揺るがない。キリスト教的に言えば、神やイエスと自分との間にぶれがないという事でしょうか。そこを今一度見つめ直す時期に来たという事だと思います。正に今はそうした核となるものとの「再会」の時期ともいえるのではないでしょうか。幸か不幸か私達はもう強制的に「変わらなくては生きて行けない」場所に立たされてしまったのです。残念ながら、まだ〇〇〇マスクを児童生徒に強要するような、権力に盲従する例が散発的にニュースで流れていますが、今こそ振り返り、何が大切なものなのかを見つめて、大切なものとの「再会」をして、これからの生き方を模索し、大切な核を持って生きて行きたいですね。
一年ぶりに素敵な再会をさせていただきました。



