先日の京都の公演で中型1号機を使ったのですが、ほんのちょっと音程が合わないなと感じていたので、早速駒をはずして高さと位置の調節をしました。
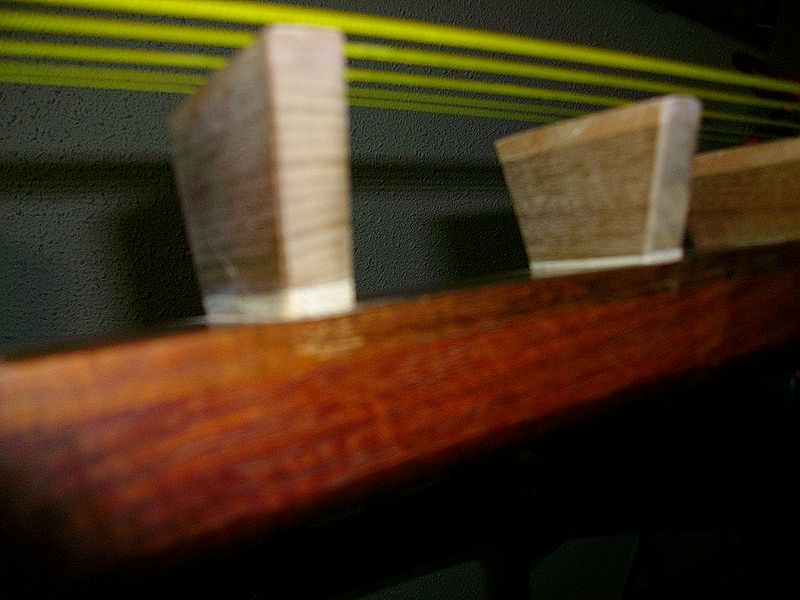
先ずはこれまでついていたところに印をつけて、駒を叩いてはずします。簡単に外れるのですが、下手をすると、駒の下の木部が割れて、竿に少し駒の木部を残してはずれてしまうので要注意です。上の写真の左側の駒は、ちょっと木部を残してはがれてしまいましたのでその分「下駄」は厚めにしました。以前は駒そのものを自分で削りだして作っていたのですが、さすがに今は、そこ迄手をかける時間が無いので調整のみにしています。
ちなみに、接着剤は100円ショップの木工用アロンアルファです。これは刷毛がついているので使い易いのと、あまり接着力が強くないので、木部を痛めないのがいいですね。

もう一つ。くれぐれも駒を取り付ける時には、目の方向を左から右へ流れるように取り付けて下さい。木には目というものがあり、目の方向を間違えるとノミが入って行きません。
そして駒の高さは大変に重要で、これが均等になっていないと弦振動が次の駒に当たって、音がつぶれてしまいます。そうすると音は汚くなるは、伸びないは、もう全く使い物になりません。演奏家生命に関わる一大事です。サワリはその都度調整が効きますが、駒は一度取り付けたら演奏の前に付け直すわけには行きませんので、駒の位置や高さはとても気を使うのです。私は1mmの厚さのヒノキ(または杉)板を一枚づつ貼り付けながら慎重に調節するようにしています。高さ、音程、そしてサワリの調整まですると結構な時間がかかりますね。今回はやり直しもしましたので、二日にかけて修理しました。

塩高モデル大中小
筝でも笛でも楽器として完成されたものと対等に音楽を奏でるには、先ず琵琶自体がそれにふさわしいものでなければ、とても音楽は創ることが出来ません。当たり前のことですが・・・。
琵琶楽が、いつまでもこぶしまわして忠義の心なんぞうたっているような所で留まり、器楽分野に進もうとしなかったら、本当に琵琶は無くなってしまうかもしれない。平曲から続く弾き語りの伝統を次世代に繋げる為にも器楽分野の発展が不可欠だと私は思っています。
私は独奏曲、笛やヴァイオリンとのデュエット曲など、色々と器楽曲を創っているので、最近では演奏会でもうたうのは「祇園精舎」とアンコールの「開経偈」くらいという機会も増えてきました。「壇ノ浦」や「敦盛」のような長いものは年に数回程度しかやりません。中世から声と共に発展してきた琵琶楽ではありますが、平安時代には弾き語りという形そのものが無く、全くの器楽で「啄木」のような素晴らしい器楽曲が演奏されていました。私はあくまで琵琶の妙なる音色を聞かせたいのです。樂琵琶を演奏してみて更にその想いは強くなっています。
私は歌手ではありません。あくまで琵琶奏者として第一級の演奏家でありたいと思っています。そのためにも琵琶のメインテナンスは完璧にしておかないと、聴衆を納得させることは出来ないのです。ヴァイオリンでもギターでも、プロの演奏家は皆さん楽器に関しては、常に完璧な調整をしています。琵琶楽では、声に意識が言ってしまっているせいか、この楽器に関する意識があまりに低く過ぎると常々感じています。この音色をぜひリスナーに届けて欲しい。その為にも、楽器の調整は「最上」を常とする意識を持っていて欲しいものです。歌に寄りかかっては、この妙なる音色は何時まで経ってもリスナーの耳に届きません。琵琶の魅惑的な音色をたっぷりと聴いて頂くのが私の仕事。琵琶が一番魅力的に響く曲をこれからもどんどん創って、演奏してゆきたいのです。
 京都天性寺にてヴィオリンの佐渡さんと新作上演中
京都天性寺にてヴィオリンの佐渡さんと新作上演中サワリの調整は、体で言えば喉の調子を整えるようなもの。駒の調整は体の骨格や筋肉などのバランスを整えるのに似ています。武術でも同じなのですが、どこか変に拘っていたり、ウィークポイントを抱えていると、本来の動きが出来ません。勿論プロは武道家でも音楽家でも、どんな事態に陥っても、それなりに対応するのですが、普段から心身ともに整えておくに越したことはありませんね。
サワリや駒のメンテのやり方を教えて欲しい、と時々言われるのですが、相当の根気と時間がないとなかなか教え切れません。中途半端だと、かえって壊してしまうこともありますので、なかなかメンテを教えるのは難しいです。私はT師匠からメンテに関して教わりましたが、本当にありがたい授業だったと思っています。自分独自のセッティングにしたいと思う人は、是非お師匠様に教えてもらって下さい。

今はもうなくなってしまった紀尾井町福田屋さんにて
以前とあるお坊さんから、琵琶に声をかけるようにして労わることを教わりましたが、
今では琵琶に話しかけながらメンテするのが普通になっています。
今では琵琶に話しかけながらメンテするのが普通になっています。
琵琶は私のパートナー。どこへ行っても琵琶と二人きりということが多いので、相方の調子が悪いとこっちもおかしくなります。何時も最高・最上の状態にしておいてあげたいですね。



