
この間「古きを慕い、新しきを求む」という記事を書いたら早速色んなところから反応がありました。
確かに皆が定家や鶴田錦史のようだったら、世の中上手く回らないでしょうね。なかなか俺流を貫いて生き、活動することは難しいですが、かといって人と同じでは面白くない。たとえ何も出来なくとも、何も遺せなくとも、「心は新たなものを求め、高き姿を願う」ようでなくては!!。その姿勢こそアーティストなのです。

邦楽では先生の声色までそっくりなんていう人も結構多いですね。そっくりなだけにその質と中身が先生とは全く違うことが、かえってよく聞こえてくるものです。
いくら優等生でも、信者でも、先生の生きてきた時代に生きることは出来ませんし、先生の人生を自分がそのまま生きることも出来ないのですから、同じ人間には成れないのです。したがって上っ面のフレーズや音色など真似したところで、音楽が同じになるはずがないのです。つまり表面上先生と同じフレーズを弾いたり唄ったりしているというのは、音楽的芸術的には、まだ稽古のほんの初期段階であり、極端に言えば自分に嘘を付いている状態といえます。一人ひとり顔も人生も違うのに、出てくるものが同じというのは、まだまだ音楽家としては発展途上にあると言ってよいでしょう。明らかに自分が見えていないし、どこかで「これが俺の音楽だ、俺はここまでがんばった」と、自分を騙し無理やり納得しているだけのこと。
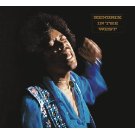 世界を見渡しても、音楽、絵画、文学などどんなジャンルに於いてもコピーが評価される例はありません。ジミヘンやプレスリーのそっくりさんは物まね芸人の域を出ないし、マイルスそっくりにTpを吹いても酷評されるだけです。音楽は我が身から溢れ出てきてこそ音楽であって、これだけがんばりましたという発表会のようなものは、意識がお稽古事ということです。
世界を見渡しても、音楽、絵画、文学などどんなジャンルに於いてもコピーが評価される例はありません。ジミヘンやプレスリーのそっくりさんは物まね芸人の域を出ないし、マイルスそっくりにTpを吹いても酷評されるだけです。音楽は我が身から溢れ出てきてこそ音楽であって、これだけがんばりましたという発表会のようなものは、意識がお稽古事ということです。
初心者の内なら、まあこつを掴むまでに真似をするのは結構なことだと思いますし、誰しも影響はいろいろなものから受けるでしょう。しかし音楽家として舞台で人に聞かせたいのなら自分の音を追求しなくてはいけない。勿論音楽そのものもオリジナルであることが、舞台人としての前提条件です。小さな邦楽の世界だけだったら、先生の物まねが出来るだけで周りに褒められのでしょうが、それはあくまでアマチュアの世界。師匠の教えを受け継ぐということはそんな程度の低いことではないのではないでしょうか。
 津村禮次郎氏 昨年12月の日本橋富沢町樂琵会にて photo Mayu
津村禮次郎氏 昨年12月の日本橋富沢町樂琵会にて photo Mayu
薩摩琵琶のようなまだ歴史の浅いものは別として、残念ながら邦楽では、能でも歌舞伎でも筝曲でも、自由に動いているのは、皆家元やその家族だけですね。本当に残念ですが、まだまだ組織の倫理優先で、誰しもが自由に活動を展開できる状況ではない、というのが現実です。津村禮次郎先生のような人は例外中の例外と言えますね。
時代は刻一刻と変わります。演じ手も聞き手も人々のセンスもどんどん変わってゆきます。流行を追うことはないですが、時代にコミットしないのは音楽とは言えません。だから時代を引っ張るのはむしろ異端の方。異端と言われる人は、次の時代のセンスを身につけているから旧社会では異端に写るのです。今古典となっているものは皆その時点で異端と言われた方々です。だからこれからの邦楽を想うのであれば、自分に無い発想と行動力を持っている若手、そして異端こそ応援するようでなくては・・・!。
邦楽は今後、その感性の本質を次代に受け継がせることが出来るでしょうか?。それとも保存会のように曲だけが残されて行くのでしょうか・・・・・?。
人はなかなか自分の感覚を中心にしてしかものを見ません。かく言う私も、新しいものを何でも受け入れることは出来ません。しかしたとえ理解できなくとも、ラベルの「水の戯れ」を酷評したサン・サーンスや、武満さんの音楽を「音楽以前だ」と酷評した山根銀二のようにはなりたくないですね。自分の感性感覚が全てだなどとは思わないし、多様なものが共存してこその社会だと思えば、彼らのような評論は書けないと、私は思います。自分が権威だと思っている人間、自分がジャッジすると思い込んでいる人間。自分の宗教しか認めようとしない人間。いつの世もこうした人間の姿こそが戦争の原因です。
少なくとも芸術家には、世がどのようであっても定家の言葉を胸に抱いて欲しいものです。
「詞(ことば)は古きを慕い、心は新しきを求め、及ばぬ高き姿を願ってうたう」



