このところ少しゆっくり過ごしていますが、とはいえ先週は琵琶樂人倶楽部、日本橋富沢町樂琵会があり、確定申告もやり終え、やっぱりばたばたと動き回っているのは変わりませんね。しかしまあ演奏会はそんなに多くはないので、こういう時期こそ普段行けない舞台を観たり、質の高い音楽を聞いたりして人生行豊かにしなくては!。ということで色々な会に出かけてきました。

先ずはちょっと前になりますが、Met Live Viewingトマス・アデスの「皆殺しの天使」を観てきました。さすがにトマス・アデスの新作だけあって最先端を行ってましたね。もうオペラというより前衛演劇という感じで、聴衆の感性の先を行くような出来栄えに唸ってしまいました。また詳細なブログはあらためて書きますが、天才はどの分野でもジャンルなど軽々超えてゆくんだな、とあらためて感じました。ジャンルや旧来のスタイルに固執しているようでは、時代は動きませんね。深く実感しました。
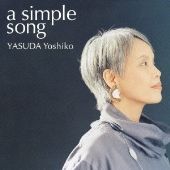 そして次はメゾソプラノの保多由子さんのサロンコンサートにも伺いました。赤坂のドイツワイン専門店「遊雲」という素敵なお店での弾き語りによる演奏でしたが、自然で伸びやかな声、そして気負いのない素直な感性から紡がれた歌曲の数々が実に気持ちが良かったです。加えて私は生意気にもドイツワインが結構好きなものでして、がぶがぶと頂いてきました。美味しゅうございました。
そして次はメゾソプラノの保多由子さんのサロンコンサートにも伺いました。赤坂のドイツワイン専門店「遊雲」という素敵なお店での弾き語りによる演奏でしたが、自然で伸びやかな声、そして気負いのない素直な感性から紡がれた歌曲の数々が実に気持ちが良かったです。加えて私は生意気にもドイツワインが結構好きなものでして、がぶがぶと頂いてきました。美味しゅうございました。
更に今週はNYで活躍していたテナーサックスの佐藤公淳さんのライブにも行ってきました。 メンバーは公淳さんのテナーの他、ピアノにケビン・マシュー、ベースにタイラー・イートンというトリオ編成。NYで一緒にライブをやっていたトリオだそうです。実に素晴らしい図太いサブトーンが鳴り響いてましたよ。以前このブログでも紹介したスーン・キムさんもそうですが、若い頃からジャズの中心地に身を置いて研鑽していると、音がそうなるんでしょうか。日本のライブでは滅多に聴けない「ジャズ」の音が溢れていました。小さなジャズクラブでしたが店内は満杯で、且つ海外の方ばかりでしたので会話もMCも英語。何だかNYにでも居るような雰囲気でしたね。これぞモノホンのジャズ!。久しぶりに「ジャズ」に浸った感じ。大満足!!!
メンバーは公淳さんのテナーの他、ピアノにケビン・マシュー、ベースにタイラー・イートンというトリオ編成。NYで一緒にライブをやっていたトリオだそうです。実に素晴らしい図太いサブトーンが鳴り響いてましたよ。以前このブログでも紹介したスーン・キムさんもそうですが、若い頃からジャズの中心地に身を置いて研鑽していると、音がそうなるんでしょうか。日本のライブでは滅多に聴けない「ジャズ」の音が溢れていました。小さなジャズクラブでしたが店内は満杯で、且つ海外の方ばかりでしたので会話もMCも英語。何だかNYにでも居るような雰囲気でしたね。これぞモノホンのジャズ!。久しぶりに「ジャズ」に浸った感じ。大満足!!!
いつもこうした実力のあるプロの演奏を聴くと思うのですが、保多さんも公淳さんも、とにかく風情があるのです。音楽家としての雰囲気といったらよいのでしょうか・・・。絵になっているのです。同じことをスーン・キムさんのライブの時にも書きましたが、
「風情というもの~TOWER OF FUNK Japan Tour」
https://biwa-shiotaka.com/blog/51377818-2/
舞台というものは非日常なのです。我々音楽家は、そこに立って始めて成立する仕事をしているのです。そういう普段と違う世界に身を置き、且つ舞台の上で絵になるというのは、我々音楽家に課せられた必須な条件のようにも思えますね。


演者の「華」とは世阿弥の昔から言われてきたことですが、確かに上手くなってくると、舞台で絵になってくるということも事実です。それは自他共に認める実力が身についてきたということでしょう。しかし自分で勝手にノリノリになって勘違いしているだけの人が多いのが現実です。賞取ったから私は凄いなんて思っている人、小さな世界で褒められて、先生なんて呼んでもらって喜んでいるような人は、見るからに素人臭いものが漂って来ます。
 ライブの現場に足を運んでくれる方々は、音楽だけでなく、その華やかさも求めて来るということです。派手な演出だけで、見せ掛けの華やかさに寄りかかったものはつまらないですが、華のない舞台はもっとつまらない。特に日常を引きずっているような舞台は最悪です。衣装やセットではなく、人を惹きつける人間力こそ舞台の魅力かもしれません。
ライブの現場に足を運んでくれる方々は、音楽だけでなく、その華やかさも求めて来るということです。派手な演出だけで、見せ掛けの華やかさに寄りかかったものはつまらないですが、華のない舞台はもっとつまらない。特に日常を引きずっているような舞台は最悪です。衣装やセットではなく、人を惹きつける人間力こそ舞台の魅力かもしれません。
私が30代の頃、所作を身に付けろと散々言われていましたが、それはお作法として格好だけつけろということではなく、凛とした落ちついた風情を身に付け、舞台で人を惹きつける人間力を身につけろということなんだと、今頃になって判ってきました。実際に自分で色々な舞台を見て、そういう風情を持った人を観ると「これか!」とよく判りますね。何度かそういう舞台を拝見してくると、所作の持つ意味も見えてくるし、そこにある深く重厚な日本文化も感じられます。

音楽家としてもう長い時間を過ごさせてもらいましたが、年が行けば行くほどに一流の舞台人の持つ風情を感じるようになりました。自分でもそんな風情になりたいものです。



