先日、琵琶樂人倶楽部開催100回記念演奏会をやってきました。

ちょっとしたハプニングもあり、終始ドタバタとした一日でしたが、とにかくここまで来たことに万感の想いがあります。
今回は独奏の他、古澤月心さんとのデュオ、尺八の田中黎山君とのデュオ、最後は「勧進帳」をやってきました。毎度のことながら多々反省はありますが、ともかくこうして形として100回目の記念演奏会が出来たことは本当に良かったと思っています。


 何ごとも、必ず新たなステップへと動く時期というものがあります。社会情勢は一番わかりやすい例ですが、こうした小さな会でも、個人の中でも、ある一定の期間を経ると必ず、次の段階へと進む時期があります。今私はそういうNext stepを踏み出そうとしている時期なのかもしれません。自分の中で色々なものが動き出しているのを感じるのです。
何ごとも、必ず新たなステップへと動く時期というものがあります。社会情勢は一番わかりやすい例ですが、こうした小さな会でも、個人の中でも、ある一定の期間を経ると必ず、次の段階へと進む時期があります。今私はそういうNext stepを踏み出そうとしている時期なのかもしれません。自分の中で色々なものが動き出しているのを感じるのです。
こういう時期が定期的に訪れるというのは日々進化・深化しているということでもあると思います。だから私は常にワクワクしていられるのです。そして能の津村禮次郎先生や日舞の花柳面先生など、常に挑戦と創造性が全身に満ちている人とも自然と繋がっていきます。志を同じくする先輩や仲間と繋がって行けるというのは、芸術活動をしてゆく上で実に嬉しいものです。逆に上手だけれども歩みを進めていない人とは、どうしても縁が薄くなりますね。
古典を継承して行くのはとても大切なこと。しかし常に創り出すという姿勢が無くては、古典も形骸化してしまいます。古典芸能は携わるだけでも充実感があると思いますが、時代によって受け手のセンスはどんどんと変わって行きます。古い演目でも、江戸時代と現代ではどんどん変わって行くのが当たり前。何処を変え、何処を遺すか、そのセンスを古典芸能は問われているのに、形ばかり遺して、新作と言いながら過去の焼き直しをしているようでは、その存在意義も意味もありません。新たな概念、センス、形式、様式、そういうものを次のステップへと導くような人が出なかったら、もう邦楽は終わりでしょう。
我々舞台人は時代を先取りして、常に聴衆の感覚を先導する位でなければ時代は進みません。それはクラシックでもロックでもジャズでも、演劇や美術の分野でも同じで、聴衆は最先端に惹かれファンになるし、次代を動かす原動力にもなって、芸術と社会がコミットして行くのです。またそういう活動があるからこそ、古典がまた意味を持ってきます。古典にも新たな命が吹き込まれ、新たな魅力が輝きだすのです。
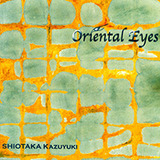
私は最近、この1stアルバムの原点に帰ろうと思っています。勿論焼き直しはしません。同じ曲でも10何年も前と今では違う意味合いが自分の中に存在するし、具体的に出て来る音も違う。つまりセンスが変わってきているのです。しかし根本精神は同じ。このアルバムで示した精神は、今こそ時代の中で輝きを持ち始めるだろうと思っています。
今日本の古典芸能が衰退しているのは、社会とのコミットが無いからではないでしょうか。少しばかりファンが増えても多くの現代人の感性を動かすような魅力がなければ、結局好き者の為の存在でしかありえません。ドビュッシーもラベルもシェーンベルクも、ルイアームストロングも、チャーリーパーカーも、マイルスもジミヘンも、パコ・デ・ルシアも武満徹も、皆その当時の人々の心を激しく揺さぶり掴みました。だから今に伝えられ、またその先に挑戦する者が後を絶たないのです。江戸時代に出来た歌舞伎なども、きっとできた当時の人々の心を強烈につかんだのではないでしょうか。

2009年ジョージア 国立ルスタベリ劇場演奏会にて
次のステップを踏み出すには、今までを乗り越えて行かなくては足は出ません。また、何かが終わりを迎えるからこそ、次のものが生まれるとも言えるでしょう。悲しい別れもまた次への序章とも言えるのです。
伝統が老害になってはいけない。常に次のステップを踏み出して行く若者を育てるのが、伝統芸能に携わるものの役目ではないか、そんなことを語り合った記念演奏会でした。



