2月の半ばから、カリブ海の国々を巡ってきました。しかし今回は帰国の次の日が「日本橋富沢町 樂琵会」。それも記念すべき第一回目の演奏会だったので、とにかく飛行機がちゃんと飛ぶか気が気じゃなかったですが、予定通り帰国でき、且つ「日本橋富沢町 樂琵会」も無事に終わりホッとしましたので、気持ちも落ち着きました。落ち着いたとたんに花粉症の症状が出てきました。体は正直ですね。
早速カリブのご報告を。


先ずはヒューストンまで飛行機で行き(ここまでで13時間もかかるので、これだけでもへとへと)、そこからトリニダードトバゴの首都ポートオブスペインへとたどり着きました。ここは何と言ってもスティールパンの聖地。色々な個性のパンのグループがひしめいていて、世界的なコンテストなども開催されています。私自身は南国にあまり縁の無い方なのですが、知り合いにスティールパン奏者が居るので、ちょっと本場の生音を聞いてみたいという気持ちはありました。実は私が行くすぐ前に日本人のスティールパン奏者がこの街で殺されるという、痛ましい事件があったばかりなので、ちょっと切ない感じもしていたのですが、結局街中では演奏を聴くことは出来ませんでした。少し残念に思っていたのですが、今回は移動が船でしたので、ここを離れる出港の際に地元の演奏家とダンサーが、こんな感じで見送ってくれました。


この明るさ、リズムなどは日本の風土からは到底出て来ませんね。雪が降るような国では、こういう風に体が動きません。やはり風土があってこそ感性が生まれ、音楽が生まれるということを実感しました。 かの地で聞くスティールパンの音は気持ち良かったですよ。亡くなった若者もこの魅力に惹かれここに来たんでしょうね。無念だったでしょう。
かの地で聞くスティールパンの音は気持ち良かったですよ。亡くなった若者もこの魅力に惹かれここに来たんでしょうね。無念だったでしょう。
こういうものに触れると、素晴らしいと思うと同時に、武満さんの「音楽にはやはり国境があるのですね」という言葉を想い出します。私は、音楽が万国で解り合える共通言語だとは思っていません。地域によって風土がこれだけ違えば、感性もまるで違う。ロックやポップスのような歴史の無い、無国籍のものだったらいざ知らず、風土に根差した民族の音に関しては、なかなか理解すら及ばないのが当たり前だと思います。
判らなくても、違う感想を持っても良いのです。多様なものがこの地球上に在るのだということが判ればそれでいい。一つの価値観に押し込めようとする、同じ感想や想いを押し付けようとするノー天気な理想主義の方がよっぽどおかしいし、怖いです。多様であるということが、生命の基本であり、文化の基本です。モンテーニュのいう通りです。今の邦楽そして日本という国に、その多様さがあるでしょうか・・・・・・?。
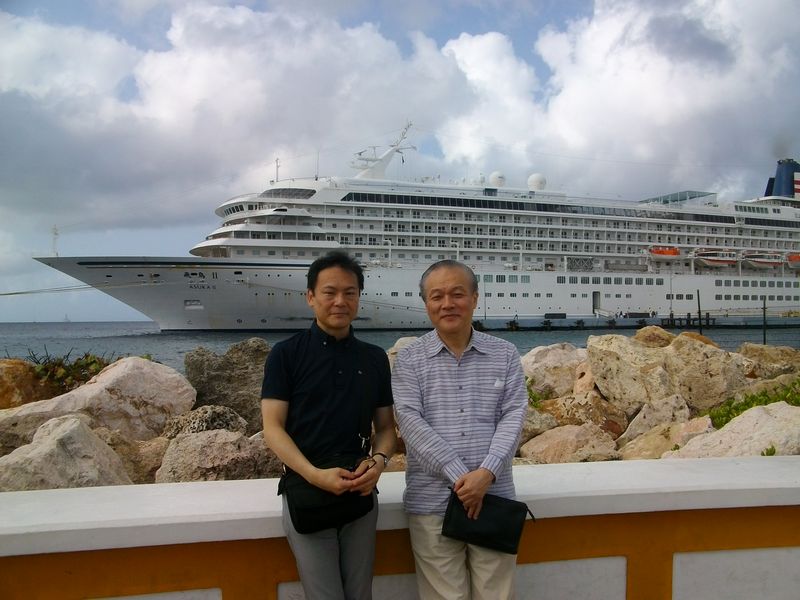 今回は手妻の藤山新太郎師匠と一緒だったのですが、とてもシンプルで且つ、話芸と共にやる手妻は外国の人には判りずらいのでしょうね。また琵琶の、あの静寂精緻なあの空気感も、彼らにしてみれば異国のお経を聴かされているような気分なのかもしれません。でも自分達のものと違うものがあるということが判ってくれるだけでも良いかなっと思います。
今回は手妻の藤山新太郎師匠と一緒だったのですが、とてもシンプルで且つ、話芸と共にやる手妻は外国の人には判りずらいのでしょうね。また琵琶の、あの静寂精緻なあの空気感も、彼らにしてみれば異国のお経を聴かされているような気分なのかもしれません。でも自分達のものと違うものがあるということが判ってくれるだけでも良いかなっと思います。
日本人は奈良平安の時代から、自分達に無いものを取り入れてきました。舶来主義はもう筋金入りなのだと思いますが、邦楽器でジャズやポップスをやったり、クラシックの曲を弾いて、カッコイイとか凄い現代的なんていわれるのは、世界の音楽の中でも邦楽だけだと思いますね。そう思うのは私だけなのでしょうか?

カリブ海の夕暮れ
連日とても良いお天気で、海も穏やかでした。海面をトビウオが跳ね、カモメがそのトビウオを狙って飛び回っていました。毎日の夕陽朝陽はとにかく美しく、地球が一つの生命体であるということを感じずにはいられませんでした。照らされる海原は一つとして同じ表情が無く、滔々として、いつまで見つめていても飽きが来ないのです。この生命の躍動に比べたら人間の小さいこと。小さなカテゴリーに拘り振り回され、プライドやら意地やら、無くてもよいような鎧を自ら背負い込み、要らぬ努力をしながら自分を生きている。もっと大きな自然の中の一部として自分を捉えることが、何故できないのだろう???
水平線を毎日眺めながら、人間の存在の危うさ、またその人間の作り出した文化の素晴らしさ、風土に展開した長い歴史・・・・、色々な想いが私の中を駆け巡りました。
普段触れることの無い風土、文化に触れることは大いに刺激になりますね。また一つ視野が広がりました。



