先日、「弦流」ライブをやってきました。
 「弦流」は、元々フラメンコギターの日野道生さんが、ウードの常見裕司さんと組んでいたグループなんですが、昨年あたりから日野さんと私の琵琶で何度か共演して、だんだん面白くなってきたこともあって、今回こうして「弦流」として3人で演奏することになりました。場所は西荻窪の「音や金時」。ここでライブをやるのは本当に久しぶりで、昨年、日野さんのライブに顔出した位で、もう7,8年ぶりのライブとなりました。マスターもママも相変わらずの笑顔で迎えてくれて、本当に嬉しかったです。
「弦流」は、元々フラメンコギターの日野道生さんが、ウードの常見裕司さんと組んでいたグループなんですが、昨年あたりから日野さんと私の琵琶で何度か共演して、だんだん面白くなってきたこともあって、今回こうして「弦流」として3人で演奏することになりました。場所は西荻窪の「音や金時」。ここでライブをやるのは本当に久しぶりで、昨年、日野さんのライブに顔出した位で、もう7,8年ぶりのライブとなりました。マスターもママも相変わらずの笑顔で迎えてくれて、本当に嬉しかったです。

日野さん、常見さんは共にその道の第一人者としてつとに知れていますが、さすがの実力で、リズムに関しては私は到底かなわないですね。特にアラブ音楽は10拍子なんていうものが普通にあるし、リズムを主体としない日本音楽とは全く違う構造を持っています。それは多分に歌と踊りが演奏とセットで常に一体となっていることが、日本音楽と違う所でしょう。フラメンコもそうですが、リズムが大変重要な要素になっていますね。アジアでも朝鮮民族の音楽などはリズムが主体となっているそうですが、日本は音色や響きの方が重要になって、「一音成仏」なんていう言葉もある位、リズムや和音、音楽の構成さえ排した響きそのものが重要視されます。
 日本でも、平安時代の雅楽には理論が整備され、リズムも結構複雑でしたが、中世に禅の思想が入ってくると、芸能・音楽に哲学性が加わり、芸能の持つ精神性や感性が明確に出来上がってきます。勿論エンタテイメントとしてのものはずっとあったと思いますし、民衆の生活の中から生まれた音楽も数多くあったと思いますが、能などに代表される、現在まで続く音楽や舞台は、わびの思想と共に、その背景に禅の思想があった事は明らかだと思います。
日本でも、平安時代の雅楽には理論が整備され、リズムも結構複雑でしたが、中世に禅の思想が入ってくると、芸能・音楽に哲学性が加わり、芸能の持つ精神性や感性が明確に出来上がってきます。勿論エンタテイメントとしてのものはずっとあったと思いますし、民衆の生活の中から生まれた音楽も数多くあったと思いますが、能などに代表される、現在まで続く音楽や舞台は、わびの思想と共に、その背景に禅の思想があった事は明らかだと思います。
それにしても同じアジアで、中東から朝鮮半島までがリズム主体音楽なのに、日本だけが音色主義の音楽になったというのは面白いですね。
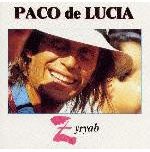
タイトルの「シリアブ」とは、中東のアッバース朝から後ウマイヤ朝へと、当時最先端の音楽を伝えた楽人の名前です。シリアブはウードと歌の名手として、アッバース朝の首都バクダッドの宮廷で活躍していましたが、あまりの才能と実力の為、師匠から疎まれて、最初モロッコに左遷されます。その後、彼の評判を聞いた後ウマイヤ朝のカリフがシリアブを宮廷の楽人として迎え、当時最先端を行っていたバクダッドの音楽がイベリア半島のコルドバへと伝えられたのです。今でも中東では「シリアブ」を知らない人は居ない位の大音楽家です。フラメンコギターのパコ・デ・ルシアはそのシリアブを大変尊敬していて「ZYRYAB」という作品を残しています。シリアブは正に風を伝えた人なのです。
現代では、「売れないものは価値が無い」というアメリカ型の風潮がどんどん加速し、エンタテイメント経済優先の価値観があまりにも蔓延し、派手なもの、目先の賑やかしのような消費される音楽があまりにも蔓延していますが、私は地味であっても、現代型のショウビジネスとして売れなくとも、後の世の人が風を感じてくれるような音楽を創り、演奏して行きたいですね。
古代アジアの風土に起こった風は、途切れることなく、現代の私達のにも吹き渡って来ているのです。



