先日、第92回琵琶樂人倶楽部が終わりました。阿佐ヶ谷の小さな名曲喫茶ヴィオロンを借りてやっている、とても地味な会なのですが、なんだかんだでもう92回とは、我ながら良く続いたもんだなと思います。今月は毎夏恒例のSPレコードコンサートでしたが、「永田錦心とその時代」というタイトルで、前半に永田錦心のSP、後半に永田錦心と同時代に活躍した他のジャンルの音楽家のSPをかけ、私が解説をさせて頂きました。
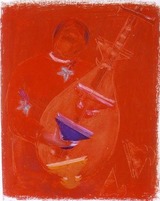
 古澤月心さん
古澤月心さん
とにかく色々な琵琶人と交流したい。そして琵琶のイメージを何とか耳なし芳一から解放したい、という想いで始めました。未だに琵琶をやっている方も流派のことしか知らないという人も多く、大正昭和に出来た曲でも、何でもかんでも流派の曲は古典だと言ってはばからない状態なのです。そんな風潮に、私は大変な違和感がありました。若手の方がそういう先生方の言葉を鵜呑みにして、洗脳されるかのように頭を固くしていく例を何度となく見ていて、自由な立場にある私が正しい琵琶の歴史と知識をもっと広めて行かなくてはいけないのではないか、という想いで、まあちょっと一石を投ずるような気持ちで始めた訳です。
琵琶樂は衰退の極みにあるとずっと言われていますが、正しい認識が無ければ衰退するのは当たり前です。何でもかまわず古典等と言い放ってしまうということは、つまりは歴史認識が無く、邦楽の他のジャンルをろくに聞いていないし、邦楽以外のジャンルもほとんど知らないからこういう意見が出てくるのです。もっと広い世界に琵琶を届ける為にも、日本音楽の中での琵琶楽の変遷や、他ジャンルの音楽との比較文化論などがぜひとも必要です。そうすれば大正や昭和のものが「古典です」なんて言葉は出て来ないでしょう。
邦楽全体に音楽学というものがほとんど無く、中でも琵琶に関しては、学者でも真面目に研究をされている方はほんのわずかです。琵琶について発言しているブログなども少しありますが、そこから何を導き、どういうヴィジョンを琵琶に持たせてゆくのか、という所まで到底至らず、オタクやマニアの資料集めの楽しみ程度で終わっているのが現状です。
同じ琵琶でも自分が弾かない他の種類の琵琶には興味も知識も無いようでは、琵琶楽全体に明日という字は見えて来ません。色々な方と共演し、現代人の感性で創作や作曲も旺盛にやって、もう一度現代の社会と生活の中に琵琶が身近に存在するような状況をぜひ作りたいと思っています。

永田錦心は「琵琶村の住人」と言って、厳しく当時の琵琶人を戒めていましたが、私は私のやり方で、面白そうな琵琶人達を繋いで行こうという訳です。琵琶樂人倶楽部に集う方や出演する方は、皆さんかなり色んな知識見識を持っていらっしゃる。私はこういう人達が好きなんです。こういう人達が次世代にバトンを渡してくれるんじゃないかと思っています。
世の中には、クラシックもロックも現代音楽もオペラも、ジャズもインドやアラブ音楽も、タンゴもブルースもある。私が個人的に好きなファドやフラメンコ、中世ヨーロッパの教会音楽など、素敵な音楽が世界に溢れている、こういった素晴らしい音楽の中に琵琶楽もあるのです。先日の会の時にも、そんな色々なジャンルに詳しい音仲間が集まりました。嬉しい限りですね。彼らの視点がきっと次世代を照らしてくれるような気がしています。

琵琶樂人倶楽部はもうすぐ100回目を迎えるのですが、これまでやってきた軌跡は自分の中で大きな糧となっています。レクチャーをするにも、音楽以外の芸術、歴史や宗教など勉強しなくてはいけないし、SPレコードの解説をするにも古い資料を只管読み漁るという具合で、この8年間で自分の中に大きな幅というものが出来ました。また多くの琵琶人とも交流する事が出来、その人達を接して行く中で、自分が行くべき方向も道もはっきりと見えてきました。
 琵琶樂人倶楽部を始めた頃の私。ちょっと?大分?若い?
琵琶樂人倶楽部を始めた頃の私。ちょっと?大分?若い?
音楽家はともするとオタク状態になり易い。一生懸命な姿勢が時に視野を狭くしてしまうものです。しかしリスナーは世に溢れる音楽を自由に楽しみ、その中で琵琶楽に接してくれるのです。オタクの感性で突き詰めても、この社会の中でどんな音楽として聴いてもらえるるのか、そこが判らなければマニアの域を出ることは出来ないし、結局琵琶で生活して行くことさえ出来ない。
この状況をどんどん変えて、琵琶がもっと日本の世の中に溢れ、世界に飛びだして行って欲しいな~~。その為にも琵琶人はもっともっと多くの音楽を聴き、勉強し、広い視野で、広い世界で活動して欲しい。流派や協会も結構だけれど、村の中に居ては琵琶の音は世に響かない。世界を舞台に活躍する琵琶人がもっと出て来て欲しいし、自分ももっと大きな世界でどんどん琵琶の音を響かせたい。



