先日、久しぶりに尺八奏者グンナル・リンデルさんと会って、ゆっくり話をしてきました。
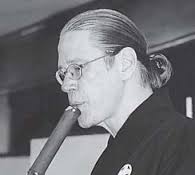 グンナルさんとは、10数年前、PANTA RHEI というコンビ名で演奏・レコーディング・ツアーと、とにかく沢山仕事をしました。楽しい日々でしたね。私は一人で演奏する事も多いですが、常に相棒が欠かせません。今は笛の大浦さんが音楽的な相棒ですが、以前はグンナルさんが正に相棒でした。彼は母国であるスウェーデンに帰り、ストックホルム大学に於いて日本学、特に中世日本文化の研究で活躍しています。ヨーロッパでは尺八奏者としても活動しているそうなので、是非またその内共演したいです。
グンナルさんとは、10数年前、PANTA RHEI というコンビ名で演奏・レコーディング・ツアーと、とにかく沢山仕事をしました。楽しい日々でしたね。私は一人で演奏する事も多いですが、常に相棒が欠かせません。今は笛の大浦さんが音楽的な相棒ですが、以前はグンナルさんが正に相棒でした。彼は母国であるスウェーデンに帰り、ストックホルム大学に於いて日本学、特に中世日本文化の研究で活躍しています。ヨーロッパでは尺八奏者としても活動しているそうなので、是非またその内共演したいです。
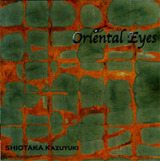
グンナルさんが参加した私の1stアルバム「Oriental eyes」2002年
グンナルさんはかなりいける口なので、ついつい杯を重ね、邦楽から仏教や神道、現代日本の風俗や社会等、とめどなく話が及びました。とにかく日本人以上に日本の文化を勉強し、勿論論文も日本語で書ける。だからとにかく話が尽きないのです。もうかなり前に、グンナルさんや筝のカーティス・パターソンさんと一緒に創ったCD「和」のライナーノーツも全てグンナルさんが日本語で書きました。
これまで尺八に関するかなり専門的な論文をいくつも書き、藝大にも彼の著作は収められています。その他、中世日本文化についての論文はいくつも書いているようで、現在は吉原文化に関する本を執筆中とのことです。全く持って恐れ入ります。
 2013年に会った時。上野の居酒屋にて
2013年に会った時。上野の居酒屋にて
彼のように言語は勿論のこと、歴史・宗教・芸能・風俗まで徹底的に勉強する人が居る反面、とうの日本人はどうでしょうね・・・?。琵琶でも二言目には「シルクロードから続く古の云々~」等と都合よく宣伝して、「古典だ、伝統だ」とキャッチコピーを付けながら近代に出来上がった薩摩琵琶を弾いている輩が多いですが、果して樂琵琶や平家琵琶は勉強しているのだろか・・・・?。
よく言われる事ですが、どうも日本人はオタク的に興味のある所は掘り下げるけれど、総合的に全体を見ることをしないですね。近代といえば近代ばかり、古代といえば古代ばかりのオタクさん達が多すぎると思うのは私だけでしょうか・・・?それにしても日本文化の素晴らしさを感じているのはもはや海外の人なのかもしれません。
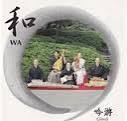
グンナルさんと10数年前から一貫して話し合っているのは、邦楽の感性や風情、つまり根本にあるものについてです。邦楽演奏家は、邦楽の魅力をどこまで感じているのだろう?と思わず思ってしまうことが多々あるのは、私もグンナルさんも同じです。
尺八や琵琶で、音を半音程変化させるような音が良く出てきますが(メリ・カリ・締め)それは音程が単に上がる下がるということでなは無いのです。音に陰影を付けているのです。その音には色々なものが表現され、正にその音こそ邦楽の音色であり、邦楽の感性が凝縮しているのです。メリカリや締める音色には滔々と流れる邦楽の歴史と文化が溢れているのです。そういう所を感じずにバラバラ弾いていても邦楽にはなりません。私はこのメリカリや締めの音を表現するのに、陰影という言葉の他に「色のうつろひ」とも言っています。色が淡くうつろって行く様と言っても良いかと思いますが、この色のうつろひ具合が感性そのものと言えます。間についても同じで、師匠と同じように0.1秒も変わらずに出来たからといって、そこに深い感性と文化が無ければ何も出て来ません。かえっておかしなものになってしまいます。
 私は日頃から短歌を作る事を勧めていますが、日々の中で目に映る事に対し、常に詩情を持って接する姿勢こそ邦楽の根本だと思っています。上手か下手かは別にして、四季によって移ろう自然の情景に想いを持ち、そこから言葉を紡ぎ、歌に表わして行くそんな意識と感性がなければ、メリ・カリ締めの陰影や色彩は何時まで経っても理解できず、ただ音を上げ下げしているだけです。あの一音にこそ、邦楽の姿があると言っても過言ではないでしょう。
私は日頃から短歌を作る事を勧めていますが、日々の中で目に映る事に対し、常に詩情を持って接する姿勢こそ邦楽の根本だと思っています。上手か下手かは別にして、四季によって移ろう自然の情景に想いを持ち、そこから言葉を紡ぎ、歌に表わして行くそんな意識と感性がなければ、メリ・カリ締めの陰影や色彩は何時まで経っても理解できず、ただ音を上げ下げしているだけです。あの一音にこそ、邦楽の姿があると言っても過言ではないでしょう。
だから常日頃から「この風土が無くては成り立たない」ということを何度も言うのです。先日も地元の神社の能楽堂でバリダンスをやっていましたが、形を真似ても風土が無ければその本質は描けません。異文化でも何でも、先ずは日本人としての感性がどれだけ豊かなのか、ということが問題です。その感性を持って異文化に接するからこそ相手の豊かな魅力を感じられるのであって、感性の無い人は、表面の目新しさに喜んでいるだけです。
この風土の中に生き、四季に想いを馳せ、日本の辿った歴史を古代から見つめ、悠久の歴史の中で琵琶という古から続く楽器と文化を我が身に抱くのです。オタク目線では到底捉える事は出来ません。知識も技術も、感性の前には全てがひれ伏すのです。

いつも書いている宮城道雄や永田錦心は、次の時代を感じさせてくれました。それも強烈に!。しかしその根底には滔々と流れる日本の感性が溢れ、脈々と続く日本文化が流れていたのです。当時の若者は、そこにこそ希望を持ち心酔したのです。ただ
の賑やかしではすぐに飽きられます。そうではない本当の魅力を湛えたものだけが次の時代のスタンダードとなるのは当たり前のこと。宮城、永田には本当の魅力があったということです。
後に続く私達は何をすべきでしょうか。先人のやったものをなぞる事でしょうか。それとも先人の志をもって、たとて及ばずとも次世代が希望を抱き心酔するような音楽を創造する事ではないでしょうか。
たとえ遠く離れていても、同士とは話が尽きないのです。



