先日、池袋の東京芸術劇場にて「音楽大学オーケストラフェスティバル」を聴いて来ました。

11月16日は 芸大と昭和音大
11月24日は 上野学園と武蔵野音大と洗足学園
12月6日は 国立音大と桐朋音大
そして私が行ったのは12月7日で、東邦音大と東京音大を聴いて来ました。其々新作のファンファーレでエールを送り合い、それからオケの演奏という形式で、東邦音大がブラームスの4番、東京音大がR・シュトラウスの交響詩「英雄の生涯」。さすが音大生、技術もしっかりとしていてどちらも良かったですが、曲が派手なこともあり、東京音大の方が盛り上がりましたね。
ファンファーレの方は東邦のトランペットのトップの方が実にいい音を出していて、元ブラバンのラッパ吹きとしては拍手が大きくなってしまいました。島崎智徳さんの作曲も秀逸でした。
東邦音大の指揮は同校の准教授でもある田中良和さん、東京音大の指揮は川瀬賢太郎さん。川瀬さんはまだ30歳の若さで、その指揮ぶりは実に明快でダイナミック。好感が持てました。将来が楽しみですね。
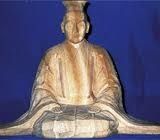 世阿弥
世阿弥
世阿弥は「時分の花」という事を言っています。若さゆえの魅力も認めつつ、それは本当の花ではない、という戒めを持って・・・・。
私の頭では世阿弥の言葉の解説などても出来ませんが、若さには何物にも代えがたい花があると常々思っています。先日の学生たちの演奏にもそれは感じました。若さには確かに稚拙な所も多々あるでしょう。しかし新鮮な魅力も又あります。若さというものが持つ、肉体的、精神的エネルギーは明らかに成熟したベテランのそれとは違います。たとえ未熟なものがあったとしても、その若さの持つ魅力は大いに評価してあげたいと思っています。
しかし世阿弥の言うように、それに溺れてはいけないし、そこを最高点だと思ってもいけない。
また残念ですが、若さの持つ魅力が歪んでいる例もよく見かけます。 まあ勘違いも奢りも若き日には許されるとはいえ、自分をエリートだと思い込むような姿にはフレッシュさは感じないですね。逆に嫌なものを感じます。邦楽では、自分を選ばれた人間だと思い込む例が目につきます。それがその人の器なのかもしれませんが、師匠はもっと愛を持って育てなければ・・・。
まあ勘違いも奢りも若き日には許されるとはいえ、自分をエリートだと思い込むような姿にはフレッシュさは感じないですね。逆に嫌なものを感じます。邦楽では、自分を選ばれた人間だと思い込む例が目につきます。それがその人の器なのかもしれませんが、師匠はもっと愛を持って育てなければ・・・。
人間が奢ったり、勘違いしたり、悩んだり、迷ったりする時、小さな枠に囚われていることが多いのではないでしょうか。「名取ならそれなりに立派でなくてはいけない」「この世界で私はそれなりの位置に居るはずだ」etc.・・・キリが無いですが、何かの枠の中で己というものを見てしまっていると、こういう発想になってしまいます。
音楽をやるのに肩書きは要らないし、聴く方だって、余計な衣が付いていない方が素直に聴ける。そういうものから解放されてゆくのが音楽や芸術のよいところです。しかしがっちりと鎧を着たがる人が多いのは何故でしょう・・・・?。若さの魅力、無垢で新鮮な魅力とは、そういう囚われが無いからこそ溢れて来るのだと思います。

実は、若い花の魅力から、どう次の花を咲かせて行けばよいか、そこが大変に難しいのです。「あの頃は良かった」なんていう人は、若き日の花を、それから先へと育てられなかったという事です。花を育てるには、自分の周りに良き先輩や教師が居るという事が大切ですね。自分では自分の事はなかなか見えないので、自分からアドヴァイスを求めない限り、指摘してくれる人等居ないものです。またそんな良き先輩を得るのもその人の花ゆえであるのでしょう。
花を良い形で育てて行くのは本当に大変で、育たないことが多いものです。20代の頃は皆それなりの花を持っていると思いますが、30代に入る頃には、その花が次の段階へと進んで行く人と、萎んでしまう人がはっきりと分かれて行くものです。本人の資質や器の問題とは思いますが、年齢を重ねれば重ねる程に、技量や知識などよりもそうした資質や器こそが問われてゆきます。それこそが「花」とも言えます。
自分への自戒も込めて言えば、ほとんどの方は「頑張る=頭を固くする」という状態になってしまいがちです。自分にとって都合の良い意見しか聞かず、且つ小さな枠の中で優等生になりたがる。それでは見えるものも見えなくなってしまいます。若者には、是非耀くような花をもっと先へとつなげていって欲しいですね。



戯曲公演「良寛」で御一緒させて頂いている津村禮次郎先生
私の「時分の花」は果たして、花として開いているのだろうか・・・・・。



