先日、年末恒例の創心会をやってきました。
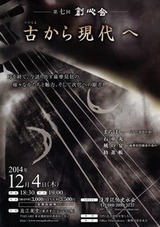
毎年初台のオペラシティーの中に在る小さな音楽サロン近江楽堂を借りて、年末にやっているのですが、今年は語り手3人と琵琶による琵琶語り勧進帳をやろうという事で、琵琶樂人倶楽部で一緒の古澤月心さん、そして勧進帳初演の時に語り手の一人として唄っていた、大ベテランの山下晴楓先生を迎え、更には尺八の田中黎山君も入れて、新たな形で勧進帳をやってみました。
テーマは「古から現代へ」。よく私が掲げているテーマですが今回は、明治を代表する「石童丸」、戦後の物語琵琶といわれる「勧進帳」、そして現代の私の作曲作品という内容にして、近代から現代というくくりで構成してみました。「勧進帳」も琵琶の手は、水藤錦穣氏の手を参考に私が作ったもので、イントロや後半の合奏部分には尺八も入れて作曲しました。
 出来の方はまずまずと言ったところなのですが、共演させてもらった山下晴楓先生には色々と教わることが多かったです。私がどう編曲しても、「自由でいいんじゃないの」という具合に、柔軟に対応してくれて、けっして以前やった通りの形に固執しない所が嬉しかったですね。こうしてまた歴史が繋がって行くんだな、という実感がありました。
出来の方はまずまずと言ったところなのですが、共演させてもらった山下晴楓先生には色々と教わることが多かったです。私がどう編曲しても、「自由でいいんじゃないの」という具合に、柔軟に対応してくれて、けっして以前やった通りの形に固執しない所が嬉しかったですね。こうしてまた歴史が繋がって行くんだな、という実感がありました。
私は伝統を受け継ぐような立場にもないし、古典をやっている等という意識もありません。ただ古くから伝えられている琵琶楽の最前線にいるという想いだけがあります。いつも書いている永田錦心や鶴田錦史も、その時々に於いての最前線だったのではないでしょうか。その最前線に居た彼らの姿こそが私の理想です。だから残された作品を勉強こそすれ、そのまま演奏する事に意味を感じません。もし永田や鶴田の音楽を古典として扱いたいのなら、その古典に対し、自分なりの哲学と答えを持って、彼らの音楽を新しい命として演奏するようにしなければ、質の悪いコピー以上のものにはならない、と思っています。
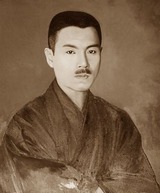 過去の遺産の素晴らしさを知れば知るほど、それをなぞる事は
過去の遺産の素晴らしさを知れば知るほど、それをなぞる事は とても出来ないという思えて仕方がないのです。だからこそ先人がどのような想いでその音楽を創り上げたのか、そこに想いが至ります。古典を研究する土台と哲学が持たなければ、とても琵琶の演奏は出来ません。そして何よりも溢れんばかりの創造性で音楽を作って行く志と姿勢が無ければ、とても舞台に立っていられません。
とても出来ないという思えて仕方がないのです。だからこそ先人がどのような想いでその音楽を創り上げたのか、そこに想いが至ります。古典を研究する土台と哲学が持たなければ、とても琵琶の演奏は出来ません。そして何よりも溢れんばかりの創造性で音楽を作って行く志と姿勢が無ければ、とても舞台に立っていられません。
私も永田や鶴田のように最先端を走り続けていたいのです。私のやっていることがろくでもなければ、後には続かないだろうし、もしそこに素晴らしいものがあれば、何かしらの形で残って行くでしょう。

私が就いた先生方は皆、一様に「自由にやれ」と言ってくれました。「こうしなさい」という先生は一人もいなかった。本当に良き師に巡り会ってきたと思います。だから「伝統を受け継ぐ」だの「古典の継承」だのそういう型にはまった思考をすることは、私にはありませんし、言われたこともありません。ありがたい教育だったと思います。そんな師に恵まれたこともあって、私はどこまで行っても自分の音楽を表現する事に没頭しているのです。そしてそれがこれまで私が就いてきた師匠たちの教えだと思っています。
今後はいつも書いているように、私は琵琶の器楽的な側面を追求しようと思っています。声に関しては従来の節やコブシに乗せた琵琶唄ではない形で、自分の琵琶楽の中の一つの要素として取り組んで行こうと思っています。これが私の琵琶楽の最先端であり、また言い方を変えれば、永田、鶴田に対する継承です。
久しぶりに先人の作った曲を自分なりに演奏してみて、想いが募りました。



