
私は18歳から20年間に渡り東京の高円寺に住んでいたので、夏の終わりには必ず、阿波踊りというのが刷り込まれていて、先週末も雑踏を避けた所からあのリズムを聴いて、夏の終わりを楽しんでいました。
それにしても私が初めて見た阿波踊りと、今のものでは感じが変わりましたね。規模も年々大きくなり、祭りというよりはフェスティバルという感じになりました。踊り自体もホールやTVなどで見せるようになったのでフォーメーションを作ったりして、かなり凝った振付の連が増えてきました。リズムの方も、特徴を出そうとして4拍子のような2拍子のような、ちょっとロックビートを感じさせる連も結構見受けられます。まあ阿波踊りにもモダンスタイルが出てきたという事でしょうね。
 しかしやっぱりあのシャッフルのリズムが無いと、
しかしやっぱりあのシャッフルのリズムが無いと、
どうも阿波踊りの風情が感じられません。また凝った
振付の連も、皆で踊り狂っているという阿波踊り特有の
雰囲気が無く、演技しているという感じがどうしても
してしまいますね。まあ勝手な感想ですが・・・・。
風情というのも人其々なのですが、物事何でも特有の風情というものがあまり感じられなくなると、違うものに進化したように見えてきます。それもまた時代の流れというものでしょうし、時間が経てばそれらも新たなものとして受け入れられていくのだと思います。私自身これまで聞いてきた音楽でも、当時は何だか違和感ばかりだったのが、10年もすると自然に感じられたりする事が良くありました。ただその変化が商業主義に乗せられ、振り回されて自らの姿を見失っているのだとしたら、残念ですね。
 八橋検校
八橋検校
風情というものは、人間感情の中で大切な部分なのですが、多分に過去の想いでなり、ノスタルジー的なものと繋がっていますので、気持ち良いという反面、旧来の感覚や感性に囚われて、引かれたレールの上に座り込んでいる、という事にも繋がります。これまでの価値観の延長線上に居るだけでは、良きものも残って行きますが、古い因習や習慣などが足かせとなって時代を進み、切り開くことが出来なくなったり、また色々なものが滞る事で悪い方向に淀んでしまうこともしばしば。
人間は社会というものを形成し、常に先へ先へと時代を進めて行くのが宿命です。なかなか動物のようには生きられない。パンタレイとはヘラクレイトスの言葉ですが、古代ギリシャの時代から人間だけでなく、世の物事は万物流転するのが定めなのです。
時代に流されて行くか、それとも次の時代を切り開いて行くか・・・。少なくとも芸術は次の時代を切り開くという宿命を負っているようです。
八橋検校も、宮城道雄も、永田錦心も、当時はかなりの前衛だったのでしょう。しかしこうして時代を切り開いていった人が居たからこそ、今がある。世阿弥や八橋検校が居なかったら、日本文化はまた違うものになって行ったでしょう。どんな国でも文化の上に政治や経済が成り立っていることを考えれば、文化こそが国家そのものといえるでしょう。こうした芸術家達は正に日本という国家そのものを作って行ったとも言えますね。
 世阿弥
世阿弥
その継承するものは単なる風情というものではなく、もっともっと根源的なものだと私は思います。どこを受け継いで行くべきなのか。何を新しくして行くべきなのか。そこにこそ感性というものが働きます。琵琶らしいとは?邦楽らしいとは?それらはいったいどの部分なのか。その見極めが出来なければ、万物流転の流れの中で消滅して行くしかないのです。
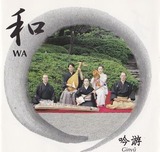
今邦楽はその見極めが出来ているのでしょうか?形や表面の雰囲気ばかりに目が行って、本来受け継ぐべき根源となるものを見失ってはいないでしょうか?格式や肩書きに目を奪われて音楽を忘れていないですか?
邦楽には今、音楽としての無垢な眼差しが一番必要なのかもしれません。
![rock[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2014/08/610d8233-s.jpg) 高円寺には私の人生の記憶がいっぱい詰
高円寺には私の人生の記憶がいっぱい詰 まっているし、色々な想い出に浸るのもまた良い時間ではありますが、私はそろそろ高円寺を卒業する時期に来ているのかもしれません。阿波踊りを見ながら、そんなことを思いました。
まっているし、色々な想い出に浸るのもまた良い時間ではありますが、私はそろそろ高円寺を卒業する時期に来ているのかもしれません。阿波踊りを見ながら、そんなことを思いました。



