真夏の暑さが続きますね。この暑さの中、珍しく先週から夏風邪を頂いてしまい、外出もままならなかったので、家でゴロゴロしてました。

普段からそれなりに聞いているCDだったのですが、健康な時は自分でも知らない内に、何か拘りや構えのようなものがまとわり付いているのか、これ程には響いて来ませんでした。「聴いてやる」的な姿勢がどこかにあったのかもしれませんね。それが体調に少し問題があることで、そんな構えがなく、素直に音に身を浸し聴くことが出来たのかもしれません。
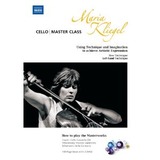
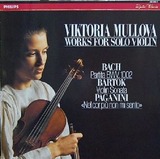
お二人とも勿論世界の超一流ですので、凄いのは当たり前なんですが、その表現の淀みの無い自由さ、大きさにはただただ感激するばかり。お二人が人生をかけて音楽に取り組んでいる姿までも感じられました。正に脱帽です。そして楽器の表現力の豊かな事。素晴らしいという言葉以外に何が出るでしょう。ここまでヴァイオリンやチェロが音楽を豊かに奏でるには、果てしのない長い時間を何千何億という人々がこの楽器に関わり、研鑽をつみ、革新と洗練を繰り返し、受け継がれてきたからでしょう。そして演奏家としてここまで楽器で表現するには、極限に立つような技術と感性、哲学が無いと、とても出来るものではありません。ただなぞってお上手にやっているのとは訳が違うのです。
こういう素晴らしい演奏を聴く度に、琵琶の現状が悲しくなってしまうのですが、とにもかくにも現時点で薩摩琵琶には器楽という発想自体が無いので、奏法的な研究・探求がほとんどされていないのが残念でなりません。楽器である以上この部分を逃げていては、洗練も発展も無いでしょう。勿論私なりにやれることはかなりやって来ているとは思っていますが、私一人がCD出したり、演奏会を回ったりしている位では、とても力及ばず・・・。
どんな楽器にも歌はある。歌と共に楽器も発展してきたのは歴史を見れば明らかです。雅楽だって最初は唱歌をばっちりと習います。しかしだからといって、「歌わないと音楽に成らない」という事は無いのです。あらゆる楽器に、その音色でないと実現できない魅力的な器楽の世界があるではないですか。どうして琵琶には無いのでしょう??まだ薩摩琵琶は誕生して間もないからでしょうか。
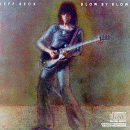 器楽が発達するという事は洗練され、発展しているという事です。器楽の発展によって楽器自体もどんどん洗練されて、その世界は大きく発展し、多くのファンも獲得している事でしょう。ロックギターもジェフベックが75年に出した「Blow by Blow」によってロックのインスト、つまり器楽分野を確立したからこそ、世界のギターキッズが熱狂したのです。ギターテクニックの底上げにも著しく貢献しました。
器楽が発達するという事は洗練され、発展しているという事です。器楽の発展によって楽器自体もどんどん洗練されて、その世界は大きく発展し、多くのファンも獲得している事でしょう。ロックギターもジェフベックが75年に出した「Blow by Blow」によってロックのインスト、つまり器楽分野を確立したからこそ、世界のギターキッズが熱狂したのです。ギターテクニックの底上げにも著しく貢献しました。日本の音楽では、筝でも三味線でも、既にその洗練を経て宮城道雄や、沢井忠雄、高橋竹山のような世界に誇る器楽演奏家が出ている事は、実に誇らしい事。それを思うと、いつまでもコブシ回して唸り声をあげることに終始している琵琶の現状がもどかしい限りです。
 八橋検校
八橋検校特に筝に於いては、「みだれ」という世界に冠たる器楽の名曲(筝独奏曲)が江戸時代に生まれています。皆さんもご存じだと思いますが、近現代の西洋の名曲と比べても一歩もその魅力は劣りません。むしろひれ伏すのではないか、と思えるほどに完成度が高い。作曲者の八橋検校は1614年に生まれ、1685年に亡くなっています。亡くなった年にバッハが生まれています。つまり西洋音楽とは全く違う
アプローチで、バッハ以前にあの名曲を書いているのです。加えて、現代の筝という楽器を作ったのもその大きな仕事です。八橋検校以前は、まだ雅楽で使
う筝で、雅楽ではない曲を弾いていました(筑紫筝など)。八橋検校が新しい筝を開発した事で、現代に続く筝曲というものが誕生したのです。
時代を作る人というのは、楽器から曲から、音楽の在り方から、何から何まで創り出してしまうのですね。
 薩摩琵琶の器楽部分が発展して行くと、歌もどんどんレベルが上がって行くと思います。琵琶唄も独立して、色々な楽器との共演も出て来るでしょう。私も筝の伴奏で琵琶唄をよく唄っています。そしてぜひ弾き語りだけでなく、声と琵琶別々の人が担当する形をぜひ確立したいと思っています。そうなってきたら異種格闘技的な曲もどんどん出来上がって、歌も楽器もレベルは更に上がるでしょうね。器楽の分野を確立して行くのは、三味線や筝の例を見るまでもなく、今後琵琶楽にとって必須だと思います。あらゆるタイプの多くの曲が作られ、その曲が世界に向けて発信されて行ったらいいですね。
薩摩琵琶の器楽部分が発展して行くと、歌もどんどんレベルが上がって行くと思います。琵琶唄も独立して、色々な楽器との共演も出て来るでしょう。私も筝の伴奏で琵琶唄をよく唄っています。そしてぜひ弾き語りだけでなく、声と琵琶別々の人が担当する形をぜひ確立したいと思っています。そうなってきたら異種格闘技的な曲もどんどん出来上がって、歌も楽器もレベルは更に上がるでしょうね。器楽の分野を確立して行くのは、三味線や筝の例を見るまでもなく、今後琵琶楽にとって必須だと思います。あらゆるタイプの多くの曲が作られ、その曲が世界に向けて発信されて行ったらいいですね。
その為には迸るような創造力や感性はもちろんのこと、技術だって果てしないほどに高くなければ、次の世界の扉は開かない。表現は常に次の扉に向かい続けなければ、淀んでしまう。表現活動をするという事は、死ぬまでその先を求めるという事なのです。手慣れた曲をいつも通りにやるようになったら、表現者としてはもう終わり。
 薩摩琵琶でも樂琵琶でも、私が魅力を感じたポイントはその音色です。だからこそその音色が一番輝くようにしたいのです。その為には最高の音が出るように改造もどんどんします。三味線も筝もそうやって世界を創ってきたし、薩摩琵琶も正派から錦心流、錦、鶴田流と、戦争をはさんだわずか50年程の間の短い期間に楽器を改良し、新しい曲も作ってきました。私は更にその先へどんどんと行きたいと思います。
薩摩琵琶でも樂琵琶でも、私が魅力を感じたポイントはその音色です。だからこそその音色が一番輝くようにしたいのです。その為には最高の音が出るように改造もどんどんします。三味線も筝もそうやって世界を創ってきたし、薩摩琵琶も正派から錦心流、錦、鶴田流と、戦争をはさんだわずか50年程の間の短い期間に楽器を改良し、新しい曲も作ってきました。私は更にその先へどんどんと行きたいと思います。
私は現在の薩摩琵琶の姿を、芸術音楽の姿に変えて行きたいのです。大衆芸能的な形で人気を博してきた薩摩琵琶ですが、私はもう少し深い表現をして行きたい。喜怒哀楽という目の前の感情ではなく、もっとその先の世界を奏でる音楽であって欲しい。そして何よりも楽器が自由に鳴り響き、この妙なる音色で、聴衆を魅了させたい。それにはやはり器楽としての薩摩琵琶を作り上げなければ!!
のんびりとはしていられないのです。



