先日、三宅榛名さんのソロピアノライブ「夏を待つ夜」に行ってきました。
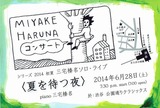
作品は皆新作のピアノソロで、まだ譜面にも書いてないとの事でしたが、その演奏はいわゆる演奏家の演奏ではなく、「作曲家自身が弾いている」と思わせるところが興味を惹きました。こういうニュアンスは音楽に携わっている方でないとなかなか判りにくいかと思いますが、作曲者自身の演奏と、別の演奏家が演奏するのでは随分と表現が変わるものです。この辺はまたじっくりと考察してみたいと思います。ライブは大変面白く聞かせて頂きました。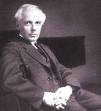 バルトーク
バルトーク
現代では、作曲と演奏は随分と分離してしまって、両方をやる人は本当に少なくなってしまいました。かつてバルトークやリスト、ラフマニノフ等のような名ピアニストであり、且つ素晴らしい作品を書く作曲家でもあるというような人は居ないですね。
もっと昔、バッハやモーツァルトの頃、日本でも江戸時代の八橋検校等の頃は、演奏と作曲の両方をやるのが音楽家でした。時代と共に移り変わって行くのは良い事だと思いますが、作曲家自らが語りかける事も、もっとどんどんとやって行くべきだと、私は常々思っています。これからはまたそんな時代が来るんじゃないかな???
三宅さんはジュリアードのご出身という事ですが、アメリカで勉強していた頃に、きっとジャズの影響をかなり受けたのではないかと思いました。和声には多分にジャズを感じましたし、部分的にはリッチーバイラークのような雰囲気も感じました。バイラークはクラシックもジャズも高いレベルで演奏する超一流
のピアニストですので、聞いていない訳はないだろうと思います。
今回演奏した曲には、先鋭的なものはあまり無く、無調の部分も抒情性を失わない感じで、無理なく聞けました。きっ
とこのスタイルが、今の三宅さんの人生のスタイルでもあるのでしょうね。


三宅さんの作品はさまざまなスタイルのものがありますが、私の作る作品も色々なスタイルがあります。ただ三宅さんと私とはちょっとは違っていて、私の場合は自分の中のバリエーションという事ではなく、もう一人の自分が作品を作っているような感じでしょうか。三宅さんの演奏を聴いていたら、かえって自分の事が見えて来ました。
誰しも自分の中に色々な面を持っていると思います。時にジャズっぽいものが出来たり、現代音楽風なものが出来上がったりするのは一人の人間の中の色々な側面からして当然ですが、私の場合はちょっと感じが違って、二つの自分がそれぞれに曲を作り演奏していると言えると思います。これらがいつかは統一されてゆくのかな、とも思う反面、この自分の中の色々な自分が共存してこそ、私という存在が成り立っているとも思います。

二つの自分とは、違う感性を持った片割れのようなもの。けっして片方だけでは成り立たないので、どうしてももう片方を求めてしまう。二つ共にないと自分が完成しないような感じです。薩摩琵琶を弾かない私は私じゃないし、樂琵琶を弾かない私も私ではない。だからどうしても二つのものが必要なのです。
邦楽も雅楽も日本の音楽とはいえ、今では一般の方々の生活からはかけ離れ、その違いも判りずらいと思いますが、樂琵琶と薩摩琵琶では、感性も構造も理論も、背景の文化も全く違うものなのです。考えてみればよくこんなに違うものが、長い間共存し得たのか不思議です。
 高野山常喜院にて
高野山常喜院にて
高野山が世界遺産になったのも、神道と仏教という異なる宗教が共存している点が世界的に例が無いという理由だったそうですが、日本人はそれを何の違和感もなく受け入れている事を考えれば、全く違う音楽がずっと長い間日本の中に共存していてもおかしくは無いのかもしれません。そう思えば私のような人間が居ても不思議はないですね。二つながらが存在する事が私の中では常なのです。
ただあえて薩摩琵琶と樂琵琶という全く違った音楽に共通点を見い出すとすれば、両方共に歌ではなく器楽という部分でしょうか。そしてショウビジネスへの志向が無いという所が一致しています。普通は薩摩琵琶奏者は弾くことよりも語る事が主となりますが、私は薩摩琵琶の音色が好きで、いわゆる薩摩の琵琶唄は自分にとって色々ある表現形態の一つでしかないので、琵琶唄には余り興味はないのです。声はとても重要な表現手段だと思うので、今後も使って行きたいのですが、一般的な琵琶唄とは違う形を作って行きたいですね。琵琶でデビッド・シルビアンみたいな歌い方が出来たらいいな~~、なんて思ったりもしますが、それもまあ私には似合わないですね・・・・。
二つの感性があり、二つの思考があり、二つの音楽がある。己というものはかくも複雑なものだ、と思った事もありましたが、最近は年を重ねたせいか、それが人間であるのだと、開き直って思えるようになりました。

まあ私のような人間は、色々と欠けているからこそ謙虚にもなれるし、何でも自由には出来ないからこそ、こつこつとやるしかない。結果つまらない事をせずに今まで生きて来れたのかもしれません。勿論失敗も何も数えきれない程あるのですが、もし自分に自信が漲っていて、経済的な心配もなく、何でも出来て自由に振る舞えるような人生だったら、私は今よりもっともっと業火の燃え盛る中を、未だにうごめいていたように思います。コンプレックスや、欠けたピースを心に思っていたからこそ、やっと今こうして生かされていると思えて仕方がないのです。片割れを常に求めているのが、ちょうど良いのかもしれませんね。
それにSideⅡが常にあるからこそ、行き詰まったり、スランプに落ちいったりしないで今までやって来れたのかもしれません。何とかこうとか色々な琵琶を弾いて生きて行けるのだから、これからも色々な自分を私という器の中でそれぞれ生かして、人生を送りたいと思います。



