オペラシティー内の近江楽堂で「Light of the Ancient 」と題された演奏会に行ってきました。

メンバー皆さん大変高い技術を持っていることもあって、即興的なスタイルを多分に交えながら、音楽が自由に流れだし、会場に柔らかく満ちていました。中でも「Cantigas de Santa Maria」という古いスペインの曲をオリジナルのアレンジで演奏した曲が素敵でした。
現代ではこうした多国籍なアンサンブルも全く違和感が無いですね。音楽も国や民族を軽々超えて演奏出来るのが現代ならでは。そこにはかつてのよう
な欧米への憧れで、ろくに言葉も判らず物まねを繰り返していた陳腐さもなければ、偏狭とも感じられるような民族的こだわりも無い。どこまでも自然に世界中の音楽と会話しているさわやかな風が吹いていました。
 音楽には確かに民族性というものが背景にあります。それゆえ一時の薩摩琵琶のような軍国主義に走ってしまうような素地も、それぞれが持っているでしょう。しかし現代の生活を見ても判るように、人間はかなり柔軟に、自分たちに無かったもの、無かった感覚を取り入れて昇華することが出来ます。雅楽もそうなのですが、ゆっくりと時間をかけて自分たちに無かったものを取り入れて、新たに自分たちのものとして創り上げて行くその行為こそ、文化というのではないでしょうか。こうした事は、衣食住すべてに渡り、人間にとって日常的なごく自然な行為なのだと思います。
音楽には確かに民族性というものが背景にあります。それゆえ一時の薩摩琵琶のような軍国主義に走ってしまうような素地も、それぞれが持っているでしょう。しかし現代の生活を見ても判るように、人間はかなり柔軟に、自分たちに無かったもの、無かった感覚を取り入れて昇華することが出来ます。雅楽もそうなのですが、ゆっくりと時間をかけて自分たちに無かったものを取り入れて、新たに自分たちのものとして創り上げて行くその行為こそ、文化というのではないでしょうか。こうした事は、衣食住すべてに渡り、人間にとって日常的なごく自然な行為なのだと思います。

グローバリズムで何でも薄まってしまうのは、私も歓迎しませんが、文化とは常に他と接触する事で、生み出されて来るものです。その生み出されたものを、国でも地域でも、そこに居る人々が「美」と感じる事によって、その地域に感性というものが生まれ、そこから色々なコンテンツが生まれて、固有の文化と成って行きます。そしてそれは日々どんどんと生まれ、また消え、取捨選択されて常に続く営みとして続いているのです。その営みが続く中で、独自の感性が磨かれ、洗練された美意識へと更に昇華して行くのです。その営みが止まってしまったら、感性もくすんで行きます。この感性を共同体の皆が共有・共感するという事がそのまま文化に繋がって行きます。分かち合うと言った方がより判り易いでしょうか。有名な本居宣長の「敷島の大和心を人問はば、朝日に匂ふ山桜花」というような歌も、心を分かち合い、日本の感性となっていったからこそ、詠まれたのです。
「嬉しい」でも「悲しい」でも自分だけの感情になってしまって、個人的な所で完結していては文化は育ちません。是非舞台で多くの人と「楽しさ」も「嬉しさ」も「悲しさ」も分かち合いたいものです。音楽でも何でも皆と分かち合ってこそ、ではないでしょうか。

グルジアのルスタベリ劇場演奏会
音楽・芸術は本来、人と人の心を繋ぐもの。愛を語り、届ける事無く、自分がやっている事で満足するようなお稽古事に陥り、イデオロギーや偏狭なプライドが優先するようでは、その素晴らしさも魅力も分かち合えません。分かち合うことが出来ないという事は、相手に音楽が響かないという事です。先ずは素敵な音楽を聴衆に届け、手を差し伸べる姿勢が大事だと思います。美的感性を皆が持ってこそ文化となるのです。マニアの為のものではありません。文化に誇りを持ち、守り受け継いで行く事と、組織を維持する事は全く違うのです。伝統芸能に携わる私達は今、そのやり方についてよくよく考える必要があるのではないでしょうか。
色々なものと接触し、新たなものを生み出し、育んで行く人間の「営み」は正に命の源泉だと思います。今回の演奏会のように、今まで出会う事のなかった色々な楽器が共に奏し、気負いなく様々な音楽を奏でる事は大いに結構な事だと思います。売らんが為に聴衆に媚びている訳ではないのです。純粋に創造性の営みとして、高いレベルで音楽をアンサンブルするのだったら、どんどんやるべきです。逆に七五調の都節による弾き語りしかやらないというのでは、世界の人と手を繋ぐ事は難しいですね。


郡司敦作品個展演奏会
色んな歌を歌い、この素敵な琵琶の音色で様々な音楽を奏で、色々な形のアンサンブルを聞かせることが出来たら、琵琶の音色を世界中に届けることが出来る。「Light of the Ancient 」のように、多くの音楽とつながり、多くの人とつながることが出来る。素晴らしいと思いませんか。
私は毎年オーケストラとやったり、舞踊とやったり、筝や尺八、笛等々色々なものと一緒に演奏しています。琵琶はその気になれば結構幅広く色々なものに対応が効いて、色々なジャンルの中で曲が弾けるのですよ。出来ないと思い込んでいるだけです。ようはどれだけ頭が柔らかくするか、そこです!
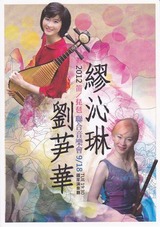
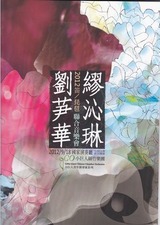
音楽に喜びが溢れ、その喜びを届け、愛を語り、人の手と心を繋いで、分かち合い、響き合う。音楽はそういうものであって欲しいですね。



