先日、かねてから友人が一押しで勧めてくれていた尼崎愛子(現在は改名をして尼理愛子)さんのライブに行ってきました。場所は高円寺の稲生座。ここは私が若かりし頃に通っていたお店でしたので、本当に懐かしかった!。楽しい一日でした。
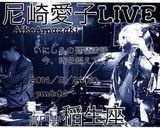
この日は「祇園精舎」などオリジナルスタイルで聴かせてくれましたが、琵琶は全て独学だそうです。この辺に私と似た匂いを大いに感じますね~~。常日頃から、こういう人が出て来ないかな~と思っていましたので、ドンピシャ!という感じでツボにはまってしまいました!。
 皆さん琵琶を弾いている人は、先ずはどこかの流派で勉強します。これは結構な事だと思いますが、オリジナルで活動している人が少ないのが大変残念に思っていました。流派の曲はイントロからエンディングまで曲の形が決まっていて、歌詞だけが変わっている。つまり曲のヴァリエーションがほとんど無いのです。琵琶を習いに行って、この点が一番残念でした。
皆さん琵琶を弾いている人は、先ずはどこかの流派で勉強します。これは結構な事だと思いますが、オリジナルで活動している人が少ないのが大変残念に思っていました。流派の曲はイントロからエンディングまで曲の形が決まっていて、歌詞だけが変わっている。つまり曲のヴァリエーションがほとんど無いのです。琵琶を習いに行って、この点が一番残念でした。
だから表現者として独自の世界を持って音楽を聴かせるには、どうしても従来の形を脱して行かざるを得ません。皆それぞれのやり方があると思いますが、永田錦心も水藤錦穣も鶴田錦史も皆オリジナルでやっていました。他の分野、例えばポップスやロックでも皆そうしてしのぎを削っていることを思えば、琵琶でも、三大巨頭に習い是非旺盛にオリジナルで活躍して欲しいのです。先人の轍を超え、新たな道を作ってこそ、初めて継承と言えるのではないでしょうか。
 確固たる独自の世界観を持って、オリジナルで勝負している尼理さんのような方にファンが居るのはとても頷けます。若手でもベテランでも「上手」や「肩書き」から逃れられず、それを自分で気づかない内に追いかけている人が多い中、彼女の存在は実に頼もしいです。以前は先輩で尼理さんのようにライブシーンで頑張っている方も居たのですが、なかなか続けていくのは難しい・・・・・。これから若手にも是非頑張って欲しいです。
確固たる独自の世界観を持って、オリジナルで勝負している尼理さんのような方にファンが居るのはとても頷けます。若手でもベテランでも「上手」や「肩書き」から逃れられず、それを自分で気づかない内に追いかけている人が多い中、彼女の存在は実に頼もしいです。以前は先輩で尼理さんのようにライブシーンで頑張っている方も居たのですが、なかなか続けていくのは難しい・・・・・。これから若手にも是非頑張って欲しいです。
私はエールを送る位しか出来ないのですが、私自身が自分の想う所を自分なりに歩いているので、尼理さんにもぜひ自分の行くべき道を想う存分進んで欲しいと思います。

私はジャズを通り越したせいもあるのですが、演奏に関しては全て自分の作曲したものを演奏しています。そうでないとどうも納得がいかないからです。色々な考え方があって良いと思うので、自分のやり方が最高だとは思いませんが、琵琶を始めた最初から、教室で習ったものをそのまま舞台で弾くという発想自体が私にはありませんでした。いつも書いているように、現在演奏されている薩摩・筑前の琵琶は明治から始まったといっても良い音楽です。曲に関しては大正~昭和初期にかけて出来上がったものがほとんどで、古典と呼べるような時代を経た曲も無いし、錦琵琶から出た鶴田流のように1970~80年代に流派として成立したものもあります。古典のようなふりをしているだけで、古典ではないのです。これらの近現代の薩摩琵琶は、弾く人によってキー、テンポからフレーズ、メロディーまで一人一人違う性質の音楽ですので、私には名曲が溢れる如く存在するクラシックより、「名演奏あって、名曲なし」と言われる、ジャズに近いものを感じます。ですから型ではなく、プレイヤーの個性を前面に聴いてもらう方が、合っているのではないかと思っています。
 そんな想いでいる事もあって、ライブでも大きな演奏会でも、全てが私にとっては表現の場。随分前、琵琶で活動したての頃、某邦楽雑誌の編集長に、「琵琶でお呼びがかかる内はまだ駄目だ。それではお前じゃなくてもいいという事だ。塩高を指名されて呼んでもらえなくちゃ!」と言われた事を肝に銘じていますが、「壇ノ浦」や「敦盛」をやるとしても、私なりの解釈とスタイルで演奏する事が出来なければ、私は舞台には立ちません。それが私の仕事ですからね!!。
そんな想いでいる事もあって、ライブでも大きな演奏会でも、全てが私にとっては表現の場。随分前、琵琶で活動したての頃、某邦楽雑誌の編集長に、「琵琶でお呼びがかかる内はまだ駄目だ。それではお前じゃなくてもいいという事だ。塩高を指名されて呼んでもらえなくちゃ!」と言われた事を肝に銘じていますが、「壇ノ浦」や「敦盛」をやるとしても、私なりの解釈とスタイルで演奏する事が出来なければ、私は舞台には立ちません。それが私の仕事ですからね!!。
スタイルは違えど私も尼理さんと同じく、「息づく音楽」をやって行きたいのです



