 もういつもの日々が走りだし、年末年始の気分は何処にも残っていないのだが、今年は今月末に川崎能楽堂での演奏会「語り合う時代」があるものの、例年のように追われるようなスケジュールでもないので、ゆっくり過ごしている。私はいつも自分を追い込むことによって何かを為すようなところが強いので、今は気分を開放しリセットするためにも、たっぷり読書をして、CDを存分に聞いて、色々な所に出かけ、精神の養生をしている最中なのだ。
もういつもの日々が走りだし、年末年始の気分は何処にも残っていないのだが、今年は今月末に川崎能楽堂での演奏会「語り合う時代」があるものの、例年のように追われるようなスケジュールでもないので、ゆっくり過ごしている。私はいつも自分を追い込むことによって何かを為すようなところが強いので、今は気分を開放しリセットするためにも、たっぷり読書をして、CDを存分に聞いて、色々な所に出かけ、精神の養生をしている最中なのだ。
最近はギターのCDをよく聞いている。ジャンルを問わず色々聞いているつもりでも、やはりジャズ系が多くなるな~。まあ好みというものはそうそう変わらない。ジム・ホールの「Live!」、ジェシ・ヴァン・ルーラーの「Live at Murphy’s law」、ジョン・マクラフリンの「Live at Royal festival hall」、ラルフタウナーの「Solo concert」はそれぞれ正に洗練の極み!聴く程に魅力が増してくる現代の最高傑作だと思う。こういうものにどっぷりとつかることが出来る時間も、そんなにある事ではないので、今はこの貴重な時間をたっぷりと味わいたいと思う。
本も、この所良い作品に多く出逢っている。毎日何かしら読んでいるので色々とあるのだが、ここひと月くらいの中では熊谷達也の「邂逅の森」と宮本常一の「忘れられた日本人」が良かった。私は元々民俗学というものが好きで、それ関係のものは、小説でもエッセイでも何でもかなり読んでいる割には、有名なこの二つの本はまだ読んでいなかった。この他では恒川光太郎の「夜市」も気に入った。SFと民俗学とホラーが混在していて、文章もさらりとしている。中でも「風の古道」という作品にはなかなかに惹かれるものがあった。
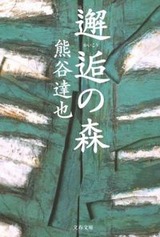
「邂逅の森」は阿仁のマタギを題材に取った優れた作品で、もう7,8年前に随分と話題になった作品なのだが、やっと読むことが出来て、深い感動を覚えた。浅田次郎氏は「本書は去勢された男たちのための、回復と覚醒の妙薬である。男とは本来どういう生き物なのかを、読者は知るだろう」と評している。私はその意見にも大いに同調できるのだが、それよりも男と女、動物、自然、それぞれの生々しい美しさを感じた。生物の命が溢れる風土は厳しくそして美しい。そしてその風土に生きるものも又厳しく美しい。やはりここでも大きなはからいによって我々は生かされているという事を実感できる。それを忘れた時、歪が生じるのだろう。歪の中で生物はいつまでも生きていられないという事も身に沁みる。読み進むほどに現代社会の姿が浮かび上がり、言葉に出来ない多くの想いが湧き上がった。久しぶりに質の良い小説に巡り会えた、嬉しい限り。
「忘れられた日本人」も民俗学の分野では有名な本なのに読んだことが無く、やっと手にすることが出来た。どの章も興味深いものだったが、後半の「文字を持つ伝承者」という所に特に興味を持った。民俗学というと、古い時代の村の話というイメージだが、これには、移りゆく時代を、前に向かって生きようとした人々の、生き生きとした姿がある。こういうものを読むと、いかに現代の我々が日常に安住し、流されて生きているか、我が身が見えてくるようだ。現代がもう今までのようにのんびりとは生きて行けない時代になった事は、皆感じていることだと思う。我々はこれからをどう生きるべきなのだろうか・・?
現代を知るには、過去を知るのが良い、とはよく言われる事。 確かに現代日本の姿は、過去の日本と日本人の姿を一度見つめ直すと、如実に見えてくるようだ。
確かに現代日本の姿は、過去の日本と日本人の姿を一度見つめ直すと、如実に見えてくるようだ。
最近、江戸文化研究家の田中優子さんの記事が出ていて、なるほどと思う事が多かった。伝統やら古典などと称しているものの実態をすぱっと切って、現代の矛盾と闇を突いている。とても伝統とは言えないようなもの、数十年しか経っていないものでも伝統やら古典やら正当だ何だと言わせてしまうという事は、その奥に事実をねじ曲げてでもそうしなければならない何かがあるという事だ。そんな現代の闇は、過去の日本の姿を見るにつけ浮かび上がってくる。
何故現代の社会はこんなにねじれ、歪んでしまったのだろうか?。我々が「豊かになる」と思っている状態になるにはどこかを歪ませなければいけないのか?この深い闇の中には何があるのだろう?。私には世の中の事を論じる知識も技量も無いが、こと邦楽について言えば、残念ながら音楽の喜びが溢れる如く聞こえて来るものは実に少ない。邦楽の中に命の煌めく音楽を取り戻す事は、現代に於いて「伝統」音楽に携わる者に与えられた使命のような気がするが、如何だろう。

私は音楽をやりたい。政治闘争でもイデオロギーのせめぎ合いでも、格式の張り合いでもない。ただ単に素敵な音楽を奏で、聴き、作り続けたいのだ。そしてそこに喜びがあればいい。その他は要らない。



