先日、ロイヤルバレエによるクリスマスの定番「くるみ割り人形」の公演が29か国に配信され、新宿の映画館にて観てきました。劇場からの衛星中継というのが何とも臨場感があって良かったです。(時差があるので生中継ではないようです)
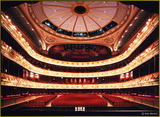
いや~~夢のような美しさでしたね。舞台も演出もなかなか凝っていて充実の内容でした。さすがはロイヤルバレエ!!私みたいなのが言うのも変ですが、西洋の美というものをしっかり見せてもらった、という感じでした。先日のパリオペラ座といい、ロイヤルバレエといい、世界の一流というのは凄いものですね。
クリスマスイブのパーティーの夜が舞台ですので時期もぴったり!。チャイコフスキーの名曲の数々と共にクリスマス気分を味わってきました。
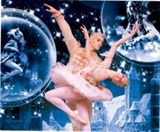 中でも主役のクララを演じたフランチェスカ・ヘイワードがとっても良い表情で、少女から大人の女性へと変わる微妙な時期の雰囲気をよく出していました。ヘイワードはロイヤルバレエスクールから入団した若手で、まだランクは下のようですが、これからが楽しみですね。写真が無いのが残念。プリンシパルのラウラ・モレーラ、フェデリコ・ボネッリ(写真左)も勿論この通り。日本人も崔由姫、平野亮一の二人がファーストソリストとして出演していて、特に崔は見事なダンスを披露していました。
中でも主役のクララを演じたフランチェスカ・ヘイワードがとっても良い表情で、少女から大人の女性へと変わる微妙な時期の雰囲気をよく出していました。ヘイワードはロイヤルバレエスクールから入団した若手で、まだランクは下のようですが、これからが楽しみですね。写真が無いのが残念。プリンシパルのラウラ・モレーラ、フェデリコ・ボネッリ(写真左)も勿論この通り。日本人も崔由姫、平野亮一の二人がファーストソリストとして出演していて、特に崔は見事なダンスを披露していました。
美しいものを見ていると、心が柔らかくなります。殺伐としたものばかりに触れていれば、心もそうなって行くものです。常に視野を広げ、色々なものに接していることは芸術家には必須ですね。「こうでなければ」「こうであるべき」という思考は自らの感性を狭めてしまいます。私自身、陥りやすい所でなので、常に気を付けていますが、素晴らしい舞台、音楽、美術、文学等々あらゆる芸術と常に接して、視野と感性を広げる事は、同時に喜びであり、楽しみであり、人生の栄養です。

バレエやオペラの華やかさ・・本当に素晴らしいレベルと芸術性があると思います。邦楽は、この華やかさをそのまま追いかけようとしたところに大きな問題があったと私は思っています。明治以降、洋楽を取り入れたことはけっして悪い事ではないと思っていますが、日本には日本の形とやり方がある。奈良平安の時代から、外の文化を受け入れ、熟成し独自の形にしてゆくのは、日本の素晴らしいやり方だったと思うのですが、明治以降は音楽に於いて、そうはならなかったですね。まだ時間が足りないのか??
振り返ると、薩摩琵琶では明治から大正時代にかけて、どんどんと新作を作り、時代が求めた音楽を作り演奏していた事が、何よりもその隆盛をもたらした要因だと思います。しかし現在は新作がほとんど出てきていない。私も少しは作曲していますが、こんなものではどうにもなりません。もっともっと流派に囚われない、旺盛な創作意欲を持った、芸術的感性に溢れる琵琶人が出てきて欲しいものです。
世代は変わって行きますし、時代も人々のセンスもどんどん変わります。常に時代に即した音楽が生まれるのは、クラシックだろうがジャズだろうが、歌謡曲だろうが同じことです。大正時代の薩摩琵琶は、明治大正という時代に於いて、その命が煌めいていた音楽だったからこそ、聴衆が求めたのでしょう。
 バレエもオペラも、100年200年前の作品であっても、常に新しい感性を持って取り組み、演出をし、現代の芸術作品として創造しているからこそ、ヘンデルも、モーツァルトも絶賛されるのです。楽器の方も、演奏場所がサロンからホールへと変わって行った事に伴って、ホールでの演奏に合うように改良され、新しい音楽が次々と生まれて行きました。仏教でも、教祖の教えを後の世に、その時代に合うように翻訳する人が居たから、現在まで伝えられてきたのです。邦楽はどうでしょうか・・・?
バレエもオペラも、100年200年前の作品であっても、常に新しい感性を持って取り組み、演出をし、現代の芸術作品として創造しているからこそ、ヘンデルも、モーツァルトも絶賛されるのです。楽器の方も、演奏場所がサロンからホールへと変わって行った事に伴って、ホールでの演奏に合うように改良され、新しい音楽が次々と生まれて行きました。仏教でも、教祖の教えを後の世に、その時代に合うように翻訳する人が居たから、現在まで伝えられてきたのです。邦楽はどうでしょうか・・・?
今日本は、夢を持って生きるという事が難しくなってきている時代にあります。それは経済だけの問題ではないと思います。この今だからこそ音楽家が大きな視野と夢を持って、旺盛な創作意欲を発揮して、本来の日本を取り戻したいです。取り戻すのはけっして経済ではないですよ。文化と誇り、そして志です。
クラシックもバレエもオペラも素晴らしいですが、日本にも魅力ある文化がまだまだいっぱいあります。それをロイヤルバレエやMetのように世界へ、日本の舞台芸術として発信して行けるような時代になったらいいな、と思います。
世界一流のバレエを観ながら、日本の姿も見えてきました



