少し前になりますが、オペラシティーアートギャラリーで開催されていた「五線譜に書いた夢~日本近代音楽の150年」展に行ってきました。

明治時代が始まって150年。この150年は日本史の中でも日本音楽がこれほど変化激動した時代は、日本の歴史史上なかっただろうと思います。それが洋楽の導入によって始まったのはご存じの通り。その軌跡を観て辿りながら、大変感慨深いものを感じました。そしてまた今の私達の姿が良く見えてくるような想いがしました。
日本の音楽は、明治という新しい時代に洋楽と出逢う事で「芸術」という概念が芽生え、「表現」という意識も発展してきました。これは明治以前には見られなかった大変に大きな変化です。文学の分野も同じですね。
今はどんな分野に於いても表現するという事が当たり前ですが、日本の音楽には自己表現という意識が元々希薄なのです。雅楽や平曲などを実際演奏してみると、人それぞれ個性はありますが、自己表現とは程遠いと感じてなりません。「私」というものを音楽の中に持ち込まない。むしろ自分を無くすような方向を向いていると思います。この辺が元々の日本文化なのでしょう。だとしたら、この日本文化の根底にある感性を、現代社会に生きる我々がどういう風に捉えるか、そこが今後の日本音楽の大きなポイントとなると思います。
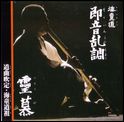 少し前には尺八でも、古典本曲を大胆な独自の解釈で演奏するというのが流行っていました。海神道、横山先生などはその先端を行っていましたね。私はその活動を現代に於ける古典の在り方として高く評価していますが、そういうやり方自体が、明治以前には無い、新しい日本音楽の接し方だとも思っています。
少し前には尺八でも、古典本曲を大胆な独自の解釈で演奏するというのが流行っていました。海神道、横山先生などはその先端を行っていましたね。私はその活動を現代に於ける古典の在り方として高く評価していますが、そういうやり方自体が、明治以前には無い、新しい日本音楽の接し方だとも思っています。
明治からの日本の音楽事情については多くの意見がありますが、洋楽をいち早く取り入れたことが、邦楽に携わる人々の意識を変え、邦楽を単なる民族音楽の枠から飛び出させ、同時に日本社会も世界舞台へと向かって行った事は確かだと思います。あの政治的変革が無ければ、今の日本はありえません。
表現や芸術という概念に関して私なりに想う事は多々あります。しかし今、邦楽全体にこの辺りの事がとても曖昧で、古典に対する姿勢もかなりあやふやになっていると感じるのは私だけではないと思います。
今回の展示を見て、明治以降の日本の音楽状況を辿りながら、色々な想いが私の中に沸き起こりました。そして何時もながらのセリフですが、今琵琶楽の器が問われているように思えてなりません。
 さて、譜面という部分に視線を向けてみましょう。先ず一番最初に判って欲しいのは、音楽はどんなジャンルの物でも紙の上には表せないという歴然たる事実です。譜面は伝えるための手段でしかない。
さて、譜面という部分に視線を向けてみましょう。先ず一番最初に判って欲しいのは、音楽はどんなジャンルの物でも紙の上には表せないという歴然たる事実です。譜面は伝えるための手段でしかない。
先ず、琵琶や尺八で今使われている譜面よりも五線譜の方が情報量が豊富なのは、一目瞭然です。だからといって五線譜でも琵琶の微妙なニュアンスは表せません。それでも琵琶譜のように、見た所でテンポも
リズムも音高も判らない単純なタブラチュア譜よりは、明確に音楽の姿を捉えることが出来ます。現行の琵琶譜は明治になって出来たもののようですが、稽古してない人には何が何だか判らないでは、譜面として機能していないという事です。演奏者のメモ書きのようなものでしかありませんね。私は琵琶譜を使う場合、リズム記号や音の強弱等を書き足したりして、五線譜の各記号をミックスして使う事が多いです。
五線譜や雅楽譜の優れているところは、調、リズム、メロディーの正確な音高等、演奏に必要な情報がちゃんと記されている点です。だから秘曲など1000年以上前の譜面でも音楽の姿が判る。これが凄い。勿論それをただ演奏しても音楽にはなりません。そこに命を吹き込むのはいつの時代も演奏家です。ここを忘れてはいけないのです。
薩摩琵琶に古典曲が残っていないのは、演奏するという事に重きを置いていて、「残す」という事に意識があまりなかったからでしょう。もし残したいのなら、筝曲のようにもう少し誰にでもわかるように譜面を工夫し、なるべく多くの情報を書き残そうとしたはずです。また筝曲などとは違い、作曲という概念自体も無かったのだと思います。
五線譜を嫌う邦楽人の一番の誤解は、五線譜に書かれていると 拙作siroccoの譜面
まるで無機質の打ち込み 音楽のようになる、と思い込んでいるところでしょう。これは全くの誤解であり、勉強不足であり、大いなる勘違いです。クラシックでも五線譜に書かれていることを自分で読み取り、そこから自分の音楽を紡ぎ出して、初めて音楽となって鳴り響くのです。この「音楽を紡ぎだす」という大変重要で大切な行為を知らない演奏家には何を言っても判ってもらえません。特にちょっと五線譜が読めると思い込んでいる人に一番この誤解が多いですね。自分の感覚に頼り切って、自分の頭の中だけで完結している人と言っても良いかもしれません。まあ、世の中何事もちょっと知っているが為にものが見えないという事は往々にしてありますが・・・。
音楽のようになる、と思い込んでいるところでしょう。これは全くの誤解であり、勉強不足であり、大いなる勘違いです。クラシックでも五線譜に書かれていることを自分で読み取り、そこから自分の音楽を紡ぎ出して、初めて音楽となって鳴り響くのです。この「音楽を紡ぎだす」という大変重要で大切な行為を知らない演奏家には何を言っても判ってもらえません。特にちょっと五線譜が読めると思い込んでいる人に一番この誤解が多いですね。自分の感覚に頼り切って、自分の頭の中だけで完結している人と言っても良いかもしれません。まあ、世の中何事もちょっと知っているが為にものが見えないという事は往々にしてありますが・・・。
大雑把な言い方をすれば、邦楽で使われている五線譜という手法は、ブロークン英語のようなものです。クラシックとは捉え方が違います。ジャズでもそんな感じですが、私はそれでよいと思います。譜面はとにかく情報が伝わってなんぼです。五線譜を使ったからと言ってもクラシックをやる訳ではないのです。邦楽というジャンルに於いては共通言語としての役割があれば良い。より詳しく、判り易く記録し伝える為に、五線譜の方が情報が豊富で有効だという話です。音楽となって行く手助けになればよいのです。その為には豊富な情報をしっかり伝える方が良い。洋楽としての正確な音程を出す必要もないし、自由に間を感じて演奏すればよい。現代音楽に見られるように小節線の無い譜面などは今や普通にクラシックでも使っています。五線譜と言っても色々な記譜のやり方があるのです。譜面を元にして、音楽家各自がそれに命を与えて、音楽を作り上げてゆくのは、邦楽でも洋楽でも同じなのです。五線譜に書かれている情報を元に、邦楽は邦楽のやり方でそれを実現すればよい。五線譜を豊富な情報が詰まった共通言語としてどんどん活用すればよいと思います。
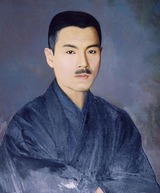 永田錦心
永田錦心
第二次大戦後は新邦楽、現代邦楽と言われる運動が具体的になって来ましたが、元々明治に出来た錦心流琵琶や都山流尺八などは、最初からモダンスタイルをその大きなテーマとしてきました。以前にも書きましたが、永田錦心は琵琶新聞の中で、これからは洋楽を取り入れて新しい琵琶楽を創って行く、と宣言しています。その永田錦心から生まれた錦や鶴田流などは正に現代邦楽の申し子と言えるでしょう。私が錦心流や鶴田流に縁があったのも当然の成り行きだったことと思います。新しい形を作りだし、新たな琵琶楽を創造するのは、永田錦心以来の使命・宿命、そして伝統でもあると感じています。
邦楽が、単なる日本の民俗音楽という枠を出て、社会のグローバル化に伴って、色々な地域、色々な世代に広がっている状況では、琵琶も弾き語りだけというのはもはやあり得ない。色々な楽器との合奏もどんどん増えて行くだろうし、次世代の琵琶楽もどんどん作るべきだと思います。それに伴い共通言語としての五線譜はこれからどんどんと活用されるべきだと思います。明治以降、音楽を芸術や表現として捉える感性が日本人の中にも広がって行ったことにより、音楽を書き表し、録音し、より多くの人に伝えて行く手段として邦楽の中に於いても五線譜が発達していったのは当然の事であると思うのです。

民族音楽は生活の中から出て来た音楽ですので、PCやスマホいじりながら音楽だけは昔の感じでやりたいというのでは、昔風のレトロ感を楽しんでいるに過ぎない。趣味でやっている分には結構なことだと思います。琵琶楽を民族音楽と捉えるならば、現代に生きる人々の生活の中から出て来る琵琶楽があって当然。明治大正の時代には確かにそうしたものがありました。だから現実生活を抜きにして過去のものを過去の形のまま楽しんでいるという事は、もはや民俗音楽としての資質を有していないとも言えるでしょう。
武満作品はじめ、エンタテイメントでない所で私のように自分で作曲し、演奏する人も居ますし、一方、グループでポップスをやるような方が活躍するのも結構なことだと思います。それは現代の姿なのですから・・・。色々なタイプの人がどんどん出て来るべきなのです。その時に色々な楽器やジャンルとをつなぐのには、五線譜が必要不可欠だと感じています。

より良い音楽を創るために、受け継ぐべきものと、その必要のないものをしっかりと見極めなければなりません。明治に出来た記譜法を受け継ぐことが伝統を受け継ぐことではないのです。私は永田錦心
の志を受け継ぎたいし、何よりも琵琶楽を豊かに、高らかに現代社会の中に響かせたい。五線譜を使ってもっと多くの人、楽器、音楽とコミュニケーションを取って行きませんか。
全ては音楽の為に!!



