先日、いつもお世話になっている石田一志先生の芸術選奨受賞記念のパーティーが東京三田倶楽部であり、お祝いしてきました。

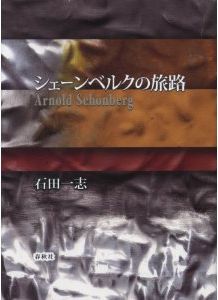 先生が昨年出したこの「シェーンベルクの旅路」が受賞したのですが、かなりの大作で、私は未だ全部読み切れてません。凄い本です。ぜひ海外でも翻訳して出すべきだ、という声も聞かれ、シェーンベルク研究の本として、歴史に残る作品となると思います。ご興味のある方は挑戦してみて下さい。
先生が昨年出したこの「シェーンベルクの旅路」が受賞したのですが、かなりの大作で、私は未だ全部読み切れてません。凄い本です。ぜひ海外でも翻訳して出すべきだ、という声も聞かれ、シェーンベルク研究の本として、歴史に残る作品となると思います。ご興味のある方は挑戦してみて下さい。
シェーンベルクは、1874年(明治7年)の生まれ。日本では西幸吉によって薩摩琵琶が東京に紹介され広まっていった頃と重なります。ドビュッシーの「牧神の午後への前奏曲」が1894年(明治27年)、1912年(明治45年)にはシェーンベルクの「月に憑かれたピエロ」が出来ていますので、西洋の現代音楽と日本の薩摩琵琶が、奇しくも同じ時代に花開いたのです。
私はこの時代の芸術的エネルギーの興隆にとても興味があって、判らないながらもシェーンベルクには大変に惹かれるのです。現代への扉はドビュッシーやラベルによって見いだされ、シェーンベルク、バルトークが開いていったのです。永田錦心はシェーンベルクのひとまわり下の生まれですから、この時期には世界的に、次の時代を作る新しいリーダーが次々と誕生していたのですね。今の私達にはピンときませんが、薩摩琵琶は当時、新時代のシンボルであったのかもしれませんね。
日本では音楽学や評論という分野がとても遅れています。「日本人は感情面が先に来て、論理を持って議論が出来ない」とよく言われますが、何か書けば誹謗中傷などと取られ、それゆえ日本の音楽雑誌などでは感想文ような評論もどきが溢れてしまうのです。 世界視野でみると何とも情けない。
世界視野でみると何とも情けない。
音楽学は芸術音楽をやってゆく上で一番に大切な部分なのです。事実の上に立ってしっかりとした史観を持ち、過去の事例を分析研究してゆくことは、芸術だけでなく学問全体として、そして国家としても大切なことだと思うのですが、現代日本人は音楽でも何でも、個人的な感覚でしか捉えようとしない。「いいものはいい」などと言って個人の感覚レベルで話を終えて、何故それがいいと思うのか、その根源にある歴史的背景や、それらに育まれた感性、民族性という所を探求しようとしない。やはり日本には芸術という概念は根付かないのでしょうか。それとも単に成熟していない民族ということなのでしょうか。
そんな中、石田先生はかなり真摯に、そして時に辛辣に評論を書きます。その評論で方向転換をしてゆく人もいるほどに、確固たる信念と理論を持って書くのです。私はそういう先生の姿勢が好きです。また学者の中には、専門以外はろくに知らないとい方も結構多いのですが、石田先生は大変幅広い範囲の知識を持っていて、前作「モダニズム変奏曲」では、アジアの近現代の流れを大きな視野で捉えています。また琵琶についても大変詳しい。この豊富な知識と、それらをまとめ上げる知性。評価されて当然ですね。だからこそ一緒にお酒を頂きながら話をしていても実に面白い。話が尽きることがないという訳なんです。

真中が石田先生。私も後ろの方に入れさせてもらいました。この日はお祝いに駆け付けた方がとても多かったので、分野別に分けて写真を撮っていました。この写真は演奏家の方々のグループです。
私ならこれだけの大仕事の後は、すぐ一休みとなるところですが、先生はそこで止まらない。淡々としながらも色々な企画を考え、進めている。賞は結果として頂いているものであって、それらに寄りかかってなどいないという事です。勿論人に対しても肩書きで判断などしない。以前、世界的なバレエダンサーK川さんも、キャリアや受賞歴は一切見ないし関係ない、舞台の実力のみで判断する、と言いきっていましたが、これは世界レベルで生きている人には当たり前の事なんです。邦楽界にも世界を視野に入れた、レベルも志も高い人物がどんどん出てきて欲しいですね。
 この日は私が知らないだけで、色々な方々が見えていたようですが、私の演奏はどんなふうに聞こえたんでしょうね??。
この日は私が知らないだけで、色々な方々が見えていたようですが、私の演奏はどんなふうに聞こえたんでしょうね??。
仕事が評価されるのはとにかく喜ばしいこと。先生にはこれからまだまだ、ひと仕事もふた仕事も期待しております。
この日は色々な先輩方々と話をさせてもらって、改めて「もっと色々なことを勉強しなくちゃ」と思った一日でもありました。
PS:来月には日本アルバンベルク協会主催による、石田先生の講演もあるようですから、ご興味のある方は問い合わせてみてください。



