今週は定例の琵琶樂人倶楽部、楽琵会に加え、光が丘美術館での演奏会をやってきました。
 ここでは以前も一度演奏したことがあるのですが、本当に素晴らしい空間なのです。落ち着いた風情、適度な響きなどなど色々なものがしっとりと調和している。だからとても自然に気持ち良く表現することが出来るのです。
ここでは以前も一度演奏したことがあるのですが、本当に素晴らしい空間なのです。落ち着いた風情、適度な響きなどなど色々なものがしっとりと調和している。だからとても自然に気持ち良く表現することが出来るのです。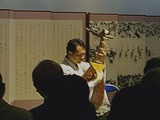
今回も版画家の井上員男先生による平家物語の版画に囲まれて演奏してきたのですが、この作品は実に壮大でかつ繊細。素晴らしい!。皆様にも是非一度観て頂きたいと思います。
こうして日々演奏会に追われて過ごしていると、本当に多くの方に出逢い、話をする機会に恵まれます。先日も陶芸家の佐藤三津江さんの自由な発想の作品達を見ていて、行くべき道を歩むとはどんなことなのか、お話しを伺いながら頭を巡らせてきました。
 もうずっと以前になりますが、某邦楽雑誌の編集長に「琵琶奏者で仕事受けている内はまだまだだよ。塩高本人を指名されて仕事するようになりなさい」とアドヴァイスを受け、その言葉を目標に自分の思う所を只管やって来ました。周りを見れば、邦楽でも一流の方は皆さん確固たる自分のスタイルを持って大舞台を張っています。刺激になりました。しかしまだまだこの世界には、真逆の姿も溢れているのも確か。演奏家はただ舞台で真摯に演奏すればよいものを、音を出す前に、○○流・○○門下・○伝etc.が先に口をついて出てしまうのは何とも…。
もうずっと以前になりますが、某邦楽雑誌の編集長に「琵琶奏者で仕事受けている内はまだまだだよ。塩高本人を指名されて仕事するようになりなさい」とアドヴァイスを受け、その言葉を目標に自分の思う所を只管やって来ました。周りを見れば、邦楽でも一流の方は皆さん確固たる自分のスタイルを持って大舞台を張っています。刺激になりました。しかしまだまだこの世界には、真逆の姿も溢れているのも確か。演奏家はただ舞台で真摯に演奏すればよいものを、音を出す前に、○○流・○○門下・○伝etc.が先に口をついて出てしまうのは何とも…。
武満徹が独学なのはよく知られていますが、その音楽が伝統であれ革新であれ、社会に音楽を響かせるには、 どうしても過去を学ぶ必要があります。それは武満さんもジョンレノンも同じでしょう。私も自分なりに学んでいますが、何を学んでもあくまで自分の音楽を舞台で表現します。古典だろうがなんだろうが聴衆が共感する音楽であれば、おのずと受け継がれて行くだろうし、そうでなければ、明清楽のように途絶えてゆく。それはその音楽の持つ器と定めというものだと思います。
どうしても過去を学ぶ必要があります。それは武満さんもジョンレノンも同じでしょう。私も自分なりに学んでいますが、何を学んでもあくまで自分の音楽を舞台で表現します。古典だろうがなんだろうが聴衆が共感する音楽であれば、おのずと受け継がれて行くだろうし、そうでなければ、明清楽のように途絶えてゆく。それはその音楽の持つ器と定めというものだと思います。
私が以前習ったT先生は、私が入った頃「これから家元制度を止め、名前の伝授もしない」と宣言したので、私はそこで勉強することにしたのです。音楽が、舞台が全てだという、T先生の言葉に共鳴したのです。まだ成立して間もない流派でしたが、ここなら一流を目指せると思いました。
自分の道を歩むという事は、多様な社会の中で生きて行く事と思っています。何かに寄りかかっていなければ存在し得ないのでは情けない。現実社会の中で、一個の自立した存在として生きていなければ、誰もその音楽を聴いてくれないと思うのですが、如何でしょうか。全ては今を生きる聴衆が支持するかどうかだと思います。
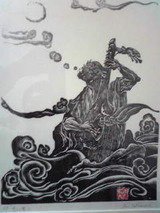
結局人間には人其々生きることの出来る範囲というものがあります。器といってもよいでしょう。FBでイイネを押してもらって満足ならそれはそれ。ライブこそ自分の居場所という人も居れば、大舞台に打って出る人も居る。何を目指すかは本人の意識次第。それが実現するかは器次第。小さくても大きくても、本人なりに生きてゆくことが一番だと思います。
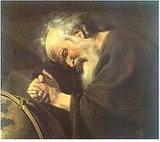 今では尺八や筝でも、五線譜を使って、カラオケで演歌や歌謡曲を楽しむお稽古場がいくつもあるそうです。基本だと思っていたものも、どんどんと変化して行くのが世の中。自分が拒否しても、社会は次々に新しいものを受け入れてゆく。ヘラクレイトスのパンタレイ(万物流転)は昔も今も世の在り様です。物も形も、価値観も何も変わらぬものはないということだけが事実です。
今では尺八や筝でも、五線譜を使って、カラオケで演歌や歌謡曲を楽しむお稽古場がいくつもあるそうです。基本だと思っていたものも、どんどんと変化して行くのが世の中。自分が拒否しても、社会は次々に新しいものを受け入れてゆく。ヘラクレイトスのパンタレイ(万物流転)は昔も今も世の在り様です。物も形も、価値観も何も変わらぬものはないということだけが事実です。
私のこの音色もいつか消えてゆくことでしょう。50年後は、全く違う琵琶楽が主流になっているかもしれません。幕末の正派薩摩琵琶が、ノヴェンバーステップスなど考えられなかったように・・・。

自分の出す音がはかなく消える音であっても、私は自分が奏でている以上、余計な鎧を着ることなく素直な気持ちでその音に向き合いたいと思います。後は良くも悪くも、私が今持っている器が、ふさわしいステージにその音を導いてくれることでしょう。
「我が為す事は、我のみぞ知る」坂本竜馬



