先日武蔵野ルーテル教会で、東京バッハアンサンブルによる「イースターコンサート」を聴いてきました。
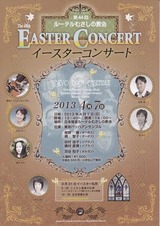
この武蔵野ルーテル教会は、先月3,11の時「響き合う、詩と音楽の夕べ」という催しで、演奏した所なのですが、地味ながらとてもいい感じの木造りの教会で、素敵な場所です。また大柴譲治牧師の人柄にも惹かれるものがあり、このコンサートには楽しみにしていました。
今回はソリストを加え、バッハ、ヴィヴァルディ、ロッシーニ等の弦楽合奏と、マスカーニのオペラアリア等充実のプログラム。聴衆への変な媚びも無く、音楽の喜びに溢れた内容で、教会でのコンサートにとてもふさわしい、楽しいひと時でした。
クラシックに比べると、同じく宗教性を根底に色濃く持っている邦楽は、どうも哲学的観念的なものに陥り易い。以前知人からも「邦楽はどうも堅苦しく、権威的で、偉そうで説教臭い」と言われましたが、邦楽は確かに強く・大きく・硬いという父権的パワー主義を引きずっている。私自身も以前は表面的な力強さに執心していた時期があるので、邦楽のそんな部分には少なからず違和感を感じています。
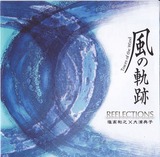 私の音楽に喜びはあるか?愛情は満ちているか?迷うとそんな事を自分に問いかけます。私のアドヴァイザーでもあるHさんは「愛を語り、届ける音楽家であって欲しい」と顔を見る度に言ってくれますが、私はその言葉を頂く度に、自らを振り返り、その時々の自分を見直すようにしています。
私の音楽に喜びはあるか?愛情は満ちているか?迷うとそんな事を自分に問いかけます。私のアドヴァイザーでもあるHさんは「愛を語り、届ける音楽家であって欲しい」と顔を見る度に言ってくれますが、私はその言葉を頂く度に、自らを振り返り、その時々の自分を見直すようにしています。
私はいつも演奏会の最後に「開経偈」というお経を唄います。これは仏の教えに 出逢って、大変ありがたい、嬉しい、そしてこの道で精進しますという仏教賛歌、まあキリスト教で言えば、短いクレド(信仰告白)みたいなものです。最後にここに至らないととても琵琶は弾いていられない。知識や技術・権威を振りかざし、大上段に構え「どうだ!」という態度では、音楽は響かない。びっくりさせる位が関の山です。
出逢って、大変ありがたい、嬉しい、そしてこの道で精進しますという仏教賛歌、まあキリスト教で言えば、短いクレド(信仰告白)みたいなものです。最後にここに至らないととても琵琶は弾いていられない。知識や技術・権威を振りかざし、大上段に構え「どうだ!」という態度では、音楽は響かない。びっくりさせる位が関の山です。
喜びを持つ事と同時に、社会と向き合う事もまた大事な事だと思っています。現実を生き、向き合う事無しに、闇に背を向けただニコニコしていても、音楽は生まれない。喜びが有るという事は、そこに至る厳しい現実も経ているという事。それでこそ喜びが伝わり、時を超えて力強く響く音楽となると思います。
 最近久しぶりにコルトレーンの「India」を聴きました。そこには60年代アメリカの混沌とした社会と真っ正直に向き合った音がありました。
最近久しぶりにコルトレーンの「India」を聴きました。そこには60年代アメリカの混沌とした社会と真っ正直に向き合った音がありました。
人間は正も邪も、清も濁も併せ持つ存在。社会もまた同様です。だから、社会にも自分にも真っ直ぐに対峙していくことが大切なのです。肩書きやら正統やら権威やら、そういうものはその時々で180度変わってしまう幻想なのです。それらに振り回されることなく、地に足を付けて生き抜く力強さがないと、音楽に喜びが満ちて行かない。

私の音楽も、聴いた人が人間の存在を愛おしく想い、人生が豊かになるようであって欲しい。
音楽には喜びが、力強く溢れていて欲しいのです。



