先日久しぶりにお会いした作曲の師 石井紘美先生の作品の上演がアサヒアートスクエアで行われました。実は先生の作品がちゃんとした形で日本で紹介されるはこれが初めてなんです。
 今回は日本電子音楽協会創立20周年の記念事業でした。先生は長い事海外に拠点がありますので、日本の協会とはつながりが無かったのですが、つい最近、北京での作品の上演の際にこの協会の方と知り合い、今回の作品発表となりました。
今回は日本電子音楽協会創立20周年の記念事業でした。先生は長い事海外に拠点がありますので、日本の協会とはつながりが無かったのですが、つい最近、北京での作品の上演の際にこの協会の方と知り合い、今回の作品発表となりました。
日本は何の分野に於いても、型や殻を破る事をとにかく嫌うので、電子音楽という新しい分野は、当然のごとくかなり出遅れているのが現状です。しかしこの所少しづつ各音大でも力を入れ始めてきました。一番早くから電子音楽に取り組んでいたのは愛知芸大で、日本で一番初めにムーグを導入したそうです。やはり中央の一番権威の高い所は、前例の無い事はやらないのでしょう。
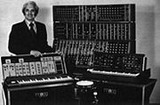 初期のムーグシンセサイザー
初期のムーグシンセサイザー
さて、この日は7人の作曲家の作品を聞きました。特に生楽器と電子音の組み合わせが多く、その意図のようなものは確かに聞こえてきました。しかし生演奏に中途半端な抒情性が見えてしまうと、とたんに電子音が安っぽく聞こえてくる。単に無機的なものと有機的なものの対比等という事ではとても成り立たない。何かもっと音以外の部分で考えるべきものを感じました。技術ではなく、哲学がまだ成熟していないと思いました。
石井先生の作品は「木を切り倒す」時の様々な音が素材となっていました。 木を切るという事は、古くは建材を得る為、今は更地を得る為であり、それは木の周りの鳥、虫、小動物の破壊も意味し、そういう伐採という行為には人間の姿そのものが現れています。それらをデジタル音分解、処理して出来た作品でした。全てが電子音だったせいか、音がとても生命感を持って感じられ、自然界の様と人間の営み、傲慢、業・・・色々なものが想起されました。デジタル音なのに、かなり有機的な音のアンサンブルに感じました。
木を切るという事は、古くは建材を得る為、今は更地を得る為であり、それは木の周りの鳥、虫、小動物の破壊も意味し、そういう伐採という行為には人間の姿そのものが現れています。それらをデジタル音分解、処理して出来た作品でした。全てが電子音だったせいか、音がとても生命感を持って感じられ、自然界の様と人間の営み、傲慢、業・・・色々なものが想起されました。デジタル音なのに、かなり有機的な音のアンサンブルに感じました。
ムーグ1C
他の作曲家の作品では、「BUNDLE IMPACTAR」という作品が印象に残りました。これも生演奏と電子音の組み合わせでしたが、生演奏の方が中心となり、音楽が広がって行く様には生命感とでも言ったらいいのか、大きな普遍的なものが見えるようで、魅力も可能性も感じました。私はこの分野の専門家ではないし、評論までは出来ませんが、全体を通して、日本の電子音楽のこれからに大きな課題を感じ、また可能性も感じました。10年先が楽しみです。
時代が求める音が現代に響いていて欲しい。それは人間界の小さな範囲のものでなく、この大地の持つ息吹、もっと言えば全てにあまねく注がれている「はからい」のような生命感に溢れるものであって欲しいですね。 宮城道雄とルネ・シュメーが当時、時代が求める音そのものであり、今でもその音色があせないように・・。
宮城道雄とルネ・シュメーが当時、時代が求める音そのものであり、今でもその音色があせないように・・。
その為には、「邦楽はこうだ、琵琶はこうであるべき」というような旧来の殻を破れない縮こまった感性を取り払いたい。そんな感覚では何も生まれない。バッハやモーツァルトでも常に時代の感性で演奏され、楽器もハープシコードではなく現代のピアノで演奏される、オペラも永田錦心もしかり。それでも尚輝きを失わないから古典となって行くのです。先生の言う通りまじめにやっていればそこそこに成る、という優等生的な惰性。それを是非飛び越えて欲しいですね。

新しいものはまだまだ成熟していないので確かに未熟でしょう。しかし人間でも老成した人ばかりでは種自体が滅んでしまう。若き命は種の伝承に必要必然なのです。そういうものを恐れ、立ち止まっているようでは明日はありません。
電子音楽という分野は時代の求める必然です。琵琶楽にも時代の求める必然の音が、どんどんと出て欲しいですね。



