八重山民謡のベテラン大工哲弘さんから「揚~八重山百哥撰」のCD(昨年のリリース)が届きました。雑事に追われている日常、ふと休みたくなった時にこのCDを聴くと、「す~と楽~に」なります。
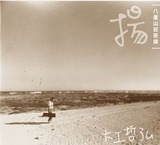
大工さんはデビューしてもう45年。その世界では、誰もが認める第一人者ですが、私はひょんなことからもう10年ほど前より、手紙やメールをやり取りさせて頂いて、CDを出すたびに聞いてもらっています。今までに色々と感想や意見を頂いているのですが、実はまだお会いした事が無いのです。不思議な御縁なのですが、いつも的確なお言葉を頂いています。
 大工哲弘さん
大工哲弘さん私は奄美島唄の前山真吾君とシルクロードを回った位で、沖縄や奄美の南方の音楽家とはあまり交流が無く、一ファンとして聞いているだけなのですが、このCDはとにかく心地良い、それに尽きます。唄も曲も自然なのです。「一生懸命やってます」とか「これが最高」などという気負いが無い。薩摩琵琶のように、顔を真っ赤にして声を張り上げるような音楽とは対極にあります。
大工さんはこうした伝統の唄もしっかりと受け継いでいる一方で、異ジャンルセッションなども積極的にやってきた人です。「不易流行」が好きだと御自身で言っているのもうなづけます。だからこうした土台となる古典も深みも増しているのかもしれません。何事もそうですが、外の世界を知り、よその釜の飯を食べるという経験は大事です!。

世の中には色々な音楽があるのが健全です。琵琶だけでももっと色々なものがあって欲しい。ギターは世界中にあらゆる音楽を作り出しているでしょ?。シルクロードの琵琶属も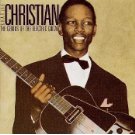 しかり、そう思えば、日本に於いて、これだけの長い歴史をつないできた琵琶に出来ないはずはないのです。ちっちゃなこだわりを捨てて、大きな世界に目を向ければ必ず出来る。三線はあれだけで実に様々なヴァリエーションを作っているではないですか。
しかり、そう思えば、日本に於いて、これだけの長い歴史をつないできた琵琶に出来ないはずはないのです。ちっちゃなこだわりを捨てて、大きな世界に目を向ければ必ず出来る。三線はあれだけで実に様々なヴァリエーションを作っているではないですか。
つい数十年前までは、琵琶の世界では「他の流派の演奏を 聴くと耳が悪くなるから聞いてはいけない」等という先生がごろごろしていたというのですから、衰退して行った様子が手に取るように判ります。永田錦心が聞いたらさぞがっかりする事でしょうね。少なくとも私は琵琶に対して、大工さんのような眼差しの向け方をしたいな~~。
聴くと耳が悪くなるから聞いてはいけない」等という先生がごろごろしていたというのですから、衰退して行った様子が手に取るように判ります。永田錦心が聞いたらさぞがっかりする事でしょうね。少なくとも私は琵琶に対して、大工さんのような眼差しの向け方をしたいな~~。


色々なヴァリエーションがあり、最先端の音楽が溢れているからこそ、古典というものが光り輝くのです。琵琶もそういう状況になったら、本当の古典が何か見えてくる!
新時代を作る奴出て来い!!一緒にやろうぜ!!



